K-POPとそれを取り巻く事象を、アーティストとファンダムの関係性や、そこに生まれる「物語」に光を当てながら批評するシリーズの第2弾。今回は韓国で一時は社会現象ともなったオーディション番組『PRODUCE 101』、その日本版である『PRODUCE 101 JAPAN』に光を当てる。
101人の参加者から視聴者投票のみでデビューメンバーを選出するという『PRODUCE 101』の斬新な仕組みは、本国で製作陣による投票の不正操作が明るみになり、もろくもその建前が崩れてしまった。しかし日本版は独自の運営体制によって制作されていることから不正はないことが公式に報告されており、まもなく12月11日に最終デビューメンバーを決める最終回が放送される。K-POPの大きな巨大なシーンやアイドルの育成システムを前提とした『PRODUCE 101』が日本に持ち込まれた結果、どのような化学反応を起こしたのか。「男性ファン」ならではの視点も交えて考察する。
(メイン画像:©LAPONE ENTERTAINMENT)
『日プ』に感じた「新しさ」やポジティブな違和感
「男たちは『日プ』(『PRODUCE 101 JAPAN』、以下『日プ』)をどう見ているの?」
新大久保の居酒屋でK-POPファン仲間の女性と『日プ』についてひとしきり語らった後、唐突にそう問われて面食らった。「川西拓実(『日プ』に出演している練習生のひとり)って男から見てもかわいいの?」と彼女は続ける。あーいや、めっちゃかわいいと思うけど……と答えると、「それってどういう感情なの?」と畳みかけられる。
彼女の疑問もよくわかる。たしかに男性アイドルの男性ファンは、女性アイドルの女性ファンよりも体感的にだいぶ少ない。自分自身、とりあえず答えてはみたものの、それが本当に「かわいい」という感情なのかはよくわからなかった。女性が女性を魅了する「ガールクラッシュ」は流行ジャンルだが、「ボーイクラッシュ」はまだ言葉として確立されていない。
そもそも、ここまで『日プ』にハマるとは思っていなかった。見始めた理由は単純で、もともと好きだった『PRODUCE 101』こと通称『プデュ』シリーズの日本版だから見てみようという程度のことだったように思う。強いて言えば、『日プ』の練習生たちに対しては「男子たち」への素朴な共感があり、当初は自分の男子校時代を懐かしむような感覚で楽しんでいた。

それが1話、2話と回が進むごとに次第に熱が上がっていき、今となっては動画を見るたび「かっこいい」「最高」「キヨ~(韓国語で「かわいい」の意)」と叫びながら騒がしく拍手するようになってしまっている。これまで男性アイドルにそこまでハマったことはなかったし、27年生きてきて初めて見る新鮮な「男」たちの姿に、自分でも少し戸惑っているというのが正直なところだ。
なぜ『日プ』の練習生たちを魅力的に、あるいは新鮮に感じたのか。なぜ、そう感じたこと自体にポジティブな違和感を覚えたのか。それは、韓国のサバイバルオーディションを日本版にローカライズしたことで、『日プ』に独特な化学反応が生まれたからなのではないかと考えている。『日プ』が本国の『PRODUCE 101』シリーズとどのように違っているのか、またその違いからどんな風に日本の新しい男性像の可能性が示されたのかを考えてみたい。
リアリティショー要素が含まれたサバイバルオーディション、『PRODUCE 101』シリーズ
『プデュ』シリーズは、アイドルグループとしてデビューするメンバーを、合宿形式の練習&パフォーマンス対決で選抜するサバイバルオーディションプログラムであり、IZ*ONEやX1などの人気グループを輩出したことでも知られている。
サバイバルオーディション自体は、韓国で2000年代後半から流行しているポピュラーな形式だ。そのなかで2016年にスタートした『プデュ』シリーズが革新的だったのは、「視聴者投票だけで練習生を選抜する」という「国民プロデューサー(通称「国プ」)」のシステムを考案したことである。プロの審査員ではなく、視聴者=潜在的なファンが評価を行なうため、参加者たちは単純にスキルを高めるだけでなく、プログラムを通じて「人気」を勝ち取っていかなければならなくなった。
加えて重要なのが、オフステージの練習生たちの様子をなるべく自然な状態で膨大にカメラにおさめていることだ。合宿での練習や話し合い、休憩時間のやりとりも含めた生の様子をひたすら定点観測に近い形で収録し、視聴者に提供する。一回きりのステージを評価するだけでなく、そのステージに至るまでのプロセスをも評価の対象とするという意味で、アイドルファンが日常的に行なっているファン行動を直接オーディション評価に組み込んだシステムとも言える。
パフォーマンス動画に至っては、本放送の全体映像とは別に、101人の練習生それぞれのソロアングル映像をYouTubeで供給する徹底ぶり。国民プロデューサーである視聴者たちは、それらの材料をもとに練習生のスキルや人間性を判断し、毎日投票を行なう。『プデュ』はパフォーマンススキルによるサバイバルであるだけでなく、「人柄」をもジャッジされる人間観察リアリティショー的なサバイバルも同時に課せられる、きわめて過酷なプログラムなのである。
トップアイドルが多数ひしめく、大きなK-POPシーンの存在を前提にした本国版
K-POPスターを目指す練習生たちが味わう厳しさを、ある意味そのままパッケージ化したような『プデュ』のシステム。だからこそ、日本版制作が告知されたときに自分も含めた本国の『プデュ』シリーズファンは戸惑いを覚えた。
『プデュ』のシステムが成り立つのは、あくまでも巨大なK-POPシーンの存在が前提にあるからだ。トップアイドルを輩出するための大小さまざまな芸能事務所が存在し、練習生はそこで何年もレッスンを重ねる。『プデュ』で爪痕を残してファンを獲得できれば、たとえ途中で脱落しても別のデビューの道が拓ける。成熟したシーンが多くの受け皿を用意できるからこそ、オープンな青田買いプログラムとしての『プデュ』が成立するのである。
対して日本の男性アイドル業界には、同じような巨大シーンは存在しない。ジャニーズやLDHといったファミリーは、あくまでもお互い独立していて統一したシーンにはなっていない。高いレベルの練習生はどこから集めるのか。楽曲は日本仕様になるのか、それともK-POPに寄せるのか。そもそもデビューしたグループはどこで活動するのか。さまざまな懸念があり、放送開始前はあまり期待値が高くなかったのを覚えている。

「K-POPサバイバルオーディションを日本人がやるとどうなるか」というローカライズ実験としての日本版。独特の多様性が開花
とはいえフタを開けてみると、想像以上に『日プ』は巧みなローカライズに成功していたと言える。統一的なシーンがないゆえの多様性が、回を追うごとに開花していったのである。
まず楽曲面。番組で練習生が披露する課題曲は、SEVENTEENやEXOなどのK-POP楽曲に混じって、Hey! Say! JUMPや三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEといった日本の男性グループの楽曲が含まれている。なかにはSuperflyなど女性シンガーの楽曲も課題曲となっている。オリジナル楽曲も、本格的なK-POPテイストのものから、ポップでかわいらしい雰囲気の曲まで振り幅が大きく、日本版ならではのオリジナリティが光っていた。
練習生たちのバックグラウンドもさまざまで、韓国のように練習生としての経験がある参加者はむしろ少なく、大半がいわば素人。一部K-POPアイドルのバックダンサー経験があったり、芸能活動をしていたりする練習生も混じっている。出身地も実にばらばらで、さまざまな方言が入り混じる。
ファン層も、K-POPファンだけでなく、ジャニーズファンやハロプロファン(トレーナーに「菅井ちゃん」こと菅井秀憲が登場しているためだと思われる)をはじめとした日本のアイドルファンにまで広がっている。予想以上に特定のクラスタに縛られない受容のされ方をしている印象だ。ファンダム同士の交流自体は今やそう珍しいことではないが、お互いの沼に引きずり込み合うのではなく、「みんなでひとつのコンテンツを見ている」という感覚が新鮮だった。
K-POPならではの「応援」の仕方。韓国のファンカルチャーも流入
『日プ』の前半戦では、1日に11名の練習生に投票できたため、自分の推し以外にも票を入れる余地があった。その浮動票を狙ったファン同士の布教活動も活発化していて、有志による駅広告や電車内広告など、韓国のファンカルチャーの流入も見られた。
また、ファイナル直前の現在は、最後の追い込みをかけるためにファンが『日プ』視聴者以外のフォロワーに投票を呼びかけるツイートも数多く流れてきている。その中には、数万のフォロワーを持つ著名人まで含まれているから驚きだ。本国版の投票には原則参加できなかった日本在住のファンとしては、初めて体験する『プデュ』の熱量にただただ気圧されている。
ファンが有志で掲出した電車内広告
もちろん、『プデュ』の本分はスキルを磨き合うサバイバルの部分だ。パフォーマンスを磨き上げなくては広い人気を獲得できず、最後まで勝ち上がれないという部分は本国版と変わらない。放送が進むごとに、98名から60名、35名、20名とどんどん人数も絞り込まれていった。
歌もダンスも未経験ながら、劇的な成長を見せて残留し続けている練習生もいれば、苦手ジャンルに挑戦して新たな持ち味を見つけた練習生もいる。当初は「できないことができるようになる」というだけで十分感動的だったが、後半戦に入るとステージそのものの完成度も上がり、パフォーマンスだけで素朴に感嘆の声を上げてしまう。練習生たちの「できる」の基準が以前よりも遥かに高いところにあることに気づくと、それだけで胸が詰まってしまう。わかりやすく「成長」という言葉を使うのはためらわれるが、人が何かを掴む瞬間に画面越しにでも立ち会えるのはこのプログラムの醍醐味だ。勝手に親心で見守っていた練習生たちのステージに心から驚かされてしまうのが、『プデュ』シリーズを見ていてもっとも幸福な瞬間である。
互いの容姿や仕草をストレートに褒め合う練習生たちの姿に感じた「希望」
そんな『プデュ』シリーズの醍醐味と比べるといささかニッチな観点かもしれないが、『日プ』ならではの特徴としてどうしても触れておきたいのが、冒頭から言及している「男」の姿へのポジティブな違和感だ。出場者が素人に近い練習生で、かつオフステージのやりとりまで放送する『プデュ』シリーズだからこそ、普段なかなか自分で客観視する機会のない男同士のコミュニケーションを外から観察できる。
もちろん、男子校の休み時間のような、仲睦まじいじゃれ合いを微笑ましく楽しむ部分もありつつ、男性である自分にとって「突きつけられる」といった方が実感に近いような、胸にくる「あるある」もあった。
その一例として、圧倒的なスキルとカリスマ性、謙虚さを兼ね備え、テーマ曲のセンターも務めた練習生・川尻蓮に対する他の参加者たちの憧れ方が印象に残っている。対等な立場のライバル同士であるはずなのに、みんなが蓮くんに選ばれたいし褒められたいと思ってしまう。その様子にどうしようもなく共感してしまう一方で、カリスマやセンスに無意識に惹かれてしまう「男子」的な性向が自分のなかに根深く残っていることを自覚させられるような居心地の悪さも感じた。鏡を覗いているような不思議な感覚、と言えばよいかもしれない。
10代、20代の、ほとんど一般人である男子が100人近く集まっているのだから、そうしたホモソーシャルな関係が生じるのは自然なことではある。むしろ、想像していたよりはずっとその度合いは少なく、安心したぐらいだった。
上位を常にキープしている練習生のひとり・川尻蓮
一方で、『日プ』を見ていて一番驚いたのは、彼らがとにかくストレートにお互いの容姿や仕草を褒め合うことだった。それも、「男としてかっこいい」「憧れる」というだけでなく、「かわいい」「きれい」といった対象としての評価をし合っている。彼らの多くは「日本で生まれ育った男性」であり、その点で自分とだいたい同じように育っているはずだと思うからこそ、「なぜそんなに衒いなくかわいいと言い合えるのか」とポジティブな違和感を持ったのである。
男同士のホモソーシャルな関係において、お互いを魅力的な対象として眼差すことは、心理的ハードルがとても高い。専門的には色々な議論があるが、あえて自分の実感に即して言語化するなら、それは「俺たち」の共感と結びつきを深いところで支えているのが「自分たちは眼差す側である」という意識の共有だからだ。男が男を眼差すと、そのお約束が崩れ、同じ「俺たち」ではなくなってしまう(女性同士でも同じことが言えると思われるかもしれないが、社会における眼差す / 眼差される構造の非対称性は無視できないだろう)。
堅い表現になってしまったが、一言でいえば「男が男を魅力的な対象として眼差すのは、男同士の関係において居心地の悪さを生み出す」ということだ。言うまでもなく、この居心地の悪さから人は自由になるべきだが、しかし頭でわかっていても実行のハードルは高い。男同士の「本音」の結びつきから、そっと疎外されるであろうことがありありと想像できてしまうからだ。だからこそ、練習生たちの姿に、大げさかもしれないが少し希望を感じた。
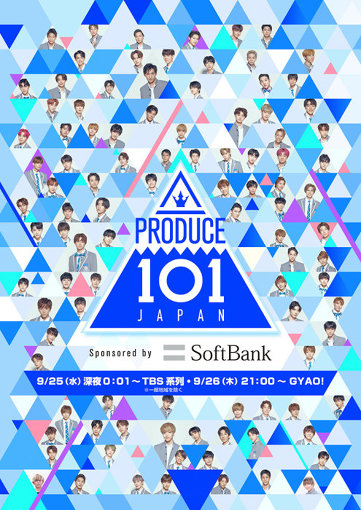
男性視聴者も、男性同士の関係性の内面化から少し自由になれる
もちろん、練習生たちがお互いを素朴にかわいいかわいいと褒め合うのは、そうしたことに自覚的だからではなく、単純に『プデュ』のプログラムの存在が大きいのだろう。
練習生たちは、(収録を見る限り大半が女性である)国民プロデューサーからの視線とジャッジに一方的に晒されている。どこまで自覚的に振る舞えるかは別として、彼らはつねに多少なりとも画面の向こうの女性たちの視線を意識し、その評価基準を内面化して振る舞ってしまうのではないだろうか。
女性の目がないはずのレッスン中や舞台裏においても、率直にお互いの魅力的な表情や仕草に言及する練習生たち。彼らの様子は、自覚的に「女性に向けたアピール」を行っているというよりも、女性から見て魅力的だと思われる部分を男同士でも普通に評価しあうように適応しただけ、という風にも見える。見られることに慣れてしまうような環境、そして全員が同じようにそうした環境に置かれているということ。それによって、いわば「ルールの変更」が生じて、コミュニケーションの形が変容したのではないか。そんな仮説を立てることもできるだろう。
だから練習生たちがこのプログラムを離れて一般の社会に戻った時に、同じように振る舞うのかは正直わからない。それでも、現にそうした男性同士で褒め合うことへの抑制から自由になっている様を目の当たりにするインパクトは大きかった。
少し前まで「普通の男子」だった彼らにとっても、そのことは革命的だったのではないだろうか。1話でメイク道具を物珍しそうに触っていた彼らは、今や普通にお互いにメイクをし合っている。少なくともそんな彼らを眺める男性視聴者としての自分は、男性同士の関係性の内面化から少し自由になり、心置きなく彼らを魅力的だと思うことができていた。
冒頭の居酒屋でのやりとりのあと、釈然としない様子の彼女に促されるままに、一人ずつ練習生の名前を挙げて「かっこいい」「かわいい」「友達にこういうやついた」「同じクラスで普段あんまり話さないけど、たまに世間話すると楽しいタイプ」など、主観で適当に分類していった。楽しい遊びだったが、同時にもどかしくもあった。男性に使う「かわいい」も「かっこいい」も、自分のなかではニュアンスがまだしっくりきていない。改めて考えると、男が男を見るときの、この「感情」を言い表す言葉のバリエーションが、まだ日本語には足りていないような気がする。
『日プ』も次の放送がファイナルだ。これで11人のデビューメンバーが決定する。待ち遠しくもあり、水曜日が来ないで欲しい気持ちもある。今はやっぱり、脱落してしまった練習生のことや、いなくなってしまうであろう練習生のことをどうしても考えてしまう。
月並みだが、全員が魅力的だし、全員にデビューして欲しいと思ってしまう。せめて彼らが見えるところにいてくれるうちに、その魅力を言い表す言葉の方が追いついてくれるとよいのだが。
- 番組情報
-
- 『PRODUCE 101 JAPAN』最終回
-
2019年12月11日(水)19:00~21:00にTBS系で放送
出演:
ナインティナイン
A-NON
サイプレス上野
菅井秀憲
Bose
安倉さやか
WARNER
PRODUCE 101 JAPAN 練習生
ほか
- フィードバック 10
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-




