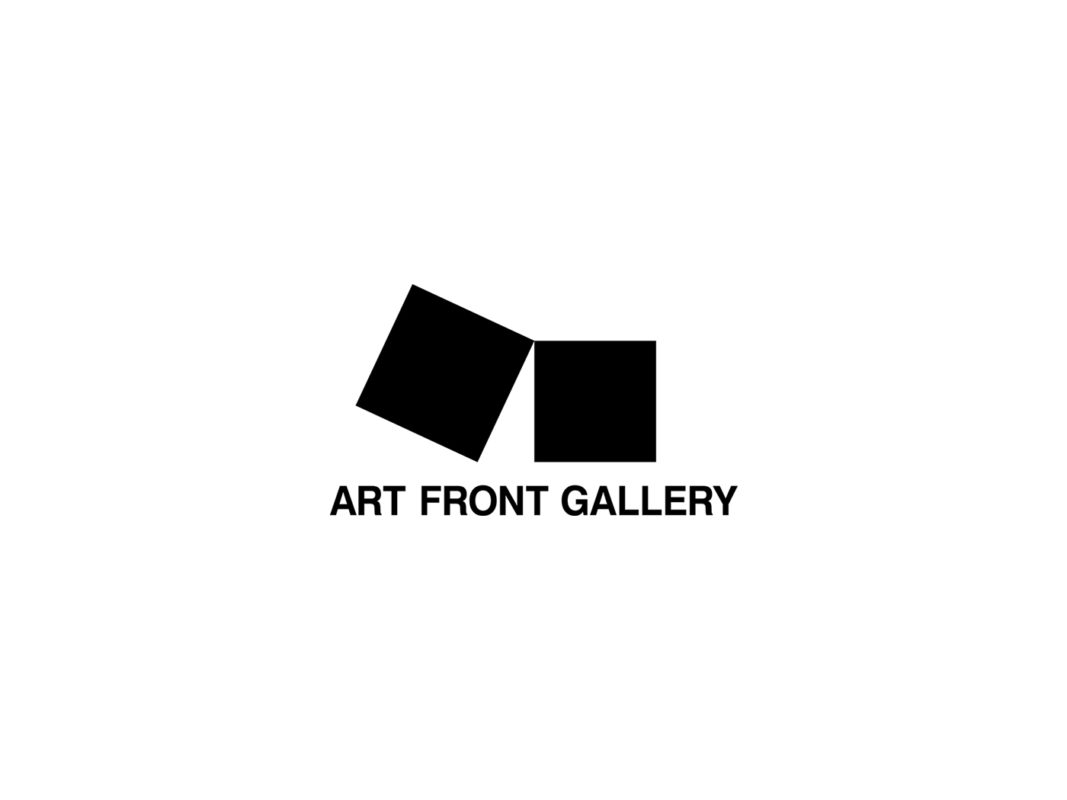香港から日本へ。恋い焦がれた異国の芸術祭を仕事にするため、海を渡る
- 2014/12/11
- SERIES
Profile
李 穎文
1984年香港出身。香港大学文学部で言語学と美術史を学ぶ。大学院に進学し、認知脳科学の研究を続ける傍ら、2009年、仲間とともにSense Art Studio株式会社を共同設立すると共にアートと社会学などの研究・企画を行う。2013年4月より来日、株式会社アートフロントギャラリーの社員となり、現在は市原湖畔美術館にキュレーターとして出向している。
香港の都市育ち、認知脳科学を研究。なのに、アート?
―香港から単身来日した李さんですが、来日前からアートや地域活性には興味があったんですか?
李:いえ、全然なんです。まず、私の出身地は香港のニュータウン。地上30階で育って、周辺には農地もありませんでした。子どもの時、美術館もなかったですし、今住んでいる千葉県市原市のようなのどかな場所でもないし、正反対の環境で育ちましたね。勉強も、公立学校に通って、ちゃんと勉強して、いわゆる「いい子」だったと思います(笑)。その頃からちびまる子ちゃん、ドラえもん、セーラームーンなどの日本のアニメは好きだったけど、真似して描いても絵は下手でしたし、あんまりアートには興味はなかったですね(笑)。
―しかも、大学では脳科学を専攻していらしたとか?
李:はい。まず、香港では大学受験が1科目6〜9時間もかかり、それが6科目もある。だからほぼ1週間が毎日受験の日々になるんです。それだけ長い試験ですから、受験までの1年間は勉強漬けで、すごく大変でした。結果、なんとか香港大学文学部に入学して、最初は言語学を専攻したんです。言語学の中でも、私は認知脳科学が専門で、大学院の修士を終えるまで、6年間その勉強を続けました。
—具体的には認知脳科学ってどんな研究なんですか?
李:たとえば、男女で脳のつくりが違うように、アルファベットを使う言語と、漢字を使う言語では、脳の違う部分を使っているんですよ。すごくないですか?!
—言語が違うと考えることも違うということですね!
李:そういうことを、実際に病院でMRIを使って見たりするんです。すごくおもしろかったですね。
—文学部とはいえ、だいぶ理系な印象です。それならなおさら、今のお仕事とはだいぶかけ離れているようにも思えますが……?
李:転機は1年生の夏休みに経験した助成金プログラムでの日本ツアーでした。そこで美術に興味を持ったのがきっかけです。もう10年以上前のことですが、私にとっては初めての日本で、関西に行ったんです。
—初めての日本はいかがでしたか?
李:とても楽しかったし、日本の人は本当に親切だと思いました。知らない街を歩いていると普通は迷子みたいな気持ちになるのに、日本のおばちゃんは「どこに行きたいの?」と日本語がわからない私にも、一生懸命話しかけてくれて。あとは、トイレに入ったら音が流れるとか、驚きの連続でしたね。
—で、そこでアートにも興味を持ったと。
李:はい。その助成プログラムのツアーは、奈良にある当時修復中であった唐招提寺など、定番の観光地ではない場所も回りましたが、安藤忠雄の建築をテーマにしたものだったんです。直島にも行きました。当時はまだ草間彌生の赤いかぼちゃはありませんでしたが、地中美術館に行ったりして、初めてアートを「おもしろい」と感じたのが、あの時です。
越後妻有、大地の芸術祭との出会い。
―アートと日本への関心が高まったんですね。
李:はい。それがきっかけで香港に帰ってからは言語学に加えて美術史も専攻するようになりました。その後2006年に、越後妻有「大地の芸術祭」のボランティアプログラムの募集を見かけて「また日本に行きたい!」という想いで飛びついたんです。学校から約15人が新潟に行って、開幕までの2週間を手伝いました。具体的には、作家さんの制作の手伝いや、古民家の掃除やゴミ出し、草刈りなど。ちなみに制作の手伝いは、クリスチャン・ボルタンスキーの展示の準備でした。藁を敷き詰めたり簡単な作業です。私を含めてほとんど日本語をしゃべれない学生ばかりだったし、法学部、医学部など誰も美術制作を専門としていなかったから、苦労したこともたくさんありました。でも、すごく楽しかったんです。その後香港に帰ってからもアート関連のインターンをしたりして、だんだんアートの方向へ向かっていきました。でも、アートのマーケットというよりは、私は妻有、大地の芸術祭の大ファンなんだと思います。
―アートそのものよりも、地域活性とか地域での暮らしに興味があるということですか?
李:そうですね。アートが最重要なのではなく、あくまでもアートを利用して自然を見せるというコンセプトに強く共感しているんです。自分が香港の高層マンションで育ったから、余計に魅力的に感じるのかもしれません。
―たしかに、外国の方で日本の地方に移住される方は多いと聞きます。
李:特に妻有は何度訪れても、自然が美しくて、人は優しく、魅力的な場所。作業自体は体力勝負なところも多かったですが、仕事が終わってから食べる新潟のお米はとても美味しい。それに温泉が最高なんです! 最初は裸になるのが恥ずかしかったけれど、一回入ってしまえば恥ずかしさよりも気持ち良さの方が上回って、虜になりました(笑)。
―でもまだ仕事じゃないですから、香港に帰国なさったわけですよね?
李:はい。認知脳科学の研究で大学院に通いながら、香港でSense Art Studio株式会社という団体を立ち上げました。私の大学の先生と、芸術祭のボランティアに参加したメンバー数人が、もっと芸術祭に関わりたいと思ってつくった団体です。
―会社を! すごいですね……。
李:私たちの初めての仕事は、瀬戸内国際芸術祭のボランティアコーディネートでした。夏に会期が始まるまで、セミナーをやったり、事務的な手続きを請け負ったり。大学院を卒業してからは、その仕事を専業でしていました。大地の芸術祭や瀬戸内国際芸術祭の総合ディレクターである北川フラムさんが香港に来たときのセミナーのコーディーネート、アートフェアに関連することなども、ともかくいろいろやっていました。
―進路で脳科学の研究を続けていく道は考えなかったのですか?
李:悩んだこともありました。でも、相談していた指導教官の言葉で、すごく大事だと思っていることがあるんです。「1週間のうち100時間かけてやりたいものはなんですか?」「起きてすぐと寝る直前は何を考えますか?」というものでした。それが研究のテーマだったら、研究員でやっていける。だけど別のものだったら、別の仕事をした方がいいと言われたんです。私は四六時中「妻有に行きたい」と思ってたから(笑)。私がやりたいことは研究ではなくて、妻有でやっているようなアートに関わることだと気づいたのです。
―前回、2012年の「大地の芸術祭」には、どのようなかたちで参加したのですか。
李:Sense Art Studioとして最後の仕事が大地の芸術祭でした。3年活動して、メンバーそれぞれが次のステージに行きたいと感じている時期だったのです。会社を一時解散することを決めてから芸術祭に参加して、前回と同様ボランティアのコーディネートのほかに、妻有の地元のお母さんたちと一緒に、小さなカフェをやりました。私自身も次に何をするか考えている中で、妻有にもっと深く関わりたいと考えはじめたんです。そのとき私は28歳。周りは結婚したり、子どもがいたりする。私はまだ独身だし、普通じゃないことにチャレンジするなら今しかないと思ったんです。
- Next Page
- 情熱的な手紙が来日の道を拓く
情熱的な手紙が来日の道を拓く
—でも、日本語もまだ堪能でなければ、仕事に就くには苦労もあったかと思います。
李:今思えばかなり無謀なことをしました(笑)。A4のレポート用紙の両面に、大地の芸術祭の総合ディレクターで、アートフロントギャラリーの会長でもある北川フラムさんに、英語で手紙を書いたんです。教わりたいことがあるので、一緒に仕事がしたいと、履歴書と一緒に送りました。ダメもとではあったのですが、それから2~3ヶ月したら突然メールが来たんです。「来年、市原アートミックスというイベントがありますが、興味はありますか? あれば一度話しませんか?」みたいな感じで。当時はまだ日本語があまりわからなかったので、グーグル翻訳に頼ってなんとか読んで(笑)。
—でも、市原がどこにあるのかすらも分からなかったのでは……?
李:はい、全く知りませんでした(笑)。でもメールの返信が来たことがとにかく嬉しくて。場所を調べて、行ってみようと思ったんです。返事が来てから市原で仕事を開始。はじめは、オープンを控えていた市原湖畔美術館の開館準備をしていました。市原アートミックスでは作品の制作を手伝いました。市原市内にある加茂学園という小中一貫校の全校生徒262人と、作家の開発好明さんとで、かかしをつくったんですよ。それを小湊鉄道7カ所の駅に設置しました。
—チャンスを自分の手でつかんだわけですね。現在はどんな仕事をしているのですか。
李:基本的には市原湖畔美術館のキュレーターの仕事で、展示も手伝いますが、メインはイベントやワークショップの企画、地域との連携を考えることですね。イベントやワークショップは参加者が命ですから、参加者を募りに、営業に出かけることもあります。ママ会とか、地元の学校の先生のところへも足を運びます。あとは、外国人のアーティストにとってこの地域はノーマークですから、大使館に連絡して、アーティストの来日予定を問い合わせたりします。来日に合わせて市原でもワークショップをしてくれないかと誘うためです。今までにイスラエル人2人、中国人の作家4人のワークショップを行いました。国外から人を呼ぶ場合は特に、作家の他の予定に合わせてもらったり、助成金を利用したりと工夫しています。
—美術館のキュレーターといっても、あちこち出かけて営業もして、行動力が必要な仕事なのですね。
李:人と話をするのが好きなので、この仕事が好きです。いろいろな場面でコミュニケーションが必要な仕事です。母語の広東語だったらもっと楽しいんでしょうけど(笑)。やっぱり言葉の壁は一番大変です。だけどラッキーなことに、私が扱うのはアートです。身振り手振りや紙に描くことで、なんとか通用することが多いから、どうにかなっています。あとは、私が外国人だから易しい日本語で話してくれる人も多いんです。そうやって気を遣ってもらわなくても話せるように、勉強をがんばらなければと思っているんですけどね(笑)。
—これまで特に思い出に残っているプロジェクトは?
李:全部と言いたいところですが(笑)、強いて言えば、毎年夏に開催するキャンプですね。2013年のテーマは「竹」で、みんなで美術館の裏にある竹林から竹を切り出して、6mもの竹を使って屋内に5つのテントをつくりました。参加者は小学校1年生から6年生で、作家と一緒につくるんです。美術館は泊まることを目的とした建物じゃないから、食事の準備だけで大ごとです。スタッフ全員でなんとか準備しました。お風呂の場所もないから移動式のシャワーを借りてきたりもして。ともかく楽しかったです。
いつかは香港で、学んだことを活かしたい。
—とても気持ちよく仕事をしていらっしゃるような印象です。
李:そうですね。それに、市原湖畔美術館は新しい美術館なので、他の施設と比べても、提案が通りやすいんだと思います。美術館のスタッフも信念があるから、私の提案に対して、真剣にアドバイスしてくれて、それが嬉しいんです。あとはフラムさんの存在。仕事のことに限らず、人と社会の関係や、芸術祭などにどんなコンセプトを持って挑むかという思想は勉強になります。長年の経験から出てくる重みのある言葉から学ぶことは多いです。そういう言葉に直接触れられるのは、すごくラッキーなことだと思っています。
—来年はまた越後妻有で芸術祭が行われて、李さんもスタッフとして関わると思います。
李:来年の芸術祭には、香港から中学生のボランティアも来る予定で、そのお手伝いをするのがこれから楽しみです。アートの交流だけではなく、地元の農家との交流も体験してほしいです。
—子ども達のコーディネートは、市原で培ったワークショップの経験が活きますね。芸術祭や市原での仕事について、これからの展望はありますか。
李:ここ市原には、ゲームセンター以外の遊び場が少ないんです。私の目標は、企画展やイベントをさらに魅力的なものにして、地元の子ども達が週末に遊びに行く場所の選択肢にこの美術館加えてもらうことです。美術館に入らなくても周りの芝生にピクニックに来てもらうだけでもいい。東京からも意外と近いですし、晴れたら気持ちいいですし。
—美術館をもっとオープンな場所にしていきたい、ということですね。いずれは、香港に帰りたいですか?
李:もちろん帰りたいです。いつになるか分からないけれど、私のふるさとは香港ですからね。帰国したら、妻有や市原で勉強したことを次の仕事に結びつけたい。香港の若い人たちが、もっと日本でちゃんと勉強して、そこで学んだことを生かせるようになればいいと思います。そうすれば、香港ももっと元気になるはず。
—香港人の李さんから見て、日本から学べることはあるんでしょうか?
李:たくさんあると思います。特に私は、妻有と市原で少子高齢化の問題をたくさん見てきました。そろそろ香港も同じ問題が顕在化してきています。香港は、開発過剰な社会です。だから、これまでの経験を活かして、都市と地方を共存させることで、地域を活性化させられるような仕事ができたらなと思っているんです。
Favorite item