新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言や、補償が不明瞭な状況の中での自粛要請を受け、多くのミニシアターが閉館の危機に晒されている。そのような状況を受け、4月13日にMotion Galleryでスタートした「ミニシアター・エイド(Mini-Theater AID)基金」は、クラウドファンディングを使って小規模映画館への支援を募っている。当初の目標であった1億円は3日で達成されたが、自粛要請が長期化する懸念も想定される。
そうした状況を受け、深田晃司監督とともに「ミニシアター・エイド基金」の発起人を務める濱口竜介監督にオンラインインタビューを実施。本クラウドファンディングを実施するにいたった経緯から、まだまだ補償が明確にならない行政、公共に対しての胸中、コロナ禍で表出した日本社会の課題を語ってもらった。
写真は、2018年8月のインタビューで撮影されたもの(参考:『寝ても覚めても』濱口竜介監督が導く、日本映画の新時代)
映画を守るというより、映画に携わる人たちの「暮らし」を守ることが第一かなと考えています。
―ミニシアター・エイド(Mini-Theater AID)基金は、映画のつくり手の方々が動いてくださったことが、大きな動きに繋がっているのではないかと感じています。どう立ち上がっていったのでしょうか。
濱口:自然発生的ですね。僕はまずは身近な人に声をかけていきました。その中にMotion Galleryを運営している大高(健志)さんもいたんです。そして、大高さんに連絡した1時間後くらいに深田晃司監督から「僕もクラウドファンディングを考えていて、さっき大高さんに電話したんです。一緒にやりませんか」と電話がかかってきて、翌日からミーティングをはじめました。深田さんは、国や公に対する「SAVE the CINEMA」という、より長期的で広範囲な動きの中心人物の1人でもあるので、ごく自然とSAVE the CINEMAとも連携して動いていくことになりました。

映画監督。東京藝術大学大学院修了制作『PASSION』(2008年)が国内外で高く評価され、演技経験のない4人の女性を主演に迎えた前作『ハッピーアワー』(2015年)がロカルノ、ナント他の多くの国際映画祭で主要賞を受賞。2018年『寝ても覚めても』で初の商業映画を監督した。「ミニシアター・エイド基金」発起人を務める。
―ミニシアターに対してアクションを起こそうと思ったきっかけはなんだったのでしょうか。
濱口:名古屋シネマスコーレの坪井(篤史)副支配人のnoteのインタビュー記事を読んだことが直接的なきっかけでした。そのときすでに外出自粛要請が出ていて、どんどん客足が遠のき、本当にまずい状態だと。シネマスコーレでは過去に自分の作品を上映していただいたことがあり、坪井さんにもお会いしたことがありました。そのため、ダイレクトに伝わってくるものがあり、「知っている人が困っている、なんとかしないと」というすごくシンプルな気持ちが湧いてきました。
ただ、単に個人的な思いでは十分ではないので、ミニシアターに対してクラウドファンディングを行う上で、「社会的に意義のあること」として呼びかけるため言語化していったところ、「緊急性」と「重要性」にたどり着きました。緊急性というのは、客足が途絶えてしまったとき、経営基盤の弱いミニシアターは確実に閉館が目に見えている状況で、既にタイムリミットが切られているということ。対して重要性は、現在の映画上映の多様性はミニシアターが支えているということです。スクリーン数としては日本全体の1割程度しかないミニシアターで、年間上映タイトルの7割が上映されています。世界各国の多様な映画を受容できているのはミニシアターのおかげ、という事実があるということ。この緊急性と重要性を言葉にして、皆さんに届けるように動くことを決めました。
―先日行われたDOMMUNEの記者会見で濱口監督は「映画に関わる人の暮らし」についてお話されていたのが印象的でした(参考:「ミニシアター・エイド基金」深田晃司、濱口竜介らが記者会見)。
濱口:当たり前の話ですけど、どの映画館も運営している人がいます。そして自分は今まで映画監督として映画をつくり、いろんなミニシアターで上映していただき、劇場の方々とお会いしてきました。「あの映画館はあの人がやっている」というように、支配人やスタッフの顔と結びついていて、「映画館」という抽象的な存在ではなく、具体的な一人ひとりの生によって構成され、営まれている場所だと感じています。
ミニシアターで働く人たちは、なにがしか映画に対する思いや志をもっています。今回改めて、その志の周りに人が集まっているんだと思いました。守ろうとしている「ミニシアター」とか「映画」とは、具体的にその人たちの暮らしや営みのことなんだと感じています。その人たちの「暮らし」を守ることができれば、必然的に映画を守ることにつながります。僕個人としては、緊急支援策としてのミニシアター・エイドのクラウドファンディングでは、映画を守るというより、映画に携わる人たちの暮らしを守ることが第一かなと考えています。
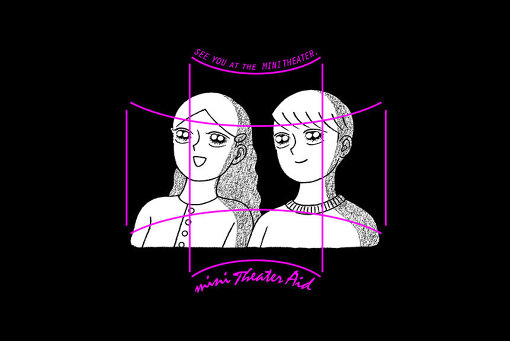
非日常でなにが起きるかということは、これまでの日常でなにをしてきたかによって左右されると思うんです。
―濱口監督は『ハッピーアワー』(2015年)のときにもクラウドファンディングを実施されていますが、そのときの経験を今回の「ミニシアター・エイド」ではどのように反映したのでしょうか。
濱口:クラウドファンディングは、まだものができる前に「できあがるものにはこういう価値があります」と説明し、その価値に対して投資をしてもらう、応援をしてもらうというシステムです。ネット社会がくれた、非常に可能性に満ちた仕組みだと思っています。ある未来のビジョンが提示され、そこに価値を感じる人、共鳴する人はお金を払い、その価値創造に対して参加することができる。そして、その価値の社会性が高ければ高いほどお金を集めやすいという実状もあるので、経済と社会を結びつける手立てとしても、すごく意義のある仕組みだと思っています。
『ハッピーアワー』のタイミングでは、まだクラウドファンディングがそこまで世の中に浸透していなかったので、「価値を信じてくれている人たちがどれくらいいるのか」ということが不安で、リターンをたくさん用意することにしました。その結果、目標額は達成できたのですが、その後のリターン対応がすごく大変で……(苦笑)。そのとき、このようなやり方では未来に疲弊してしまうので、リターンにではなく、プロジェクト自体に価値があることを伝えていくプレゼンテーションをファンディング開始時にすることがすごく大事だと気づきました。今回は僕がお金の受け取り手ではありませんが、劇場の負担をできるだけなくすことがそもそもの目的なので、支援者になることが最大の価値であると伝わるようにプレゼンテーションをしていこうと思いました。
―ミニシアター・エイドの動きや反応を見ていると、映画やミニシアターの持つ価値が、改めて世に伝わり、ミニシアターを知らない層にも魅力が届いていく機会になっているようにも感じています。
濱口:僕個人としては、このクラウドファンディングは今までミニシアターに通っていた人やミニシアターの価値を認識している人、今、映画が大事だと思っている人たちにちゃんと伝われば成立すると思っていて、人の価値観や優先順位を変えようとするものではありません。
ただ、今までミニシアターを知らなかった人たちが、この活動を見て「人がこんなに必死になって守ろうとしているものが、どうもこの世の中にあるらしい」ということを認識し、興味を持ってもらえたらより嬉しいです。みんなが自発的に生き生きと思い入れについて語る、そういう場所がミニシアターなんだ、映画館なんだということが伝わり、再開したら行ってみようかな、と思ってくれたら最高の結果ですね。
―濱口監督ご自身にも、ミニシアターから呼び起こされる記憶や思い出などあるんでしょうか。
濱口:ミニシアターの記憶はたくさんあるのですが、観客というより監督として覚えている体験としては、東京藝術大学大学院の修了制作でつくった『PASSION』(2008年)を修了制作展として、1日だけユーロスペースで上映したときですね。上映する前に『映画芸術』や『NOBODY』などでインタビューを掲載いただいたこともあって満席になったんです。そのとき、ご出演いただいた渋川清彦さんが、「映画っつうのは映画館で観るもんです。」とおっしゃっていて、満席の光景と相まって、すごく腑に落ちたんです。本当にそうだなって思って、その言葉は今でも自分の中に残っています。
―特集上映など、上映作品のラインナップも各ミニシアターの個性や魅力ですよね。濱口監督が感じる、映画を上映すること以外でのミニシアターが持つ魅力ってどんなところだと思いますか?
濱口:ミニシアターには、「この映画を上映したい」、そして「この映画は上映する価値があると思っているから上映した」という強い思いが劇場からのアクションとして伝わってくるところがあると思っています。たとえば渋谷のイメージフォーラムでは、入ってすぐ受付の向かいに、今上映している映画を紹介する記事のコピーが貼ってあります。シネコンではあまりそういうことはないですよね。それは、この映画は一体どういう価値があるのか、どういう観方があるのかということを、劇場側が主体的に提示してくれているものだと思っています。
また、神戸の元町映画館は、1階が劇場で2階がイベントスペースになっていて、その2階のイベントスペースでは、上映が終わったあとにトークイベントなどが行われる交流の場にもなっているんです。そこで、子どもを預けて母親が映画を観られる「託児付き上映」のようなことが実施されていたことも印象的でした。観客とスタッフが互いに「顔が見える」映画上映の仕方を探求しているのがミニシアター、だといえるかもしれません。
―そうした映画館への思いもある一方で、以前から濱口監督は、ご自身の作品を配信で公開されている映画監督でもありました。映画館で映画を観ることと、配信で映画を観ることの違いについての考えを教えていただきたいです。
濱口:今も「LOAD SHOW」というサイトで自作を2本見ることができるのですが、それらの作品を公開したのは、ちょうど東北でドキュメンタリー映画を撮っている時期でした。東北にもミニシアター系の劇場はあるのですが、東京に比べると圧倒的に数が少なく、映画に対する「渇き」をすごく感じました。映画館はどこにでもあるわけではないし、シネコンでは上映されないような多様な映画をかけてくれるミニシアターがないところにまで映画を届けるためには、配信はとても大事な仕組みだと思うようになりました。オンライン配信は、文化的格差を埋める可能性のあるものです。
映画に対する「どうしても見たい」という渇きさえあれば、配信でも集中力をもって映画を見ることができると思います。ただそれでも、昼間だと部屋は明るいし、スマホが鳴ったら気になってしまう……。そんな中、画面や音響そのものに集中することは非常に難しいと思います。実はオンラインで見ることで、改めて映画館がどれだけ優れた視聴環境なのかということがわかるというサイクルがあると思います。現代において、ネットワークを断ち切って、目と耳を完全になにかに差し出すっていう体験というのは、劇場とかそういう空間でないとなかなか難しいですよね。そして、集中体験によってしか得られない体の感覚というのがあって、その身体感覚そのものが現代では、ものすごく貴重なものなんです。それで得た体の感覚は、やがて自分の体を動かしていくものになります。簡単にいえば、映画館で映画を観たから、映画監督になっているんです。映画産業という生態系の中で、やはり映画館はつくり手を生み出す土壌として、決定的な役割を持っています。絶対に必要な場所だと思っています。
ただ現在は物理的に映画館はあっても、開くことができない状況です。そんな中、やはりオンラインで公開を決める人たちもいて、想田和弘監督が配給会社の東風と「仮設の映画館」というデジタル配信の場で『精神0』を公開していますね。配給会社と映画館をともに支えるという観点から、非常に素晴らしい動きだと思っています。

―興行収入の配分方法も含め、よい仕組みですよね。映画館を営業することができない、映画館で映画を観ることができないなど、できていたことができない今だからこそ、気づけたことや、見えてきたことはありますか?
濱口:今は社会の誰もがまさかこんな状況になるとは想定していなかったある種の非日常が始まっていると思うんですけど、非日常で起きることはすべて、これまでの日常でしてきたことの延長線上にある、ということを改めて思います。記者会見のときに深田さんが「今我々は、自分たちが政治的な関心を払ってこなかったそのツケを払わされている」とおっしゃっていましたが、それも1つの結果。そして、今回のクラウドファンディングのように、ミニシアターに対して3日で1億円が集まったことも、今まで日常の中で営まれていたことの1つの結果なんです。今まで各地のミニシアターがやってきたことに対する価値がみんなハッキリとわかっているから、これだけ早く、多くの人たちが賛同し、参加してくれたんだと思います。
これからも、日常という形で営まれていくものはあると思うんですけど、同じ暮らしが戻って来るとは全く思っていません。コロナ禍の状況はまだ長く続いて、それが新たな日常の一部になっていくでしょう。今まで日常だと思っていたものを部分的には取り戻せるかもしれませんが、これからはもう全く違うことが起こり、取り返しがつかない形で変わっていくのだと思っています。
今必要なのは、みんながみんなその変化に耐えられるような態勢づくりをするということです。クラウドファンディングという試みは、そのための「余裕」を分配するためのものです。今かろうじて余裕のある人が、明らかに余裕のない人に分配することによって、社会全体が余裕を保つように少しバランスを取る。そうしてこの変化をできるだけ多くの人が耐え抜けるようにする。そういう動きだと思っています。

これからの日本の社会にとって重要なのは、ある種の率直さなのではないかと思います。
―ミニシアター・エイドの動き、そのほか署名やクラウドファンディングなどの互助の動きが働くこと自体は素晴らしいと思うのですが、あくまで市民同士によるアクションになりますよね。国や公と市民の関係でこうした動きが起きないことに強い抵抗を感じます。
濱口:私もその意見に概ね賛成です。このクラウドファンディングがガス抜きになってはいけないし、「うまく集まってよかったね」という話にはなっては絶対にいけないと思います。公共的な補償がミニシアターに届くまでは時間がかかる、もしくは届かない可能性もあるという危機感があり、我々も追い詰められて始まったアクションなので、本来はやはりこうした支援が可能になるような仕組みが、日常からあるのが望ましかったと思います。
ミニシアター・エイドは政府に長期的に働きかけるSAVE the CINEMAと連動していて、セットでの動きであると思っています。ミニシアター・エイドだけでは緊急支援にしかならないです。仮に150万円を分配しても1カ月ももたない劇場が非常に多いということを、ヒアリングしていくうちにわかってきました。ミニシアター・エイドは、劇場主にとってつかの間の精神安定剤にはなるかもしれないけど、ある種、焼け石に水ではあると思います。余裕があるところからないところへの再分配は、本来は政府が担う役割で、現状そこが上手く機能していないというのが問題ですが、更に深い問題があるとすれば、そういう風になる状態まで放ってしまっていたということ、我々が関心を払わずにここまで来てしまった、ということでもあります。

―先ほど濱口監督は「同じ暮らしが戻って来るとは全く思わない」とおっしゃいましたが、非常時には、取り返しのつかないレベルで「日常」が変化する一方で、不変の「倫理観」「正しさ」のようなものを求める風潮もまた、強くなると思います。監督が東日本大震災を取り扱った『寝ても覚めても』(2018年)を観たときには、その「正しさ」の概念すらも揺さぶられる感覚があったのですが、非常時の「正しさ」を描く上で、監督が意識されていた部分はありましたか?
濱口:非常時は、普段の倫理観や社会規範の中では許されないことも正当化されてしまいます。究極的には、自分自身を保つためにはなにをしてもいいということが起こり得るので、非常時は物事を考える上でのベースにはならないと思っています。結局、日常をどう過ごすか、どうつくっていくかというのが一番大事なことです。「正しさ」は日常のコミュニケーションから合意形成されていく必要があるし、非常時であってもそれが拠りどころになります。
『寝ても覚めても』(2018年)の話でいうと、朝子というキャラクターは単に、自分自身に対して率直な行動を選んだだけです。それは「正しさ」とは無縁の話です。ただ、これからの日本の社会にとって重要なのは、ある種の「率直さ」なのではないかとは、ずっと思っています。
濱口:(「率直さ」について話すために)少し迂回しますが、「責任」という言葉にはざっくり分けて、責める・咎めるという意味の「blame(ブレーム)」と、日本語に直訳すると応答能力という意味の「responsibility(レスポンシビリティ)」という2つのニュアンスが含まれています。現在の日本では「責任」というとき、人を咎める「ブレーム」の意味のほうが肥大化していますよね。たとえば「自己責任」という言葉は多くの場合、なにかした人を咎めるために発せられます。一方で「レスポンシビリティ」は空疎化している。総理が不祥事を起こした大臣の「任命責任は私にある」といってもなにも行動を取らなかったり、記者会見で批判的な質問に対して官房長官が「その批判は当たらない」で済ませてしまう。「応答能力」としての責任の空疎化とは、たとえばそういうことです。もちろん責め・咎めの「ブレーム」は社会を維持していく上で間違いなく大事なんですが、恐らく日本の社会と折り合いの悪い「レスポンシビリティ」としての責任を我々がずっと育てて来なかった、そのアンバランスが問題の根っこではないかと思います。
なぜ日本と「レスポンシビリティ」が折り合いが悪いかといえば、本音と建前というのが行動のベースになっている、つまりは率直じゃない社会だからです。応答したようでしない、ということが行動様式の根本にある。前に元官僚の方が「私の行動原理は、面従腹背なんです」といいました。それは、組織の中で自分の誠実さを貫くための態度をいい表したものとは思ったんですが、非常に日本的だと思ったことも覚えています。
この面従腹背をすべての人がするとなにがおきるかといえば、トップの立場の人の命令に、ナンバー2の人は従ったフリをするけれど、ナンバー3に「上はAといっているけど、Bにしておけ」と指示をする。命令は、公的な「法」に基づいたものと、不文律としての私的な「掟」に基づいたものに二重化します。下の立場になるほどその二重性がどんどん積み重なっていく。「掟」は重層化して、すべてを同時に遂行するには複雑すぎるものになります。「空気を読む」とか「忖度する」というのは、この複雑に積み重なった「掟」を読み解く、ということですよね。ただ、それが「動くこと」の社会におけるコストを非常に高くしています。どれだけ考えても、十分にその場の掟を読み解けるかはわからないので結局動かない、もしくは今の場を保つことが一番安全な選択肢になります。なぜなら、今起きていることが誰にも咎められていないなら、現状こそがその場の「掟」にかなっていると考えられるからです。そうして動くことなく、現状をひたすら追認することが行動のベースになる。
これは、現在の日本社会全体に根づいてしまっていることなので、これを変えていくのは生半可なことではありません。でも、それが今起きていることの理由だし、それは変える必要があります。わずかでもそこを変えていくには、一人ひとりが「レスポンシビリティ」を高めていく、応答能力としての責任を身に着けていくことしかないんだろうと思っています。そして強調したいのは、応答能力の一番の基本は「聞く力」だということです。問いを聞き取らなければ、正確な応答をすることは不可能だからです。それは相手から、自分に対する「NO」の意見まで率直に引き出すような聞き方、聞く態度になるでしょう。ときには自分自身の立場や力を弱めるようなコミュニーケーションのしかたが必要になると思います。
しかし、それをすることによって自分自身が率直さを失ってしまって、自分の態度がおもねりや媚というものに変わってしまうとしたら、別の問題が生じています。「面従腹背」に回帰している。そこで重要なのが、その聞く態度を自分にも向けて、自分自身からも率直な意見を引き出していくということです。その自分の意見とは、やっぱり他者への「NO」になるのかもしれません。ただ、他者への「聞く」態度と組み合わさったとき、その率直さは攻撃的なものというより「やわらかい率直さ」として現れるはずです。このやわらかさは、必ずしも日本的なものと相反しないとも思います。この態度が「自分も相手も同時に、率直である」ための基盤になります。それによってシンプルで、精度の高いコミュニケーションが可能になります。もしそれができれば、「動く」ことのリスクやコストは、少なくともその相手と自分の間ではグッと下げられるはずです。まず、私とあなたが率直になる。その輪をだんだんと、少しずつ広げていく。
ただ、自分だってできているかわからないことなので、人にそうしろとはいえません。基本的にはまず自分が他者に対して、やわらかく率直な態度を身に着けたいと思っています。できる限り多くの人が、やわらかい率直さを身に着けられたら、なにかが変わるのかもしれないとは常々思っていますが、先程もいったようにそれは生半可なことではないです。自分自身から、少しずつ始めていくしかないんだと思います。

- プロジェクト情報
-

- ミニシアター・エイド(Mini-Theater AID)基金
-
新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言が発令され、政府からの外出自粛要請が続く中、閉館の危機にさらされている全国の小規模映画館「ミニシアター」を守るため、映画監督の深田晃司・濱口竜介が発起人となって有志で立ち上げたプロジェクト。5月14日中旬までクラウドファンディングを実施中。
- プロフィール
-
- 濱口竜介 (はまぐちりゅうすけ)
-
東京藝術大学大学院修了制作『PASSION』(08)が国内外で高く評価され、演技経験のない4人の女性を主演に迎えた前作『ハッピーアワー』(15)がロカルノ、ナント他の多くの国際映画祭で主要賞を受賞しその名を世界に轟かせた気鋭・濱口竜介。原作に惚れ込み映画化を熱望した『寝ても覚めても』で満を持して商業映画デビューを果たす。日常生活の中にある人間の感情や、人間関係、人々が暮らす街の姿など、普段見過ごしてしまいがちな細かい場面にまでこだわる演出で、繕いのない本当の人間らしさを映像に映し出す。特集上映の度に満席続出になるほど日本の映画ファンに熱狂的な支持を集めている。『ハッピーアワー』は、5月にフランスでも公開されて10万人を動員する大ヒットを記録。『寝ても覚めても』が初の世界三大映画祭出品でありながら、カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出されるという快挙を成し遂げ、「近年稀に見る新たな才能の出現!」「日本のヌーヴェルヴァーグ!」など海外メディアも称賛。今世界が最も注目する日本人監督となった。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-


