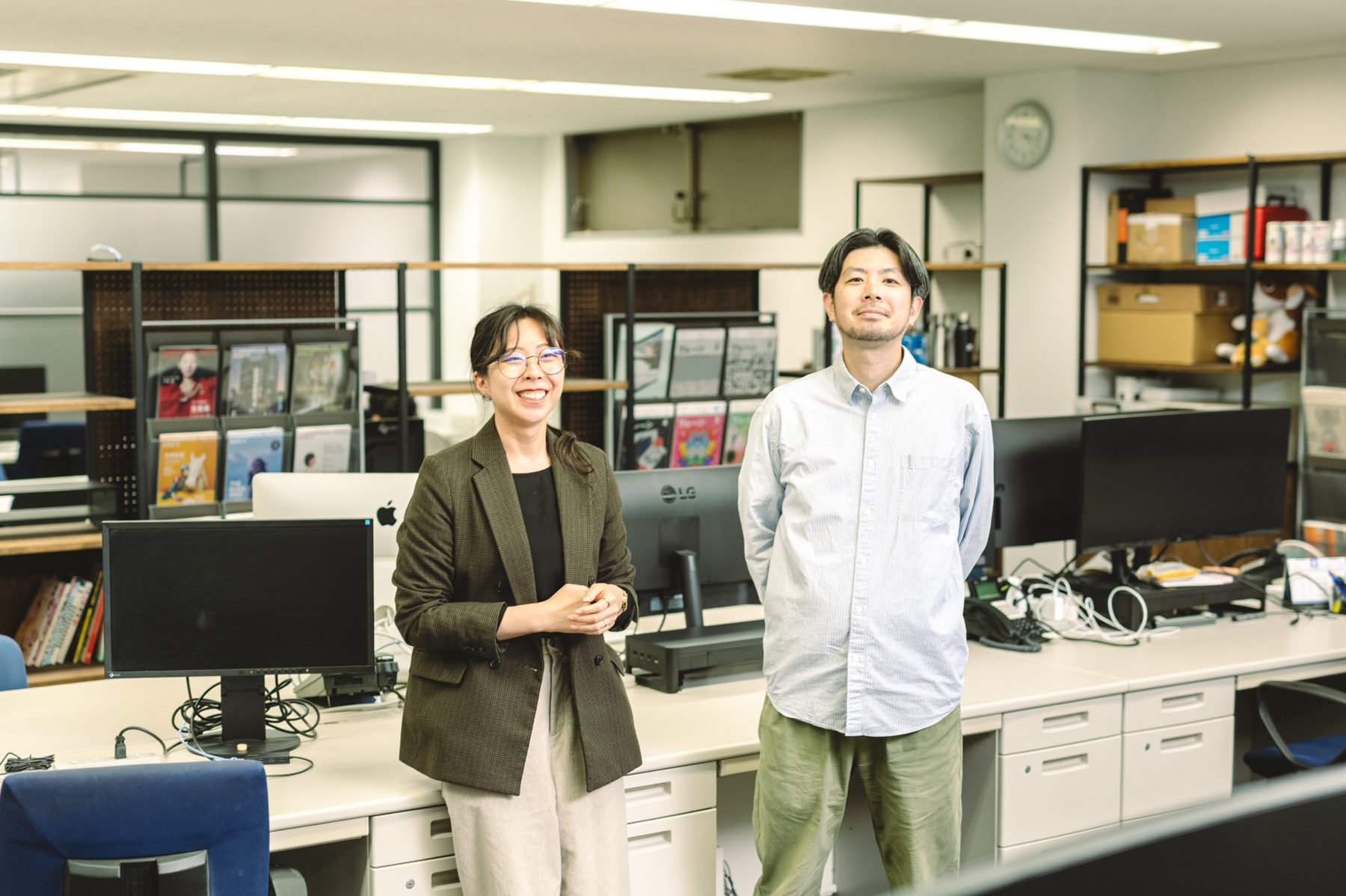フリーランスから会社員へ。マンガ編集者・豊田夢太郎が語る、後悔しない選択
- 2020.12.25
- SERIES
- 取材・文:辻本力
- 編集・撮影:𠮷田薫(CINRA)
Profile
豊田夢太郎
1973年生まれ。実業之日本社『漫画サンデー』編集部勤務を経て、2002年よりフリーランスに。小学館『月刊IKKI』専属契約編集者として従事し、同誌休刊後は『週刊ビッグコミックスピリッツ』増刊『ヒバナ』、マンガアプリ「マンガワン」(ともに小学館)の専属契約編集者を経て、2019年より株式会社ミキサーに所属。ミキサー編集室編集長を務める。以降、「マンガワン」「LINEマンガ」(LINE Digital Frontier)「モーニング・ツー」(講談社)ほかで担当作品を持つ。また、2015から17年に京都精華大学マンガ学部マンガ学科マンガプロデュースコース非常勤講師(編集実践演習、編集実習)として勤務。第24回文化庁メディア芸術祭マンガ部門選考委員も務める。
「18時半には飲みに行く」。意外にのんびりだった『漫画サンデー』編集部時代
高校生くらいまでは「普通に、ちょっとマンガ好きな人」だった豊田さんが、マンガにのめり込んだきっかけは、大学の音楽サークルだったという。妙にマンガ好きが集まっていたことから、過去の名作からアングラ系まで大量に読み漁ることになり、その奥深さに魅了され、編集者を志すことに。
豊田:就職活動はマンガを扱う出版社に絞り、唯一受かったのが実業之日本社。入社後、念願叶って、希望を出していたマンガ雑誌『漫画サンデー』(2013年休刊)の配属になりました。当時の『漫画サンデー』は、ヤクザ、ギャンブル、女、義理人情みたいなテイストの作品が人気の、いわゆる「おっさん向け」のイメージが強い雑誌でした。少なくとも、新卒の若者に人気、とは言えない配属先ですね(笑)。でも、かつては杉浦日向子先生、内田春菊先生、近藤ようこ先生が描かれていた時代があり、ぼくはその頃の作品が大好きで。思い入れのある雑誌だったので嬉しかったです。

マンガ編集者といえば、描けない作家に張りついて必死に原稿を催促したり、連日徹夜で編集部のソファーで寝泊まり——といったベタなイメージもあるが、豊田さんが配属された当時の『漫画サンデー』は、思いのほかのんびりとしていたそうだ。
豊田:作家さんが全員ベテランなので、締切をちゃんと守ってくれるんですよ。1時間と変わらず、毎週同じ曜日の同じ時間に原稿が上がる。残業もほとんどなかったし、校了日じゃない日は、18時半くらいには上司と連れ立って飲みに行く、みたいな世界でした。ぼくが就職した1990年代の終わりは、まだバブルの残り香がちょっとあった時代で、出版業界に余裕があったんですよね。まあそこから、現在まで続く長い不況に突入するわけですけれども……。
豊田さん曰く「いまじゃ考えられない」ような穏やかな環境でのキャリアスタートとなった。当時、特に印象に残っているマンガ家を尋ねると、『メッタメタガキ道講座』などで知られるギャグマンガの大家、故・谷岡ヤスジさんの名前が上がった。
豊田:引き継ぎで担当になったんですけど、初めて一人で原稿をいただきに向かったら、指定された日に、事前にお電話差し上げてからうかがったにもかかわらず「できてるわけねえだろ! お前の思うとおりに原稿が上がると思ったら大間違いだからな! 明日出直して来い」と怒られてしまって。次の日、おそるおそる菓子折を持って謝罪にうかがったら、なぜか大笑いしてるんですよ。そしたら、「俺、新しい担当には必ずこういうことやるんだ」って。一種のプレイだったわけです(笑)。その日は「お前、余裕あるだろ? 俺は本当の締め切り日時も把握してるんだ。ちょっとビール飲んでけ」って、鰻とビールを用意してくださって。
晩ご飯やお酒をご一緒しました。「結婚したいんですよね」みたいなプライベートのことも相談したりして。早くに亡くなられてしまったことが残念でなりません。思い出深い、大事な作家さんの一人です。『漫画サンデー』編集部では、こういった作家さんとの交流も含めて、とても貴重な体験をさせてもらったなと思いますね。

え、契約社員のはずでは……? 編集部所属の「フリーランス編集者」になったワケ
実業之日本社を辞め、フリーランスになったのは勤め始めて6年目、28歳のとき。よく「30歳を前に、これからを考えて」フリーになったり転職をしたりする話は耳にするが、どういう理由からだったのだろうか。
豊田:同年代の作家さんと仕事をしてみたかったんです。当時の『漫画サンデー』は、新人や、20代の作家さんがまったくいない媒体だったので、同年代の方と面白いマンガを一からつくる、みたいなことに憧れがあって。そんなとき、小学館の『週刊ビッグコミックスピリッツ』の増刊号として発行された『スピリッツ増刊IKKI』(2000年)を読んだら、その内容が本当に素晴らしかった。あまりに好きすぎて、当時小学館に勤めていた友人に仲介を頼んで、編集長の江上英樹さんに会いに行きました。吉田戦車先生の『伝染るんです。』や、江川達也先生の『東京大学物語』などを手がけた敏腕編集者です。
「いま務めている会社には内緒でアルバイトさせてほしい」と、江上さんにお願いしたんですけど、「さすがに、それは難しい」と。でも、それから半年後くらいに連絡があって、「『IKKI』が月刊誌として独立創刊することになったので、ついては会社を辞めてウチに来ない?」と誘われ、悩んだ末に行くことにしました。

2003年、こうして月刊化1号目から『月刊IKKI』編集部に参画することになったが、いきなり予想外の事態に直面することになる。
豊田:「契約でウチに来ない?」と言われていたので、てっきり契約社員だと思ってたんですよ。福利厚生もあって、1年契約みたいな話かなと。でも、いざ蓋を開けてみたら業務委託契約だった。ということを、入ってから知らされて「マジか!」と。それがわかってたら、もうちょっと悩んでたかもしれないですね。
こうして豊田さんの、大手出版社の編集部にフリーランスとして身を置く、という働き方が始まった。
豊田:この雇用形態に不安がなかったわけではありませんが、それでも働くことにしたのは、まだ若かったのと、雑誌のクオリティーや可能性を考えたとき、すぐに休刊にはならないだろうし、しばらくはここではやっていけそうだな、という確信があったからですね。
なお、『IKKI』編集部は、編集長と副編集長以外はすべてフリーランス、というマンガ編集部としてはやや特殊な形態を取っていた。フリー編集者同士は、境遇が近いゆえの親近感とともに、ある種の切迫感も共有していたという。
豊田:やっぱり連帯感はありましたね。自分たちは何かあったら切られてもおかしくない立場である、ということはみんな了解していましたから。それゆえに、自分たちの居場所は自分たちで守らないと食いぶちがなくなるぞ、みたいな気持ちを共有していたように思います。外からは好き勝手にやってるように見えていたと思いますが……。
大好きな作家との仕事が実現。しかし紙のマンガ誌不況で2誌連続休刊に
『IKKI』はマンガ好きからの支持も厚く、優れた作品を多数、世に送り出すとともにメディアミックスの成功もあり、低空飛行ながらもどうにか刊行を続けられていた。そして、「同年代の作家と一から作品をつくってみたい」という願いは、ここで叶えることができた。
入って最初に担当した作品のひとつがジョージ朝倉先生の『平凡ポンチ』でした。先生とは同年代で、しかも当時比較的近所に住んでたんですよ。編集部に入ってすぐに、前から大好きだった作家さんと、『IKKI』という媒体でしかつくれないとんでもない作品をつくれた、という手応えがありました。
また、『IKKI』には新人賞があったので、それをとおして野田彩子先生や、亡くなられた青山景先生といった作家さんのデビューに立ち会えたのも貴重な経験でした。

ジョージ朝倉『平凡ポンチ』1巻(小学館)

デビュー作を担当した青山景先生が作画を担当した『ピコーン!』(原作:舞城王太郎 / 小学館)
しかし、豊田さんの目の前に、次第に暗雲が立ち込め始める。コアなマンガ好きに支えられ、一定の人気を保ってきた『IKKI』だったが、紙のマンガ誌不況が吹き荒れていた2013年に休刊が決定。その後継誌として2015年に新雑誌『ヒバナ』が創刊されるも苦境は続き、こちらも2年ほどで幕となった。仕事をしていた雑誌が連続で休刊の憂き目に遭った豊田さんは、仕事がなくなるという恐怖心から、大学でマンガ編集を教える非常勤講師など、編集以外の仕事も積極的にやった。
豊田:妻からは「どこかの会社の正社員として、就職してほしい」と言われてましたし、当時は、子どもが小さかったから不安も大きかったですね。自分なりにいろいろ考えざるを得なかった時期でした。
「マンガ編集」を題材とした大学の講義を受け持ったのも、あるいは同じ時期に、さまざまなマンガ編集者の方にお話を聞いた『漫画編集者』(木村俊介著 / フィルムアート社)というインタビュー集を企画したのも、同じ問題意識が根底にあったから。ぼくは、いまにいたるまで一度も「ヒットメーカー」であったことはないので、そんな自分が「40歳過ぎてもマンガ編集者として生きていくにはどうしたらいいか?」「できないのであれば、いま自分に足りないものは何なのか?」それを知りたかったんです。正直、答えが見つけられたわけではないのですが、マンガ業界や出版業界、編集者という仕事を俯瞰できた時間は、いまの自分につながる大事な時期でした。

そうした自問自答の日々を経て、豊田さんは小学館のマンガアプリ「マンガワン」の専属契約編集者に。その後、専属は外れた形で引き続き同アプリの編集にも携わりながら、アニメの制作・宣伝・声優のマネジメントなどを手がける株式会社ミキサーのマンガ編集部門「ミキサー編集室」に正社員として所属し、編集室の制作物に一通り目を通す編集長を務めている。マンガに特化した編集プロダクションで、マンガアプリやWEBメディアからの要望を聞き、それに応えるかたちでマンガ家と組んで作品をつくり上げているという。
豊田:もともとは、フリーランサーのギルドをつくりたかったんです。1人の編集者が、特定の媒体に縛られないかたちでいろいろなところで、いろいろな作家さんと、いろいろなジャンルの作品をつくれる場所です。でも現実的には、お財布だけ一緒にして活動はフリーランスにするというのはなかなか難しく、いまの編プロ的なスタンスに落ち着きました。

ミキサー編集室のホームページ。イラストは鎌谷悠希先生の描き下ろし。
豊田:単純に、ミキサー編集室に身を置かせてもらっているというわけではなく、株式会社ミキサーからコミカライズの相談を受けたりと、お互いに頼り合いながら仕事をする環境は刺激的ですし、ある種の「ホーム」として拠り所になっています。
かつても編集部という「チーム」で仕事はしていましたが、やはりフリーランス同士なのでライバルでもありましたし、最終的に「自分の責任は自分で」というのが基本だった。いまはそれぞれが手一杯なら、仲間を頼れる。そういう意味では、安心感がありますし、そうした働き方に着地できたのは良かったなと思っています。
フリーランスから会社員になってチャレンジできたこと
ミキサー編集室への所属により、「仲間」を得ると同時に、「comico」に代表される縦カラースクロール作品(webtoon)など、ドラスティックに変容しつつある「インターネット時代のマンガ編集」のスキルを得る機会にもなったと、豊田さんは言う。
豊田:作品の掲載先がWEBなのか、アプリなのか、紙なのか。それによって内容やニーズは変わってくるかもしれませんが、「編集」という仕事自体にはそれほどの違いはないと思うんです。とはいえ、縦スクロールで読んでいくマンガなどは、これまで1ページに分割させていたコマを縦に並べ直せばOK、というような単純な話ではない。独自の編集眼が要求されるとは思います。そうした作品を扱った経験のない自分はどうすればいいのか、ということはやはり考えました。
いま、ミキサー編集室で一緒に働いている北室美由紀は、マンガアプリ・ブームの早い段階から人気を博していた「comico」で編集長を務めていた人です。ぼくはそれこそ縦カラースクロールのマンガのノウハウなんかを知りたくて、彼女と組んだようなところがある。逆に北室は横に読んでいく、いわゆる普通のページマンガをつくったことがなかった。お互いノウハウを交換し合うという目的も、ミキサー編集部にはあったんです。
また、近年、IT企業によるマンガ・ビジネスの参入のみならず、出版社が豊富な自社コンテンツを武器にWEBメディアを次々にスタートさせるなど、マンガメディア百花繚乱の様相を呈しており、編集者のニーズも増え続けているという。
豊田:IT企業や出版社だけでなく、版元や編プロに頼らずオリジナル作品を発表する電子書籍の書店も現れていたり、とにかく媒体が飛躍的に増えています。それに対して、編集者も作家さんも足りていないという状況がここ2年くらい、ずっと続いている印象です。いかんせん即戦力になる経験者の人材にも限りがある。だから、本当はマンガ編集者をゼロイチのところから育成する場がもっと必要なんでしょうけど、どこもその余裕がないから、未経験の人が参入しづらくなっているという面はあると思います。
そうした状況のなかで、ぼくがこれからやってみたいのが「下を育てる」という仕事です。これは、かつてのようにフリーランスの立場ではなかなかできなかったこと。いまはまだ3人しかいない編集部ですけど、ゆくゆくはぼくや北室がノウハウを伝え、それをもとに面白いマンガをつくる若い編集者が1人でも増えることが目標の1つにあります。

豊田さんが担当した作品。左から野田彩子『潜熱』、大島智子『セッちゃん』、浅野いにお『勇者たち』、いがらしみきお『I』(すべて小学館)
ニーズに応えるだけでいいのか? データからは見えてこない面白さ
新入社員時から約25年、マンガ編集者一筋でやってきた豊田さん。紆余曲折ありながらも、趨勢変動激しいマンガ業界で途切れることなく作品を担当し続けてこれたのは、作家や媒体からの厚い信頼はもちろん、読者の「ニーズ」に応える作品をつくってきたからこそだろう。しかし、そこには少なからざるジレンマもある。
豊田:いまは、デジタル媒体が増えたことで、「ニーズ」がPVのような具体的な数字として可視化されましたよね。こういう年代の、こういう属性の人が、こんな作品を求めて読んでいる——みたいなことがデータとしてあって、それを前提に「売れる」作品を用意することが要求される。実際、そういうオファーはすごく多いです。もちろん、可能な限り応えるべく頑張りますけど、一方で「それだけじゃないよな」とも思ってしまうこともあります。

豊田:かつて『漫画サンデー』の編集長から言われて、すごく感動した言葉があります。「編集者は名刺1枚持っておけば、誰にでも会いに行ける。『漫画サンデー』はおっさん向けの雑誌だけど、例えばマンガ以外のコラム欄とかは、雑誌のニーズとか、売れる売れないとか考えずに、自分が面白いと思う人に会いに行って頼めばいい」って。
それでぼくは、劇作家・演出家の松尾スズキさんに会いに行って「松尾さんのファンとか、たぶん1人もいないような媒体なんですけど、コラムを書いてもらえませんか」とお願いをして、書いていただいた経験があります。で、そのコラムがマンガ誌のなかにあることが、すっごい面白かったんですよね。そうした、データからは見えてこない、やってみたからわかる面白さの可能性を追求する姿勢は、こちら側のマインドとして、変わらずキープしていきたいなと思っています。
編集者は必要か? 激変するマンガ業界にいてもブレない軸とは
「データに縛られがち」など少々窮屈な部分もあるとはいえ、デジタル媒体の活況は、マンガ産業に新たな可能性を多々もたらしていることも事実。豊田さんは、近年のマンガを取り巻く状況を「作家にとって最高の時代」と語る。
豊田:Twitterに載せれば作品を簡単に見てもらえますし、見てもらえるだけではなく課金システムのあるサービスを利用すれば、お金を取ることもできる。そうした自己発信する環境が年々強化されてきています。それにより、これまでニッチ過ぎたりして成立しなかった内容の作品でも、ファンを集め、収入を得て、作品を継続的に発表することが可能になってきました。
そうした作家の自立は、時に「編集者不要論」のような言説を生む。わざわざ並走し、アドバイスをくれる存在がいなくても、現にその作品を読んでくれる読者がいる以上、問題ないのではないか、と。
豊田:クリエイティブ面から言えば、自己否定するようですが「編集者は必要です!」とは断言できないんですよね。編集者なしで優れた作品が描かれ、それが多くの読者を獲得するのであれば、それでもうなんの問題もないわけで。実際、そうした作家さんや作品がどんどん生まれています。でも、もしぼくや「ミキサー編集室」を頼ってくれて、面白い作品をつくりたいと思ってくれる媒体や作家さんがいるのであれば、できるかぎりその期待には応えたいと思っています。
変動期にあるマンガ業界に身を置きながらも、まっすぐにやりたいことを貫く豊田さん。最後に、そのブレない姿勢の根底にある、シンプルだが、重要な行動原理を教えてくれた。
豊田:身も蓋もない言い方になってしまいますが、端的に言えば、「情熱」しかないと思うんですよね。ぼくは、思えばずっと「自分が面白いと思えるマンガをつくりたい」という身勝手な願望を、将来的な生活の安定よりも優先して生きてきました。これまでも、正社員として中途採用のお誘いは何度かありましたが、「いま担当しているこの作品に、最終回まで携わっていたい」という気持ちを優先して、お断りしたり。人生において選択に迷うことは当然あったし、上手くいかないことも普通にあります。でも、情熱を傾けられる対象に殉ずることができれば、もし上手くいかないことがあっても、自分の行動に後悔はないんじゃないでしょうか。自分が言えるのは、結局そういうことだけだなって思いますね。