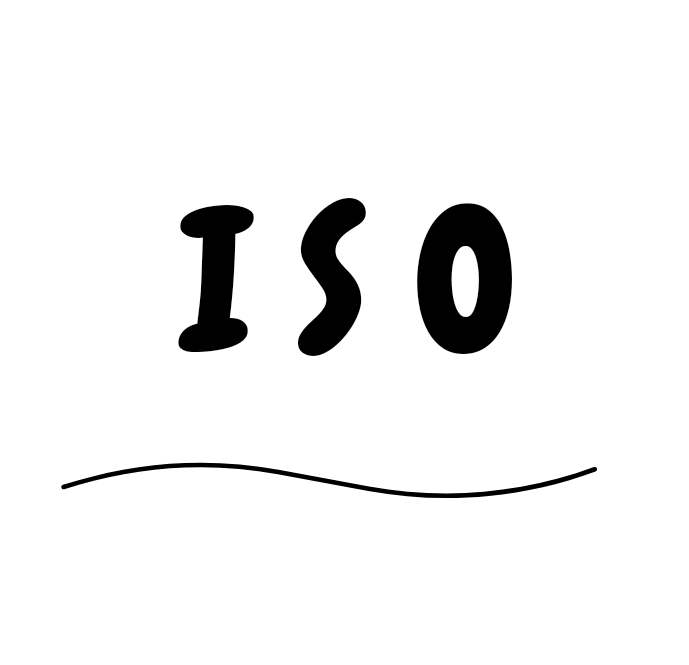© 2024 SEVEN ELEPHANTS, KINGS&QUEENS FILMPRODUKTION, HAÏKU FILMS
1月27日は、「ホロコースト犠牲者を想起する国際デー」。その日は、ユダヤ人強制収容所のアウシュヴィッツが解放された日だ。ユダヤ人をはじめとする無数のマイノリティが殺害されたホロコーストを再確認し、人種差別や偏見の危険性を警告することを目的として、国連総会が定めている。
その日が近づく1月16日、ホロコーストを生き延びた父とその娘が祖国ポーランドをめぐる映画『旅の終わりのたからもの』が公開された。原作は、リリー・ブレットの『Too Many Men』。戦争を直接体験していないものの、両親を通して痛みを抱える「第二世代」の視点から描かれる物語だ。
すでに第三世代・第四世代が生きているいま、かつての負の歴史や、いまの戦争に、私たちはどう向き合うべきだろう?
このたび、ドイツ出身の監督ユリア・フォン・ハインツがオンラインインタビューに答えてくれた。映画で反民主主義的な脅威に対して声を上げる彼女は、過去の過ちを繰り返さないために、家族を通して歴史に個人的な文脈を見つけること、世代を超えて物語を共有する必要性をまっすぐに語ってくれた。
あらすじ:ニューヨークで生まれ育ったルーシーは、ジャーナリストとして成功しているが、どこか満たされない想いを抱えていた。その心の穴を埋めるため自身のルーツを探そうと、父エデクの故郷ポーランドへと初めて旅立つ。ホロコーストを生き延び、その後決して祖国へ戻ろうとしなかった父も一緒だ。ところが、同行したエデクは娘の計画を妨害して自由気ままに振る舞い、ルーシーは爆発寸前。互いを理解できないままアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所を訪れた時、父の口から初めて、そこであった辛く痛ましい家族の記憶が語られるが……。
舞台は1991年のポーランド。本作の背景をおさらい
ポーランドは1939年、ナチス・ドイツとソ連からの侵攻を受け、20世紀のうちの長い時間を支配された苦難の歴史がある。1989年にソ連が崩壊したことで、40年以上続いた親ソ連政党による一党独裁が終止符を打ったものの、経済は深刻な落ち込みを余儀なくされた。『旅の終わりのたからもの』の舞台は、社会主義体制が崩壊した翌年、1991年のポーランドだ。

ルーシー(レナ・ダナム)=写真右=とエデク(スティーヴン・フライ) © 2024 SEVEN ELEPHANTS, KINGS&QUEENS FILMPRODUKTION, HAÏKU FILMS
本作は、ユダヤ系オーストラリア人作家、リリー・ブレットの自伝的小説が原作。ニューヨーク在住の音楽ジャーナリストのルーシー(レナ・ダナム)は、母親の死後、両親が幼少期を過ごしたポーランドで家族のルーツを探るべく、かつての住居や戦争の跡地を訪ねる。アウシュヴィッツの生存者である父エデク(スティーヴン・フライ)も一緒だ。
ルーシーの両親は、アウシュヴィッツに連行され、財産を没収されたユダヤ系ポーランド人。そんな父は、過去の経験を決して口にしようとしない。娘ルーシーは語られない家族の歴史を知りたいと望む一方で、その計画に乗り気ではない父は、トラウマを享楽的な態度で隠しながら、できるだけ娘の気をそらそうとする。

© 2024 SEVEN ELEPHANTS, KINGS&QUEENS FILMPRODUKTION, HAÏKU FILMS
『旅の終わりのたからもの』監督でドイツ人のユリア・フォン・ハインツは、アンティファ(※)から映画作家になった背景を持つ。1990年代、10代の頃から外国人排斥的な情勢に危機感を抱き、ネオナチに抵抗する政治活動家だったのだ。イスラエルに移住した第三世代のドイツ人女性が祖国の歴史と向き合う『Hanna’s Journey』(2013年)、反ファシスト活動に邁進した自身の青春時代を回顧した半自伝的な『そして明日は全世界に』(2020年)、そして本作までを「余波三部作」と位置づけたうえで、第二次世界大戦後のドイツ人への、世代を超えたナチスの影響を探求してきた。
※ 極右や人種差別主義者、ファシスト団体に反対する分散型の左派運動。
「レナ・ダナム以外の誰もこの役を演じることはできなかった」

© 2024 SEVEN ELEPHANTS, KINGS&QUEENS FILMPRODUKTION, HAÏKU FILMS
─主人公ルーシーはあたかもレナ・ダナムに当て書きされたかのようなキャラクターだと感じました。本作と同様に、彼女はこれまでも半自伝的なドラマ『GIRLS/ガールズ』(2012~2017年)で世界への好奇心に満ちた物書きを演じ、ダナム自身が抱える強迫性障害の側面を投影していました。レナ・ダナムにルーシー役を演じてもらうことが、重要でしたか?
ユリア:とても重要です。原作者であるリリー・ブレットとレナ・ダナムには、多くの共通点があります。リリー・ブレットは自身の著書のなかで、肥満とメンタルヘルスとの闘いについて詳細に綴っています。まだ世間がそういった健康問題に注目する前、1990年代のかなり早い段階から、非常にオープンに語っていました。

ユリア・フォン・ハインツ
1976年生まれ、ドイツ・西ベルリン出身。映画監督・脚本家であり、社会的・政治的テーマを扱った作品で国際的に評価されている。代表作『そして明日は全世界に』は、2020年の『第77回ベネチア国際映画祭』コンペティション部門に出品され、反ファシズム運動を描いた作品として注目を集めた。学術的な側面では、2012年に「友好的な乗っ取り—ドイツ映画に対する公共テレビの影響、1950年から2012年」というテーマで博士論文を完成させた。さらに、ケルン芸術大学(KHM)やミュンヘン映画大学(HFF)でゲスト教授を務め、2019年からはHFFの名誉教授として、テレビや映画の機能に関する研究プログラムの共同リーダーを務めている。
ユリア:レナ・ダナムのほうがリリーよりも40歳ぐらい年下なので、2世代後の世代になりますが、彼女も現代で同じような問題に声を上げ、代弁してきました。しかも、彼女たちはニューヨークのほぼ同じ地域に住んでいた。ふたりともアーティストであり、サブカルチャーに通じています。レナ・ダナム以外の誰もこの役を演じることはできなかったでしょう。
─エンドロールで、ダナムは家族や夫に謝辞を捧げていて、実際に曽祖母をホロコーストで亡くした彼女自身にとっても本作がどれほど意義深い取り組みだったか伝わってくる思いがしました。
戦争経験者の第二世代が抱える「痛み」とは?世代間トラウマをどう捉えたか
—レナ・ダナムは身体に複数のタトゥーがあることで知られています。本作では、ダナム演じるルーシーが自らの手で身体に番号を彫ることで、アウシュヴィッツの記憶の余波として表れています(アウシュヴィッツでは、ユダヤ人に鑑識番号を刺青し名前を奪っていた)。また、ルーシーはポーランド語を理解できず、現地の人とはつながりを持つことができません。戦争経験者の子どもたち、つまり第二世代に受け継がれるトラウマを、どのように捉え、本作に落とし込んだのでしょうか。
ユリア:美しい格言があります。それは、「トラウマの痛みは、家族間や世代を超えて包み隠さず出せるようにならないと、受け継がれていく」(※)というものです。
私たちの親の世代は、何を経験したかについて、包み隠さずに言えない状況にありました。劇中では、両親がトラウマについて語らないため、ルーシーはなかなかホロコーストの痛みについて解き明かすことができません。旅の終わりに父親がようやく口を開き、涙を流したとき、抱えていた痛みが表出される。第二世代であり子孫であるルーシーは、そこで初めて彼らのトラウマを痛切に感じ、解き明かせるようになります。
※マーク・ウォリン(心理療法・セラピーの理論と実践を研究・教育・普及するための「ファミリー・コンステレーション・インスティテュート」創設者であり所長)は、「トラウマが語られず解決されないままだと、次の世代に影響を与え続ける可能性がある」としている。著書に『心の傷は遺伝する』(河出書房新社)など。

© 2024 SEVEN ELEPHANTS, KINGS&QUEENS FILMPRODUKTION, HAÏKU FILMS
ユリア:痛みについて語るというのは非常に難しいことですが、ふたりは映画の最後の局面で語り合うことができるようになるのです。これは、すべての世代を超えたトラウマに当てはまります。
ホロコーストについては、アウシュヴィッツを実際に体験した第一世代は沈黙する傾向にあって、それが直系子孫である二世にトラウマ的な影響を与えました。ルーシーのあのタトゥーは、まさにその兆候です。彼女は自分が予感している痛み、自分自身で感じたい痛みを探し求め、あらかじめ耐えられるようにしようとしているのです。また、ルーシーはポーランド語の意味を理解できませんが、映画の終盤でははじめよりも馴染みのある言葉になっていくように、サウンドデザインも意識しました。
何より重要なのは、当初はポーランドで出される料理を拒否し、ニューヨークから持ってきた自分の食べ物しか食べずにいた彼女が、最後にはタクシー運転手が差し出したポーランド料理も喜んで食べるようになることです。このように、ルーシーがポーランド文化に親しみを抱いていくような演出をしています。
─ルーシーが夜に自ら針で太ももに父の強制収容所の番号を彫るという行為は、自傷行為のようにも見えます。そのような解釈もできるように意図していたのでしょうか。
ユリア:残念ながら、第二世代の人々が自傷行為をするケースが多いのは事実です。本作はリリー・ブレットの小説に基づいていますが、彼女もまた自傷行為をさまざまなかたちで記述しています。その根底には、両親が体験したトラウマに対して、第二世代が罪悪感のようなものを背負ってしまっているため、自傷行為で痛みを感じる、ということがあると思います。

© 2024 SEVEN ELEPHANTS, KINGS&QUEENS FILMPRODUKTION, HAÏKU FILMS
─ルーシーは、父親がかつて暮らしていた家で使っていた品々を買い戻すことにこだわりますね。本作に「Treasure」(原題)というタイトルをつけた意図を教えてください。
ユリア:映画に登場する品々は、彼女が得られない感情の代替品なのです。冒頭で彼女が古家のドアノブを持ち帰るシーンがありますが、それはアメリカに移り住む前に自分の家族が暮らしていたことを証明する何かがほしかったゆえの行動です。その後、(かつて父親の家族の所有品だった)磁器や銀の皿などの品々が宝物のように次々と現れます。ルーシーは、それらのものを購入することで、それまで両親と持てなかった対話の欠如、満たされない感情を補おうとしているのです。
偶然同じ構成の映画『リアル・ペイン』。対して、本作には政府から資金援助がなかった理由
─偶然にも時を同じくして公開された『リアル・ペイン〜心の旅〜』(2024年)も、ホロコーストの世代間トラウマとダークツーリズム(※)を描いていました。どちらも正反対の性格の父娘 / 従兄弟同士が、自身のルーツをたどるべく祖国ポーランドの戦争遺跡へ旅をする二人組ロードムービーですが、世界的に右傾化が強まっているなかで、同時にこれらの映画が生まれていることをどう思いますか。なぜいま注目を集めるのでしょうか?
ユリア:ジェシー・アイゼンバーグが『リアル・ペイン』を制作したのはまったくの偶然でした。じつは、私たちの映画の撮影が終了した直後、チームのメンバーの多くが彼の映画にも参加したんです。そして、このふたつの作品が非常に似たストーリー、似た前提、似た展開を持っていることに、みんな驚きました。
本作に出演くださったレナ・ダナムもスティーヴン・フライも、そしてジェシー・アイゼンバーグもみんな、いま世界で起きていることに対して、同じ懸念に突き動かされていたのだと思います。だからこそ、私たち全員が、あの過去を振り返り、現在の私たちの姿を表現したいと思ったのでしょう。
※ 戦争、災害、差別、事故など悲劇や死と関連する場所を訪れ、歴史の暗い側面を学ぶ観光スタイルのこと。「ブラックツーリズム」とも呼ばれ、歴史を繰り返さないための平和学習や記憶の継承が目的で、広島の原爆ドームやアウシュヴィッツ強制収容所などが代表例として挙げられる。近年では「ピースツーリズム」とも呼ばれる動きもある。
『リアル・ペイン』あらすじ:ニューヨークに住むユダヤ人のデヴィッド(ジェシー・アイゼンバーグ)とベンジー(キーラン・カルキン)は、亡くなった最愛の祖母の遺言で、ポーランドのツアー旅行に参加する。従兄弟同士でありながら正反対の性格の二人は、時に騒動を起こしながらも、祖母に縁あるポーランドの地を巡る。
─『リアル・ペイン』がポーランドからの資金援助を得て製作されている一方で、本作は資金援助を受けていませんよね。『旅の終わりのたからもの』劇中では、父が幼少期に住んでいたアパートに暮らすポーランドの一家は、ルーシーが父の思い出の品々を買い取ろうとしても法外な値段を提示するなど、必ずしも単に「善良な犠牲者」ではありません。その描き方が資金援助の有無に関係あると考えたのですが、当時のポーランドの人々の描き方についてもおうかがいしたいです。
ユリア:おっしゃる通り、あのような家族の描き方が、私たちがポーランドから資金提供を得られなかった理由でした。
製作当時、ポーランドではPiSという政党(※)が政権を握っていて、映画の助成金を事実上コントロールしていました。映画の助成金を出すにあたってガイドラインが敷かれていて、「ポーランド人を犠牲者か英雄としてしか描いてはいけない」という指針がありました。私たちは、劇中の家族を犠牲者でも英雄でもなく、複雑な個人として扱っているため、ポーランド政府から資金提供を受けられなかったのです。
※保守ナショナリスト系政党の野党「法と正義(=PiS)」。
「みんな家族を通して、何らかのかたちで歴史とつながり、関わっているから」
─前作『そして明日は全世界に』でファシズムの復活を懸念していました。本作では同じ思想が過去にもたらした傷跡を掘り下げていますね。ファシズムへの危機感が「余波三部作」を生んでいるのでしょうか。
ユリア・フォン・ハインツ(以下、ユリア):その通りです。世界中、特にここドイツで極右やファシスト的な動きが再び非常に顕著になり、社会の中枢にまで浸透してきた。だからこそ、私はこの主題に、映画を通して再び取り組むようになりました。
『そして明日は全世界に』(英題:AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD)オフィシャルトレーラー
─ドイツは「記憶の文化」(第二次世界大戦中にナチスが犯した負の歴史を忘却せず、後世へ伝え継いでいく社会的な取り組み)を重んじていますが、日本では自国の戦争責任を批判的に問うことが忌避される傾向にあります。第二次世界大戦を直接経験していない私たちは、過去の戦争をどのように見つめるべきだと考えますか。また、現在も戦争が起こっていることをどう受け止めていますか。
ユリア:1990年代から2000年代にかけて、歴史から学び、より平和な時代がきっと訪れるのだと考えていた時期が、私たちにはありました。しかし、ここ5年間で決してそうではないことがわかりました。戦争の火種が再び至る所で発生し、その規模も拡大している。
過去を振り返ることは、未来をつくるための教訓として役立つと思っています。だからこそ、ドイツが、かつては強制的に、そして現在では自発的に、この「記憶の文化」を重要視していることを、うれしく思います。幼い頃から触れられるよう、学校教育の場でも取り入れられているのはいいことですね。私は、かつてファシズムで犠牲を生んだすべての国々が、加害者の立場として、同じような取り組みをしていくことを願っています。

© 2024 SEVEN ELEPHANTS, KINGS&QUEENS FILMPRODUKTION, HAÏKU FILMS
─日本で本作は、ホロコースト犠牲者を想起する国際デー(1月27日)に近い公開日となります。第三世代、第四世代であるいまの私たちは、戦争とどう向き合うべきだと考えますか。また、トランスジェネレーショナル・トラウマ(精神的、肉体的、そして社会的苦しみが子孫へ受け継がれること)を癒すために、どうすることが必要になってくると思いますか。
ユリア:この映画で私が最も伝えたいのは、家族のなかで歴史的な出来事について語り合うことの大切さです。そのためには、方法がいくつかあります。学校教育、数字(データ)、事実に触れるといったことはたしかに重要。ただ、それだけでは何か血の通わない取り組みになってしまう気がするんです。
より個人的なレベルで質問して話を聞くこと——祖父母に「どんな経験をしたのか」、両親に「どんな話を親から聞いてきたのか」など——が、とても効果があるのではないでしょうか。自分の家族のトラウマを知ることが、真に意味のある変化を何かもたらすかもしれない。それが、歴史の記述なのです。
日本、ドイツ、そしてイタリア、当時ファシズムで罪を犯した立場の国家は、自国の歴史を振り返る必要があると思います。私たちはみんな家族を通して、何らかのかたちでこの歴史とつながり、関わっているからです。
- 作品情報
-
 『旅の終わりのたからもの』
『旅の終わりのたからもの』
2026年1月16日(金)kino cinema新宿ほか全国ロードショー
監督:ユリア・フォン・ハインツ
原作:『Too Many Men』リリー・ブレット著
出演:レナ・ダナム
スティーヴン・フライ
- プロフィール
-
- ユリア・フォン・ハインツ
-
1976年生まれ、ドイツ・西ベルリン出身。映画監督・脚本家であり、社会的・政治的テーマを扱った作品で国際的に評価されている。代表作『そして明日は全世界に』は、2020年の『第77回ベネチア国際映画祭』コンペティション部門に出品され、反ファシズム運動を描いた作品として注目を集めた。学術的な側面では、2012年に「友好的な乗っ取り—ドイツ映画に対する公共テレビの影響、1950年から2012年」というテーマで博士論文を完成させた。さらに、ケルン芸術大学(KHM)やミュンヘン映画大学(HFF)でゲスト教授を務め、2019年からはHFFの名誉教授として、テレビや映画の機能に関する研究プログラムの共同リーダーを務めている。
- フィードバック 5
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-