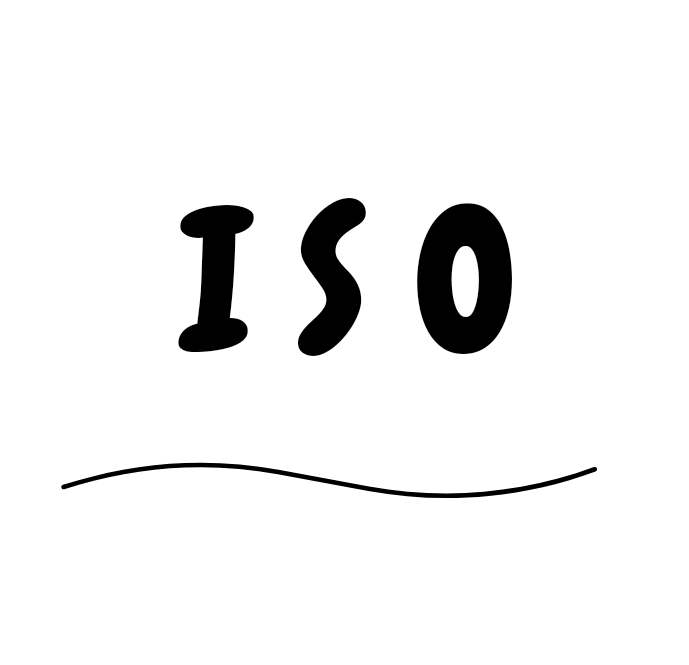メイン画像:© 2023 FACES OFF RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
ルッキズムの問題点が叫ばれて久しいなか、外見——特に「美醜」にまつわる社会的な関心は絶えず盛り上がっている。自らのアイデンティティをなすうえでも、また他者とのコミュニケーションにおいても大きな存在である「顔」について、観客の潜在的な意識にまでもぐって、問いをぶつけるような映画『顔を捨てた男』。
A24製作。本作の主人公は、顔に変形がある俳優志望のエドワード。『アプレンティス』でドナルド・トランプ役を演じ、『第97回アカデミー賞』主演男優賞にノミネートされたことが記憶に新しい、セバスチャン・スタンが演じている。エドワードは治療によってまったく別の顔を手に入れて新しい人生を歩み始めるが、かつての自分の顔に似たカリスマ性のある男性に出会い、そこからまた物語は大きく動きはじめる……。
口唇口蓋裂を治療した経験があるというアーロン・シンバーグ監督は、本作で描いた問題は「私自身がつねに問い続け、葛藤し、闘い続けてきたものである」と語った。インタビューでは、これまで数多くの映画が、障害や身体的欠損を悪のメタファーとして、またはいわゆる「心温まる物語」で同情を引くための装置として扱ってきたことを指摘しながら、本作では監督自身が体験してきた「現実」を描いたのだと話した。個人の経験を出発点としてつくられた本作に、私たち観客は何を考えるか? シンバーグ監督の答えから、探っていきたい。
あらすじ:顔に極端な変形がある俳優志望のエドワード。隣人で劇作家を目指すイングリッドに惹かれながらも、自分の気持ちを閉じ込めて生きる彼はある日、外見を劇的に変える過激な治療を受け、念願の「新しい顔」を手に入れる。過去を捨て、別人として順風満帆な人生を歩み出した矢先、目の前に現れたのは、かつての自分の「顔」に似たカリスマ性のある男オズワルドだった。その出会いによって、エドワードの運命は想像もつかない方向へと猛烈に逆転していく───。
「顔」とアイデンティティの問題——監督自身が闘い続けてきた疑問。時代性は?
—アイデンティティの中核であり、他者とのコミュニケーションを行う媒体としても機能する「顔」ですが、整形などで意図的にかたちを変える人が多い部位でもあります。監督はこの「顔」がアイデンティティを形成する上でどのような役割を果たすと考えますか?
アーロン・シンバーグ(以下、シンバーグ):その質問は私が映画のなかで自分に問いかけていることですね。明確な結論を出せてはいないのですが、劇中で描いたのは、私自身が絶えず悩まされてきた問題でもありました。というのも、私は生まれつき口唇口蓋裂(※)があったからです。わかりやすくいえば、顔に穴が空いた状態で生まれ、のちに矯正手術を受けました。治療はしたものの、顔には誰が見ても明らかな跡が残っています。そのことが私の人格や周囲からの扱いにどのような影響を及ぼしてきたのか、またその「欠落」がなければいまごろどんな顔で、どんな人生を歩んできたのだろうかと、つねに考えてきました。
私自身が手術で矯正をしたという経歴があり、ある意味で、この顔も医師によってつくられた顔であるとも言えます。思うに、この特徴を持って生まれたことは私の人生、自己についての認識、他者が私をどう見るかということすべてに、大きな変化をもたらしました。ただ私の顔に向けられる他者の視線が私の性格にどれだけの影響を及ぼしたのか、あるいは特徴がなくとも私はこういう人物だったのか、ということを判断することはとても難しい。だからこそ、この映画のなかでも答えは出すことができませんでした。
ひとつ言えるのは「顔」が持つ役割というのは、私自身がつねに問い続け、葛藤し、闘い続けてきたものであるということ。そしてその疑問こそがこの映画をつくるきっかけになったとも言えます。
※生まれつき上口唇、いわゆる「うわくちびる」が割れている状態。医療機関によると、日本人ではおよそ500人に1人くらいの割合で出現する比較的頻度の高い疾患だという。

アーロン・シンバーグ
米イリノイ州出身の映画監督、脚本家。ニューヨークを拠点に活動。口唇口蓋裂の矯正治療を受けた経験にインスピレーションを得て、外見やアイデンティティをテーマにした作品を発表。 長編2作目『Chained for Life(原題)』(2018年)ではアダム・ピアソンを主演に抜擢し話題に。長編3作目となる『顔を捨てた男』(2023年) では、主演のセバスチャン・スタンを『ベルリン国際映画祭』、『ゴールデングローブ賞』最優秀俳優賞に導いたほか、『シッチェス・カタロニア国際映画祭』最優秀脚本賞受賞、『ゴッサム・フィルム・アワード』では最優秀作品賞を受賞した。
—ルッキズムや視線の暴力性というテーマから、日本でも5月に公開された『サブスタンス』との共通点を見出す人が多くいるかと思います。海外のインタビューでも『サブスタンス』を観たかと尋ねられていましたよね。そこであらためて、いまこのテーマが多くの人の関心を集め、共感を得ている理由をどう考えているかを聞かせてください。
シンバーグ:まず『顔を捨てた男』がこれほど多くの人々の共感を得るとは予測していなかったのでうれしい驚きでしたね。おっしゃるとおり『サブスタンス』など近しいテーマを扱った映画が近いタイミングで公開されたこともあり、「現代を生きる私たちは外見に執着しすぎている」といった時代の潮流に乗ったテーマだと、よく言われました。ただ正直なところ、本作をつくるうえで時代性や現代社会の状況というものはまったく意識していません。というもの描いているトピックは、私にとっては生まれてからずっと関心を持ってきたことなので。
この映画はとりわけ障害(disability)と外見の損傷(disfigurement)、及びそれらを抱えた人々の経験に焦点を当てています。そのため個人的に近しい経験がない多くの人にとっては共感できず、ごく一部の人にしか刺さらないテーマではないかと心配していました。その予想に反して、あらゆる人々がエドワードに自分を重ねてくれたことは、私にとってとても興味深い出来事でした。とはいえ、それでもこの映画が現代を反映しているものだとは思いません。むしろ美しさや他者からの視線という、いつの時代でも語られる普遍的なテーマを扱っています。

© 2023 FACES OFF RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
—なぜ多くの人が本作に時代性を見出したのだと思いますか?
シンバーグ:新たな医療技術の誕生や、この題材に対する社会の関心の変化が本作に現代的な感覚をもたらしているのでしょうね。ただ知ってほしいのは、この映画がそういった時代性に反応したものではないということ。私が表現しようとしたのは、外見に障害があることで異常や異質だとみなされる差別的な社会で生きるという体験でした。そしてそのような偏見や差別を、どのようになくしていくべきかを本作を通じて考えたかったのです。
「他人は自分の映し鏡」を体現し、「ご都合主義」ではない現実を描く
—本作はエドワードやオズワルドが受ける偏見や差別を描いていますが、直接的な暴言に晒されることはないですよね。マンションの住民をはじめとする人々の態度から、表面上は多様性を尊重しようという態度が浸透している社会であるようにも感じました。一方で、エドワードが俳優としての雇用機会に恵まれないなど、構造的な差別は確実に存在することも示唆されていますが。
シンバーグ:たしかにエドワードが直接的に受ける攻撃や差別はありません。というのも、私はいわゆるマイクロアグレッション(※)や、より微細で有害な形態の差別——つまり、エドワードに対して「普通」に振る舞おうとしているが、かえって繊細なかたちで彼に影響を与えるような人々の言動——に焦点を当てることを念頭に置いていたためです。この表現を選んだのには理由がありました。
というのも、類似のテーマを扱ったさまざまな作品を観ていて、あることに気付いたんです。たとえば障害のある主人公に対して積極的に危害を加えるいじめっ子のような悪役がいる場合、観客はその悪役から距離を置いて、いかにその状況が正されるのかという展開に固執してしまいますよね。主人公が悪役に復讐する姿や、あるいは主人公が残酷な仕打ちに抗って生き延びる姿を観たいと、多くの人が期待してしまうんです。もしその主人公が残酷な仕打ちを「これが現実だ」と受け入れたらどうでしょうか。観客は「主人公は何を考えているんだ? それで対処したつもりか?」と考えて、その先を観ることがつらくなるかもしれません。それは観客の多くが、現実でそのような扱いを受けた人がどのように対処するかを理解していないからです。
※マイクロアグレッション(microaggression)とは、意図のあるなしに関係なく、相手を傷つけたり差別的な態度をとったりする「些細な」言動や態度のこと。多くのケースで、無意識の思い込みや潜在的な差別意識から発生する。

© 2023 FACES OFF RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
—わかりやすく「加害者と被害者」という構図を提示されると、痛快な展開や勧善懲悪の結末を期待してしまうのはたしかにありますね。
シンバーグ:だからこそ私はこのテーマで、観客が悪役への復讐や抵抗を期待する作品はつくりたくありませんでした。そこで執筆したのがこの物語なのです。エドワードが変身したあと、それまで彼が社会から向けられてきた「障害や外見の損傷のある人」に対する目線を、同じようにオズワルドに向けることで、彼との関係を構築していきますよね。そこからわかる通り、本作ではエドワードこそがオズワルドを差別しているのです。彼は過去の自分と重なるオズワルドが幸せそうだったり、成功したりする姿を決して見たがりません。そして自分の気持ちをたしかめるように、社会や他者の目線からオズワルドを見ようとするのです。
ただ単に障害や損傷のある人物に対して残酷な行為を行う悪役を描くのではなく、オズワルドに自分を重ねるエドワードの姿を見せることで、オズワルドに敵対する彼の心情を観客に理解してもらうこと。それがこの映画において非常に重要なポイントでした。必ずしも公正な描写ではないかもしれませんが、エドワードがオズワルドに向ける視線は私が社会から感じてきた視線であるとも思います。ただエドワードに関していえば、その行動は必ずしも残酷さによるものではなく、オズワルドに自分を見出したことでその姿に嫌悪感を抱いているのです。そういう意味で彼の言動、そしてこの映画自体が「他人は自分の映し鏡」というよくある言い回しを体現しているとも言えますね。
※以下、本編のネタバレを含みます。あらかじめご了承ください。

© 2023 FACES OFF RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
映画は、障害や身体的欠損を悪のメタファーとして扱ってきた歴史がある
—終盤にエドワード(ガイ)のリハビリを手伝う作業療法士が、オズワルドに対し暴言を吐きますよね。本人に向けてではないですが、それまで描かれてきたマイクロアグレッションとは異なる、本作で唯一とも言える明確な差別的意思を持った発言でした。
シンバーグ:それまで作中で露骨には描かれていないけれど、観客の多くが薄々感じていたであろう人々の差別心や社会の差別的構造が実在すると裏付けることが、そのシーンの目的でした。その差別発言を聞いたエドワードは、この作業療法士を包丁で刺してしまう。なぜなら作業療法士がオズワルドに向けた言葉は、彼に自分を重ねるエドワードに向く言葉でもあるから。エドワードにとってその行動は復讐だったんです。

© 2023 FACES OFF RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
—顔の変形や損傷を描く上で細心の注意を払われていたかと思いますが、差別感情や偏見を助長しないようどのように取り組まれたのかを教えてもらえますか?
シンバーグ:私自身が生まれつきの特徴に悩まされてきたということもあり、映画における障害や身体的欠損の表現に対してはつねに敏感でした。そしていつも感じていたのは、これまでのそういった描写のほとんどは、正確に描けていなかったということ。ほかのアートフォーム(特定の芸術表現の形式)でも同様ですが、とりわけ映画は障害のある人にとってネガティブな影響を与えてきたと感じています。映画は長い歴史のなかで障害や身体的欠損を悪のメタファーとして、またはよくある「心温まる物語」で同情を引くための装置として扱ってきました。そのような描き方は、観客にも確実に負のイメージを植え付けてきたと思います。
—身体の損傷や変形を悪と結びつけてきた映画業界に対し、是正するように求める「I Am Not Your Villain」(※)というキャンペーンもありましたね。
シンバーグ:そのため私が映画づくりをする際には、私自身の体験を観客に伝えたいと考えてきました。実際、私が口唇口蓋裂により経験してきたことは、間違いなくいまの映画制作の土台になっていると思います。ただ忘れてはいけないのが、それが障害や身体的欠損のある人みんなに通じるものではないこと。私は他者を代表するつもりなどは一切なく、あくまで個人的に経験してきた出来事や感情、考え方を、これまでになかったかたちで共有したいのです。それこそが私の監督としての出発点でした。2013年に長編映画デビューをしてから3作目となる本作に至るまで、かたちは違えどすべての作品で同様のテーマを扱っています。
※傷跡、火傷、印など「見た目の違い」を悪役の象徴として描く風潮に対して異議を唱えるキャンペーンで、イギリスの団体Changing Facesが2018年から主導。偏見ある描写の見直しを映画業界に呼びかけている。英国映画協会(BFI)も賛同し、差別的描写を含む作品への資金提供を行わない方針を表明している。
アダム・ピアソンの存在と、監督自身の変化。観客は自らの潜在的な「偏見」とどう向き合うか
—監督の前作『Chained for Life(原題)』(2018)はテーマが底通していることに加え、本作でオズワルドを演じたアダム・ピアソンが主人公を演じています。彼のカリスマ性溢れるキャラクターが本作を特別なものにしていますよね。
シンバーグ:『Chained for Life(原題)』でアダムという協力者を前作で見つけたことは私にとってとても大きな意味がありました。私とアダムにはそれぞれ異なる当事者としての経験があり、問題への対処法も当然異なります。映画をつくるうえでスタッフにも私たちの経験を共有しましたし、だからこそスタッフやキャストたちも私を信頼してくれ、このテーマにしっかりと向き合うことができたのだと思います。また『Chained for Life』でアダムと仕事をした経験は『顔を捨てた男』にも大きく影響しています。
『Chained for Life』あらすじ:映画の撮影現場を舞台に、俳優のメイベル(ジェス・ワイクスラー)が、俳優ロゼンタール(アダム・ピアソン)との共演を通して、「美」と「見た目の違い」にまつわる偏見に向き合っていく姿を、映画内映画というメタ構造で描いた。
シンバーグ:とりわけインスピレーションを与えてくれたのは、アダムの物事への向き合い方や、彼の明るく外交的な性格でした。彼の前向きな姿を見ていると、なぜ私はこんなにも自分のなかで「問題」をつくりあげているのだろうと、自分自身に疑問を抱くようになったんです。顔の変形のなかでも比較的軽度かもしれない口唇口蓋裂によって、なぜ私は自分の人生をこれほどネガティブに定義してしまったのだろうか、と。
アダムが明るく社交的に振る舞っているのは、ある意味彼にとっての防衛手段でもありますし、さまざまな葛藤を抱えていてそれに対処していることももちろん知っています。ただ私はアダムと接するなかで、自分のなかに芽生えた問題に対処するために大事なのは、真実と向き合い自分に正直であることだと気付きましたし、彼のおかげで多少前向きに変わることができたと思います。

© 2023 FACES OFF RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
—最後に、観客が『顔を捨てた男』をどのように受け止めることを期待しますか?
シンバーグ:私は観客に「このように観て、このように感じるべきだ」と指図したり、何かを押し付けたりすつもりはありません。当然のように本作に共感する人もいれば、共感できない人もいることでしょう。なかには顔の変形に対する偏見を持つ観客もいるでしょうが、その偏見を持ったまま本作を観て何を受け止めたのか、自分なりの方法で反応してくれることを願っています。
ただ一つ言っておきたいのですが、私は映画づくりをするうえで障害者コミュニティの誰とも問題を起こしたことはありませんし、映画が公開されたあとも当事者から「この表現は問題だ」と言われたこともありません。ただ『Chained for Life(原題)』が公開されたときに、障害のない非当事者の人から「当事者俳優を起用して本作のようなテーマを扱うことは搾取的だ」と指摘されたことはありました。もちろん過去に障害を描いてきた作品に搾取的なものが多かったことは事実ですが、自身の体験を土台とする私の作品が搾取的だとは考えていません。仮に搾取的だと感じたのであれば、それはこの映画の問題というわけではなく、その人の気持ちや感情的な問題ではないかと思うのです。
- 作品情報
-
 『顔を捨てた男』
『顔を捨てた男』
2025年7月11日(金)からヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国公開
監督・脚本:アーロン・シンバーグ
出演:セバスチャン・スタン
レナーテ・レインスヴェ
アダム・ピアソン
- プロフィール
-
- アーロン・シンバーグ
-
米イリノイ州出身の映画監督、脚本家。ニューヨークを拠点に活動。口唇口蓋裂の矯正治療を受けた経験にインスピレーションを得て、外見やアイデンティティをテーマにした作品を発表。 長編2作目『Chained for Life(原題)』(2018年)ではアダム・ピアソンを主演に抜擢し話題に。長編3作目となる『顔を捨てた男』(2023年) では、主演のセバスチャン・スタンを『ベルリン国際映画祭』、『ゴールデングローブ賞』最優秀俳優賞に導いたほか、『シッチェス・カタロニア国際映画祭』最優秀脚本賞受賞、『ゴッサム・フィルム・アワード』では最優秀作品賞を受賞した。
- フィードバック 23
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-