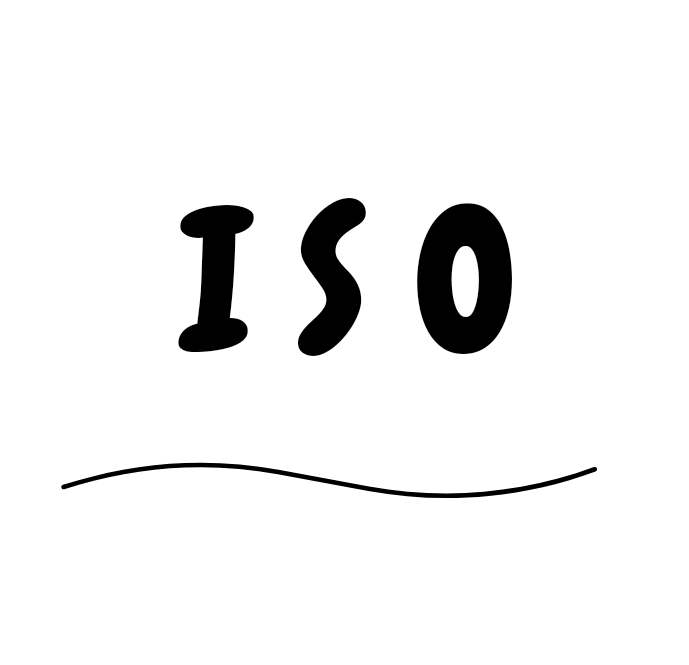多くの人が映画を楽しむために、どんな変化が必要なのだろうか。
7月15日からNetflixで日本での配信が始まる『火垂るの墓』において、安田章大は日本語の音声ガイド(主に視覚に制限をもつ人に向けたナレーション。英語ではAudio Description/オーディオ・ディスクリプションと呼び、音声ガイドと表記される)を担当する。
今回のインタビューでは、地元・兵庫が舞台の『火垂るの墓』に対する思いや、初めての参加となる音声ガイド制作への向き合い方、自身も光過敏の症状をもつ安田にとっての、音声ガイドの存在意義などについて話を聞いた。
「ショッキングなことはショッキングなものとして包み隠さず描写する作品」
—安田さんにとって、『火垂るの墓』というのはどういった作品か教えてください。
安田:子どもの頃に観たときは衝撃的でした。みんなが目を背けたくなるけど見逃してはいけないものを「歴史」として残してきた作品だと思うので。だからこそ初めて観たときはショッキングだったし、目を伏せたくなりました。
とはいえ僕自身、戦争に対して子どもの頃から敏感に反応できていたわけではありません。ただ、大人になったいまも国と国がうまく交われず、紛争や戦争が起きる世の中が続いている。80年前と世界は変わらないということに目を向けざるを得ませんし、40歳となった自分がいまだ起こる「戦争」を描いたこの作品から目を背けてはいけないなと思いますね。

安田章大
STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドル。音楽・舞台・映像など多方面で活躍する一方、2017年に脳腫瘍(髄膜腫)の手術を受けた経験を持ち、現在も光過敏の後遺症と向き合いながら活動を続けている。当事者の視点から、視覚に課題を抱える人々にとっての映像体験のあり方に深い関心を寄せており、今回Netflixでは音声ガイド制作に初めて参加。
安田:じつは今回の仕事を機に思い出したことがありまして。僕が小学校の中学年くらいのとき、ある友達が海外で罹った風邪のウイルスによって目が見えなくなったんです。僕はずっとその子のそばいたので、腕を引いて学校の行き帰りをしたり、学校内の移動をしたり、一緒に点字を覚えたりということをしていた時期が1年間以上あるんです。
そういった経験をしたのと同じ時期に、地元の公民館に付近の区域の子どもたちと集まって観たのが『火垂るの墓』だったんですよ。そこで作品に衝撃を受けたわけですが……そういった子どもの頃の出来事が、今回ナレーションを録るなかで鮮明に蘇ってきました。
—いろいろつながっている感じがしますね……。子どもの頃といまでは映画の見え方もかなり変わったのでは?
安田:ちゃんと大人にはなっているので、この国で起きてきた事実や史実に関しての理解度はもちろん上がっていますが、改めて感じたのは「ショッキングなことはショッキングなものとして包み隠さず描写されているな」ということ。
『火垂るの墓』という作品にとっては、それはすごく大事な点だと思うんです。冒頭から清太が1945年9月21日に亡くなったという導入で始まりますし、中盤以降も赤く焼けていったものたちと蛍をリンクさせながら描写されていきますよね。
映像は美しいですが、美しさゆえなのかそれが悍ましく恐ろしくも感じる。そしてそれを許されない出来事として、高畑さんをはじめとする皆さんが、この物語を「歴史」として紡いでこられた。そう思うと40歳になったいま、今度は僕自身がその立ち位置で『火垂るの墓』を次の世代に渡していかないとなと思います。

安田:昨年亡くなられた唐十郎さん(※)は、さまざまな作品を通じて失われゆく伝統芸能を次の世代に伝えていこうとしていました。それは僕が仕事や人生においても大切にしていること。なので今回、手を差し伸べてもらって参加した本作でも、伝えられるべき歴史をこれまで知らなかった方や、知りたくても怖くて触れられなかった方々に渡していきたいと感じていますね。「ペイ・イット・フォワード」という訳ではありませんが、音声ガイドの経験を通じてよりそのように感じました。
※唐十郎(から じゅうろう):劇作家・演出家・俳優。安田は唐の作品を10数年前に観劇し魅了され、今年、唐の初期作品『アリババ』『愛の乞食』で主演する。
音声ガイドを担当して安田が得た「発見」
—安田さんは兵庫県尼崎市出身ですが、『火垂るの墓』の舞台となっているのも兵庫県ですよね。そういう意味でも縁を感じさせます。
安田:本作の舞台である西宮は僕の地元である尼崎の隣町。自転車で10分くらいの距離なので、当たり前のようによく行っていました。お父さんが阪神タイガースの大ファンなので甲子園にもよく連れて行ってもらいましたし、国道2号線と43号線あたりはすっかりお馴染み。阪急電車に乗って西宮北口駅の塾や三宮にも行ってたので、『火垂るの墓』の映像を観ているとその辺りの景色が浮かんできます。土地は知っているし、あの時代の重さはいまもたしかに残されていると感じますから。
とはいえ僕は『火垂るの墓』当時の三宮駅や西宮市には行ったことがないので、映像で描かれているものを決してリアルとは言い切れない。知らないのに「リアルに感じた」と言うと嘘くさいじゃないですか。でも尼崎市で生まれ育っているので、写真や映像で「隣町でこんなことが起きていたんだ」と史実に触れてきたという意味ではとても近しくもある。だから近いけど遠くもある謎の中間地点にいる感覚なんですよね。

—私も一度音声ガイドの製作現場に参加したことがあるのですが、映画制作者や当事者のモニター、アドバイザーが議論しながらより的確で明確な表現を突き詰めていくクリエイティブな作業であることに驚いた記憶があります。『火垂るの墓』の音声ガイドも同様に協議を重ねつくられたものかと思うのですが、初めてその台本を読んだとき、どのように感じましたか?
安田:音声ガイドの台本は今回初めて読ませていただいたんですが、物語を多面的な角度から観られたことが個人的発見でした。物語を追えば、節子と清太、そして彼らの周りにいる登場人物の目線に自ずとフォーカスが行くと思うんです。でもそのなかに僕という人間が時代を超えて音声ガイドを吹き込むことで、ちょっといまの空気を孕むんですよね。現代の人間が話している言葉が物語のなかに入り込むことによって、節子と清太ではない音声ガイド目線の多面的な見え方が含まれてくる。2Dで触れていた情報が3Dに変わるような感覚と言いますか。
何度も校正され、書き上げられた選び抜かれた言葉たちが端的にその景色や匂い、温度や湿度、人間関係を表現してくれるんです。その音声を追いかけることで、これまでとはまったく違う角度から物語を観ることができた、というのは気づきでしたね。
—それはとりわけどういったシーンで感じたのでしょうか?
安田:どれを挙げようか悩みますね……。たとえば焼夷弾が投下されたときに、バケツの水やハシゴ、そしてあらゆるものが焼けていく様子が描写されていくんですが、その映像に音声の説明が乗っかるわけですよね。そうすることで、一つ一つの画の持つ意味が浮かび上がる。何を表現したくてその画を挟んだのかが際立つんです。
そしてその瞬間に節子が兄ちゃんにどんな想いを持って、一人で泣いて待っていたのか。逆に清太が妹にどんな想いを持って、何を目的に一人で走っていたのか。そういったことさえも言葉が乗ることによって、このように表現することができるものなんだと気づかされました。そのような、音声ガイドがあったからこそ初めて拾えた感情が全編にあったんですよね。
—視覚障害者の方が「単に音声情報を並べられても困る。音声ガイドによって映画を楽しみたいんだ」と話していたのを聞いたことがあります。そのために必要なのは作品の温度や空気をいかに音声ガイドに込めるかだと思うのですが、安田さんのお話を聞いているとそこはしっかり練り込められているのだろうなと感じました。
安田:言葉を乗せるうえで単に「ガイド」をされても困るという点に感しては、僕自身も台本を読ませていただくなかで感じ取ったことだったので、どこの着地点に音声を置けばいいのかということはすごく意識しました。
今回演出をしてくださった小笠原さんから教えていただいたのは「あまり感情を乗せすぎると物語が二軸で走ってしまう。『火垂るの墓』という物語がまず走っているので、そこに寄り添うガイドであるために、ときに淡々といく必要もある」ということ。そのうえで、家でも時間に合わせて読み上げる練習などをするうちに「ここは淡々とはいきたくない」と思ったり、「淡々としつつ感情のグラデーションを練ろう」と考えたりするシーンがたくさんあったんですよね。なので、その落とし所を自分のなかで相談しながら表現していきました。

安田が感じる俳優、表現者、人間としての成長
—安田さんはAudibleの『夜行観覧車』でも朗読を担当されていましたが、とても柔らかな声という印象がありました。ただ今回のような映像作品のナレーションは初ですよね。感情を込めるバランスのみならず、話す間やトーンなどあらゆる面で朗読や演技とは異なる作業だったかと思いますが、どのように狙いを定めて収録していったのでしょうか。
安田:『火垂るの墓』というのは、節子と清太が生きたくても生きられなかった時代の話じゃないですか。命を落としてしまう哀しみで始まり、劇中にはさまざまな辛い想いもある。そういったものを表現するため、尖りのある声色や柔らかい声色、あるいは有声・無声なども使い分けながら繊細に声の調子を整えていきました。
—今回音声ガイドを担当するにあたり、ほかの音声ガイドを参考にすることはあったのでしょうか?
安田:じつはこれまで音声ガイドに触れたことがなかったんです。そして今回のお仕事をいただいたあとも、どういうふうにすれば良いのかということ自体を自分で模索したほうが良いと考えて、あえてほかのものを観たり聞いたりしないようにしました。
自分のなかで前例のないものを、ほかの作品を前例として持ち込むとその「型」ができてしまう。そういった型を持たず、ノーモーションで挑むことで到達できる場所もあると思うので。
—先ほど「この物語を次の世代に伝えていく必要がある」とお話していましたが、「伝える」うえで特に意識したことはありますか?
安田:塩梅が難しかったんですが、感情と無感情のグラデーションはとても気をつけたポイントですね。物語のなかで描かれているできごとはどれも感情的になりたいと感じるものですが、感情を感情のまま読んでしまうと観る方に拒まれてしまう。人は相手から一方的に感情を向けられると、その感情を閉め出したくなるんですよ。だからある程度は観る人が感情を開く隙間をつくらなければいけない。そのバランスはとても考えました。
これはどのような戦争でいかにして敗戦に至ったのか、という史実に関しては調べたら出てきますよね。なので今回はそういった事実の部分ではなく、『火垂るの墓』で描かれる感情や心情、人々の動きや景色をリアルに伝えることで、「その当時どういうことが起きていたのか」を観る人に受け取ってもらいたいなということに意識を向けていました。
—音声ガイドをご担当されたことは、俳優、表現者、そして一人の人間としてどのような経験になりましたか?
安田:これまで僕はアイドルという仕事を通じて歌を歌ったり、お芝居をしたり、バラエティに出たりとオールジャンルな活動をさせていただきましたが、仕事を始めたばかりの若い頃からずっと「声の仕事がしたい」という思いはあったんです。だから今回こうして『火垂るの墓』という大きな作品に声で参加させていただけたことに幸せを感じています。
そしてこの仕事を通じて、人の感情というのは 一面や二面だけじゃないんだなと改めて感じました。子どもの頃に「相手の気持ちになって考えなさい」と怒られた経験は誰しもあると思うのですが、相手の気持ちを想像することと、節子や清太たちの気持ちを考えながら台本を読んだことはすごく似ていて。
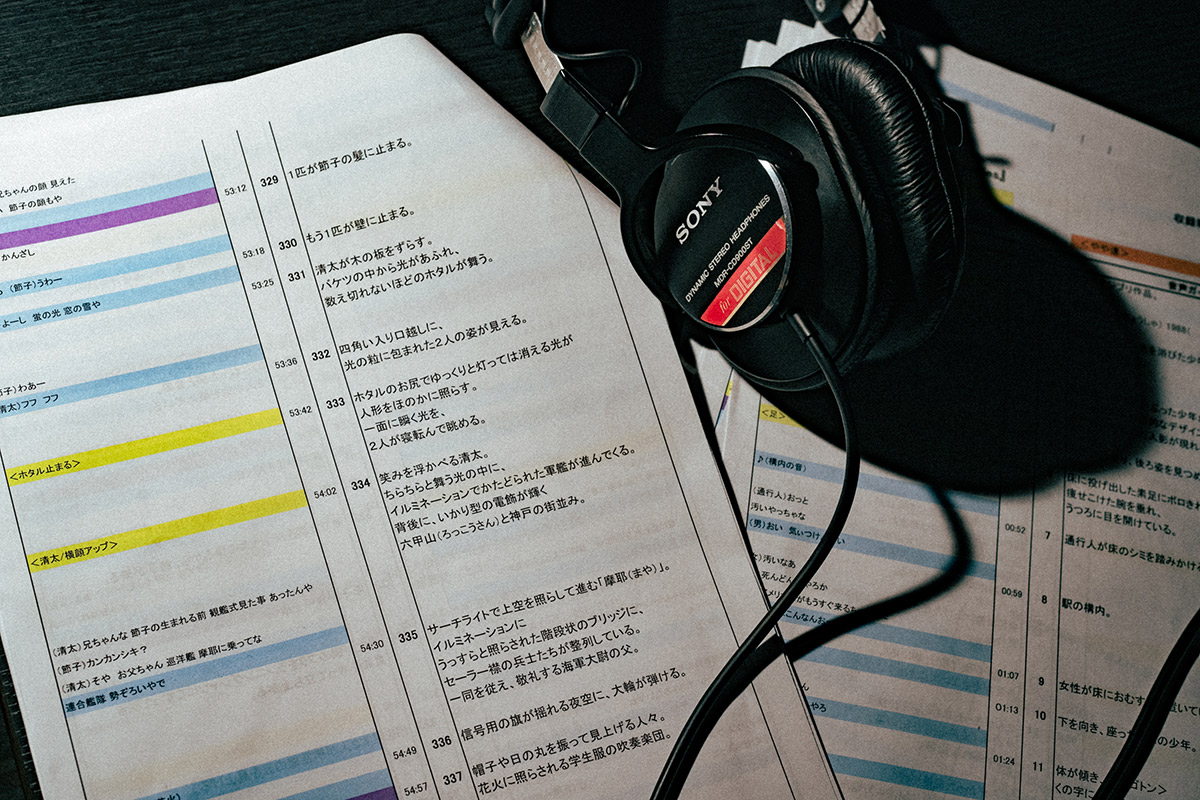
安田:台本を読みながら「この人の心情に入ってみよう。ここの感情はグラデーションのどこに位置しているのか。この人の言葉の裏にはどんな心情があるんだろうか」といったことを考えることで、自分が誰かの位置に立って、その誰かの感情になって意見を言うという感覚があったんですよね。
そういった体験ができたので、今回の仕事を経てより相手のことを考えるようになりましたし、相手の言葉にある本音やそこにある感情は何なのかと探求するようになりました。より相手の感情にタッチしようとするキャパシティが広くなったと言いますか……それは僕が心理学を勉強しているということもあると思いますが。
「ポジション・チェンジ」という心理ケアの手法があるんです。さまざまな物事や人間関係について、立ち位置や視点を「自分・相手・第三者」と自分のなかでチェンジしていくことでこれまでと異なる見え方や考え方を発見しよう、というものですね。それと似た体験でした。
光過敏に悩まされる安田にとっての、音声ガイドの存在
—「光過敏」に悩まれてきた安田さん自身の経験が、今回の音声ガイドにつながったと感じた部分はありますか?
安田:大前提としてみんなに当てはまる言葉ではないのですが、改めて言葉にさせて頂きます。僕は病気を経て今年で9年目なんですが、それまでできていたことができなくなると、頭では理解できても感情が追いつかないことがあるんですよ。その感情が追いついていない物事に対して、再度触れにいって、自分の痛みを知って、そうして再スタートをして……と何度も繰り返す作業が自分を遥かに強くしてくれると病気の経験で学びました。
人生の途中で病気を経たり、物理的なきっかけで見ることができなくなったりした方々のなかには、僕のこの気持ちに共感してくれる方もいれば、まだそうは思えないという方も当然いると思います。でも、いつか自分の思う「前」に進めるかもしれない。そのためにも、病気や体験は違えど、僕のような人間もいるんだということを知って言葉や想いを受け取ってもらえたら嬉しいですし、今回の音声ガイドを聴いてもらいたいなと思います。
そして先天的に見ることができない方々にとっても、人生のどのタイミングで感情を、そして自分自身を生まれ変わらせることができたのかというのは人それぞれだと思うんです。
すでに自分の痛みに触れて新しいところに行けている方もいると思いますが、まだ前を向く途中の方にとっては、僕が添え木になることで一緒に歩いていけるんじゃないかなと。それが病気の経験を経たうえで、僕が一番みなさんに届けたい本音の言葉かなと思います。

—光の点滅が強い映画作品も多く、安田さんも光過敏の症状で観るのが辛い映画もあるのかなと推察します。いろんな人が映画を楽しむため、今後映画や映像業界においてどのような変化を期待しますか?
安田:たしかに最近の映画は大きな展開や場面の切り替えとともに大きな光が放たれることがよくありますね。ただ、出来事が大きくうねらずとも人の感情が動く映画って昔からいっぱいあるじゃないですか。
時代が変わって映画も「タイパ」などと言われるようになっていますが、僕はもともとそういう映画がとても好きだったので、穏やかでも情感のあるものが表現される映画がまた増えることをとても期待しています。家のなかでキャンドルをひとつだけ付けて、一人で静かに映画を観ることも多いので。
そして、そういう映画でもどんどん音声ガイドが増えてほしいと思います。音声ガイドは目が見えない人が映画を楽しむためのものなのですが、同時に音声ガイドによって人の感情が足されていき、違う目線から観られることに僕も面白さを感じるので。
—おっしゃるとおり音声ガイド有りで映画を観ると新たな発見があったり、理解がしやすくなったりして面白いんですよね。どうしても音声ガイド=視覚障害者のためだけのものと思われていますが、いろんな人に触れてもらいもっと馴染みのあるものになってくれると良いなと思います。それが音声ガイド普及につながると思うので。そして音声ガイドが普及することで「映画を観たいけど観れなかった人」「映画のターゲットから外されてきた人」にもっと作品を観てもらえますよね。
安田:目が見えない方のなかにはもともと映画が大好きな人も大勢いらっしゃると思うので、そこの受容性が上がるのは音声ガイドの大きな利点ですよね。かつナレーションを担当する人がどういう人生を経験してきたかによって作品に孕む温度や空気、説得力が変わってくると思うんです。
つまりナレーターが100人いれば、物語も100通りになる。今回はありがたいことに僕が読ませていただきましたけど、僕じゃない誰かが『火垂るの墓』を読めばきっとまた違う温度を持った作品になるんですよね。
きっと声を仕事にしていない方でも、人生経験を活かすとその方特有の豊かさが出る。それはとても良い点だと思いますし、僕自身が今後楽しみにしている点でもあります。
- 作品情報
-
 『火垂るの墓』
『火垂るの墓』
原作:野坂昭如(新潮文庫版)
脚本・監督:高畑 勲
音楽:間宮芳生
声の出演:辰巳 努 ⋅ 白石綾乃
上映時間:約88分
配給:東宝
公開日:1988年4月16日(土)
2025年7月15日(火)からNetflixで日本初配信
- プロフィール
-
- 安田章大
-
STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドル。音楽・舞台・映像など多方面で活躍する一方、2017年に脳腫瘍(髄膜腫)の手術を受けた経験を持ち、現在も光過敏の後遺症と向き合いながら活動を続けている。当事者の視点から、視覚に課題を抱える人々にとっての映像体験のあり方に深い関心を寄せており、今回Netflixでは音声ガイド制作に初めて参加。
- フィードバック 86
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-