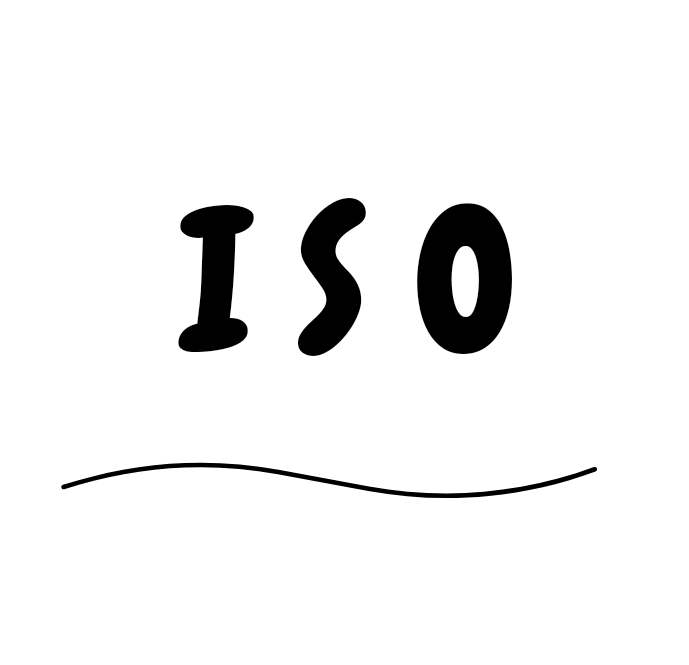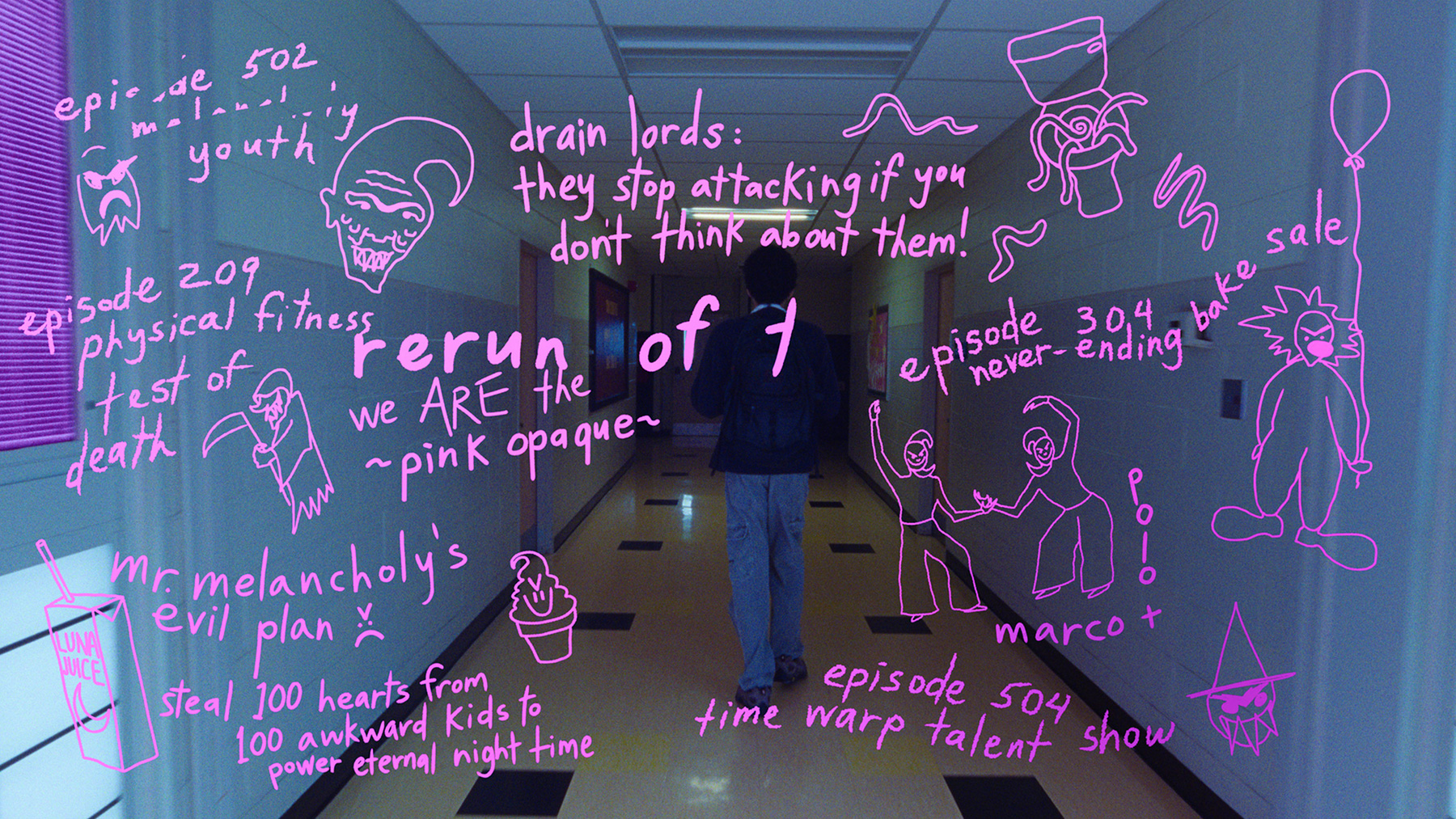メイン画像:© 2025 Real Time Situation LLC. All Rights Reserved.
爆炎。銃声。飛び交う無線の指示。負傷した仲間の兵士は、叫び声を上げ続ける。いったい何と、何のために戦い、どうしたら「達成」なのか。それすら劇中では明確にわからず、観客は95分間、ただ戦場に投げ込まれたような感覚を味わう。『ウォーフェア 戦地最前線』は、元米兵であるレイ・メンドーサ監督の体験を「再現」した作品だ。
2001年9月11日、ニューヨークの世界貿易センタービル2棟に、国際テロ組織「アルカイダ」がハイジャックした航空機が激突した。アメリカはイラクのフセイン政権がアルカイダとつながっているとして、イラクへ侵攻。2003年、イラク戦争へと突入する。
レイ・メンドーサ監督は、当時アメリカ特殊部隊の小隊に所属し、危険地帯ラマディで、アルカイダ幹部の監視と狙撃の任務についていた。その経験を当時の同僚にも聞き取ったうえで、同じ時間幅で再現し、映画として立ち上げた。
自身にとっても大きな傷であるトラウマ的経験を、わざわざ映像に起こした理由とは? そこには、壮絶な体験から記憶を失った同僚の存在があった。そして、映画製作が監督と同僚にもたらしたのは、トラウマを治癒するような効果だったという。
戦争経験から映画製作におけるセラピー的な効果、そしてイラクの民間人に対する犠牲についてまで、メンドーサ監督にインタビュー。戦争とは何か、監督の目線を通して考えたい。
あらすじ:2006年、イラク。監督を務めたメンドーサが所属していたアメリカ特殊部隊の小隊8名は、危険地帯ラマディで、アルカイダ幹部の監視と狙撃の任務についていた。ところが事態を察知した敵兵から先制攻撃を受け、突如全面衝突が始まる。反乱勢力に完全包囲され、負傷者が続出。救助を要請するが、さらなる攻撃を受け現場は地獄と化す……。
なぜトラウマ的経験を映像作品に? 記憶を失った「エリオット」の存在
—イラク帰還兵の多くがPTSDやうつ病を患っているように、この記憶は監督にとっても大きな傷であると思います。それでもその記録を映画として再現したのはなぜだったのでしょうか?
レイ・メンドーサ(以下、メンドーサ):本作をつくった理由はいくつもあります。まず第一に、私の指標となったのは「エリオット(※)に何が起きたのかを再現すること」でした。というのも、エリオット自身はその出来事を覚えておらず、知りたがっていたんです。
※アメリカ特殊部隊の小隊8名のなかで、狙撃手を務めていたエリオット。皆から信頼されていた存在。作中では、爆撃により意識を失ってしまう様子が描かれている。
メンドーサ:私が映画業界に入ったのは15年ほど前ですが、その頃はまだこのことを映画にしようとは考えていませんでした。むしろ軍を退役した当初は、自分がやりたいことを見つけるまでのつなぎとしてスタントマンをしていたような状況で、本格的に映画業界で働くつもりもなかった。特段望んだ仕事ではなかったんですが、娘を養わないといけませんでしたから。
ところが、仕事のなかで映画という表現形式やストーリーテリングについて学び始めると、次第にその魅力に惹かれるようになっていきました。

レイ・メンドーサ
元米海軍特殊部隊(ネイビー・シールズ)出身の映画監督・脚本家。アレックス・ガーランド監督作品『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(2024年)に、軍事アドバイザーとして参加。イラク戦争従軍中に遭遇した出来事を再現した『ウォーフェア 戦地最前線』(2025年)では、ガーランドと共同で監督・脚本を手がけた。
メンドーサ:さらに言えば映画づくりは、私にとってセラピーのような役割も果たしました。『ウォーフェア』以前も、私はさまざまなアクション映画に携わっています。そこにも私の軍隊での経験——数々の銃撃戦や悲劇的な出来事、そして楽しかった記憶も含め——を、作品に落とし込んできました。観客からはそう見えないかもしれませんが、ある意味、私がつくってきた映画はすべて「自伝的作品」とも言えるかもしれません。
経験を芸術に昇華していく行為には、心を癒す効果があります。人によって、それは詩を書くことだったり、音楽をつくり演奏することだったり、絵を描くことだったりする。私にとってはそれが映画制作でした。映画は自分の心に影を落とす経験を、直接的にさらけ出さずとも、表現できた。そのプロセスは、まるでセラピストと話すような感覚でした。
そうやって自身の体験を映画にするうち、「エリオットがあの出来事を覚えていないなら、いつか彼のために再現できるかもしれない」と考えるようになりました。当初は30分くらいの映像を、自費で製作するつもりだったんです。質の高いものにしつつ、制作費を抑えるため有名俳優も起用しない。ただ彼がDVDを再生することで、曖昧な記憶のなかで答えがないと感じていた疑問に向き合ってもらうことだけが目的だったから。
そうこう考えながら時間が経ったある日、アレックス・ガーランドと出会いました。私はそれまでにストーリーテリングについてさらに学び、カメラやグリップなどさまざまな仕事も経験して映画製作の全体像の理解を深めていました。最後に必要だったのは、誠実な考えを持って一緒に制作をしてくれる人々を見つけること。それがアレックスたちだった。
ありがたいことにA24は、私たちに裁量を与えてくれました。アレックスも私の目的を理解してくれて、「事実に忠実であること」「エリオットの物語を再現すること」を徹底的に支えてくれました。

© 2025 Real Time Situation LLC. All Rights Reserved.
軍事アドバイザーを務めた『シビル・ウォー アメリカ最後の日』から『ウォーフェア』製作へ
—軍事アドバイザーを務めた『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(以下、『シビル・ウォー』)の撮影時に、アレックス・ガーランド監督に海軍時代の出来事を共有したそうですね。『シビル・ウォー』での経験がどのように『ウォーフェア』製作につながったのかを教えてください。
メンドーサ:私はスタントマンからキャリアをスタートさせましたが、経験を積むにつれ、技術アドバイザーとして大規模な爆発や銃撃戦を伴うアクションシーンの演出を手掛けるようになりました。参加したのは『ローン・サバイバー』(2013年)や『マイル22』(2018年)、『アウトポスト』(2019年)といった作品ですね。それらの作品において、俳優にはとても激しくダイナミックな動きが求められ、多くの訓練と調整が必要だったんです。
『シビル・ウォー アメリカ最後の日』あらすじ:連邦政府から19もの州が離脱したアメリカ。テキサスとカリフォルニアの同盟からなる「西部勢力」と政府軍の間で内戦が勃発し、各地で激しい武力衝突が繰り広げられていた。ニューヨークに滞在していた4人のジャーナリストは、14か月一度も取材を受けていないという大統領に単独インタビューを行うため、ホワイトハウスへと向かう……。
メンドーサ:そういった仕事をするうちに、著名なスタント・コーディネーターであるジェフ・ダシュノーから『シビル・ウォー』に誘われたんです。「終盤に大規模な銃撃戦がある。西部勢力がホワイトハウスを占拠しようとするんだ」とおおまかに説明されたんですが、曖昧な部分が多く、詳細が詰められていなかったんです。だからこそ私の役割は、すべての部門と連携して、その世界をあらゆる角度から立体的に構築することでした。
ただ時間の制約があり訓練時間も限られていたので、私は軍隊時代の同僚を呼ぶことにしました。「彼らは本物の動きが安全にできるし、武器にも精通していて、訓練の必要も最小限で済む。非常にダイナミックで映画的なアクションシーンが撮れるはずだ」と。それで撮影時には、あらゆる場所で同時多発的に戦闘が行われていて、カメラをどこに向けても何かが起きている状況を生み出しました。
アレックスはカメラのオペレーターという立場から、その撮影をものすごく楽しんでいました。まるで子どもがお菓子屋さんにいるような気分でね。全方向でクールなアクションが行われているので、それをできるだけ多く、標的を狙うように素早くカメラに収めていきました。

アレックス・ガーランド
1970年、イングランド・ロンドン生まれ。小説家としてキャリアをスタートし、『ザ・ビーチ』や『The Tesseract』などの作品で知られる。その後、脚本家に転身し、ダニー・ボイル監督の『28日後...』(2002年)でデビュー。2015年、監督デビュー作『エクス・マキナ』(2014年)で、『アカデミー賞』オリジナル脚本賞のほか、『英国アカデミー賞』優秀英国映画賞、『優秀英国新人賞』にノミネートされた。脚本・監督作品に『アナイアレイション ‒全滅領域‒』(2018年)、オリジナルテレビシリーズ『DEVS/デヴス』(2020年)、『MEN 同じ顔の男たち』(2022年)などがある。『ウォーフェア 戦地最前線』(2025年)では、レイ・メンドーサと共同監督・脚本を務めている。
メンドーサ:また編集作業中にアレックスが映像を送ってくれたので、それに対する意見も伝えるようにしていました。最終的にホワイトハウスの最終シークエンスは伴奏もなしで、ほぼ撮ったまま使われています。そして完成後、アレックスから「『シビル・ウォー』の最終シークエンス自体を一本の映画にしてみないか? 監督は君にしてほしい」と提案してもらい、受けることにしたんです。
いくつかアイデアはありましたが、時間の圧縮や「わかりやすい敵役」をつくるための脚色、主人公が明確な三幕構成といった映画的な技を一切使わずやりたかった。かつ、実際に起きた時間幅で描けるという条件に合致したのが、まさにエリオットの物語でした。そして関係者全員に連絡を取り、了承を得て、制作が始まりました。
戦争経験を語り合うことが「治癒」になった。蓋をしていた感情が溢れ出す
—この出来事について、当時一緒に任務についた仲間たちにも話を聞いたそうですね。そしてみんなの記憶を脚本としてまとめていったと。
メンドーサ:おっしゃるとおり、当時そこにいたほかの兵士たちにインタビューを行いましたが、彼らとこの出来事について話すのは、じつに20年ぶりでした。若い頃の私たちはいわゆる「アルファ男性(※)」タイプで、内に秘めた感情を話すことを良しとしなかった。加えて、イラクでの過酷な任務をこなすためには、心に蓋をする必要がありました。日々を耐え抜くために、みんな感情を押し殺すことを学んでいくんです。
そして帰国するとそれぞれ別の部隊に配属されるから、最後まで語り合う機会が得られず、みんな自分のなかで「何が起こったのか」を整理できない。そしてまた別の戦場へと派遣され、さらなるトラウマ体験を積み重ね、再び散り散りになる。そのサイクルがただただ繰り返されていたんです。
※動物行動学におけるアルファ動物とベータ動物の指定に由来するスラング。「アルファ男性」とは、自信に満ち、組織においてリーダーシップを発揮するタイプの男性を指す。

© 2025 Real Time Situation LLC. All Rights Reserved.
メンドーサ:そんなかつての仲間達と語り合うことは、セラピーのような効果をもたらしてくれました。もちろん「あのとき何が起きたのか」も話しましたが、それ以上に「あの一瞬一瞬に彼らが何を感じていたのか」に耳を傾け、理解し合うことが重要でした。
恐怖を感じている者がいれば、自分の行動を恥じている者もいて、たった一つの小さなミスを一生悔やみ続けている者もいた。彼らがそんなことを感じていたことを、私は知りませんでした。なぜなら、それについて話し合ったことがなかったから。素晴らしい行動をとった仲間もたくさんいましたし、彼らが何を成し遂げたのかをエリオットにも知ってほしかった。それはエリオットのためだけでなく、私たちみんなが心の整理をするためでもありました。結果として、それは全員にとって癒しの時間となりましたし、多くの意味で気持ちに区切りをつけてくれました。
—20年が経っているとはいえ、そういった過酷な過去や感情について語ることは監督にとっても大変だったのでは?
メンドーサ:ええ、じつに大変なプロセスでした。何年もセラピーに通い、その体験について話す方法を学んできました。本作で扱っているのはエリオットの人生を致命的に変えたトラウマ的な出来事ですが、戦場の悲劇はそれだけではありません。私は17年間軍に所属していたので、そのあいだに人生に暗い影響を及ぼし続けるような、仲間の負傷や死を目撃することもありました。そうやって積み重なった多くの出来事を一つひとつ解きほぐしていく必要があったんです。
個人的な問題から除隊したときも、それまでに受けたトラウマは解消されていなかった。退役軍人省(The VA)は除隊した兵士たちが本当に必要としていた支援——より個別化された、一人ひとりに寄り添った治療——を用意できていなかった。本来個別に対処すべきものを「PTSDならこの処方箋、この薬、この手順」というように、決まった型に押し込められているようでした。だから今回語り合うことは大変でしたが、結果的に今回の経験がかつての出来事を掘り下げる良いきっかけになりました。

© 2025 Real Time Situation LLC. All Rights Reserved.
—仲間との話し合いのみならず、戦場の体験を再現し、撮影するということも監督にとって治癒的なプロセスとなったのでしょうか? 下手をすれば、トラウマがフラッシュバックする危険もあったのではと思うのですが。
メンドーサ:製作や撮影プロセスも治癒的な効果がありましたが、その大きな要因がアレックスでした。彼はこれまで出会ったどんなセラピストよりも聞き上手。セラピーで一番苛立ってしまうのは、自分が何かを説明したときに、相手がそれをまったく違う解釈で繰り返す瞬間です。
それは相手が悪いわけでなく、理解しようと努めている感情や想いを自分がまだうまく言葉にできていないから。けれどアレックスは私が脚本を書くために説明をすると、同じ言葉を繰り返してから、鋭い洞察力で「なぜ私がそう感じているのか」という視点を与えてくれるんです。
それでもいくつかの出来事に関しては話すことも、実際に撮影を行うことも気が重かった。特に爆発のあと、エリオットに駆け寄る瞬間ですね。現実でそれが起こった瞬間、私はエリオットが死んだと思ったんです。彼はパワーリフトのように体格が良いうえ、装備一式も身につけていてとても重く、車道から引っ張るのが本当に大変でした。私の足にも火傷をしたような痛みが走り、空気中のリンのせいで呼吸もできず、「このまま撃たれて2人して死ぬんだ」と本気で思ったことを覚えています。間違いなく人生で一番恐ろしい瞬間でした。
その場面を撮影する日、私はロンドンのセットにエリオット本人を呼び寄せました。それまでも私は彼に「何が起きたか。どれほど怖かったか」を伝えていましたが、セットで再現されたその瞬間を見たときの彼の姿はまったく違っていました。言葉を発せず、感情が込み上げてきたようで、やがて静かに泣き始めたんです。
彼の姿を見て、20年もの間押し込めていた私自身の感情——怒りや悔しさ、悲しみのような——も表面化し、一気に押し寄せてきました。カットがかかった瞬間すぐにセットから飛び出して、一人でただただ泣き続けたんです。結局その日は撮影どころじゃなくなってしまって、アレックスが代わりに引き継いでくれました。この映画製作のなかでセラピー効果を感じた、数ある瞬間のひとつでしたね。大袈裟でなく、それをきっかけに生まれ変わったような気分になったんです。
米兵の痛みと、イラクの民間人の犠牲と。監督がいま思うこととは
—米兵たちの姿に心を痛めつつも、同時に彼らに突如家を占拠されたイラク人家族や、米兵の先頭に立ち亡くなったイラク人の通訳者についても考えてしまいます。あくまで本作は実際に起きたことを当事者の記録から再現したものであるとわかったうえで聞くのですが、監督が被害を受けたイラクの人々についていま現在思うことを教えてもらえますか?
メンドーサ:イラクには豊かな文化や歴史があって、一部では「文明のゆりかご」とも呼ばれていますね。本当に素晴らしい人たちもたくさんいる場所です。ただあくまで私の意見ですが、そこに入り込んだ邪悪な存在に操られてしまった人たちがいた(※1)。
おっしゃるとおり私は自分が目にした事実を伝えたいだけで、政治的な観点や意見を押しつけるつもりはありません。戦争というのは、はっきり白か黒かで分けられるものではなく、とてもグレーなんです。外から見ていても、得られる情報はとても限られていて、現地で実際に体験していなければ、わからないこともたくさんあります。

© 2025 Real Time Situation LLC. All Rights Reserved.
メンドーサ:人間は誰しも欠点がありますし、時に感情に支配されてしまいます。友人が傷ついたり、亡くなったりするのを見れば当然怒りのような感情が湧きあがります。しかし国から12か月ものあいだ戦地へと派遣され、それが何年も続けば、物事の見方や感情の扱い方といった脳の回路は書き換えられてしまう。戦時の混沌とした攻撃的な環境——相手だけでなくこちらも攻撃的にならざるを得ない——のなかでね。
そうして私たちは対処法を学んでいく。誰かがこちらを撃つなら、こちらは倍返しで撃ち返す。仲間が殺されたら、その10倍相手を殺すというように。それが戦争なんです。もちろん米軍がそう主張しているわけではないですが、戦地で生き残るためには時にそういう心構えが必要となる。
巻き込まれた民間人には責任はない。けれどこれはとても複雑な戦争で、わかりやすく軍服を着た相手と戦うわけではありません。「こっちは青、向こうは赤」というように敵が明確にわかる状況ではないんです。民間人のなかに敵が紛れ込んでいて、それが私たちの意思決定を混乱させていく。それでもし誤って間違った人物を撃ってしまったら、そのことを一生背負っていくしかない。
「兵士は冷酷に現地の人々を撃ちまくっている」と思っている人もいますが、そうではありません。人の命を奪ったことに対する呵責で、自ら命を断った仲間もいました。一瞬の判断とその結果が、彼を深く蝕んだんです。
現地の人々は、ただ普通の生活を求めていました。ただテロ組織であるアルカイダは民間人を強制的に利用し、意思に反して即席爆発装置(IED)を仕掛けさせていた。私たちは当初それを知らず、ただ敵の何者かが街を巡回する海兵隊員を攻撃していると思っていたんです。そうなると私たちも海兵隊を守るために動かなくてはならない。
もし私や誰かが爆弾を仕掛けてこようとする人物を撃たなければ、多数の海兵隊員が吹き飛ばされ、多くの命が失われるかもしれない。そうなると、その罪悪感が一生ついてまわります。「あのとき撃つべきだった。交戦規定上でも撃つことは認められていたのに」と。でも良心が邪魔をしてやめてしまう。いくら戦地で感情を押し殺していても、私たちは機械ではない。思考も感情もある。
でも次に同じような瞬間が来ると「もう海兵隊員が死ぬのを見たくない」と考えて、条件を満たした相手を撃ってしまう。けれどそれが最終的に間違った相手だとわかり、撃った人物の心を生涯蝕み続けることもある。どちらに転んでも、最悪の事態が起こりうるんです。
イラクの人々は本当に素晴らしく、美しい文化を持っています。私たちは、虐待を受けた女性や搾取された子どもたちのために、多くの医療クリニックを設置しました。現地でできるかぎりのことはしたつもりです。当然ながら傷つけたいわけではありませんでしたが、そこには悪意を持って彼らを利用する敵がいて、私たちはそれと戦っていた(※2)。歴史が証明するように、あらゆる戦争で民間人はいつも犠牲になってしまう。戦争がある以上、それは絶対に起こる。どうにかそれが避けられるものであるよう願っていますが、残念ながらそうはいかないのです。
※1 メンドーサが「邪悪な存在」として語るのは、スンニ派過激組織「アルカイダ」を指している。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロを実行した国際テロ組織であり、この事件を契機にアメリカは「テロとの戦い」を宣言し、イラク戦争へと突入した。
※2 イラク戦争は、イラクのフセイン政権にアルカイダとの結びつきがあること、大量破壊兵器を所持しており、それがアメリカと国際社会に対する脅威であることを主な理由として、国連安保理の決議もないままに実行された。この戦争によって、イラクの国土は破壊され、多数の民間人が犠牲になったほか、米兵によるイラク人への虐待や性暴力といった非人道的な行為も報告されている。しかし現在に至っても、イラクとアルカイダとの結びつきは立証されておらず、大量破壊兵器は発見されていない。アメリカは正当な根拠なくしてイラク戦争を実行した疑いが極めて強いとされている。
- 作品情報
-
 『ウォーフェア 戦地最前線』
『ウォーフェア 戦地最前線』
1月16日(金)TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開
脚本・監督:アレックス・ガーランド
レイ・メンドーサ
- プロフィール
-
- レイ・メンドーサ
-
元米海軍特殊部隊(ネイビー・シールズ)出身の映画監督・脚本家。アレックス・ガーランド監督作品『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(2024年)に、軍事アドバイザーとして参加。イラク戦争従軍中に遭遇した出来事を再現した『ウォーフェア 戦地最前線』(2025年)では、ガーランドと共同で監督・脚本を手がけた。
- フィードバック 85
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-