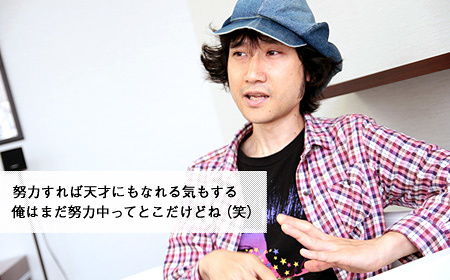「誰もが困難で困った世界の住民である。その事実は生きることよりもシステムに生かされることを選んでしまう方が楽なのではないかと甘く誘う。それは魂を萎えさせ、持っているエネルギーを見失わせてしまうけれど、音楽や文学やアートという人間の『創造』が再度光をあててくれる」
活動歴17年を超える日本ロック界の至宝、ズボンズの実に6年振りとなるオリジナルアルバム『The Sweet Passion』の発表に合わせ、ドン・マツオはこんなコメントを寄せている(一部抜粋)。そう、なぜ今もズボンズはロックバンドであり続け、一度ステージに上がったドンは無我の境地に至ったかのようにギターをかきむしり、シャウトを繰り返すのか。それはロックを鳴らすことが、ドンにとっての光であるからに他ならない。もちろん、それを続けることは非常に困難な作業であることは言うまでもないが、それでもドンは自由を愛し、学ぶ姿勢を崩すことなく、創作の渦中を全身全霊で楽しんでいる。だからこそ、彼のひとつひとつの言葉は重く、僕らの胸にずっしりと響いてくるのだ。
常に創作の渦中にあるっていうのが好きだから、外から出来たものを眺めるっていうことが、あまり得意じゃないんだな、きっと。
―『The Sweet Passion』はオリジナルアルバムとしては実に6年ぶりの作品になるわけですが、2009年に新録のベスト盤が出ていて、当時のインタビューでドンさんは「次のアルバムもできつつある」っていうことを話していらっしゃったと思うんですね。ただ、実際にはそのさらに2年後、昨年末にEP『AGITATION』が自主という形で発表されています。まずは、このあたりの経緯から話していただけますか?
ドン:ずっと作り続けてはいるんだけど、リリースしないでいると、作ったやつをどんどん忘れていっちゃう(笑)。レコード会社とか事務所が予定を立ててくれて、「ここまでにアルバムを」というのが決まってれば、それに合わせて完成させるのだけど、今はインディペントだから全部自分で決めることになる。そうなると、いつまでも締め切りが来ない状態なんですね。『AGITATION』は、去年そろそろ年内のスケジュールを決めなきゃという時期に、「あれ、米ツアーはやったのに、今年国内ツアーやってないんじゃない?」って話が出てきて、だったら「そのとき売る為のCDがないとダメなんじゃない?」、前に作った曲を引っ張り出してまとめたわけです。
―では、『The Sweet Passion』のリリースが決まるまでの経緯は?
ドン:昨年の米ツアー終わりの1週間でアルバム1枚分を録音したんです。でも例によっていつリリースするかは考えてなかったので1年近く放っておいたんですね。それでズボンズを今回はスペースシャワーがレーベルとして力を入れて一緒にやってくれることになったので、「じゃああれを」と聴き返したら、「あれ? 今やってることとずいぶん違ってるんじゃない?」と思って、慌てて東京で追加録音して、最終的にはアメリカ録音のものと半々になりました。

ドン・マツオ
―じゃあ、今は「早く作品をリリースしたい」っていう気持ちはあまりないわけですか?
ドン:「出す」と決まらないと、完成させたくないようなところもあるんじゃないかな。完成させちゃうと、終わっちゃうから放ったらかしにしていることが多いです。曲はものすごくいっぱい作るのだけどね。
―資料にも「ギターを弾き始めた瞬間からそれは作られていき、終わったときに完成している」っていうコメントがありました。
ドン:そう。曲はいくらでもあるというか、インターネットの世界につながってるような感じで、自分が作っているというよりも、どこかにあるような感じかな?
―常時接続で、パッと開けば、すぐに何かが出てくる?
ドン:何か巨大なデータベースに繋がっているみたいな、何となくそんな感じですかね。それが自分の創作のスタイルなんでしょう。だから家でフォークギターを鳴らして試行錯誤して作ることは、滅多にないです。
―つまり、作品を完成させることよりも、自然に曲作りを続けることに喜びがあると。
ドン:うん、常に作ってる途中の状態が好きなんだと思うんですよ。だから最終的に「出来た」ものにはあまり興味がなくて、全然聴き返したりしない。だから、今回みたいに過去のPV集制作に立ち会ったときに、ものすごく久しぶりに昔のを聴き返して…「案外悪くないな」と思いました(笑)。作った直後は「どうも上手く出来なかったなぁ」と感じるから、「2度と聴きたくない」と思っていたのだけど。
―それって、「もっとよくなるはずだった」みたいなことなんでしょうか?
ドン:基本的に自分を過大評価してるんでしょうね。だから、何を作っても「こんなはずじゃない、こんな程度じゃないんだけどな」って感じる。客観性にすごく欠けてると思う。常に創作の渦中にあるっていうのが好きだから、外から出来たものを眺めるっていうことが、あまり得意じゃないんだな、きっと。
―古い曲を聴いて「悪くない」と思えたのは、やっと客観視ができるようになったっていうことかもしれないですね。
ドン:10年くらいたって、ようやく。でもそう思うことで、自分に満足を覚えてしまうと、まだまだもっといいものを作らなきゃっていう意識やモチベーションが、その分薄弱になってしまう気もします。何しろ過去にもう10枚もアルバムを作っていて、曲もふんだんにあるし、例えばライブのセットに「お気に入りの昔の曲」を入れ始めると、そればっかりで新しいことをやる隙間がなくなっちゃう。だから、結局のとこはあんまり振り返らない方がいいんじゃないかと思っているのだけど。
先行きの読めない中に俺たちがいる、そこが一番面白いとこなんじゃないかな。
―今って一般的にCDとか音源の価値が下がって、ライブが大事って言われてるじゃないですか? そういったことはどうお考えですか?
ドン:みんなそう言うけど、それは単なる経済的な話だと思うんです。でも、芸術表現としてのポップミュージックの有り方というのは、それとは離した形で考えないといけないと思う。ライブや作るレコードをより良いものにするっていうのは、経済の話じゃなくて、アーティストそれぞれの本質的な意欲によるでしょう? そこは掛け値なしに努力したくなってないとイカンですよね。
―意識の低さを感じることが多いですか?
ドン:さてね。ただ現代はすごいライブや音源を簡単に見たり聴いたりできるわけでしょう? 60年代のジミ・ヘンドリックスも、最近の海外のインディーロックも、様々なエクスペリメンタル音楽の映像もインターネットを介してすぐ見れる。そういう経験を通過して「これよりもっといいものを、より面白いものを作りたい!」という、貪欲に挑戦する姿勢を持ってガツガツやっている人は、そんなに多くない気がしますね。だから、メディアとかハードの発展・進歩と、表現能力・欲求の向上が比例してるとは言い難いなと思う。
―今ドンさんはDON Matsuo Groupとして若いミュージシャンとも共演されてるじゃないですか? それって若いミュージシャンの意識を高める、ある種「伝えていく」っていう意識みたいなものが近年出てきてるのかなとも思ったのですが?
ドン:うーん、伝えようとしてるわけではないかな。とにかくステージに集まって、曲っていうものが無いフリーな状態から、すごい簡単な取り決めだけで、あとはステージ上で作り出されている音楽に反応する。それをひとつのショウとしてまとめ上げるっていうことをやってるんだけど、つまりは創作のプロセスの、まさに現在進行形の中に、いきなりみんなを飛び込ませるという、そういう試みなんです。
―それをやることの意義をどこに感じているのでしょう?
ドン:うーん、意義はあるのかな。ただボクの興味は、とにかく「今ここ」にいる様々な寄せ集めメンバーで、一体何をこれからやるんだろう、何が生まれるのだろう、というとこですね。先行きの読めない中に俺たちがいる、手持ちの資質は限られているけれど、ここで「何か」をやらなければならない。その時にそれぞれがどんな「火事場の馬鹿力」を出してやり切るのか。そこが一番面白いとこなんじゃないかな。ボクの考えるロックの本質、「プリミティブな創造力の発露」みたいなものが体感できるってわけですよね。創作の渦中にいることで。
―今の若いミュージシャンのライブ全般に対して思うこととかってありますか?
ドン:「ロックバンドのライブ」という、ひとつの形みたいなものが出来過ぎてるところがあるように思う。30分のステージだったら、どの曲と何と何をやって、ここでMCをして、終わったら物販に回ってTシャツ売ってっていう、決まりきったシステムとしてやってるような。自分たちとしては自由を表現するために音楽をやっていると思ってても、「無意識の下の形式」に囚われてはいないだろうか。自由である、というのは本当に難しい。一方では暴れたりとか、悪い態度取るのも同じく…。
―それはそれで、ひとつの型にはまってる行為であって。
ドン:そうですね。結局、無意識のうちに今までのロックの歴史の中のある1つの「羽目を外す」パターンをトレースしてるに過ぎないというかね。難しいです。だからボクは常に、「これは自分が何かを演じようとしてないか、そういうパターンに陥ってないか」ということは、考えてしまいますね。

THE DOORSのファーストとか、THE ROLLING STONESの『STICKY FINGERS』とか、そういうのが雲の上の手に届かない存在とは思えないです。
―『The Sweet Passion』を聴けば、ズボンズはズボンズでしかないと思います。いい音と、いい演奏と、いい録音があって、もう何をやってもズボンズだっていう。
ドン:そうであればいいと思うけど。でも今回のアルバムに限って言えば、長くやり続けてきてやっとちゃんとした曲が書けるようになってきたとは思いましたね。初めてそんな感じ。
―10枚目にして初めて?
ドン:そう。今までのは、いいのもあるし、どうでもいいようなものもあるというか、「なんかちょっと真似っぽい感じなんじゃないか」という心の嘘を押し隠していたりして、完全には自信が持てない部分もあったと思うんだけど、今回はそういうのがないですね。そうだなぁ、例えば、THE DOORSのファーストと、『The Sweet Passion』は、良し悪しの問題というより、好みの違いだなって思う感じ。
―上下の関係ではなくて、並列に並んでいるもののひとつとして捉えられる?
ドン:そういう風に感じますね。THE DOORSのファーストとか、THE ROLLING STONESの『STICKY FINGERS』とか、確かにロックアルバムとしては最良のものなんだけど、そういうのが雲の上の手に届かない存在とは思えないです。
―10枚目にしてそこにたどり着けたのは、何が大きかったんでしょう?
ドン:まあ…年かな(笑)。97年にデビューした時点では、ボクはほとんど何も持ってないような状態だったと思う。曲を作るにしても、アイデアと勢いだけ。例えば、あのブルースのリフと、このヒップホップのリズムと、レゲエのベースラインをミックスして曲にして、歌詞を乗せたらそれでいいんじゃないかと思っていた。ギターの練習なんかクソくらえとか、そういうパンク・オルタナティブ以降の感性でやり始めてたものだから、アイデアぐらいしか持ってなかった。でも、一個人の感性っていうのは、実に全然大したことないんですよね。だから、やり始めてすぐにたまたま色んな人に知られることにはなったけれど、実際は全然器量不足だったというか、そういう形でのスタートだった気がしますね。
―そこからどう変化して行ったのでしょう?
ドン:「これじゃ全然ダメかもしれない、底が割れてしまうかもしれない」というのはどこか気付いていて、自分のキャパシティを広げるために、それまで怠ってたいろんな方面の勉強をやる必要が出てきたんです。そこからもう10年は経ってるんじゃないかな。それでまあ、今になって若い子たちとやって、説教するようになったりして(笑)。ようやく筋肉がついてきたというか、そんなような状態な気がしますね。
何も決めないでステージに上がって、でも何の恐怖もなく、それをちゃんとした形でやり終えることができるっていう風に思えるようになった。
―「音楽を続ける」ということ自体に迷いはありませんでしたか?
ドン:続けるのはやっぱり大変なことですね。よく、「やりたいからやってる」と言うのだけど、ボクの場合は「やりたいかやりたくないかはどっちでもいい」という感じがある。ただ、やる必要性が自分にとって人生の中であるのかないのかという事を真剣に考えてみれば、やる必要があるかもなって思うわけです。つまりそれは、もし自分がこの「創作する」という活動全部を捨ててしまったら、自分の人生にどれくらいの損失を与えるかっていうね。
―それは「やりたいから」っていうのとは違うと。
ドン:もうすでに、創作し続けることに自分の人生全部が深く関わり過ぎてしまっている。巻き込まれ過ぎてる、完全に。だから、それを止めて、普通の仕事をやって普通の人の生活をしてこの後の一生をやっていけるのかというと、ちょっと無理だなと思う。そうしてしまうと抜け殻の余生みたいになってしまうかもしれない。生きていくことはできるだろうけど、本質的には、自分の「生きる」というエネルギーや喜びを伴ったものとは違うものになるでしょう。だから、「止められない」んですね。「やりたいから」っていうのとはちょっと違う。

―なるほど。
ドン:一方でもしかしたら、あんまり幸せになれないかもしれないという心配もある。 創作することそれ自体に一番の喜びの中心を持ってきてるわけだから、「一般的な幸せ」というものを優先して考えれなくて、普通の目で見れば不幸というようなところで終わるかもなと考えたりもしますね。ただ、もう完全に巻き込まれてしまっているから、それを取り除くっていうことは、イコール自分の人間性のある部分を完全に抜き取ってしまう、なんだかロボトミー手術みたいな、そんな感じになってしまうのだと思いますね。
―いつから創作の渦中に巻き込まれたのでしょう?
ドン:自分が今やってるようなことを、これがもしかしたら誰にもできない自分の一番得意なことかもしれないなと思い始めたのは、ここ数年ですね。何も決めないでステージに上がって、でも何の恐怖もなく、何かを創り出した形でやり終えることが出来ると思えるようになったのは。
―そう思えたのは、どんな部分が大きかったのでしょう?
ドン:まぁ、何度もやっていくうちに確信が強くなっていっただけでしょう。ノープランで空っぽの状態でステージに上がっていったとしても、やり始めて出てきたものを上手くキャッチできさえすれば大丈夫、と。自分というちっぽけな存在の創造性に頼るのではなく、もっと大きな「音楽」という存在に身を任せるということが出来るようになった。だから、自分の持ってる頭・脳ではっきり認識できる能力と、ユングなんかが言うような、人間の無意識にあるデータベースみたいなものとの繋がりに関しては、いろいろ考えたり勉強もしましたね。意識のある状態から無意識の状態に、ある種の瞑想状態みたいなものかもしれないけど、そういうところに自分をすぐ持って行けるようにはなりましたね。
―もう少し細かく説明していただけますか?
ドン:うーん、説明するのは難しいのだけど。ある種「いたこ」みたいな状態にも近いかもしれない。とりあえず自意識を放り出して、そこで生まれている音楽に身を任せる。その音楽は自意識が作り出したものというよりも、無意識下から出てきているようなものと感じる。でも演奏中にそっち(無意識)側にだけ入り込んでしまっていては演奏が無理だから、その間でバランスを取ってるわけ。こっち(意識)の状態がずっとアウトプットしているのだけど、それと同時に、無意識の状態で、音楽全体が流れる方向を感じて変換しているんです。その瞬間の「音楽の流れ」を上手くつかんで、こっち(意識)のフィジカルな部分に情報を伝えていく、それがライブの現場で起こってること。ものすごくバンドの演奏が上手く行ってるときっていうのは、みんながそこ(無意識)に巻き込まれてるんです。言うと、難しいな。
―自分の意識もそこにはあるけど、あくまで音楽の流れる方向に従ってると。
ドン:そうね。それは一般的なロックバンドがやってることではないかもしれない。サン・ラとか、オーネット・コールマンだったら近いのかな? でもボクらはあくまでロックバンドで、演奏もロックですから。そういう意味では、ユニークだろうなと思います。でも、自分の見解としてはごくごく真っ当なロックをやってるんだけどな、とも一方では思いますね。結局、ロックというものの解釈によるかな。
―では改めて、ドンさんのロックの解釈を聞かせてください。
ドン:ボクはロックというものを、自然発生的で、かつプリミティブで、底のものすごく深い精神と意識の自由みたいな、そういうものを解放してくれるものだと考えています。だから、形式として「こういう音楽がロック」っていうものではない。限りなく自由な存在でありますね。だから自分が考えているロックについて語っても、すごく抽象的になるんじゃないですかね。「ロールしてればロックなんだよ、ベイビー」というわけにはいかない。ロックに対して強い思い込みがあるというか、ほとんど信仰に近いと思いますね。だからやり続けているのだと思います。
みんな天才とか好きだから、あらかじめ持った能力とか、そういう風に考えがちなんだけど、実際はほとんど絶え間ない努力な気がするんですよ。逆に言うと、誰もが努力すれば(天才にも)なれる。
―CINRAの読者って、音楽に限らず、創作・表現に対しての強い関心があって、自分もその道を志してるっていう人も多いと思うんですね。そういう若い人たちに、ドンさんから何かアドバイスをいただければと思うんですけど。
ドン:この前大阪にライブに行ったときに、カメラマンを志望してる男の子が一緒に来たいというんで、一緒の車で連れて行ったんですね。そのとき話したのは、例えば、ある老人の写真を撮るとして、すごくいいカメラマンが撮ったら、その人が重ねてきた年齢なり、知恵なり、歴史みたいなものすら見えるような写真になるかもしれない。でも、その辺の人が撮ってもただのスナップ写真にしかならない。その違いはどこから来るのか? そこはつまりは、「自分が」相手から何を読み取れるかっていうところで、その差が出てくることになる。ということは、「自分」がそれを対象から読み取れるだけの何者かになってない限りは、「何か」という写真は撮れないのではないか。
―なるほど。
ドン:創造する人間というのは、自分の中の感受性みたいなものを豊かにするための努力を延々とやり続けなくちゃならない。自分が何かを感じたときに、具体的に言語化できる言葉の能力だって必要になる。 「かっこいい」「楽しい」「なんかいい」っていう、最大公約数的にまとめてすべて表現できる言葉じゃなくて、もっと自分の感じている微細な存在をより正確に、的確に表現できるような言語力が必要になる。そうすることで「感性」がよりしっかりしたものとして、その人に定着するでしょう。その為には本を読んで勉強して…みたいに、ものすごく時間と労力を注ぎ込まなければならないんですよね。ひとつの絵を見て、これがどう良いように感じるのか、どこに響いたのかを、自分の見方で話せるか、実際に感動できるかどうか、そういうことをひとつひとつ表していき、蓄えていければ、それは立派な表現者ですよね。
―ドンさんもまだ途上にある?
ドン:そうね〜、10年とかじゃ終わらなかった(笑)。ホントまだまだ。音楽ひとつとっても、クラシックミュージックなんかずっと避けてきてたのだけど、ここ1〜2年は分かろうと集中的に聴き続けてみたりして、分かってくるとやっぱりいいものね。当たり前のことだけど。そうやってひとつのことが分かると、それまで見てきた景色がもっと微細に分かるようにもなってきて、より楽しみも多く・深くなりますね。

―ああ、よくわかります。
ドン:みんな「天才」というのが好きだから、すごい人を見ると、あれはあらかじめ持った能力だから…とか、そういう風に考えがちなんだけど、実際はほとんど絶え間ない努力じゃないかという気がするんです。逆に言うと、誰もが努力すれば(天才にも)なれる。ボクも努力の結果、43になってそれなりに曲が作れるようになってきた(笑)。
―(笑)。
ドン:表現するしないに限らず、自分が意欲的に勉強を続けていけるかどうかというのは、その人のその後の人生を大きく変えてしまうと思う。資格を取るとか、自分の今後の仕事に有利かもしれないからこれをしようとかだけでなくて、偉大な芸術・文学作品を理解することとか、アートと言われるあらゆるもの、ある意味ハイカルチャーみたいなものを理解しようとする意識が強い方が、人生はより実りの多いものになるのではないかな。年は誰もが取るけど、内面っていうのは自分の努力ででしか磨き上がっていかない。
―ドンさんを見ていると、まさにその通りだなって思います。
ドン:いやいや、永遠に努力中ってとこだけど(笑)。
- リリース情報
-

- Zoobombs
『The Sweet Passion』(CD+DVD -
2012年6月6日発売
価格:2,800円(税込)
Zbon-Sya1. Plasticity
2. Big Picture
3. We're Gonna Get Down
4. Come With Us
5. Bored Kid
6. Amazing Grace
7. New They,New We,New You,New Me
8. African Beat Drive
9. My Big Friend
[DVD収録内容]
1. Highway A Go Go
2. Black Ink Jive
3. Mo'Funky
4. Bomb The Bomb
5. South Central Rock
6. Hot Love
7. Tighten Rap
8. Doo Bee
9. Jumbo
10. Funky Moving
11. Superman
12. DON's Dream
- Zoobombs
- プロフィール
-
- Zoobombs(ズボンズ)
-
1994年9月、満月の夜に東京にて結成されたオルタナティブ・ロックバンド。Rolling Stonesの"正統的"なRockサウンドを基礎に持ち、James BrownのFunk、Miles DavisのElectric Jazz、Stoogesのサイケデリック&アバンギャルド感覚をミックス。Hip Hop以降、オルタナティブ・ロック以降の感性で演奏する。18年目にして、オリジナル・アルバムとしては10枚目、6年振りの「The Sweet Passion」(日本盤)を6/6にリリース。8月〜10月とWorld Release & World Tour(Japan/Australia/Canada/USA)が予定されている。ZOOBOMBS are DON Matsuo(vo,gu)/Matta(key)/Moonstop(ba)/Pitt(dr)
- フィードバック 4
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-