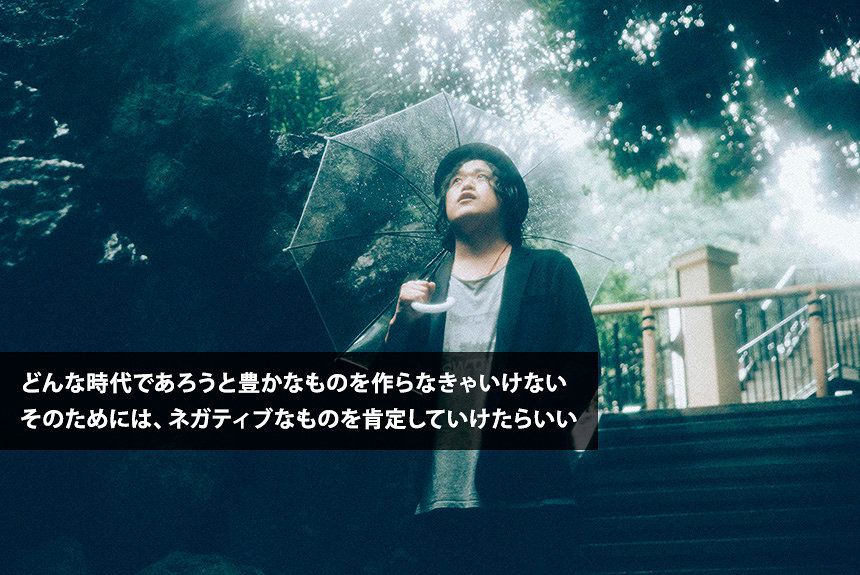長澤知之の“あああ”という、身も蓋もないようなタイトルの曲は、間違いなく、僕にとっての2019年のベストトラックのひとつだ。たったの1分2秒しかない曲だが、その1分2秒の間に、真実がある。これは長澤知之の歌だが、僕にとっての真実の歌でもある。こういう音楽に出会ったときに、なにも信じていない自分でも、実は、信じているものがあるのだと気づく。
この“あああ”を1曲目に置いたミニアルバム『ソウルセラー』を3月に、そして、続くミニアルバム『SLASH』を10月にリリースした長澤。「信仰」というモチーフを、現代的かつアイロニックな物語に落とし込んだ衝撃作“ムー”から始まる『SLASH』も、いい。“90's Sky”のようなロックサウンドを聴かせる曲からも、長澤の音楽に対する無邪気な愛情や、音楽と共に歩んできた人生を感じさせる。長澤知之とは、個人も時代も、自分も他人も、思想もユーモアも、すべてを「音楽」という点で交錯させる稀有なシンガーソングライターなのだと、改めて感じ入る。
変化を求めて声を荒げる人がいる。冷静な振りをして絶望している人がいる。傷ついているのに泣けない人がいる。笑っているけど怒っている人がいる。いろんな人がいる。いろんな人がいるなかで、長澤の歌は人間の「弱さ」に寄って立つ。この歌は、あなたを映すだろうか。聴いて、たしかめてみてほしい。
長澤知之“あああ”を聴く(Apple Musicはこちら)
怒りは大きいですね。いい動機になります。
―今年は『ソウルセラー』と『SLASH』という2枚のミニアルバムがリリースされましたけど、僕としては、この2作品を聴いていると非常に安心できるというか、「よく眠れるなぁ」という感覚があって。もちろん、サウンド的には激しい部分もあるし、エグイ感情が歌われている曲もあるんだけど、でも、長澤さんの歌を聴いている間は、毛布にくるまれているような安堵感を抱くことができるなぁ、と。
長澤:……最高ですね、それ(笑)。基本的に、音楽でなにかを傷つけたいとかは思わないですからね。僕は未熟な人間なので、イガイガが飛び出しちゃうことはあるのかもしれないですけど、基本的に、音楽を聴くときには気持ちよく聴いてほしいなと思っています。

10歳でギターを始め、1年足らずでオリジナル曲の制作をスタート、18歳でオフィスオーガスタのデモテープオーディションでその才能を認められる。2006年8月、メジャーデビュー。2015年にはAL(小山田壮平×長澤知之×藤原寛×後藤大樹)のVo&Gtとしても活動を正式にスタート。2019年3月にアコースティック・ミニアルバム『ソウルセラー』を、そして10月2日にはバンドサウンド・ミニアルバム『SLASH』をリリースした。
―今年、こうして2枚のミニアルバムにわけてリリースされるというところには、なにかしらのコンセプトがあったのでしょうか?
長澤:この2作は単純に、アコースティックなもの(『ソウルセラー』)と、バンドサウンドもの(『SLASH』)っていうくらいの違いですね。歌っていることも、自分の喜怒哀楽や考え方が根底にあるのは変わらないので、同じベクトルで、デコレーションが違う感覚です。
あと、できるだけコンパクトに曲を出せたらいいよねって、周りの人とは常々話をしていて。自分が考えていることは日々変わっていきますから、それを曲にしつつ、できるだけタイムラグのない状態で出したいんですよね。
長澤知之『ソウルセラー』を聴く(Apple Musicはこちら)長澤知之『SLASH』を聴く(Apple Musicはこちら)
―それだけ、長澤さんにとって音楽はリアルな感情の発露であるということですよね。この2作を聴いて改めて感じるのは、とてもパーソナルな場所から生まれてきた想いや感情が、時代性や社会性をはらんだ歌へと昇華されていくのが長澤さんの音楽なんだな、ということで。
長澤:音楽を作るときに意識していることは、自分のなかにあるものをただ出すということだけですね。音楽ではかっこつけたりせず素直でありたいと思うし、普通の会話のなかでは言わないであろう言葉でも、音楽のなかでそれが適切だと思ったら書くようにしています。
僕にとって音楽を作るのは、いわば、デトックスみたいなものなんです。「怒り」のような感情を自分のなかに溜め込んでしまったら健康によくないから、音楽にすることで昇華させている。それで感情がポジティブな方向に向かえば自分の生活にとっていいことだし、もし、同じような怒りを感じている人がいたら、共感によって、お互いがすっきりできたりもするのかなと思うので。
―音楽が生まれる根源の感情としては、「怒り」は大きいですか?
長澤:怒りは大きいですね。いい動機になります。

根本的に僕は、日本に対して、わりと悲観的な考えを持っているんです。
―たとえば、『SLASH』の7曲目“シュガー”は、<誰かの描いた物語のヒーロー ヒロインになろうと / 君は君から飛び出して挫けてスマホへうつむいた>という歌い出しからも、曲の前提には今の社会の在り様が浮かび上がってきますよね。そのうえで、長澤さんは<ビターな歌はどうだい>と問いかけている。
長澤知之“シュガー”を聴く(Apple Musicはこちら)
長澤:“シュガー”では、「不条理ってあるんだよ」ということを言いたかったんです。不条理を肯定したうえで、すごく簡単なことだけど、「また陽は昇るし、明日は来るよ」ということを歌っている。この曲は、最初に作っていたときは、友達の子どものことを思い描いていて。
―たしかに、大人が子どもに語りかけているような歌詞ですよね。
長澤:根本的に僕は、日本に対して、あまり楽観的になれなくて。わりと悲観的な考えを持っているんです。

―それは、どういった部分で?
長澤:なんというか……僕からすると、「シュガーすぎる」というか。インターネットの影響なのかなんなのかは知らないですけど、みんな言いたいことがあるのに、それをなかなか言わなくなっているような感じもするし。もっとみんな、素直に会話ができたらいいなって思うんですけど。
でも、僕らがこれからを作っていくわけですし、カルチャーも、どんな時代であろうと豊かなものを作っていかなきゃいけない。そのためには、ネガティブなものを肯定していけたほうがいいよなって思うんです。
―「自分が生きている環境を豊かにするためには、ネガティブなものを肯定するほうがいい」というところが、すごく長澤さんらしいなと思います。
長澤:“シュガー”自体は、結構、救いのないことを歌っていますから。でも、それをマイナーコードで暗くどんよりと歌うんじゃなくて、ちょっとレゲエっぽくしておちゃらけてやると、音楽って不思議なもので、歌詞もどこか肯定的に聴こえてきたりするんですよね。
―おちゃらけたり、笑えたりするということは、すごく大事ですよね。
長澤:そういうものは好きですね。「そうでもしないと……」というときも、もちろんありますけど。「悲劇と喜劇は背中合わせ」って言いますけど、「クソだなぁ」と思うことがあったら、それを俯瞰して笑うような視点は持っていたいなと思います。

誰かにとってのリアルが、誰かにとってのフェイクな場合もある。60億人いれば60億通りあるわけで。
―先ほど出た「不条理」というものを、どこか前提として受け入れているというのは、長澤さんの音楽に一貫してあるものなのかなと思うんです。こういう感覚は、どのようにしてご自身のなかに培われたのだと思いますか?
長澤:ちょうど昨日は地元の福岡にいたんですけど、福岡で暮らしていた当時に、あんまりいい思い出はなくて。今地元に戻ることは楽しいですし、時間が経ったことによって優しく見えるものもあるんですけど、学校が好きではなかったのでほとんど行ってなかったりもして。そのときに感じていたことは、自分の感覚に影響しているのかなって思います。
あと、僕の親はクリスチャンなので、僕も幼い頃に洗礼を受けているんです。でも、そこで信仰があったりなかったりって、揺れてしまうこともあったし、いろいろ祈ったり願ったりしてみたけれど、まったくなにも解決されないことだってあったし……そういうところですかね。もちろん、困ったときの神頼みのために信仰があるわけではないと思うんですけど。

―「信仰」って、人間存在にまつわるとても大きなテーマだと思うんですけど、長澤さんは信仰について、よく考えられますか?
長澤:うん、考えます。今がっつりとキリスト教を信仰している人間ではないんですけど、音楽を作ることの喜びや琴線は、そこに根が張っていると思うんですね。メロディや風景において、「これが好きだ」っていうものが明らかにわかるので。その琴線を具体的に説明することは難しいんですけど、その中心点に近づけていく作業が、僕にとってはレコーディングやライブだったりするんです。そういう意味での「信仰」が、自分にはあると思います。
ただ、これは僕自身の信仰ですから、他人に委ねるものではなくて。なにかに干渉することによって自分のアイデンティティを築けるとは思っていないので、僕は、自分の琴線を信じて曲を作っているっていうことだと思います。

―『SLASH』の1曲目“ムー”はまさに、「信仰」と「個人」の関係性を描いている曲のように感じました。この曲の主人公はUFOの存在や陰謀論めいたものを狂信的に信じていますけど、そうした個人の人生が、どこか滑稽さと哀愁を持って描かれている。
長澤:この曲はおっしゃっていただいたように、なにかを信じている人の曲ですね。なにかを信じているんだけど、その信仰が裏目に出てしまったりする……そういうことを、ちょっとコメディタッチに書いた曲っていう感じです。
―ここにもやはりユーモアがあるのが素晴らしいなと思うのと、キャラクター造形が絶妙ですよね。
長澤:曲を作るときは、自分のなかでなにか特定しているものがあったとしても、想像の世界に置き換えるようにはしていますね。このやり方は、蛭子能収さんと同じだと思っているんですけど。
―蛭子さんですか。
長澤:蛭子さんは、たとえば東大出身者のムカつくやつに出会ったら、家に帰って、東大生を切り殺す漫画を描いたりするらしくて……なんてジェラスなんだ、と思いますけど(笑)。
―ははは(笑)。
長澤:でも、それをちゃんとギャグ漫画として物語に昇華することは、「わかるなぁ」という感じがするんです。


―具体的に、“ムー”の主人公のような人物像は、どのようにして生み出されるものなのでしょうか?
長澤:やり方としては、自分から見た世界の、いろんな人間の考え方をひとりの人に集約していくっていう形ですね。この曲のようにモチーフが「信仰」だとしたら、自分自身の信仰や、自分が見た「世界を変えたい」と思って活動している人の姿、それとは別の誰かが信じる思想や信念を、ひとりの人物に詰め込んで曲にしていくんです。
自分がストーリーを書くときは、自分を投影したり、世の中の事象を投影したり、複合的な形で人物ができ上がっていくことが多いんですよね。なので、フィクションであってフィクションではない、というか……。そもそも、「フィクション」とか「フェイク」とか、あるいは「リアル」という言葉は、あまり好きではないんですけど。
―なぜでしょう?
長澤:フェイクとはなんなのか、リアルとはなんなのかっていうのも、60億人いれば60億通りあるわけで。誰かにとってのリアルが、誰かにとってのフェイクな場合もあるし。「こいつはリアルな音楽をやっている!」って言っても、それは結局、「そいつにとってのリアルである」ということじゃないですか。
そういう意味で、“ムー”も、フィクショナルな曲だけど、フィクションではないんです。自分が見ている、実際にあることをひとりの人間に集約させて書いているっていうだけで。たまに、リアリティを正義化し始める人もいますけど、そういうものは、僕はあまり共感できないんですよね。
―リアルとかフェイクって、便利なだけの言葉なのかもしれないですね。
長澤:カテゴライズの言葉ですよね。「ネトウヨ」とか「パヨク」とかもそうだし、「老害」とかもそうだし……。「老害」という言葉が、僕は一番嫌いですけど。そうやってレッテルを貼れば思考しなくていいから、安直な方に逃げてしまいがちなんですよね。

自分が弱い人間だからこそ、「想いやりたい」と思うのかもしれないですね。
―お話を聞いていて改めて思うのは、長澤さんの表現は多角的な視点から、「個人」というものの存在を描いているような感じがします。「人がひとり生きている」ということを、すごく大切に描こうとしている、というか。
長澤:このインタビューの現場でも、僕が話していることを聞いてくださっているあなたの世界があって、あなたが話を聞いてくださっているのを見ている僕の世界があって。それぞれが瞳に映し合っている、お互いが「自分」であるっていうことは、かなりミラクルなことだなって思うんです。

―そうですよね。
長澤:結局、僕らは全員が「自分」で、「自分」の視点や感情を持って生きているんですよね。さっきのフェイクとリアルの話もそうですけど、この世界に60億人いるなら、60億通りの世界があり、60億通りの正義がある。それによって意見の食い違いが生まれるのは必然だし、それこそがミラクルで美しいことだなって思うんです。
考え方や、悲しみや喜びのような感情は、自分のなかにだけ内在するもので。だからこそ、生まれ育った環境が違う他人も「自分」なんだと思えるようになったら、優しくなれるような気がするんですよね。
―結果として、長澤さんの歌は「ラブソング」と呼びうるものになっていると思うんですよね。もしかしたら、長澤さんは「ラブソング」という言い方はピンとこないかもしれないですけど。
長澤:いや、ラブソングだと思いますよ。人間のことを歌うので。生きることに対して肯定的な歌が多いので、それは、ラブソングになっているんだと思います。否定的で投げやりになってしまったら、「人を愛する」っていう積極的な行動にも出ることはできないですからね。
さっきから「お前何様だよ?」っていう感じのことも言っていますけど、基本的に、人が好きですね。可愛らしいなって思う。でも、こう思うのはひょっとしたら、僕が弱い人間だからかもしれないです。
―弱さ、ですか。
長澤:弱いから、自問自答もしますし、「自分ってどういう人間なんだろう?」って考えるのと同じように、相手に対しても「この人は、どういうふうに考えるんだろう?」って考えたりもするし……弱いから、「考えたい」って思うのかもしれないです。「どうでもいいや」と思えるほど強くないんですよね。もちろん、それが強さだとも思いませんけど、でも弱いからこそ、「想いやりたい」と思うのかもしれないですね。

12年前に書いた曲は、「助けて!」って言っている。でも、それも「肯定的に生きたい」って思っていたんだろうと思うんです。
―長澤さんが、歌の根底に「弱さ」を内包していることは、デビューした頃から一貫していると思うんですけど、それが、どんどんと「優しさ」になって溢れているような印象もあるんです。長澤さんは、ご自身の歌の在り様の変化で、自覚されることはありますか?
長澤:なんとなく、変化してきているような気はします。「ここがターニングポイントだった」というような極端な変化はないですけど、ゆるやかに変わってきているというか、増幅しているというか。
12年くらい前に書いた“P.S.S.O.S.”は、とても寂しがり屋な曲で、「助けて!」って言っている曲なんです。でも、それもやっぱり人が好きだから生まれてきた曲だったんだと思うんですよね。「助けて」と言えているうちは、なんとか、その状況を打開したいと思ってるっていうことなので、生きることに肯定的な状態でもあると思うんですよ。あの曲は引きこもっているときに書いた曲だったんですけど、そのときから、「状況を打開したい」「肯定的に生きたい」って思っていたんだろうと思うんです。それから年齢も重ねて、肯定的に生きることができるようになってからは、ますますその感覚が増加していったんだと思います。
―たしかに「助けて」って、生きたいから言うんですよね。
長澤:そう、ある意味、前向きな行動なんですよ、助けを求めるのは。
―長澤さんの歌は、時期に応じて形が変容している部分はあるとも思うんですけど、「人が好きだ」ということ、生きることを肯定しようとしている部分は、一貫しているんでしょうね。
長澤:そうですね。誰とも会わなかった時期に曲を書いていたときも、Policeの“Message in a Bottle”みたいな感じで、無人島から手紙を書いているような感覚で曲を書いていたので。ずっと、「いつか誰かに届けばいいなぁ」という感じで、曲を書いていたような気がします。

―「歌」って本当にその人自身が出るし、ときには、聴き手自身が反映されるものだなと思うんですけど、長澤さんは、ご自身の「声」に対しての向き合い方はどうですか。デビューして以降変化している部分はあると思いますか?
長澤:歌声の部分に関しては、自分でテープレコーダーやMDプレイヤーに吹き込んで歌ってみて、最初に自分の声を聴いたときは、「うわっ」って思ったんですよ。でも、録り続けていくうちに慣れてきて、デモテープをプロダクションに送って、今に至るんですけど……。最初にステージに立たせていただいたときに、「気持ち悪い」っていうリアクションがきたんですよね。そのときに、「うわっ、俺の声って気持ち悪いんだな」って、「最初に自分でもそう思ったなぁ」って、改めて思い出して(笑)。……でも、声から逃げることはできないんですよ。絶対についてくるものなので、「いかに自分の声を好きになろうか?」って考えましたね。
―今、ご自身の声は好きになれていると言えますか?
長澤:振り切った、ということでしょうね。思いっきり、ガーッ! と(笑)。
―(笑)。
長澤:そういう部分も含めて肯定しようと思って、今は歌っています。



- リリース情報
-

- 長澤知之
『SLASH』(CD) -
2019年10月2日(水)発売
価格:2,530円(税込)
POCS-18301. ムー
2. Back to the Past
3. 90's Sky
4. KYOTON
5. いつでもどうぞ
6. 世界は変わる
7. シュガー
8. 戦士は夢の中
- 長澤知之
『ソウルセラー』(CD) -
2019年3月20日(水)発売
価格:2,530円(税込)
POCS-17741. あああ
2. ソウルセラー
3. 笑う
4. 金木犀
5. コウモリウタ
6. 歌の歌
7. ゴルゴタの丘
8. Close to me
- 長澤知之
- イベント情報
-
- 『Nagasawa Tomoyuki Band Tour 2019 'SLASH'』
-
2019年12月2日(月)
会場:大阪府 umeda TRAD2019年12月3日(火)
会場:愛知県 名古屋 APOLLO BASE2019年12月5日(木)
会場:福岡県 Gate's72019年12月12日(木)
会場:宮城県 仙台 space Zero2019年12月16日(月)
会場:東京都 WWW X
- プロフィール
-

- 長澤知之 (ながさわ ともゆき)
-
8歳でビートルズとブラウン管ごしに初対面。10歳でギターを始め、1年足らずでオリジナル曲の制作をスタート、18歳でオフィスオーガスタのデモテープオーディションでその才能を認められる。以後、福岡のライブハウス「照和」、東京のライブハウスでのマンスリーライブを行いながらデモ音源を作成し、2006年8月2日、シングル『僕らの輝き』でR and C Ltd.よりメジャーデビュー。ミニアルバムのリリースを連発した後、2011年自身初のフルアルバム『JUNKLIFE』をリリースした。その後もコンスタントに作品を発表、2013年にセカンドフルアルバム『黄金の在処』をリリース。2015年にはAL(小山田壮平×長澤知之×藤原寛×後藤大樹)のVo&Gtとしても活動を正式にスタートし、2016年4月に1stアルバム『心の中の色紙』リリース、8月にはソロデビュー10周年を迎え、12月に6thミニアルバム『GIFT』をリリースした。2017年4月にはデビュー10年をアーカイブした『Archives#1』をリリースし、唯一の新曲である“蜘蛛の糸”は大きな話題を呼んだ。また、ALとしてもセカンドアルバム『NOW PLAYING』を2018年1月リリースし、2019年3月にアコースティック・ミニアルバム『ソウルセラー』を、そして10月2日にはバンドサウンド・ミニアルバム『SLASH』をリリース。精力的な活動を見せている。
- フィードバック 5
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-