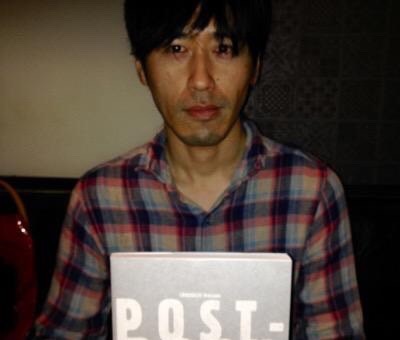音楽ライター、金子厚武の連載コラム「up coming artist」。注目の若手アーティストを紹介し、その音楽性やルーツを紐解きながら、いまの音楽シーンも見つめていく。第3回目にフォーカスするのは、昨年発表した1stアルバムから音楽ファンのあいだで話題になっている3ピースバンド、雪国だ。
2003年生まれの3人が2023年に結成した雪国は、2024年6月に1stアルバム『pothos』を発表し、『CDショップ大賞2025』で関東ブロック賞を受賞。この7月の『FUJI ROCK FESTIVAL』でも、新人アーティストの登竜門として知られる「ROOKIE A GO-GO」に選出された。ちなみに「雪国」という名は川端康成の小説から取られているそうで、その楽曲も文学的かつ哲学的な表現が内包されている。
「up coming artist」で金子はこれまで、kurayamisaka、yubioriを紹介したが、その流れのなかで「雪国をちゃんと取り上げておきたい」と語る。自然の美しさとともに、ものがあふれる社会の心許なさ、そして生き方への問いを含むような歌詞。DTMに触れながらも、生々しい「うた」が両立されているその音楽性。そして、全員が空間づくりに奉仕するようなライブの特異性……雪国というバンドを、立体的に紐解いていく。
音楽は好きだけど、最近、新しいアーティストに出会えていない……情報の濁流のなかで、瞬間風速的ではない、いまと過去のムーブメントを知りたい……そんな人に、ぜひ読んでほしい連載です。
2023年結成、2003年生まれの3人。1stアルバム、EPからすでに注目を浴びる
前回の「up coming artist」では、今年の『FUJI ROCK FESTIVAL』「ROOKIE A GO-GO」に出演したyubioriを取り上げたが、今回は同じ日に「ROOKIE A GO-GO」に出演していた3ピースバンド、雪国を紹介する。

雪国
2023年結成。京英一(Vo,Gt)、大澤優貴(Ba)、木幡徹己(Dr)の3人で、東京を中心に活動している雪国。2024年6月に発表した15曲入りの1stアルバム『pothos』が音楽ファンのあいだで話題になり、『CDショップ大賞2025』で関東ブロック賞を受賞した。今年1月には1st EP『Lemuria』を発表、4月には新代田FEVERでのワンマンをソールドアウトで終えると、『SYNCHRONICITY』や『YATSUI FESTIVAL!』といった都市型フェスに出演。7月にはHomecomingsのイベントでART-SCHOOLとも共演し、「ROOKIE A GO-GO」でも多くのオーディエンスを集めていた。
昨年以降、ライブハウスでよく会う音楽の趣味が近い関係者とは、この連載の初回で取り上げたkurayamisakaと同じくらいの頻度で「雪国が面白い」という話をしたように思う。
自然の美しさを映像的に表現する世界観。デジタル飽和時代への問いかけも

雪国『pothos』
1stアルバム『pothos』は、繊細なアルペジオ(※1)を軸にしながら、ときに激しく歪むギター、スローコア(※2)にも通じるゆったりとしたテンポ感でボトムを支えるリズム隊が特徴。多彩なコーラスやフィールドレコーディングの要素も取り入れつつ、京が柔らかな歌声でリリカルなメロディーを紡いでいく。それを「ポストロックやシューゲイザー(※3)からの影響を受けた日本語ロック」と紹介するのはやや単純ではあるが、決して間違いではないはずだ。
現時点での代表曲である“東京”をはじめとした15曲には、indigo la Endの、きのこ帝国の、羊文学の初期作がそうであったように、すでにインディロックの名作としての風格があり、この先でさらなるポピュラリティを獲得することを予感させる。
「雪国」というバンド名は川端康成の小説から取られていて、その世界観に惹かれた京は、高校生の頃から旅をするのが好きだったという。その経験が落とし込まれた雪国の楽曲は非常に映像的であり、光、夜、星、海といった単語が散りばめられている。歌詞から自然の美しさが香り立ち、都市生活者を心の旅へと誘う。そこにはエスケーピズム(現実逃避、※4)の感覚と同時に、物質主義が飽和状態を迎え、デジタル化に突き進む社会への違和感や心許なさが投影され、それぞれの生き方に対する問いが含まれているのも魅力的だ。
<イヤホン外し耳を澄ませば 息をしている自分がいた><ふとした景色が頭に残るような事 大切にするって決めたんだ>と歌う“真夜中”は、雪国の哲学が端的に表現された一曲であるように思う。
DTMの視点と生々しい「うた」をバンドとして併せ持つ、稀有で現代的な存在

雪国『Lemuria』
今年発表されたEP『Lemuria』を聴けば、彼らがすでに「ポストロックやシューゲイザーからの影響を受けた日本語ロック」から一歩先へと踏み出していることがわかる。全体的に音数を絞り、歪みの要素が減って、その分シンセがフィーチャーされた楽曲からは、アンビエント(環境音楽)を好み、音響的な側面も重視するバンドの現代性が伝わってくる。
ミュートの効いたドラムはMen I Trust(※5)などを参考にしたようで、ポストロックなどからの影響を受けたバンド、talkで活動していたエンジニアのKensei Ogataの助力も大きい。小説『雪国』の有名な冒頭文<国境の長いトンネルを抜けると雪国であった>を体現するような“Blue Train”は『Lemuria』を象徴する一曲であり、音数を絞ることで生まれる広い景色と、浮遊感のある星空のようなサウンドスケープがとても美しい。
『Lemuria』におけるミニマリズムとシンセの重用からは、Xでいち早く“東京”に反応していた元スーパーカーの中村弘二の作風を連想させるし、メンバー3人がそれぞれのミュージシャンシップを持った音楽家の集まりである感じも含めれば、先日再始動をしたD.A.N.とも通じる部分があるように思うが、個人的には君島大空とのリンクを強く感じる。
『pothos』には京による弾き語りの小品も収録されていて、今年2月にはクラシックギターによる弾き語りを軸にしたソロアルバム『放心』を発表しているように、生々しい「うた」が雪国の表現の一つの軸であることは間違いない。その一方で、世代的にもいち早くDTM(※6)に触れてきたであろう彼らは、バンドという形態を選びながらも、当たり前のように音の帯域や位相(※7)に対する目線も持っている。君島のように、この両方を併せ持つソロアーティストは増えているが、バンド形態ではまだまだ少なく、その意味でも雪国は非常に現代的な存在である。
また、楽曲が映像的であることも君島との共通点だ。SNSなどで言葉の暴力性が浮き彫りになり、さまざまな規模で分断を引き起こしている現代において、映像的な曲作りは聴き手それぞれの解釈を許容するという点で重要だと言えるだろう。
特異性が際立つライブ。どこかホーリーな静かさの裏に、音に対する熱量がこもっている
雪国の特異性がより明確に表れるのがライブ。ギターののざきなつき、ソロアーティストとしても活動するriliumの2人をサポートに迎えて行われるライブは、ステージに立つ全員がその場の空間づくりに奉仕するような感覚が特別だ。遠目から見ると一瞬「同期(録音済みの音)も鳴ってるのかな?」と思うが、よく見ればドラムの隣でriliumがシンセとコーラスを担当している。
なかでもドラムの木幡の、ダイナミクスを削ぎ落とし、「弱さ」を意識したようなプレイは特徴的。できるだけ空間を空けながら、曲が盛り上がり、ギターが歪むと、今度はシンバルを打ち鳴らして空間を埋めていく、その対比が非常にドラマチックだ。ショートディレイ(短い遅延を加えること)をかけたボーカルの感じも含め、どこかホーリーとも言える雰囲気は、「雪国」という名前からして、親和性の高いアイスランドを代表するバンド、Sigur Rosを連想させるものである。
「OTOTOY」での京、木幡、Ogataによる鼎談(※8)で、京は「オルタナティヴ・ロックが1を基準として1以上を出す音楽だとしたら、雪国は0と1の間で、1をピークにして抑揚をつける、というのを作曲段階から意識しています」と話している。この考え方は非常に雪国らしさを表していると思うが、この「0と1の間」の感覚はライブにおいてもはっきりと体現されている。kurayamisakaのライブが「動」の魅力なら、雪国のライブは「静」の魅力。しかし、音に対する熱量に変わりはない。そんな比較がわかりやすいかもしれない。
9月16日にはdowntやNo Busesらを迎え、渋谷WWW / WWWβで主催イベント『Hakoniwa Fest. 2025』を開催する。これまでにも彼らはメンバー個々でイベントを行っていて、新たなシーンをつくっていこうとする野心が垣間見えるのもいい。間違いなく、今後も要注目のバンドである。
※1 アルペジオ……和音(コード)を構成する音を順番に一つずつ弾く奏法のこと。
※2 スローコア……寒々としたメロディと歌詞、スローテンポのミニマルなリズム、クリーンでリバーブを多用したギターサウンドが特徴のオルタナティヴロックのいちジャンル。
※3 シューゲイザー……The Jesus and Mary Chainを源流とするムーヴメントのこと(1990年代に起こった)。「Shoe=靴+Gazer=見る人」、つまりは下を向きながらギターを掻き鳴らすUKロックの一部分の総称。90年代の日本でもフォロワー的なバンドが数多く出現した。
※4 エスケーピズム……escapism。現実の困難や不快な状況から意識をそらし、別のことに気を紛らわせること。
※5 Men I Trust……カナダのインディーポップバンド。
※6 DTM……「Desk Top Music(デスクトップミュージック)」の略で、パソコンを使って音楽制作を行うこと。作曲、打ち込み、録音、編集、ミキシング、マスタリングなど、音楽制作のプロセスをデジタルで完結できる。
※7 音の帯域や位相……帯域とは、音の周波数の範囲を区切ったもの。人間の可聴範囲はおよそ20Hz〜20kHzで、低音・中音・高音などに分けて扱う。楽器や音響機器の特性を理解・調整するための重要な概念。位相とは「音の波がどこから始まっているか」というタイミングのこと。波のタイミングが合えば音が大きくなり、ずれると音が弱まったりする。ステレオ録音や音響設計で重要な要素となる。
※8 雪国が奏でる、余白の芸術──「Lemuria」の研ぎ澄まされたサウンドに迫る──【In search of lost night】
- イベント情報
-
 『雪国pre.〈Hakoniwa Fest. 2025〉』
『雪国pre.〈Hakoniwa Fest. 2025〉』
2025年9月16日(火)OPEN 17:30 / START 18:00
会場:渋谷WWW、WWWβ
料金:前売4,500円 20歳以下2,500円
出演:
・WWW
雪国
No Buses
downt
乙女絵画
・WWWβ
エスキベル
メコン
- プロフィール
-
- 雪国 (ゆきぐに)
-
2023年結成。京英一(Vo,Gt)、大澤優貴(Ba)、木幡徹己(Dr)という2003年生まれの3人で東京を中心に活動している。2024年6月に発表した15曲入りの1stアルバム『pothos』が音楽ファンの間で話題を呼び、『CDショップ大賞2025』で関東ブロック賞を受賞。2025年1月には1st EP『Lemuria』を発表した。
- フィードバック 3
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-