いわゆる「クリエイター」だけでなく、広く社会にクリエイティブな考え方が行きわたれば、もっとおもしろい世の中になる——そんな思いを起点に、2026年4月より、京都の総合大学・立命館大学に「デザイン・アート学部」が新設される。
本学部では一般的に別のものとしてとらえられている「デザイン」と「アート」の垣根を取り払い、新たな学びの場を創出。京都のまち全体を学びの場ととらえる、革新的なカリキュラムも見どころだ。
CINRAでは、立命館大学デザイン・アート学部について全3回にわたり特集。その第1弾として、学部設立に携わった八重樫文教授と、デザインオフィス「れもんらいふ」で代表を務める千原徹也氏の対談をお届けする。
本学部のコンセプトやビジョンはどのようなものなのか? そして、アートディレクター・映画監督として最前線で活躍する千原氏の目に、その構想はどう映るのだろうか?
デザインやアートの定義にはじまり、真に「クリエイティブである」とはどういうことか、そしてこれからの社会で力を発揮する「センス」の磨き方まで、たっぷりとディスカッションしてもらった。
クリエイティビティを、社会に実装するために。学部が掲げる「デザイン・アート学」とは?
―まず、一般的に別ものだと考えられがちな「デザイン」と「アート」を、八重樫さんがどうとらえているのかうかがいたいです。
八重樫文(以下、八重樫):私としては、デザインとアートを個別に定義したくないんですよ。まだ自分の専門を決めていない若い人たちにとって、デザインとアートってそこまで厳密に分かれていないと思うんです。
むしろいまの社会は、デザインとアートが過剰に分けられてきたことで、いろんなことがうまくいっていないんじゃないかと。そんな問題意識から、二つの融合を掲げたのがデザイン・アート学部なんです。

八重樫文(やえがし かざる)
立命館大学 デザイン・アート学部、デザイン・アート学研究科設置委員会 事務局長。2026年度よりデザイン・アート学部教授
―デザインとアートを足し算するのではなく、「デザイン・アート」という新しい横断的なジャンルを立ち上げるようなイメージでしょうか?
八重樫:そう受け取ってもらうのが一番いいと思います。私たちはどうしても「デザインとは?」「アートとは?」と分けて考えてしまいがちですが、そもそもそういう発想を持たない人たちが、これからの社会をつくっていく。本学部初の卒業生が出るのは2030年ですが、その頃にはきっと、デザインとアートを分けて考える時代ではなくなっているはずです。
―横断的な「デザイン・アート」の構想は、デザイン会社を経営しながら、監督として映画も撮っている千原さんの実践にも近いのではないでしょうか。ご自身のキャリアと照らして、デザイン・アート学部の構想をどう思われますか?
千原徹也(以下、千原):八重樫さんに代わってあえて定義をしてみると、僕にとってアートは「問い」を起こすものです。その「=(イコール)」の先の答えは、鑑賞者に考えてもらう。逆に、デザインはその「=」の先の「答え」を探す仕事なのかなと。
ただ、「問い」を持っていないと「答え」にたどり着けないことも多い。だから、やっぱり頭のなかにデザインとアートの両方が必要なんです。その意味で、世の中のいろんな課題に取り組むクリエイターになるために、「デザイン・アート」という構想はぴったりだと思いますね。

千原徹也(ちはら てつや)
株式会社れもんらいふ代表 アートディレクター
千原:僕の経営する「れもんらいふ」も基本的にはデザインの会社ですが、アート的な「問い」の思考がないとクリエイティブなデザインはできません。逆にアートをやるにしても、デザインを理解していたほうが絶対に鑑賞者に伝わりやすくなるはずです。
八重樫:ありがとうございます。さらに私たちは、デザイン・アートに、また別の考え方を加えることも重視しています。そこには組織運営や合意形成、実務を大切にすることなど、これまでデザインやアートの真逆にあるとされてきた考え方も含みます。
これからの社会で力を発揮するのは、それらの考え方を総合的に持った人なのではないかと。クリエイティブでありながら、しっかりと現実を見据え、理想の実現に向けて人や組織に働きかけることができる人。
だからこそ、デザイン・アート学部では、デザインやアートについての演習や講義はもちろん、歴史や社会、環境、情報など、さまざまな学問に触れる機会が開かれています。

―なるほど、革新的なアーティストを演じるだけでは世の中は変わらないと。
八重樫:実際に職場などで皆さんが悩んでいるのは、新しい提案をしても会議で却下されるとか、決裁が通らないとか、そういうことだと思うんです。それはクリエイティブな考え方を組織運営に落とし込む機能が不足しているから。
現在は特に、企業の意思決定に関わる部署にクリエイターが少ない。とはいえ、斬新なアイデアばかり出すだけの人がそこに入っても、対立が生まれるだけです。だからこそ、現状を変えるには、理想と現実のバランスを取れる人たちが必要だと思うんですよ。
「売れる広告」ならAIでも簡単につくれる。そんな時代に、人が考えるべきことは?
―まさに千原さんは日々たくさんの組織を相手に、さまざまな提案や調整を実践していると思います。そのなかで、DX(デジタル・トランスフォーメーション)ならぬCX(カルチャー・トランスフォーメーション)という概念を打ち出していますよね。
千原:簡単に言えば、「デザインやアートといったカルチャーを大切にする考え方を組織にインストールしよう」そして「カルチャーを大切にする経営を行う企業を日本に増やしていこう」という思考がCXです。
日々いろんなクライアントと接していると、いまの日本の企業って「こうすればヒットする」「売れる」といったマーケティングや、会社をスケールさせる術には、すごく長けていると感じます。
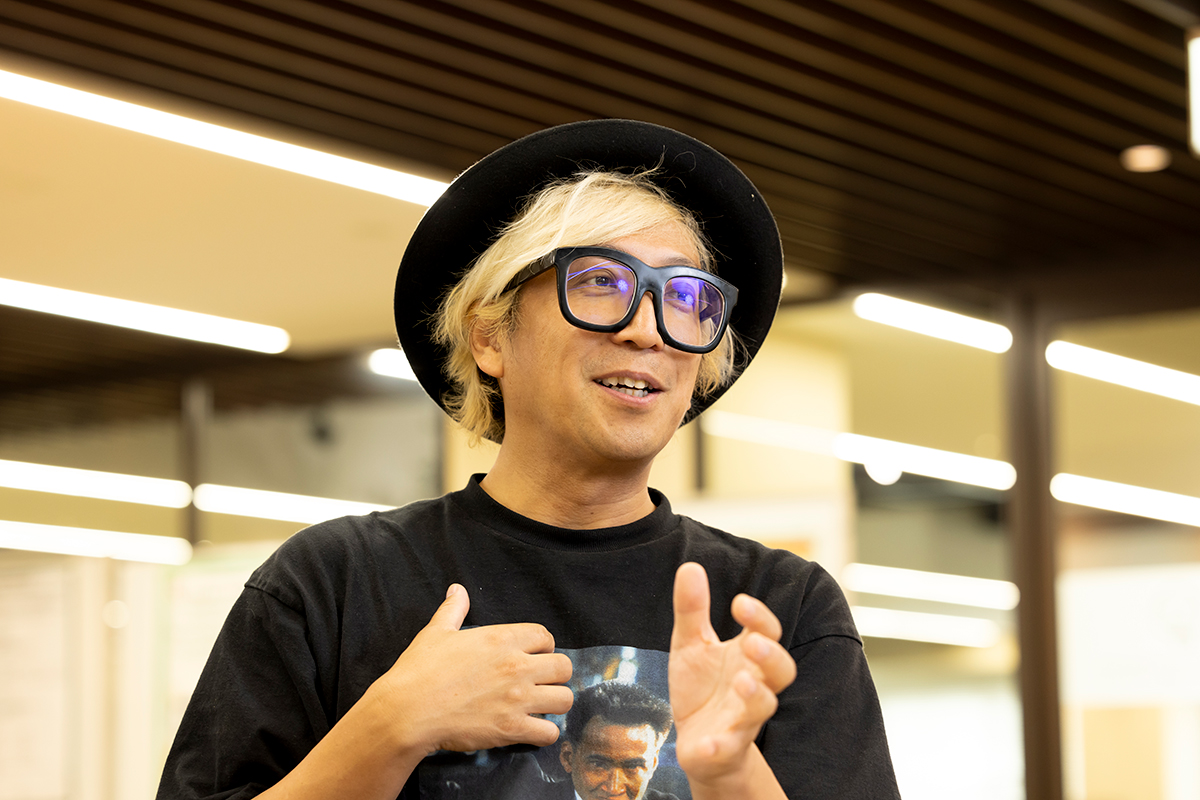
千原:ただ、ブランディング力が弱いんです。それは言い換えれば、「長く会社を続けていくための方法論」でもあります。それを確立するには、デザインやアートに造詣が深い人が会社にいないといけないし、その人を大事にする仕組みがないといけない。
いまの時代、「売れる広告」なら、AIでも簡単につくれてしまいます。たとえば、AIにキャッチコピーを提案させると「いまから30分間だけ50%オフ!」とか平気で提案してきます(笑)。しかも、それで実際に売れる。ただ、瞬間的に商品が売れたとしても、10年後にその商品が残っているかというと難しい。だから、やっぱりマーケティングやスケールと同時に、ブランディングにも力を入れる必要があるんです。
それは日本社会全体も同じだと思います。単発的な打ち上げ花火でお金を儲けるだけじゃなくて、長い目で見てブランディングしていかないと、あとに続く人たちも苦しくなっていきますよね。
映画に携わっていても感じるんですが、何百億円と大ヒットする映画はもちろんすごいけど、そのいっぽうで何十年、何百年と残り続ける作品がないと、芸術としての日本映画が、世界の映画業界から消えてしまう可能性だってあるわけです。
―CXの視点を通して、短期的なマーケティングだけでなく、ブランディングという長期的な見通しを立てることが重要であると。
八重樫:実は、図らずも私たちもCXを提唱してるんですよ。
千原:なんと、そうだったんですね。
八重樫:私たちの場合は、クリエイティブ・トランスフォーメーション。よく「卒業生のイメージってどんな人なの?」と聞かれますが、卒業生が活躍する場は、デザイン会社や企業のクリエイティブ部署だけじゃないし、博物館や美術館のなかだけでもない。「〇〇デザイナー」とか「〇〇アーティスト」とか、職種名で考えてもしっくり来ないんです。

八重樫:むしろ、職場や職業を限定せず、社会全体にクリエイティブなマインドセットを実装する——つまり、さまざまな場所で「クリエイティブに変革を促す人」を増やしていこう、というのが私たちのビジョンなんですよ。
企業では、デザインや広告などを担当する部署以外では、クリエイティビティを求められないのが現状です。たとえば営業や経理などでも、長く活躍している人は、なんらかのクリエイティビティを発揮しているはずなんですが、会社はそこを評価しない。評価する指標も持っていません。
ですが、本当に大事なのは、クリエイター以外の社員たちが日常的にクリエイティビティを発揮できる環境をつくること。それによって会社は活性化し、よりよいものやサービスを世の中に生み出していくんだと思います。そうした状況をつくっていくために、本学部の卒業生たちに活躍してほしいと願っています。
キャンパスは京都のまち全体。体験から学ぶ実践的なカリキュラム
―卒業生の話も出ましたが、立命館大学という総合大学に新しくデザイン・アート学部をつくろうと考えたのは、そもそもどうしてなんでしょう?
八重樫:本来、学問を総合的に網羅しているからこそ「総合大学」と呼ばれるはずですが、明らかに芸術を専門とした学部が足りていませんよね。
あまりこうした分け方は好きではありませんが、いわゆる理系の学部と文系の学部があり、それぞれに研究のセオリーや認識の枠組みがある。こうした「枠組み」や「指標」を持つということは、世の中をそれによって切り取り、見つめることができるということです。
そう考えたときに、やはり現状の学部では足りない。「感性」や「クリエイティビティ」をしっかりと一つの学問として扱う学部がなければ、世の中の大切な側面を取りこぼしてしまう。そんな思いから、デザイン・アート学部の構想が立ち上がりました。
千原:先ほど八重樫さんのお話にもありましたが、クリエイティブな視点を持っておくことは、社会に出てからどんな仕事をするにしても大切になりますよね。
デザイナーだって、言われたことだけやるのであれば、ルーティンの仕事と変わらない。どんな職業や職種でも、「何かを変えたい」「現状に一石を投じたい」と思っている人がクリエイターなんだと思います。だからこそ、クリエイティブな姿勢や考え方を学ぶ学部が、総合大学のなかにできる意義は大きいと感じます。

―千原さんは自社で「Re:DESIGN SCHOOL」というスクール事業もやられてますよね。
千原:そうですね。スクールをやっている理由はいくつかありますが、一番はクリエイターやその卵が事務所に出入りしやすい仕組みをつくりたかったからです。
れもんらいふの事務所は、原宿駅目の前の交差点に建つ商業施設「ハラカド」のビルに入っています。「どんな施設にしたらいいか相談に乗って」と、ビルの所有者である東急不動産から依頼いただいた際、総合大学にデザイン・アート学部が必要なように「ハラカドにはデザイン会社も必要なんじゃない?」と伝え、自ら入居しました。
その一角にはもともとセントラルアパートという建物があって、タモリさんや糸井重里さん、浅井慎平さんといった方々の事務所が入っていました。そこにクリエイターが集まることが、街の文化をつくっていたんですね。
だからハラカドっていうのは、いわば原宿の街を担う、文化的にすごく大事な場所。そこで一緒におもしろいことをはじめる仲間を見つけたくて、スクールを開いたんです。
―「そこがどんな場所であるか」は、ものづくりにあたって非常に重要な意味を持ちますよね。
八重樫:デザイン・アート学部のカリキュラムも、地元の企業や組織とともに現実の課題に向き合うプロジェクト形式の学びをメインに据えたうえで、「まち全体がラーニングプレイス」というコンセプトを掲げています。まち全体があなたの学ぶ場所ですよ、と。やっぱりクリエイティビティって、キャンパスや教室のなかだけで学ぶものじゃないと思うんですよ。
千原:本当にそうですよね。
八重樫:普段学生たちと接していると、意欲的、自主的に学んでもらうことの難しさを実感します。でも、学生のうちからいろんな組織に入って、現場で仕事に携わってみれば、そこで自分がどう機能するのかを体感できます。すると、「自分がなぜ学ばないといけないのか」「何を学ぶべきなのか」が自然とわかるはず。
実際、わざわざ時間とお金をかけて、リスキリングのために大学に通い直す社会人は多いです。実践型の学びは、そうした「学びへの内発的な欲求」を呼び起こすはずです。そして学ぶことの必要性を実感したら、大学で好きなだけ勉強してほしい。現場のプロジェクトと大学の講義を、うまく循環させていければと考えています。

―「まち全体がキャンパス」ということで言うと、立命館大学が立地するのは京都ですよね。お二人にとって京都というまちの印象は?
千原:僕は出身が京都なんです。大学には行かず、高校を卒業してから大阪のデザイン事務所で働いていましたが、28歳で東京に出るまでずっと京都にいました。
僕にとって、京都はまさに大学みたいな場所でしたね。東京よりコンパクトだから、街を自転車で回りながらレコード屋、映画館、クラブなどに通って、たくさんのものを吸収しました。学んでいるという意識はなく、ただ楽しんで過ごしていただけですが、28歳まで京都のカルチャーにどっぷり浸かった経験が、いまの仕事にもめちゃくちゃ活きてますね。
八重樫:私は北海道出身ですが、やはり京都は日本の歴史・文化・芸術の象徴とされている都市です。海外からは特にそういった評価が高いですし、それゆえ国際的につながる可能性にも開かれている。新しい研究や教育を発信するのに最適なまちの一つだと思います。
未来社会でAIに負けない「センス」を獲得するために
―最後に、デザイン・アート学部を通じてどんな人が育ってほしい、また、どんな社会になってほしいと思いますか?
八重樫:やっぱり、世の中が少しでもおもしろくなってほしいという思いがあります。おもしろいっていうのは、「笑える」という意味ではなく、「ワクワクする」ということ。自分がおもしろいと感じることを大事にできる人が育てば、そのエネルギーできっとまわりの人も触発されて変わっていくはず。自然とおもしろい世の中、豊かな社会になっていくんじゃないでしょうか。
千原:同感です。そして、僕の周りにいるおもしろい人って、まず知識がある人なんですよね。僕はよく「千原さんはセンスがいいから」と言われたりするんですが、それって「センスがある人・ない人」が生まれつき決まっているみたいな言い方だと思うんです。でも本当はそうじゃなく、いわゆる「センス」って、単に「引き出しの多さ」だと思うんです。だから、基本的には誰でも学べば習得できるものなんですよ。
ビジネスの話をするときも、アートやアニメやファッションや音楽……いろんなカルチャーの知識を織り交ぜながら会話ができる人は、やっぱりすごくおもしろいし、周囲に人が集まってくる。そういう人がイノベーションを起こしていく気がしますね。

八重樫:幅広い知識は本当に大事だと私も思います。デザイン・アート学部では講義をオンラインコンテンツ化するので、場所も時間も回数も選ばずに、好きなだけ知識に触れることができます。だから学生たちも、現場での実践を踏まえて、広範な知識の獲得に向かってほしいですね。
千原:最近、いろいろな業界の人たちに話を聞くなかで「AIが人間の仕事を代替する」という状況がすぐそこまで来ているのを実感します。だからこそ、これから人間が生きていくうえで重要になるのは、ものごとを楽しめるセンスを自分で持つことだと思うんです。
そのためには、やっぱり知識が必要。デザインやアートはもちろん、歴史や社会、ビジネスのこともそう。いろんな知識を吸収していくことで、AIに負けない豊かな人生を歩めるんじゃないかな。
- サイト情報
-
 『立命館大学 デザイン・アート学部』
『立命館大学 デザイン・アート学部』
立命館大学デザイン・アート学部および、立命館大学大学院デザイン・アート学研究科は新しい学部と大学院です。美的感性を磨き、世界に新たな価値を創造するための学びを提供します。
- プロフィール
-
- 八重樫文 (やえがし かざる)
-
1973年北海道江別市生まれ。武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科卒業、東京大学大学院学際情報学府修士課程修了。デザイン事務所勤務や、美大を含むいくつかの大学・学部での助手・講師・准教授を経て、2014年より立命館大学経営学部教授。2015、2019年度ミラノ工科大学訪問研究員。立命館大学 デザイン・アート学部、デザイン・アート学研究科設置委員会 事務局長として学部設立に携わる。専門はデザイン学、デザインマネジメント論。2026年度よりデザイン・アート学部教授に着任予定。
- 千原徹也 (ちはら てつや)
-
1975年京都府生まれ。デザインオフィス・株式会社れもんらいふ代表。広告、ファッションブランディング、CDジャケット、装丁、雑誌エディトリアル、ウェブ、映像など、さまざまなジャンルでアートディレクターとして活躍。2023年には映画監督としての作品『アイスクリームフィーバー』(原案:川上未映子、主演:吉岡里帆)が公開。現在は、原宿の商業施設・東急プラザ原宿「ハラカド」にれもんらいふを移転させ、新たなプロジェクトに取り組んでいる。
- フィードバック 25
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-





