4月3日にTSUTAYA O-EASTで開催されるCINRA.NET主催のライブイベント『CROSSING CARNIVAL -visual edition-』。「二度は同じものが生まれない、この日限りの祝祭」をコンセプトに2017年からスタートし、異なるジャンルのコラボレーションを特徴とするイベント『CROSING CARNIVAL』の特別編に、indigo la End、odol、The fin.の3組が出演する。
「Film & Stage Visual Producer」として参加するのは、Mr.Childrenのツアーや安室奈美恵の展覧会など様々なアーティストの映像演出を手がけ、ポップかつアートな感性が高く評価されているクリエイティブカンパニー「KITE」。タイプの違う3組をトータルでプロデュースすることにより、ワンマンとは異なる特別な一夜となることは間違いないだろう。
フェスやイベントがアーティストとオーディエンスの双方にとって「日常」となった今、もう一度「強烈な体験ができる場」を作り出そうとする試み。そして、カルチャーやアートをクロスさせることによって、新たなクリエイティブへと繋げていこうとする挑戦。『CROSSING CARNIVAL - visual edition-』の意義と内容について、indigo la Endの佐藤栄太郎、odolの森山公稀、The fin.のYuto Uchinoの3人に語り合ってもらった。
音楽は聴いてくれる人がいないと成立しないし、存在できない。(森山 / odol)
—昨年は3組ともに手応えのあるアルバムを発表し、現在は次のステージに向かっているところかと思います。実際、現在バンドとしてはどこを目指していて、「フェス」や「ライブ」の意義をどう位置付けているかをお伺いしたいです。

森山(odol / Pf,Synth):以前までは、曲を作ることだけが自分の本当にやりたいことで、ライブは「ついで」みたいな感覚があったんです。でも、活動していく中で、「どうもそうじゃないな」と思い始めて。去年からやっとライブを増やしていて、今はライブが一番大事だと思っています。
—非常に大きな変化ですね。
森山(odol):よく言う話ですけど、音楽は聴いてくれる人がいないと成立しないし、存在できないわけで。聴いてくれる人が目の前にいる状況って、「音楽が強く存在している状況」だと思ったんです。今出した音に、今ここにいる人たちが反応して、ひとつの空間になるというのは、一番「音楽が生まれている瞬間」だと思う。だから、そこをもっと洗練させていかないといけないと思うようになりました。
去年出したアルバムの『往来するもの』というタイトルは、音楽は机の上やスタジオの中というような「ここ」で生まれるのではなくて、往来すること、その運動の中で生まれるんだということを表していて。お客さんと僕らの間で、時間や距離も超えて往来させ続けることが理想ですね。
—『CROSSING CARNIVAL』のコンセプトには「音楽と人の力がクロスしたときに生まれる、非日常的な祝祭感に満ちた場を、今一度作りたい」と書かれていて、言ってみれば、「往来するもの≒CROSSING」でもあるし、目指しているところはすごく近い気がします。
森山(odol):そうですね。その意味で「CROSSING」は僕らのテーマでもあります。こうやって会話をしている中でも音楽は生まれていると思っていて。ここで言葉を使って行った往来が、明日のライブの最中にふと思い浮かんで、音に反映されることは絶対にあるので。

まったく欲望が出てこなくなっちゃったんですよ。(佐藤 / indigo la End)
—indigo la Endはどうでしょう?
佐藤(indigo la End / Dr):メンバーみんな30歳を超えて、武道館とかさいたまスーパーアリーナでワンマンをやることに対して、まったく欲望が出てこなくなっちゃったんですよ。これは別にネガティブな意味ではなくて、無理やり広げるようなことをする必要はないタームに来ているなということで。
昔はその欲望もあったんです。僕が入る前(2015年に加入)には、いわゆる邦楽ロックの乗り方ができるような曲を作らなきゃっていうタームもあったらしいし。
—メジャーデビュー(2014年4月)くらいの時期がそうだったと記憶しています。
佐藤(indigo la End):今は、4人が思ってることが形になること自体、すごくかけがえのないことだと思えるんです。もちろん歩みを緩めるわけではなく、一歩一歩が楽しいし、充実感あるし、幸せな気持ちになるので、まずはそれをしっかりやっていく。まあ、1年後には全く別のことを言ってるかもしれないですけど(笑)、今はそういう気持ちですね。

自分がやりたいことと、バンドというフォーマットが乖離してきている。(Yuto / The fin.)
—The fin.はどうでしょうか?
Yuto(The fin. / Vo,Synth):もともと楽曲制作は俺一人でやっているということもあって、だんだん「バンド」というよりも、プロジェクトベースに変わってきているんですよね。自分がやりたいことと、バンドというフォーマットが、だんだん乖離してきている。
しかも、数か月ごとにイギリスと日本を行き来したり、ツアーに出たりして、いろんな人と交流をしていく中で、自分の中の感覚もバンドからは離れていってて。それが寂しくもあり、楽しくもあるんですけど、そういった感覚を最終的に音楽に落とし込むのが、今自分のやってることなのかなって思っていますね。
—じゃあ、ライブのあり方にも変化がありそうですね。
Yuto(The fin.):変わっていきますね。スタジオミュージシャンに入ってもらうことが多くなるんじゃないかな。自分がやりたいこととバンドというフォーマットが離れて行く一方で、イギリスで知り合ったドラマーとか、いろんなミュージシャンのよさに気付いたので。
そうやって、ちょっとでも新しい風を吹かせられたらって思うんですけど、たぶんいつまで経っても完成はしないんですよ。だから常に自分のベストを探していければいい。2019年は、ただただいい音を出したいですね。

オファーをいただいて、「このイベントは絶対にやったほうがいい」って話になりました。(佐藤 / indigo la End)
—『CROSSING CARNIVAL』はフェスやイベントがアーティストとオーディエンス双方にとって「日常」となる中で、1日限りの強烈な体験を作り出し、さらには、この日がきっかけとなって新たなクリエイティブに繋がることを、開催の意義としています。イベントの趣旨について、それぞれどのように受け止め、出演を決めたのでしょうか?
佐藤(indigo la End):まず、僕たちはさっきも言ったように、今めちゃくちゃ「オーガニック」に、つまり化学調味料を入れてなにかを早めたり遅めたりすることなく活動をしているので、そういうバンドを呼んでくれるだけでもすごくありがたいです。
その上で、今回の対バンは普段なかなか一緒になることがない方々なので、オファーをいただいて、「このイベントは絶対にやったほうがいい」って話になりました。KITEさんが全部のバンドの演出を担当するということも面白いと思いましたし。このイベントに出ることで、もっといろんな人が僕らのことを誘ってくれたら嬉しいなって。
—これまでとは違う層にアピールするきっかけになるかもしれないと。
佐藤(indigo la End):「indigo la Endって、邦楽のギターロックでしょ?」という見られ方もあって。別にそれを打破しようとかは思わないし、どんなイメージを持ってもらっても構わないんですけど、ジャンルレスな共演はどんどんしていきたい。
僕自身は今回の対バンをそこまでジャンルレスだとは思ってないですけど、ちょっと特殊だと思う人は思う対バンだと思うんですよね。なので、こういう形で呼んでいただけるのはすごく嬉しいです。

森山(odol):odolは一昨年くらいからフェスやイベントに少しずつ出るようになって、去年の『FUJI ROCK』とかもそうで、出演したらやっぱりめちゃくちゃ楽しかったりするんですけど。なんとなくフェスはあんまり居場所がないというか、自分たちには合ってないんじゃないかというイメージを持っちゃっていて。
ただ、そんな中でも、いくつかのフェスにはすごく出たいと思っていて、『CROSSING CARNIVAL』は「ここならodolらしくいられるんじゃないか」と感じていました。
—「このイベントなら」と感じたのは、どんな部分がポイントですか?
森山(odol):過去のラインナップにもシンパシーを感じていましたし、コンセプト的にも、「ただ30分なり40分のライブをして帰るだけ」というものではないということが、はっきりと伝わってきたので。去年自分たちで始めたイベントも、ただその日集まって帰っていくだけの対バンにはしたくないと思ってやっているのですが、それを実現して続けていくのはすごく難しくて。『CROSSING CARNIVAL』はその意味でもすごいなと思いますね。

—The fin.はイギリスに拠点を置きながらヨーロッパやアジアなどのイベントに多数出演していて、その中で日本のフェスとの違いを感じる部分はありますか?
Yuto(The fin.):いろんな国のフェスに出てすごく思うのは、アーティストは「ただ呼ばれてるだけ」というか。特に大きなアーティストだと制作チームも一緒にまわっていて、パッケージングされたものを呼ばれたフェスのステージで見せるわけですよね。そうなると、フェスとしてある程度の括りはあったとしても、雑多というか、ステージが違えばまるで違う体験ができて、それが大型フェスのいいところだったりする。みんな自由に音楽をやってる、自由に生きてる、ということを、1日で体験できる市場みたいな。
逆に、今回の『CROSSING CARNIVAL - visual edition-』みたいに、全然違うバンドをひとつにパッケージングするフェスというのは、あんまり見たことがなくて。
—確かに、バンドにとってもチャレンジではありますよね。
Yuto(The fin.):海外ではなかなかこういうことができにくいと思うんですよ。なので、日本でこういったイベントに出ることは、自分たちが日本に戻ってきて活動することの意味のひとつになると思うし、すごく楽しみです。
まあ、自分が見たいっていうのもありますけどね(笑)。ステージが終わって、「今日は映像がよかった」「照明がよかった」とか言われても、ステージにいるこっちはわからないのでいつも悔しいんですよ。今回は特にそう思いそうだなって。

チャレンジをする人がいないと、進歩が止まっちゃうじゃないですか?(Yuto / The fin.)
—『CROSSING CARNIVAL -visual edition-』では、KITEが3組の演出をトータルで手掛けます。ライブにおける音楽と映像演出の関係については、それぞれどういった考えを持っていますか?
佐藤(indigo la End):フェスでヘッドライナーが発表されると、そのアーティスト自体が一番前に見えがちですけど、僕は「プロジェクト」だと思っているんです。今年『Coachella』(毎年4月にカリフォルニア州にて開催される音楽フェス)のヘッドライナーがTame Impalaですけど、あれも「バンドがヘッドライナーをやる」ということではなくて、「総合演出としてすごいから、Tame Impalaがヘッドライナーをやる」ということだと思う。アーティストが一番前というわけではなくて、ライティング(照明)、PA(音響)、VJ(映像)、全部並列なんだということが言いたいんじゃないかなって。

佐藤(indigo la End):実際、音より映像とか照明のほうが、輪郭がはっきりと見えるというか、早く入ってくるってのはありますよね。
森山(odol):視覚からは聴覚の何倍もの情報量を受け取ってしまうので、視覚情報に引っ張られて音の聴こえ方も変わるんですよね。
—森山くんは、藝大でそういったことを研究されているんですよね。
森山(odol):それこそ最近作った作品が「音の視覚化」をテーマにしたものだったんです。スピーカーに3mくらいの糸をつけて、音楽を流すと、音の振動で糸が揺れて模様になる、というもので。揺れた瞬間に「糸が音出してるの?」って言う人がいたくらい、やっぱり視覚って強いんですよね。
森山公稀(odol)が制作した作品
森山(odol):視覚に引っ張られて聴こえ方が変わるのは、音楽を作ってる側からすれば由々しき問題なので、本当は音以上に真剣に考えないといけないことかもなとも思っていて。
僕たちは普段のライブで映像を使うことはほとんどないんですけど、映像に引っ張られちゃうから、使うなら自分でやるか、音に対してかなり密に理解してもらえている人でないとダメだと思うんですよね。でも今回、ステージの映像演出をずっと考え続けてこられて、映像を使うメリットもデメリットも知り尽くしている方とご一緒できるのは、なにか大きなヒントを得られそうだなと思っています。
Yuto(The fin.):そもそも音楽って、聴くことの積み重ねがあってこそわかるものだと思うんですよ。ステレオイメージとかも、本当はめちゃくちゃ3Dで、広い空間があるんだけど、そこまで聴いてる人はそんなに多くない。
逆に、現代人はみんないつもスマホを見てるわけで、視覚的な情報を読み取る能力は高いと思う。だから、視覚で世界観がバチッと決まれば、鳴ってる音が何倍もよく聴こえるかもしれない。ただ諸刃の剣でもあって、音と映像が合ってなかったら、全部壊しちゃう。アーティストからすればちょっと怖さもあり、でもそれが合ったときには最高なんじゃないかなとは思いますね。

—今日はKITEの稲垣哲朗さんにも来ていただいています。稲垣さんは今回の演出プランについて、現状ではどのようにお考えですか?
稲垣(KITE):昨今僕が感じていることは、ステージが「音」「照明」「映像」の3つの要素で成り立っているとしたら、「照明」と「映像」が独立してしまっていることが非常に多くて。大きな規模のライブステージになると、最終的にそれらを調整してステージに昇華するんですけど、立ち上げの段階から「照明」と「映像」を密な関係で作り上げていくことってほとんどないんです。そこを今回、まずはやってみたいなと。基本はプロジェクターで映像を投影するんですけど、「映像」と「照明」の境界線をあやふやにするようなステージをできたらなと考えています。
あとは、3バンドそれぞれ特徴があると思うので、そこに対する大きなポイントをピックアップして広げていく。それら3つの要素をクロスさせて1つのステージを作るということを、今回やってみたいなと思っています。

—3組それぞれの特徴を、稲垣さんはどう感じ取っているのでしょう?
稲垣(KITE):僕の勝手な感覚ですけど、The fin.さんは有機的で、景色的なんです。寒いとか温かいとか、湿気があるとか。odolさんは数学的で、「配置」の音楽。indigo la Endさんは、人のそばにあるものというか、日常に寄ってる。
映像で考えると、The fin.さんは柔らかい感じで、odolさんはもうちょっと硬い感じ。indigo la Endさんは抽象的なものが動いてるだけの映像だと成立しない気がするので、なにか具体的なものが必要かなって。実は、一番悩んでるのがindigo la Endさんなんです(笑)。
佐藤(indigo la End):アイデアのひとつですけど、リアルタイムのライブ映像を使うのもいいかなって。前にサインフェルドというDJを観に行ったら、スクリーンを含めたDJ本人をブラウン管に一度映して、それをプロジェクターで投影することで合わせ鏡のようにして、レイテンシーがあるので揺れる映像になっていて。すごくバイオレンスな感じで、いい意味で、ガツンと殴られた気がしたんですよね。そういう、なにかチャレンジングなことをやりたいですね。
森山(odol):言っていただいた「数学的」とか「配置」っていうのは、自分たちとしてもアイデンティティのひとつだと思っています。感覚も大事にしながら、構造の美しさがないとダメなんじゃないかなって。
ただ、途中の話でもあったように、耳からの情報だけでそれを理解するのは簡単じゃないし、ライブは音源以上にそこが見えづらくなると思うので、構造の美しさを視覚でも見せていただけると嬉しいです。
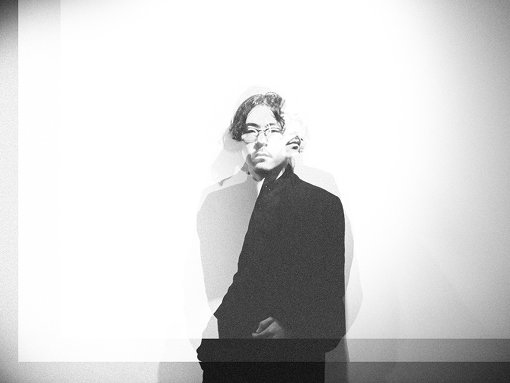
—当日はまだ稲垣さんご自身でも使われていない、最新の技術を使う予定だとお伺いしたのですが。
稲垣(KITE):日本で著名なアーティストの大きなプロジェクトに関わっていると、常に最新のことをやっている感覚になるんですけど、海外の方とお話をさせていただくと、実は遥かに遅れていることがあって。
極東にいる以上、言葉の壁もあって、海外の情報が手に入りにくく、向こうではスタンダードになっていることが日本ではまだ日の目を見ていなかったりする。『CROSSING CARNIVAL』ではそこにもトライしたいと思っています。
Yuto(The fin.):それって音楽の現場も一緒で。書かれている文献も、開発されてる国も、基本的には英語の国だから、日本にはなかなか知識が入ってこないんです。たとえば、向こうのインディバンドは自分たちだけで映像を同期してライブやってるけど、日本のバンドだとほとんどいなくて、俺たちも今そこをやろうとしてます。
そういうチャレンジをする人がいないと、進歩が止まっちゃうじゃないですか? その点でも、こういうイベントには意味があるのかなって思いますね。
—まずは3組の素晴らしいライブを楽しんでもらいつつ、日本の音楽や映像、ライブ演出にも一石を投じるような1日になるかもしれない。当日を楽しみにしています。

- イベント情報
-

- 『CROSSING CARNIVAL - visual edition-』
-
2019年4月3日(水)
会場:東京都 渋谷 TSUTAYA O-EAST出演:
indigo la End
odol
The fin.
Film & Stage Visual Producer:KITE料金:3,900円(ドリンク別)
チケット一般発売日:2019年3月2日(土)
- プロフィール
-

- indigo la End (いんでぃご ら えんど)
-
2010年2月川谷絵音を中心に結成。2014年8月に後鳥亮介が加入。2015年に佐藤栄太郎が加入し現在の体制となる。歌とギターのツインメロディとそれを支えるリズム隊、それらが絶妙なバランスで重なり合う。
- odol (おどる)
-
福岡出身のミゾベリョウ(Vo,Gt)、森山公稀(Pf,Syn)を中心に、2014年東京にて結成。既存のジャンルでは形容できない美学と、新たな日本のバンドポップスを奏でる6人組。全楽曲の作曲をしている森山公稀は、現在東京藝術大学に在学中であり、舞台や映像作品の劇伴、他アーティストへの楽曲提供なども手掛けている。2018年『FUJI ROCK FESTIVAL ’18』に出演。
- The fin. (ざ ふぃん)
-
Yuto Uchino、Ryosuke Odagaki、Kaoru Nakazawaからなる兵庫・神戸出身バンド。2012年頃に活動開始。シンセ・ポップやシューゲイザーからチルウェイヴやドリームポップを経由したサウンドスケープが特色で、初期から海外を視野に入れた活動を展開。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-


