思想や民族、経済格差についての「分断の時代」と語られた2010年代後半から、2020年代に入った現在。依然として状況が変わっていない今だからこそ、演劇やダンスといった芸術を、「人が集うということ」「人と人とが関わりあうこと」を考える材料としてとらえ直したい。
この対談記事はその専門性の高い舞台芸術のシーンについて、アーティストや作品ではなく、それを裏から支える制作者の視点から見た「いま」を紹介するものだ。そして、同時により広い意味で現代社会の「いま」の状況と関わりあうような内容でもある。
今年2月に横浜で開催される『TPAM 国際舞台芸術ミーティング in 横浜』からディレクターの丸岡ひろみ、秋の京都で開催されている『KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭』からプログラムディレクターの橋本裕介の2名を迎え、それぞれの芸術祭のこれまでを振り返ってもらった。
昨年は、『あいちトリエンナーレ2019』を起点に、文化芸術も大きな変節に直面した1年となったが、今年は「その後」をうらなう年となるはずだ。激動の時代に、芸術を作る人たちは、何を考え、どう行動していこうとしているのだろうか?
国や行政の指針を実直に遂行していたら10年間も続けられなかった。(橋本)
―2019年から2020年は『TPAM』と『KYOTO EXPERIMENT(以下、『KEX』)』の両方にとって節目の年となりました。そこで、まずはこれまでを振り返っての感想をお伺いしたいと思います。
『KEX』は橋本さんがディレクターを務めた10年間の体制が今年で終わり、来年からは3人が共同ディレクターを務めるコレクティブ体制になりますね。アーティストと制作者による混合チームなのも面白いですが、そのうち一人は20代の女性だというのも、時代に対して意識的に思えました。
橋本:じつを言えば、結果的にコレクティブになったというのが実情なんです。たしかに外から見ると意欲的な変化に見えますが、コレクティブという形式を優先したわけではありません。継続していくことが重要であるフェスティバルにおいては大きな変化はリスクでもありますから、変化と連続性のバランスを意識しました。
将来的に大きな変化も起こせるような、連続性のあるインフラが確保されているっていうのは絶対に得なことで、のびのびと働ける環境を次の人に引き渡すことも大事にしたかったんです。

2010年より『KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭』を企画、2019年までプログラムディレクターを務める。2013年~2019年、舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM)理事長。2014年1月よりロームシアター京都勤務、プログラムディレクター。

橋本:これまで『KEX』でやってきた仕事を、いわゆるキュレーションの部分以外に何があるのかと考えたとき、自分なりに大きく3つに分けることができると思いました。1つは作品作りのためのアーティストとのコミュニケーション、2つ目はフェスティバルを存続するために不可欠なアイデンティティーの確立、つまり観客との信頼関係の構築。そして最後に、作品の中身やフェスティバルの体験を充実させるための安定したマネージメント体制。
この3つを複数人のディレクターで担っていけば、これまでのイメージとスケールを保ちながら新しい実験もできる。3人ともこれまでの『KEX』に何かしらのかたちで関わってきたことも『KEX』を任せることになった大きな理由です。


丸岡:興味深いです。特に海外の作品をプログラムをするための作品リサーチの総量は、感覚的にこの10年で3倍くらいになったんじゃないかと。ちょっと前までは、情報は量も出所も限られていたので、それを元に出向いていく。
出向く先の候補も限られていたでしょう。「信頼できる筋」からの情報を元に、あとは現地で実際に作品を見て「たまたま出会った」素晴らしい作品を招聘することから動き出すことが多かったように思います。

国際舞台芸術交流センター(PARC)理事長。2005年より『TPAM』(2011年より『国際舞台芸術ミーティング in 横浜』)ディレクター。舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM)副理事長。
丸岡:しかし今は手元のパソコンで一定以上のリサーチをしてから観に行くというのが普通になっている。手元でできるんだから簡単になったようで、じつは処理すべき情報量が莫大になってしまっていて、1人でやる作業としてはこれはとても大変な量です。
だからディレクターが3人になると聞いて、そういった状況へのリアクションでもあるのかと思いました。インプットしてきたものを他の2人にアウトプットできるのもいいですよね。それは全員が同じ立場であることが保証されているからこそできることだから。
フェスティバルにとって大切な財産は、人的なネットワーク形成だ、と丸岡さんが教えてくれた。(橋本)
橋本:この『KEX』の10年は丸岡さんからの応援がなければなかったと思っているんですよ。最初に丸岡さんとちゃんと話したのは10年ちょっと前のベルギーのブリュッセルでした。
ちょうど『KEX』の立ち上げ準備のために、海外のいろんなフェスティバルに行って学んでいる頃に、たしか「スープ飲みに家に来なよ!」と誘ってくれたんです。

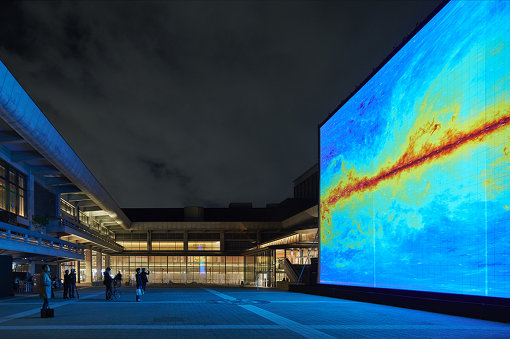
丸岡:複数人でキッチン付きの共同アパートを借りて滞在してたんです。それでスープを作りすぎてしまったので(笑)。でもそれは一種の口実で、いろんな話をあれこれしたかったんです。
橋本:その頃から丸岡さんがずっとおっしゃっていたのが「フェスティバルの目的はネットワークを作ることだ」ということでした。一般的に、国際フェスティバルって、一部の「舞台芸術見本市」と呼ばれるものと同様に、上演作品を国内外で流通させる、つまり買ってもらうことが大きな目的の1つと理解されていますけど、本当はそうじゃない。人的なネットワーク形成こそがフェスティバルにとって大切な財産なんだ、と。
丸岡さんのその言葉と出会っていなかったら、『KEX』も京都 / 関西のアーティストの作品が海外に売れて流通していくことばかりにフォーカスしていたかもしれない。国や地方自治体は、「国際交流支援事業」であっても、補助金を出すにあたって「交流」よりむしろ「日本や京都の文化を発信する」ことに重きを置く傾向があります。でも、それを素直に遂行していたら10年間も続けられなかったし、作品の創作にも悪い影響を与えていたと思っています。
ネットワークという言葉には、個人同士が水平的に結ばれてつながりを持つイメージがありますよね。そうやって出会うこと、意見や価値観をのびのびと交わせる関係が、結果として質や数にも反映されていく……というのがこの10年で得た感覚です。

東日本大震災以降、「つながりたい」という気持ちは「自分たちだけが助かるための共同体」を志向する方へと性質を強めてきた。(丸岡)
―丸岡さんがディレクターを務める『TPAM』のMは「ミーティング」と呼ばれているように、舞台芸術やアートに関わるプロフェッショナルが集まって交流することを主目的にしたプラットフォーム的な催しですね。たくさんの作品も上演されますが、それを話のタネにして、世界中のアーティストやプロデューサーたちがダイナミックにつながっていく。2015年からは、アジア各地との共同制作などを強化した「アジアフォーカス」シリーズを続けてきて、今年はその最後の年ですね。
丸岡:国際交流基金アジアセンターのおかげで「アジアフォーカス」に取り組めたことで、『TPAM』の射程は大きく広がりました。しかし、当初から5年を目処にということで、『TPAM』も大きな節目を迎えていると言えます。
でも、振り返ってみるとそういう節目はこれまでにも幾つかありました。開催地を東京から横浜に移した2011年あたりから特にネットワークに対する実践は強まってきたと思っています。つまり、東日本大震災があって以降、「ネットワークの時代」ということが日本の文化芸術の世界でも盛んに言われるようになりました。


―未曾有の被害を受けて「絆」みたいなものが注目された時期でもあります。
丸岡:一般的にですけど、いまの感覚で言われているネットワークや、つながりたいという気持ちって、裏を返せば「自分たちだけが助かるための共同体」を志向する方へと性質を強めてきているかもしれない。でもあの当時は、みんなが公正さやフラットさを目指して、ネットワークと言っていた気がしています。
私たちの舞台芸術の仕事でも、ネットワークを作ることで自分がしていることもうまくいくし、海外で活動する相手がやっていることもうまくいく互恵的な関係を作ろうという意識が国際的に共有されていたんです。そういう機運があるなかで『KEX』は始まろうとしていたから(『KEX』の第1回目は2010年)、橋本さんという若いフェスティバルディレクターの登場と合わせて「新しい風」が吹いたと感じましたよ。
橋本:光栄です。2011年の『TPAM』と併設していた『IETM』(ベルギー・ブリュッセルに本部をおく舞台芸術専門家のネットワーク構築を目的にした会議)で、フリー・レイセン(ヨーロッパを代表する舞台芸術のキュレーター)と、キーホン・ロー(香港のアートセンター西九文化区で演劇部門を統括するディレクター。当時は『シンガポール・アーツ・フェスティバル』のジェネラルマネージャー)の対談をモデレートする機会をいただいたときは、大役すぎて本当に震えました(苦笑)。

日本って、まず東京にいろんな作品が集まってそこから全国各地に流れていく。でも必ずしも東京をクッションにする必要はないはず。(橋本)
丸岡:これまでに『KEX』と『TPAM』の間では国際共同製作を何度も重ねています。特にアジアの作品で言うと、マーク・テの『Baling(バリン)』。

―マレーシアで活動する演出家の作品ですね。戦後のマレーシア(マラヤ連邦)の知られざる歴史に光を当てる異色の演劇作品でした。
丸岡:マークはいまでこそ日本や海外でも人気だけれど、2015年頃は「マレーシアの作家の作品を共同製作したってチケットが売れるわけない」って感覚が圧倒的で、彼の作品の話をできる人が国内にはほとんどいなかった。でも、橋本さんならすぐにピンと来てくれるんですよね。それまでにマークが何をやってきたかをネットワークのなかで把握しているから。
そういう風に、ネットワークが拡張するなかで、「プロダクション(作品創作)を通して新しい価値を創造するんだ!」という気持ちが周囲にも共有されていたんですよ。橋本さんも「『KEX』があるから京都に来る人」を増やしたいと言ってましたよね。
橋本:たしかに、それまでの作品流通の形態に物申したい気持ちがありました。日本って、まず東京にいろんな作品が集まってそこから全国各地に流れていくようなあり方がありますけど、都市ごとに特徴的な環境があるのだから、それぞれが独自のネットワークを築ければいいじゃないかと思っていました。
例えば福岡の人たちは、海を挟んで隣り合っている韓国とダンスのプロジェクトを自ら立ち上げたりしているわけで、そこで起きている面白そうなことにみんなが直接注目していくという流れこそが健全で、必ずしも東京をクッションにする必要はないはず。その意味では、東京中心の状況に対して『KEX』は何らかの提案をできたかな、とは思っています。


大事なのは、プロフェッショナルが作品に触れて触発され、議論が生まれる環境があること。(丸岡)
丸岡:『TPAM』がなぜネットワークに力を注いだかと言えば、2005年あたりまでの日本やアジアの「国際」ネットワークって欧米を経由したものだったんです。アジアの人と出会うのもヨーロッパという状況で、そんなに遠くに行かずにもっと近い距離で交流したいという気持ちがありました。それと、かつて『TPAM』のMを「マーケット」としていましたが、舞台芸術のジャンルって見本市の形式で売買が成立するかというと、かなり難しかった。
―舞台作品を作るために関わる人の数は、アートや工芸とは比較にならないくらい多いですよね。人件費だけでも莫大だし、作品がかたちになるまでの時間もかかる。
丸岡:だからこそネットワークに賭けたいという気持ちが当時は特にありました。でも『TPAM』では作品上演も欠かせなかった。プロフェッショナルが集まって交わす一番大事なことは「作品論」であってほしいんです。
『TPAM』開催中、一緒にランチを取ったり、観劇する道すがら一緒になったり、大勢の人は1週間以上横浜に滞在しますから、夜一緒に飲んだりする機会もあります。自然とオフで話す機会が多くなっていく。そうやって非公式に話を重ねる機会はとて貴重です。
新鮮な見解を聞けることもあるでしょう。観劇直後に同業者で議論が気軽にできるような環境はとても大事だと思います。

橋本:2011年に『TPAM』のMが「マーケット」から「ミーティング」に変わったことで、少なからず日本の舞台芸術の言説や批評は変わったんじゃないかと思います。つまり「欧米へ日本の作品を売るのだ」という呪縛から少しずつ自由になり、日本の作品もそして意欲的に紹介して来られた他のアジアの作品も、これまでと全く異なる文脈で、それもいわゆるヒエラルキーを意識させないような形で紹介されるようになった。それは結果として、欧米から見たオリエンタリズムに則った作品論だけではなくなっていくことを促したのではないかと感じています。
丸岡:そういった環境の変化が、『TPAM』自体にも影響を与えていったと思います。例えば前回の2019年は、アジアにおけるかつての共産主義の歴史を題材にして、「いま世界で起きつつあることを考える」という裏のテーマが設けられました。
「設けた」のではなく、「設けられた」というのは、その歴史を題材にして創作する作家が複数同時に出てきて「TPAMディレクション」で上演したいという状況が生じたから。それをどのように議論の俎上にあげられるかと考えて、全体のプログラムをつくりましたが、作る側と観る側の間で、そういった議論が交わせるようになったことが大きいですね。
社会に共有されている「身体が失われていく」という感覚を、身体表現や芸術の問題として考えたい。(丸岡)
―今年2020年のテーマである「身体」についても伺いたいです。「身体」がテーマだとすると、今年の上演作品にダンスが多いのもうなずけます。
丸岡:東アジアのダンスプラットフォームが今回の『横浜ダンスコレクション』(2020年で25周年を迎える舞踊フェスティバルで、特にコンテンポラリーダンスに特化している)に併設されると計画の段階から伺っていて、それと提携させていただきたいと思っていました。なので、このテーマは2年前ぐらいから考えていたものだけれど、なかば自ずと作品が集まってきたような感じもありますね。
いま、いろんな意味で「身体が失われていく」という感覚が共有されているとも思うんです。実際に傷を受けている肉体に対する感受性も変わってきているでしょう。


―例えば昨年から続いている香港民主化デモの参加者の中には亡くなった方もいて、路上に出ていった身体が傷つけられ摩耗されていく……という感覚もあります。
丸岡:そういった状況を、職能上、私たちは身体表現や芸術の問題として考えたいんです。今回の上演作品で言うと、タイを拠点とするピチェ・クランチェンの『No.60』は、彼のルーツであるタイの宮廷舞踊からのある意味での訣別をテーマにした作品です。全部で59個ある伝統的な型の先に、オリジナルな自分の60番目の型を作ろうとしています。

丸岡:ピチェ同様に、何度も『TPAM』に参加してもらっているインドネシアのエコ・スプリヤントは『イブイブ・ベルー:国境の身体』を発表します。『Cry Jailolo』に始まる三部作で、彼はインドネシアのマイナーな地域の少年少女たちと世界中をツアーしましたが、その中でコレオグラファーとしての意識も大きく変わっていったように感じます。その彼が、いまインドネシアと東ティモールの国境付近に伝わる伝統舞踊のリサーチに基づいて、「国境の身体」というテーマに取り組もうとしているのは、時代に対して非常に示唆的であるし、重要なことだと思います。そういった経緯もあって、ピチェとエコの2作品は、今回の『TPAM』ディレクションという枠組みで、国際共同製作作品になります。

―過去に「TPAMディレクション」に参加した多数の制作者が、再びディレクターとして加わっているのも特徴的です。
丸岡:これまでの総括の意味もありますね。韓国のコ・ジュヨンさん、マレーシアのジューン・タンさんは去年に引き続いての参加で、小倉由佳子さん、横堀ふみさんはそれぞれダンスのスペシャリスト。
それから今回がはじめての参加になるジョグジャカルタ(インドネシア)のヘリー・ミナルティさんはダンスの研究者・キュレーターで、2007年以来ずっと『TPAM』とお付き合いがあったけれど、なかなか機会がなかったので満を持しての登場。この5人がそれぞれ1作品ずつディレクションしています。
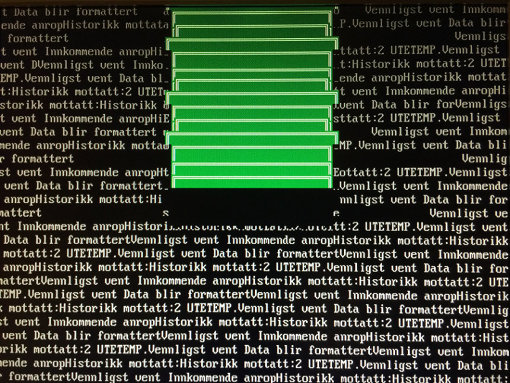
橋本:ディレクター全員が女性なのは意図したのですか?
丸岡:そこは偶然なんです。でもじつは(社会からの)要請を感じていたのかな(笑)。自分ではわからない。
―それから、fieldworks / ハイネ・アヴダル&篠崎由紀子さんも2011年の『TPAM』に参加していますね。やっぱり、これまでの『TPAM』の総括的な感じがあります。
丸岡:「身体の喪失」という文脈で言っても、そのことをこれほどユーモアと不気味さをもって、かつ詩的に表現できるアーティストは希有だと思います。
これまで関わってきた芸術というものが、力強く自分を肯定してくれるものに思えなくなりつつある。そういうマインドを要請してくる、時代の雰囲気があると感じます。(丸岡)
―こうやって上演作品の並びを見ていくと、必ずしも「ダンス」の枠組みに収まらない印象も受けます。
丸岡:ダンスというジャンルには固有の傾向や特質があって、それはいろいろな表現の可能性を拓くことに役立ってきましたから、それを批判するつもりは毛頭ないですけれど、特に小倉(由佳子)さんのディレクションで紹介する劇団態変はそこから大きく逸脱していますね。

―劇団態変は、パフォーマーの大半が重度身体障碍者のカンパニーとして知られています。主宰の金滿里(きむ・まんり)さん自身、首から下を自由には動かせない障碍者です。
丸岡:劇団態変の参加については、小倉さんと『TPAM』事務局とで相談して決めました。こう言ってよければ、小倉さんと私たちとのコラボレーションのような感じもあります。そう聞くと「それぞれのディレクターの裁量権とは?」と思われるかもしれないのですが、そのことに、私は時代状況の反映や、プログラムディレクションという仕事の特殊性を考えたりもします。

―具体的にどういうことですか?
丸岡:少なくとも自分の周りにいる舞台芸術界で働いている人たちの多くが、いま「自分の仕事に迷いがある」と言っています。つまり、これまで関わってきた芸術というものが、力強く自分を肯定してくれるものに思えなくなりつつある。そういうマインドを要請してくる、時代の雰囲気があると私は感じます。
そもそも「TPAMディレクション」は、日本の若手制作者にプログラムをゼロから構想して立ち上げる機会を提供するものとして始まりました。いまでこそ橋本さんや相馬千秋さん(『あいちトリエンナーレ2019』パフォーミングアーツのキュレーションを担当。2009~2013年の『フェスティバル/トーキョー』プログラムディレクターを務めた)のように強い理念を持ってプログラムする人が脚光を浴びるようになりましたし、2015~2017年に「TPAMディレクション」のディレクターの1人だったタン・フクエンはその後『台北芸術祭』の芸術監督になりましたが、当時はそういう人はとても珍しい存在でした。
でも、それは時代が舞台芸術に「社会への応答」を要請していたから生まれた職能でもあるように思うんですね。そして、時代の要請に応えるというミッションを私たち舞台芸術に関わる人たちも信じることができた。ところが、それから10年が経ったいま、信じられなくなっている。

―たしかに、たとえば『あいちトリエンナーレ2019』での『表現の不自由展・その後』の展示中止問題以降、一気に芸術と社会の関係性に変化が生じたように思います。
丸岡:そのとき、劇団態変の金さんの姿勢、すなわちアクティビズムと芸術至上主義を同時に成立させているそれに、私は多くのことを考えさせられます。彼女は「(自分がすべきことは)芸術である」ということを力強く肯定して作品を提出し続けている。芸術家なのだから当たり前といえばそれまでですが、しかし現代社会においてはそれは驚くべきことだと思うんです。
―以前インタビューした際、金さんは「自分がやっているのは、障碍者の社会参画や多様性社会のためではなく、芸術のためだ」と断言されていました。
丸岡:その強さですよね。「芸術に与する」と即答するアーティストがいて、その理念に小倉さんと私たちがそれぞれの実感や文脈から引きつけられ、その話がすぐにできた。このことは『TPAM』の決して短くない歴史が得てきた財産だと思っています。
―時代への迷いも含めて、丸岡さんや各ディレクターが考えたいと思っていること、そして作家や作品のあり方が、2019年から2020年のあるポイントにおいて一致したということですよね。少なくとも、それを共有してともに考えたいと思えた。
丸岡:約1か月ある『KEX』と比べても、1週間しかない『TPAM』の期間ってほんの一瞬だから、きっかけになるくらいのことしかできない。でも、そうなれたならネットワークのプラットフォームとして意味があると思うんですよね。

日本の舞台芸術界は理念がなさすぎた。(橋本)
―先ほど述べたように、5年間続いた『TPAM』の「アジアフォーカス」は今年が最後です。では、その次は何を目指していくことになるのでしょうか?
丸岡:いままで話してきた時代の雰囲気や要請を踏まえると、ネットワークのためのプラットフォームだけでは足りない。何か別の軸が必要だと思っています。しかし、それが何かは、まだ言語化できていません。名称を「マーケット」から「ミーティング」に変えて約10年ですが、グローバル資本主義は加速する一方です。この先に何が起こるか、何が必要なのか予想するのは、とても困難です。

丸岡:でも、そういった時代の変化に最初に反応するのはつねにアーティストの直感だと私は思っています。1つの国が歴史認識を変えるのに100年かかるところを、アーティストは1秒でできるかもしれない。自分たち制作者やプロデューサーは、それに気づくことができるか問われ続けている。
そのことは昔もいまも変わりません。その変化を受け入れることのできる受動性を担保しておくことが必要なんです。そういう意味で、私たちは「ディレクションしている」のではなく、時代やアーティストによって「ディレクションされている」と言えるかもしれない。

橋本:丸岡さんから僕に与えられた影響の1つは、その「受動的であってよいんだ」という意識だと思います。むしろそうすることで考えが自由になっていく。
もちろん僕の場合は最終的にフェスティバルをディレクションしていくので、プログラムの意図を主体的に発する立場ではあります。けれど、だからと言って、その全てを予め設計図のように完全に把握しているわけではないんです。最初の直感の正体をプログラムを作っていく中、あるいはフェスティバルを準備していく中で把握していき、言語化できるようになる、というのが正直な感覚です。
丸岡:プログラムの決断には責任が伴いますし、さまざまな人たちや作品に対する権力を多かれ少なかれ伴います。その権力を持っていないふりをするということではないんですが、あらかじめ設定したテーマにうまく当てはまる作品を集めるというやり方は、少なくとも私は、舞台芸術には馴染まないような気がします。

橋本:劇団態変はまさにそうですよね。こちらが設定したテーマで切ってしまっては、カンパニーと作品が持っている豊かさを切り刻んでしまうことになる。「生身の人間の身体がメディアである」というのが舞台芸術と他の芸術との基本的な違いであって、ひと通り完成したと思った作品も、上演するごとに作品の状態、そしてそれに伴う意味合いは絶対に変わってきます。
高谷史郎さんというアーティストがセゾン文化財団のニュースレターで書いていましたが、「舞台は、美術のような特定のパトロン(美術館 / コレクター)ではない、一般の複数の観客が、ある一定の時間を共有する目的でお金を出しあって成立させて」いて、「民衆的なメディア」であると。私はその考えに同意するとともに、こうした条件が課せられた舞台芸術のディレクション / キュレーションというものの在り方について興味があります。
「テーマを掲げないほうがよい」ってことではないですが、日本の舞台芸術界はむしろディレクション / キュレーションについての理念がなさすぎた。だから『TPAM』や『KEX』がやってきたことには絶対に意味があると信じたいですね。

- イベント情報
-

- 『国際舞台芸術ミーティング in 横浜 2020』
-
2020年2月8日(土)~2月16日(日)
会場:神奈川県 横浜 KAAT神奈川芸術劇場、Kosha33、横浜市開港記念会館、横浜ボートシアター、クリフサイド、関内新井ホール、横浜赤レンガ倉庫1号館、Amazon Clubほか
- イベント情報
-
- 『TPAM フリンジナイト』
-
2020年2月3日(月)
会場:東京都 渋谷フクラス1階 shibuya-san
登壇:
長島確
森隆一郎
丸岡ひろみ
- プロフィール
-
- 橋本裕介 (はしもと ゆうすけ)
-
1976年、福岡生まれ。京都大学在学中の1997年より演劇活動を開始、2003年橋本制作事務所を設立後、京都芸術センター事業「演劇計画」など、現代演劇、コンテンポラリーダンスの企画・制作を手がける。2010年よりKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭を企画、プログラムディレクターを務める。2013年2月より舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM)理事長。2014年1月よりロームシアター京都勤務、プログラムディレクター。
- 丸岡ひろみ (まるおか ひろみ)
-
国際舞台芸術交流センター(PARC)理事長。2005年より『TPAM』(2011年より『国際舞台芸術ミーティング in 横浜』)ディレクター。2003年ポストメインストリーム・パフォーミング・アーツ・フェスティバル(PPAF)を創設。2008年、2011年TPAMにてIETMサテライト・ミーティング開催。2012年、サウンドに焦点を当てたフェスティバル『Sound Live Tokyo』を開催、ディレクターを務める。舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM)副理事長。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-


