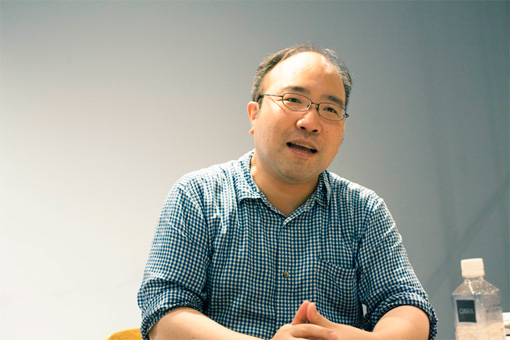ちょっと歯ごたえのあるインタビューをお届けしたい。ニコニコ生放送で、最新のアニメや映画を論じるポップカルチャー批評家、あるいは各種アートの表現を美学的に捉える表象文化論の研究者という、いくつかの表情を持つ石岡良治は、現代の知の巨人、博覧強記の鬼と言えるだろう。
現在、東京の森アーツセンターギャラリーで開催中の『ルーヴルNo.9 ~漫画、9番目の芸術~』展。この後、約1年をかけて全国を巡回する同展には、フランス語圏伝統の漫画表現バンドデシネの巨匠たちの作品、そしてそれに共鳴する荒木飛呂彦や谷口ジローなど日本人漫画家たちの作品が数多く並んでいる。今回、石岡良治を招いてそれらを比較し、バンドデシネの魅力、そして日本の漫画の表現性を考えていく。
石岡が語る漫画表現の魅力、そこから得られる体験の豊かさ、そして「ミュージアム(美術館・博物館)」の存在意義を問い直す、刺激的な思考の数々。読めば読むほど味わい深くなる、スルメのような知的好奇心の旅に出かけよう。
ある一つの表現の歴史を、無茶な比較を通じて考えることに惹かれるんです。それは今回の展示で紹介されているバンドデシネにも共通するところがある。
―美術批評家である石岡さんが、漫画やバンドデシネを見ていくとき、どういったところにいちばん関心を抱かれているんでしょうか?
石岡:「イメージの歴史」ですね。
―「イメージの歴史」ですか……?
石岡:これは、芸術の把握の仕方の一つなのですが、文化人類学や宗教学など多様な文化領域に広がる「イメージ」を前提に、そこから派生するブランチ(枝)の一つとして芸術を捉えるというものです。
―具体的にどういったことでしょうか?
石岡:例えば、国立新美術館で2014年に『イメージの力 国立民族学博物館コレクションにさぐる』という展覧会が開催されましたが、そこで展示されていた世界各地の仮面などは、民族博物館では「地域」や「文化」によって分類されています。
しかし、それを異なる分類ルールを持つ美術館に並べることで、造形性や審美性という美術側の視点で、民族学的な考古遺物を「なかば無理矢理に」捉え直すというのが同展の主旨だったんです。その結果として鑑賞者にもたらされるのは、さまざまなイメージを作り出してきた人間の活動と歴史の広がり、いわば「イメージメイキング」の歴史なんです。この発想に基づいて展開するタイプの美術史は、19世紀末あたりから散見されますが、ここ数十年でより活性化した印象があります。
―つまり、異なる文脈から漫画やバンドデシネを見ることで、まったく違うイメージが生まれてくる。そこに石岡さんは面白みを感じているんでしょうか?
石岡:ざっくり言うとそうですね。『かぐや姫の物語』の高畑勲監督が、『鳥獣戯画』などの絵巻物にアニメーションの原点を見いだしていることはよく知られていますが、私からするとこれはけっこう奇抜な発想なんです。
―奇抜というと?
石岡:高畑さんは著書の中で、絵巻物を見て「フレーミングが悪い、カメラワークがだめだ!」とダメ出ししているんですが、平安~鎌倉時代に映画があったはずもないのに「なんでこの人は現代人のアニメーション監督の目で絵巻物を見てるんだ?」という不思議な気持ちになったんですよ(笑)。これは、アニメーションという観点から絵巻物に迫った結果生まれた、高畑さんなりの「イメージメイキング」の比較検討の試みだという感じがして、その奇抜さが好きなんです。
―石岡さんの批評の立ち位置として、ハイカルチャーとサブカルチャーで批評対象を分けず、むしろその交差から視覚文化全般について考えていくというのは一貫していますよね。
石岡:ある一つの表現の歴史を、完結しているものとして追うよりは、そういう無茶な比較を通じて考えることに惹かれるんです。それは今回の『ルーヴルNo.9 ~漫画、9番目の芸術~』展で紹介されているバンドデシネにも共通するところがあって。ここで展示されている新作は、個々の漫画家にとっても普段の制作とはちょっと異なる、グラフィックに寄った試みが成されているように感じます。
―なるほど。そもそも、石岡さんが初めてバンドデシネをご覧になったのは?
石岡:バンドデシネ代表作家のメビウスですね。大学生の頃に『The INCAL』(アンカル / アレハンドロ・ホドロフスキー作、メビウス画によるバンドデシネの金字塔)冒頭部の翻訳を読んだのが最初です。
―メビウスから影響を受けている方は多いですよね。
石岡:そうですね。当時も、メビウスからの影響を公言している大友克洋さんの描線と比較しながら「なるほど!」と唸ったりしていました。私自身は『スター・ウォーズ』以後のアメリカ発信の1970年代カルチャーを子供の時から無意識に摂取してきたけれど、実はそこにもフランスの文化が作用していたし、シュルレアリスム的な風景に具体的なディテールを加えて展開したような幻想性が、バンドデシネにはありましたよね。
―フランスを含めたヨーロッパ圏の芸術・文化は、時代的にも石岡さん個人にとっても重要だったんですね。
石岡:そうですね。1960~70年代に流行したSF的イマジネーションは、映画、イラストレーション、コミック、バンドデシネなど、ジャンルをまたいで展開されましたが、その多面性がとても重要なんです。ところが、私が学んでいたモダンアートの愛好者には、そうした多面性を疎む教条的な面があって、幻想性や大衆性を軽んじるところがありました。アートの世界でも、サルバドール・ダリなど、シュルレアリスムに見られる大衆文化との接点や、わかりやすい具象性は単純すぎる、という風に(苦笑)。
私も例外ではなく、本当は興味津々だったダリのことを「嫌いだ!」と考えざるをえない空気に染まったあと、長い時間を経て、もう一度ダリを軽蔑しないことを学び直して、バンドデシネにおける幻想性について改めて考えるに至る……というわけです。
―そういう風に、一度否定したものを改めて肯定しようと思ったきっかけは何だったのでしょうか?
石岡:モダンアートからポップアートまで、特にアメリカ美術史を学んでいったことが大きかったですね。それによって、例えばロイ・リキテンシュタイン(新聞連載漫画の1コマをクローズアップしたペインティングなどで知られるアーティスト)の「作品を見る」眼差しで、コミックの描線を見るという逆の発想が現れたんです。
印刷物や書物では、一枚の絵画で得られる経験とはまったく異なる探求がなされているんですね。そのような、画家には及びにもつかないような「連鎖するイメージの力」を積極的に肯定していきたい。これはバンドデシネに限らず、漫画全般について思っていることです。
ある人物の視点を借りて、世界を旅するように観覧していくというのは面白い体験だと思います。
―展示会場の構成も、バンドデシネやルーヴル美術館の世界を再構築したようなグラフィカルな試みがあるのが本展の特徴ですが、先ほど石岡さんがおっしゃった「イメージメイキング」という点で、今回出品している日本人作家たちも共通点を持つように思います。荒木飛呂彦さん、松本大洋さん、寺田克也さん、五十嵐大介さん。みなさん具象的な描写に優れた漫画家ですが、作中でそのイメージがどんどん奇天烈に変形していく展開を好んでいる人たちでもありますね。
石岡:荒木さんが『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズで描写するスタンド(主要登場人物が持つ特殊能力の総称で、目には見えない存在を駆使しての戦いが描かれる。直接的な戦闘能力を持つだけでなく、時空間のルールを歪ませるようなトリッキーな能力を持ったスタンドも数多く登場する)はまさにその代表例ですよね。平面と立体的な空間を行き来するような。
私が思うに、異なる時空を跳躍的に行き来するかのような漫画内の描写は、日本人にとって親しみのあるものではないでしょうか。例えば平野耕太さんという漫画家がいらっしゃいますよね。
―『HELLSING』『ドリフターズ』など、超常的な異能力バトル漫画を描く方ですね。
石岡:全国を巡回した後、現在川崎市民ミュージアムで開催中の『「描く!」マンガ展』にも『HELLSING』の原画が出品されています。同作では、吸血鬼である主人公が、どろっと身体が溶けたりするような能力を持った存在として描かれているのですが、出品されていたのも、まさにそういうシーンだったんです。平野耕太さんは、奇想的なアイデアの視覚化や空間把握の点で優れた漫画家ですが、作中に登場するボイド(闇、空白)とソリッド(固体、実質)が反転するイメージを描くことにおいて、その最良の部分を見ることができる思います。
それは『ルーヴルNo.9 ~漫画、9番目の芸術~』展に参加している日本人作家にも共通する部分で、みなさん、白黒の印刷物である漫画の画面上で「形状の確かさ」と「空虚の曖昧さ」を、同居 / 通底させてしまう表現を得意としている。
―欧米圏の漫画やアニメが立体としての合理性を重んじるのに対して、日本の作品は絵ヅラとしての見栄えを重視して、空間やデッサンの整合性を崩すことに抵抗がありませんよね。
石岡:それがバンドデシネと日本の漫画の大きな相違点だと思います。もちろん、現在はそれぞれから影響を受けた作家、作品も数多くあるので全部がそうだとは言い切れませんが、とはいえ根幹には造形に対する認識の違いがあるのは間違いないでしょう。
―なるほど。
石岡:さきほど私は漫画の「『連鎖するイメージの力』を、積極的に肯定していきたい」と言いました。それはまさに平野さんの作品に当てはまることで、平面性と立体性がするっと越境したり、ボイドとソリッドがくるっと入れ替わる経験は、アニメーション的、映画的なイメージの連鎖、動きを持ったイメージの展開ではなかなか表現できないものだと思っています。だからこそ、コマとコマの関係が分散的に現れる漫画上で、そのような経験を具現化できる作家が現れると「おお!」と驚かされる。
―そのイメージの連鎖、イメージの可塑性はバンドデシネにも当てはまるものでしょうか? 例えばブノワ・ペータース×フランソワ・スクイテンの『闇の国々』などは、ずいぶん遠近法に忠実な、建築的な描写の作品にも思えます。
石岡:作品世界に対する認識の違いがあるんでしょうね。でも、そこから得られる経験はやはり動的なものであるように思います。『闇の国々』は、作家によって構築された風景の奥行きをどんどん深めていこうとするような感じが常にあります。「日本=平面、欧米=奥行き」という二分化した把握には慎重であるべきですが、それでもバンドデシネが空間の深さを感じさせる奥行き表現を伝統的に得意としているのは、事実でしょう。では、なぜバンドデシネはある種の写実的なデッサン力、イラストレーションとしての洗練を必要とするのか?
―そうです。気になるのはそこです。
石岡:私はイラストレーションの大きな魅力は、作品世界の中を歩き回りたくなるような環境を、作中に登場する人物とともに経験できる点だと思います。生物学者のヤーコプ・フォン・ユクスキュルが提唱した「環世界」(象やアリなど、それぞれの種が知覚可能な特有の世界があり、すべての動物はその枠に則って行動しているという考え方)という概念があります。
バンドデシネの作家たちの多くが、これに近い意識を持っているように感じるんですね。彼らがバンドデシネで描こうとしているのは、自ら創造した世界観を示すことであり、登場人物を介して読者をその「環世界」へと誘うことではないでしょうか。
―箱庭的、建築的、造園的な発想が「第9の芸術」であるバンドデシネに備わっているというのは面白いですね。というのも、その上位に位置する「第1の芸術」は建築とされていて、バンドデシネはその原則を忠実に踏まえているかもしれない。
石岡:あと、展覧会のプレスリリースを眺めていて発見したのですが、音声ガイドが声優の神谷浩史さんなんですね! 大ファンなので個人的にも必聴なのですが、声優さんの音声によって作品世界へと誘われていくのは、バンドデシネの構造とも合っている予感がします。イラストレーションやバンドデシネにおいて、ある人物の視点を借りて、世界を旅するように観覧していくというのは面白い体験だと思います。特に神谷さんはゲーム版の『ジョジョの奇妙な冒険』で岸辺露伴を演じた経験もありますから、ファン的には胸熱ですね(笑)。
異なる価値観を生み出す世界が数多存在していて、「それぞれを楽しむのだ」という姿勢が豊かだと思う。
―最後に、石岡さんが『ルーヴルNo.9 ~漫画、9番目の芸術~』展で見たいもの、期待することをお伺いしたいです。
石岡:今回のようにフランスのバンドデシネと、日本の漫画が併置されると、相対的に違いや共通点を探る視点が生じると思うんです。でも、私はそれに少し異論を唱えたい。相対主義的に見ていくと、例えばアートが上で、ポップカルチャーは下といった考えがどうしても浮かんでしまいますが、私にとっては「さまざまな絶対性がいっぱいあるぞ」という感じなんです。
―さまざまな絶対性?
石岡:表現、作家、作品ごとにそれぞれの絶対性があるから、多世界的だということです。一つの世界、一つの視点しかないと、それを規定する価値観で対象を見てしまいがちですが、異なる価値観を生み出す世界が多数存在していて、「それぞれの絶対的な良さを楽しむのだ」という姿勢の方が豊かだと思うんです。 もちろんフランスでは第1から第9まで芸術に位階をつけているわけだから、すでにヒエラルキーはあるわけですけれども(笑)。でも、そもそもルーヴル美術館自体、フランス語では「Musée du Louvre」であって、美術館=Art Museumではないですよね。
―日本語に訳すと美術館とか博物館になってしまいますが、字義としては単に「ミュージアム」です。
石岡:私は「美術館」「博物館」という言い方があまり好きじゃなくて、ミュージアムで総称した方がいいと思っているんです。日本で言うと、東京国立博物館みたいな状況が一つの理想型。つまり、考古学的なものもあれば、美術品もあれば、工芸もある、といった感じでいろいろ含まれていますよね。
ルーヴルにある『サモトラケのニケ』(ギリシャ共和国のサモトラケ島で発掘された、勝利の女神ニーケーの彫像)は美術品として見ることも可能ではあるけれど、やっぱり考古学の世界に片足を踏み入れているものであって、世界の有名ミュージアムの多くが作品を盛るための器として非常に寛容に設計されている。

ルーヴルの代表的作品『サモトラケのニケ』と漫画がコラボレーションしたダイナミックなインスタレーション
―大英博物館もスミソニアン博物館もそうですね。
石岡:最近はミュゼオロジーの議論が盛んで、美術館でアート以外の展示を行うことが是か非かという意見が交わされていますが、ミュージアムを今言ったような枠組みで捉えれば、それは偽の問題に過ぎないとも言えます。私が先ほど述べた「イメージメイキング」というのは、実を言うと、ミュージアムのポテンシャルを最大化するためのものでもあるんですよ。
さまざまなイメージの実践がミュージアムで行われることで、アートの価値もまた改めて照らし出されうる。そう考えると、バンドデシネや漫画を「第9の芸術」として位置づけようとするルーヴルの試みは、意識的に自らを広げているということで興味深いし、多くの作家たちを勇気づけるものだと思うんです。
- イベント情報
-
- 『ルーヴル美術館特別展「ルーヴル No.9 ~漫画、9番目の芸術~」』
-
参加作家:
二コラ・ド・クレシー
マルク=アントワーヌ・マチュー
エリック・リベルジュ
ベルナール・イスレール(画) / ジャン=クロード・カリエール(作)
荒木飛呂彦
クリスティアン・デュリユー
ダヴィッド・プリュドム
エンキ・ビラル
エティエンヌ・ダヴォドー
フィリップ・デュピュイ(画) / ルー・ユイ・フォン(作)
谷口ジロー
松本大洋
五十嵐大介
坂本眞一
寺田克也
ヤマザキマリ東京会場
2016年7月22日(金)~9月25日(日)
会場:東京都 六本木 森アーツセンターギャラリー
時間:10:00~20:00(入場は19:30まで)大阪会場
2016年12月1日(木)~2017年1月29日(日)
会場:大阪府 グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル イベントラボ
- プロフィール
-
- 石岡良治 (いしおか よしはる)
-
1972年東京生まれ。批評家・表象文化論・ポピュラー文化研究。東京大学大学院総合文化研究科(表象文化論)博士後期課程単位取得満期退学。青山学院大学ほかで非常勤講師。著作として『視覚文化「超」講義』(フィルムアート社)、『「超」批評 視覚文化×マンガ』(青土社)がある。
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-