21世紀になり、すでに20年以上が経ってしまった。時代は進んだけれど、私たちの世界は生きやすくなっているのだろうか。今から30年以上前、1986年に発売された藤本和子『ブルースだってただの唄』が、2020年11月に文庫化。本書は、著者の藤本がアメリカで専門職(臨床心理医、会計士等)に就く人々と、犯罪者として服役中の2人に話を聞き、それを文章にしたもので、そのテキストからは黒人女性が直面している困難が浮かび上がってくる。文庫の発売後、反響が大きく、1月に重版がかかったという。
その文庫版の解説を書いた、韓国文学の翻訳家・斎藤真理子と、文庫化の企画に関わった『水牛』の八巻美恵。この2人と、アフリカン・アメリカン文化に精通する音楽ライターの渡辺志保が本書について会話を交わす。本書が復活した経緯や、今も変わらない本書の魅力、現代まで続くアフリカン・アメリカンが置かれた立場を語ってもらった。30年の時間を経て、変わったもの、そして変わらなかったものとは。
多国籍の寄り集まった家族を築いた。視野の広い藤本和子
―まずは、『ブルースだってただの唄――黒人女性の仕事と生活』(以下、『ブルースだってただの唄』)が今回、ちくま文庫より蘇った経緯からお伺いしたいなと思います。いつ頃からどのように働きかけていらっしゃったのでしょうか。
八巻:『塩を食う女たち――聞書・北米の黒人女性』(以下、『塩を食う女たち』)が岩波書店から復刊されたのが2018年で、その前に初めて斎藤さんとお会いしました。くぼたのぞみさんや岸本佐知子さんもいらして、4人の席だったんです。
斎藤:最初に顔合わせしたのが、『塩を食う女たち』の件だったんですよね。復刊のきっかけは、Twitterだったんです。くぼたさんとかと、「『塩を食う女たち』っていい本だったよね」という話になって。その流れで、「これ、どっかで文庫化できないの?」って。

八巻:そうそう。それぞれ、いろんな編集者の方と知り合いなので、ダメもとでかけあったところ、岩波さんが手を挙げてくださった。私は現在、『水牛』というウェブサイトをやっているのですが、それ以前は月刊雑誌の『水牛通信』(1978年から1987年まで刊行)に携わっていたんです。その『水牛通信』の後半に藤本さんが編集員として加わっていたので、雑誌からウェブに移行したときに、藤本さんの著書をいくつかデジタル化して公開することにしたのですね。
20年くらい前の話なんですけど、当時は、PDFというものがないから、手で入力するしかない。それに、インターネットは便利な反面すごく制約が多くて、ダイアルアップ回線でアップしていたから時間もかかりました。とにかく、そんな状況でもウェブにアップしていたので、『塩を食う女たち』復刊を掛け合うときにも「もうテキストはありますから」と交渉することができた。そうした経緯があって、まずは『塩を食う女たち』が出版されたのよね。
斎藤:同時に、「藤本和子さんには自分で書かれたいい本がいっぱいあるから翻訳者としてしか知られてないのはもったいない」「若い世代の女の人にももっと読んでほしい」みたいな思いが出てきて。それで、「藤本和子ルネッサンスを興そう」と話していたんです。今回の1冊で終わりにするんじゃなくて、「藤本和子の仕事」というものを強くフィーチャーしていきたいみたいなことを言いながら。それで、今回の『ブルースだってただの唄』も復刊されることになったんです。

翻訳家。訳書に、パク・ミンギュ『カステラ』(共訳、クレイン)チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』(筑摩書房)、ハン・ガン『回復する人間』(白水社)『誰にでも親切な教会のお兄さんカン・ミノ』(亜紀書房)などがある。
八巻:本って、出た当時は話題になっても、10年、20年と経過していくうちに、その話題が埋もれていっちゃうでしょ。それがすごく残念だったのは、藤本さんのどの本も今読んでも全然古びていないと思うから。ぜひ他の本も、ということになって。
―先に『塩を食う女たち』が復刊されたとき、若い女性読者からの反響はいかがだったのでしょうか。手応えなど感じることはありましたか?
八巻:Twitterである程度は見ましたけど、このときは案外静かでしたね。
斎藤:『ブルースだってただの唄』のときのほうが、声は聞こえてきますね。
八巻:『塩を食う女たち』を出したときとは世界が違ってきていますよね。そういう意味では、受けとめやすいし、ちょっと惹かれる内容ではあるのかな。Twitterではこちらのほうがずっと賑やかです。
―ちょっと遡って『水牛』時代のこともお伺いしたいなと思いまして。そもそも、1980年代から月刊誌としてスタートされていましたが、八巻さんと藤本和子さんが最初に接点を持たれたのはどういうきっかけだったのでしょうか。
八巻:『塩を食う女たち』を読んだ後からですね。それまでは、実際には会ったことがなくて。というのは、彼女は東京にいなかったの。
―その頃から、藤本さんはアメリカ、イリノイ州を拠点とされていた。
八巻:そうです。『水牛通信』のデザインをしていた平野甲賀さんと藤本さんとは若い頃から知り合いで、ちょうど『塩を食う女たち』が出たころに、藤本さんが東京にいらして、平野さんのお宅で会いました。
―ご友人の関係から、ともに『水牛通信』を編集するようになっていかれた。
八巻:『水牛通信』という媒体があったので、「興味があれば」と執筆や編集にお誘いしました。月刊の薄いミニコミだったので、編集の内容については、実際に担当する人が好きにやっていいという方針でした。そういう意味では、入りやすかったのかなと思います。『水牛通信』の最後の頃には、藤本さんが編集長を務めた号もあります。今はもうほとんどPDFにして『水牛』のサイトで公開しているので、彼女の短い原稿なども読めますよ。

編集者。青空文庫の創設メンバーで、伝説的ミニコミ『水牛通信』を復活させた『水牛』の編集長を務める。
―この『塩を食う女たち』も『ブルースだってただの唄』も同じくですが、当時、1人ずつアポイントメントを取って会いに行く、しかも自分で運転してあの広い全米中を廻る……って本当にスタミナのいることだったのではと思うんですけれども、当時の藤本和子さんは、一体どういう方だったのでしょうか。
八巻:友人のことを短く紹介するのはむずかしいですね。「バイタリティーはない」と本人は言うんですけど、もちろん、あります。真摯で、かつ、ユーモアもある。彼女が結婚したデイヴィッド・グッドマンさんはユダヤ人なんですね。それから、養子が2人いて、上の娘さんはペルーの生まれ、そして、下の息子さんは韓国の生まれです。世界の寄り集まり的な家族だったので、視野が広くならざるを得ないですよね。

読んだあとにどう生きられるか、を考えることになる。政治的なだけではない『ブルースだってただの唄』
―今回、改めて1980年代を振り返ってみると、1985年には、あのアリス・ウォーカーの『カラーパープル(当時のタイトルは『紫のふるえ』と訳された)』も翻訳されて出版されています。そして、藤本さんが編集された『女たちの同時代――北米黒人女性作家選』も出版され、ゾラ・ニール・ハーストンやトニ・モリスンらが紹介された。あと、私が学生時代からバイブルのようにして読んできた『黒人として女として作家として』(クローディア・テイト編 / 晶文社)というインタビュー集の翻訳本もあり、この本も1986年に日本で出版されている。それに、高橋茅香子さんによる訳者あとがきには、藤本和子さんのお名前も出てくるんです。当時、文学を通して日本に黒人女性の声を届けようという、ある種のムーブメントのようなものがあったのでしょうか。
斎藤:その辺りの動きに関する入り口は、本当に藤本さんが主導されたと思います。『カラーパープル』が出て、(黒人女性作家の作品に)すごくポピュラリティーが出たんですよ。『わたしたちのアリス・ウォーカー――地球上のすべての女たちのために』(河地和子 / 御茶の水書房)っていう本も出ていたくらいだし。そこに行き着くまでのことを、藤本さんがとても精力的に担ってくれた。
『女たちの同時代~』も、全巻に藤本さんのすごくいい解説がついていますが、それだけではなく、森崎和江や石牟礼道子、津島佑子といった書き手の素晴らしい解説エッセイがついているんです。それを読むと、単純にアメリカ文学の紹介という次元にとどまらず、女の人たちのための一種の文化活動、という側面がはっきり見えてくるんですよね。

八巻:黒人という存在がいて、彼らが差別されている、ということは知識としてわかっているわけですよね。そして、中でも黒人女性はさらに差別を受けているという知識もある。だけど、それだけで生きているわけじゃないって言うのが、『ブルースだってただの唄』を読んで実感したことでした。全体として描き出している問題は政治的なものかもしれないけれど、この本に登場する一人ひとりの話は、そういう政治的な問題だけでは括れないですよね。
たとえばサブタイトルにあるように、「仕事と生活」という部分が描き出されているということ。ですから『ブルースだってただの唄』を読んだら、文句なく面白いですよ。読んだ後では世界が違って見えてくるから、自分はこれからどう生きていくのかと考えることになります。
斎藤:最初に読んだとき、すごく親しみを持って読みましたね。すごく能力のある人たちがたくさん出てくる。仕事して、あるところまで昇り詰めたらぱっと次のところに行く。私はすごくそれが素敵だなと思ったわけですね。それはやっぱり、藤本さんの日本語だったから。彼女たちが喋ったことを、誰か他の人がテープを起こしてレポートを書いたらこうはならなかったと思うんですよ。
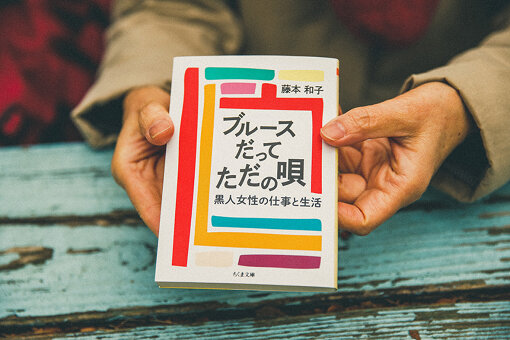
―余白の部分というか、広がりを持たせるような表現、言葉が多いと感じました。その余白部分に、自分自身のことを投影しながら読み進めることができる。
八巻:読み始めたらすぐに入っていける、っていうのかな。
斎藤:「入っていける被抑圧者の話」って、そんなにないですからね。それは、本当に稀有だったと思うんですね。
生活する「1人の人間」の視点で見ることの大切さ
―実際に本を開いて読んでみると、藤本さんの質問文が、他の文章よりも段落が下がって書かれている。前後に行の余白があって、読んでいて温かみを感じました。みなさんに囲まれてお話を聞いていた様子が伝わってきているのかな、と。
八巻:藤本さんの質問文が何字か下がっていて、しかも短い。それがすごくいいんですよね。そういうところはとても上手だと思います。話や質問の感じに自由さがあふれている。
―私も、アフリカン・アメリカンのミュージシャンや活動家の方にお話を伺う機会があるのですが、彼らの歴史や苦難、なにかネガティブな事実に対して質問するときって、本当に言葉を選んで、顔色を伺うようにしながら聞くことが多いんです。藤本さんもそこには細心の注意を払ってらっしゃったかと思うんですが、なんかこう、話し相手に対して気さくに質問していらっしゃるような感じも出ていて。
八巻:そうですね、気さくに、しかし、ズバッとね。
―実際、お話していた場面にはヒヤリとするような場面もあったのかもしれないですけど、それを全く感じさせない。そこはすごく勉強になる点でもありました。それに、どの質問や、そこから浮かび上がるストーリーも、生活にすごく密着している感じがあるな、と思いました。
斎藤:自然に、そういうところに目がいく人なんじゃないかと思いますね。他のエッセイを読んでいても、いろんなところでいろんな人と出会ってらっしゃるんですけど、その出会い方が同じで、面白くて。
八巻:そうね。

斎藤:藤本さんのエッセイである『砂漠の教室――イスラエル通信』(河出書房新社)を読むと、知らないところに行って、知らない文化に足を踏み入れたときに、女の人がどう動いているかを見るんだって。その女の人が立ち働いているときに、周りの男たちがどう手伝うか、手伝わないのか、そういうところを見ていく、と。藤本さんがすごいのは、フィールドワーカーみたいな能力をいろいろ持っているけど、全部をプロみたいにはやらないの。
―それは、ある種の素人らしさをあえて出しているということでしょうか?
斎藤:そうではなくて。プロになるって、なにかを捨てることだと思うんです。普通の目じゃなくなる、ということ。でも、藤本さんは、それはしないの。だから、別に黒人の女性だけじゃなくって、色んな人との出来事をエッセイに書いてらっしゃいますけど、とても独特な好奇心を持って、ユーモラスな感覚で見てらっしゃるんですよね。それってやっぱり、毎日ご飯を作って子どもの面倒を見て暮らしている人の、生活者の目だと思います。
出版された1986年から復刊した2020年まで。変わったもの、変わらないもの
―この本は、ソーシャルワーカーの人も出てくれば、刑務所にいる女性の話も出てくる。色んな立場の方を受容している本ですよね。
八巻:私たちは、この本が出たときをすでに知っているわけで。だから、下の世代の人に読んでほしいと思って、今回の復刊の作業にあたったわけなんです。だから、実際にどういう風に読んでくれているのかな、というのはとても強く思っていて。なので、ぜひそういうお話も聞かせてほしいと思います。海外で、人種も異なる人々が話をしていて、この内容は日本に住む人にとっては遠い話じゃない? だけど、そうじゃない。隣に住んでいる人の話よりも、こっちのほうが精神的には近いでしょ?
―はい。本当に、たくさんの読者に届いてほしいと思います。2020年は「ブラック・ライブズ・マター」ムーブメントの高まりもあり、さらに人種やエスニシティーをめぐる分断や融和が取り沙汰されてきました。偶然にも、この2020年にこの『ブルースだってただの唄』が復刊される。これまで埋もれてきた彼女たちの声に対して耳を傾けるには絶好の機会なのかなと思います。
斎藤:やっぱり、この本は2020年に出てよかったな、と思います。これは1986年の本ですけど、今のこの状況にぴったりだなって思うフレーズがバンバン入ってきて。第1章のところに「たたかいなんて、始まってもいない」って書いてあるけど、当時の私には十分に闘っているように見えたし、黒人の人たちは地域ごとに、一つひとつ、言論を持って獲得しているんだなと思っていた。でも、この本を読み直して、終わってないどころか、始まっていないというのはその通りなんだなと、びっくりしちゃって。
でもそれって、日本に置き換えると、在日コリアンへの差別とヘイトスピーチの問題なんですよ。1980年代にちょっと変わるだろうと思っていて、結果、1990年代に入ったらかなりいい方向に変わったんですね。日本なので、なし崩し的にしか変わらないんですけれど。でも、1回変わったものは戻らないだろうと思っていたの。だから、その後、2000年代になってヘイトスピーチが出てくると思ってなかったんですね。それはやはり、ちゃんと解決しないグズグズに腐ったものがどっかで残っているからなんだと思います。だから『ブルースだってただの唄』で語られている内容も、ある程度達成されていたとしても、その問題のなかに徹底的に焼いて殺してしまわないといけないものが残っていたら、芽が出て花が咲いてしまうんだと。そういう読み方ですね。

―私は、この中に書かれている「彼女らの視線は、にほん列島に生きる少数者に、同化が答えです、といって疑うこともなかったわれわれにほん人を撃ちはしまいか」という1文にかなり衝撃を受けて。この本の中では、マイノリティーであるアフリカン・アメリカンの女性たちが彼女らのルーツをしっかり捉えながら、アメリカで生きていくことについて話していますけど、日本では、多民族、多人種のルーツを持つ少数者にも、できるだけ「普通の日本人」と同化して生きていくような、無理やりな融合を求めることが少なくないな、と。しかもその状況は、この本が書かれてから30年以上経っても、なおひどくなっているように思います。
斎藤:日本って、すごく平準化された社会に見えますよね。あたかも、「普通の人々」という人たちがいるような空気がすごく強い社会だと思うんです。だけど今、それではもうやっていけなくなっている。たとえば、この本とともにブラック・ライブズ・マターの問題を自分の社会における問題として見るときに、『ブルースだってただの唄』はすごく古い本だけど、その内容が古くなっていないのはなぜだろう、ってことを考えるきっかけになるんじゃないかと思っていて。なので、みなさんが『ブルースだってただの唄』を読んで考えたことも私が聞きたいなと思います。

- 書籍情報
-
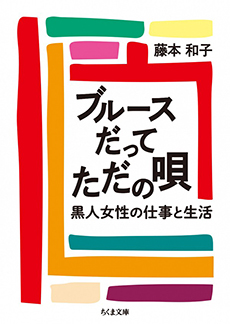
- 『ブルースだってただの唄――黒人女性の仕事と生活』
-
2020年11月10日(火)発売
著者:藤本和子
価格:990円(税込)
発行:筑摩書房
- プロフィール
-
- 斎藤真理子 (さいとう まりこ)
-
翻訳家。訳書に、パク・ミンギュ『カステラ』(共訳、クレイン)チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』(筑摩書房)、ハン・ガン『回復する人間』(白水社)『誰にでも親切な教会のお兄さんカン・ミノ』(亜紀書房)などがある。
- 八巻美恵 (やまき みえ)
-
編集者。インターネット図書館『青空文庫』の創設メンバーで、伝説的ミニコミ『水牛通信』を復活させた『水牛』の編集長を務める。
- フィードバック 17
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-




