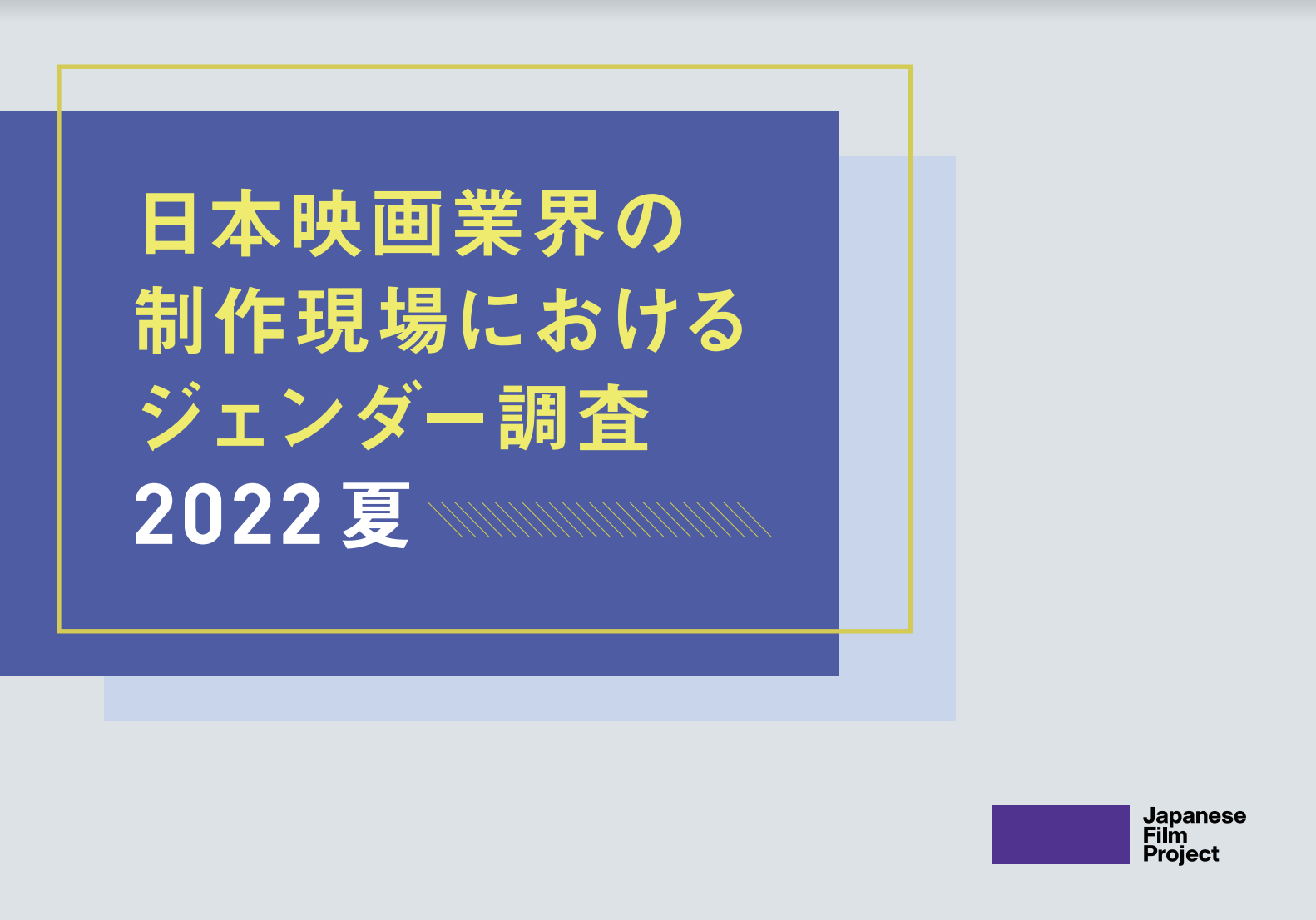女性の撮影カメラマンが数少なかった頃から活躍し、道を切り拓いてきた、撮影の名手・芦澤明子。『トウキョウソナタ』、『散歩する侵略者』といった黒沢清監督作品をはじめ、『南極料理人』、『滝を見にいく』の沖田修一監督、『海を駆ける』の深田晃司監督など名だたる映画監督から絶大な信頼を受けている。また、新鋭・中川奈月監督の長編デビュー作『彼女はひとり』も手がけるなど、業界歴40年以上とは思えないフットワークの軽さと好奇心に、胸が高鳴る存在だ。
そんな芦澤が新たに共作したのは、国内外で数多くの受賞歴を誇るインドネシアの新鋭・エドウィン監督。全編フィルム撮影に挑戦した映画『復讐は私にまかせて』は、『第74回ロカルノ国際映画祭』で金豹賞を受賞した。
若く、活気のあるインドネシア映画界。特に重要ポジションでの女性の活躍が目立ち「希望を感じた」と芦澤は話す。日本映画界は大きな転換点にある。芦澤のこれまでの経歴やインドネシアでの撮影を振り返りながら、映画を志す次世代への想いも聞いた。

2022年8月20日から全国順次公開『復讐は私にまかせて』 © 2021 PALARI FILMS. PHOENIX FILMS. NATASHA SIDHARTA. KANINGA PICTURES. MATCH FACTORY PRODUCTIONS GMBH. BOMBERO INTERNATIONAL GMBH. ALL RIGHTS RESERVED

芦澤明子(あしざわ あきこ)
東京生まれ。学生時代、8ミリ映画作りが高じて映画制作の世界に入る。中堀正夫氏、川崎徹監督に多くを学ぶ。ピンク映画、PR映画、TVCFなどの助手を経て31歳でカメラマンとして独立。1994年、平山秀幸監督『よい子と遊ぼう』から映画にシフト。以後、黒沢清監督の『ロフト』(2005年)、『叫び』(2006年)、『トウキョウソナタ』(2008年)、『岸辺の旅』(2015年)、『旅のおわり世界のはじまり』(2019年)、沖田修一監督『南極料理人』(2009年)、『滝を見にいく』(2014年)、『子供はわかってあげない』(2020年)、原田眞人監督『わが母の記』(2011年)、矢口史靖監督『WOOD JOB!〜神去なあなあ日常〜』(2014年)、深田晃司監督『さようなら』(2015年)、『海を駆ける』(2018年)、吉田大八監督『羊の木』(2018年)、大友啓史監督『影裏』(2020年)など数々の撮影を担当し、『毎日映画コンクール』、『芸術選奨文部科学大臣賞』など多数受賞。
「女の子にカメラマンは無理だよ」と言われた40年前
─芦澤さんがカメラマンの道を歩まれて、40年以上。もともと青山学院大学在学中から、自主映画を制作されていたそうですね。
芦澤:学生時代から自主映画をつくっていたというとすごく映画好きのように聞こえますけど、そうではなくて、始まりは不純な動機でした。好きな男性がゴダール好きだったんですね(笑)。それで映画を観るようになって、友人同士で映画をつくるようになりました。
─そこから映画業界に入っていくわけですが、監督、脚本家など数ある職種のなかで、なぜカメラマンを選ばれたのでしょうか。
芦澤:監督のお仕事って人間関係そのものが仕事に結びつくところがありますけど、私はそういう細かいことに気を遣えるタイプではないんです。あと、撮影部になる前に、1年ほどピンク映画の現場で演出部にいたら、チーフ助監督になってしまって。そのときに、重要な役者さんを「出番が終わった」と勘違いして帰してしまったことがありまして……そんなミスが、二度も。そこで自分に対する自信をなくしてしまって、この仕事は向いていないから辞めようと思いました。
ですが、映画制作は好きなので、業界に未練がありました。周りを見渡したときに、カメラマンなら面倒な人間関係づくりもなさそうだったので、何人かに「カメラマンをやってみたい」と相談したんです。ほとんどの人に「女の子には無理だよ」と言われましたが、伊東英男(※)さんという方だけが「女性のカメラマンも面白いかもね、いいよ」と気軽に受け入れてくださったんです。ご自身も苦労人で、人生を達観していらした部分もあったのだと思います。
※若松孝二の作品などを多く手がけたカメラマン

─その当時、女性カメラマンのロールモデルにあたる方はいらっしゃったのでしょうか?
芦澤:映画業界にはいませんでしたが、テレビ界には女性カメラマンが現れた時期でした。ちょうど東京オリンピックが開催されるタイミングで、報道の現場に採用されたんです。映画業界には同性の同業者はほとんどいなかったけれど、別の業界に同志がいたので不安は特になかったですね。
あと、そこまで先を考えていなかった部分もあります。助手までやれたらいいかな、くらいに思っていました。
─そこから現在まで続けてこられたのは、どうしてだったのでしょうか。
芦澤:撮影が向いていたということもありますが、出会いには本当に恵まれたと思います。伊東さんの撮影助手をされていたのが高間賢治さん(※1)で、彼は非常にフェミニストでした。女性を受けつけてくれないような現場だと、高間さんが盾となって「関係ない」と闘ってくださいました。
独立をして、最初に使ってくれたのがテレビCMの現場だったんですね。映画よりも歴史が浅いので、誰でも受け入れてくれる雰囲気がありましたし、女性に対する遠慮や偏見がなかったので、とてもやりやすくて。性別関係なく、仕事で評価してくれる現場でした。当時は第一線のクリエイターがCMの現場に集結している時代でしたから、川崎徹さん(※2)をはじめ、いろんな方に教えてもらいながら仕事をできたことも、その後につながったと思います。
※1:『ラヂオの時間』『ナビイの恋』など数多く手がける。日本にハリウッドの「撮影監督スタイル」を持ち込んだ第一人者
※2:1970年代から数々のヒットCMを生み出したCMディレクター

監督に手紙を送ってつかんだ縁。「女性カメラマン」でなく、個人として見てもらいたい
─映画の現場には、どのように戻られたんですか?
芦澤:CM業界は能力主義かつ新しいもの好きなので、長くは続けられないだろうと思っていました。映画は観続けていたので、そのなかで気に入った作品の監督にお手紙を書いたんです。
─「ご一緒できませんか?」と。
芦澤:そうです。それが、平山秀幸監督の『ザ・中学教師』(1992年)という作品。「感動しました」といった青臭い手紙を書いたら、お返事をいただいたんですね。そこからご縁あって、『よい子と遊ぼう』(1994年)というWOWOWドラマでご一緒して以来、映画の仕事も入ってくるようになりました。
─女性が少ないことでご苦労も多かったのではないかと想像していましたが、芦澤さんのたしかな仕事ぶりが評価されて、着実に道を歩まれてきたんですね。
芦澤:もちろん苦労はありましたが、最近の映画業界をめぐる状況から昔のことを聞かれて、久しぶりに当時のことを思い出したくらい、嫌な思いはほぼしていないです。忙しいとそんなこと言っていられないという部分もあったと思います。もちろん女性カメラマンに対する偏見がある人もいたと思いますし、私はラッキーなだけかもしれませんが、みんなと同じように扱ってもらいました。

─芦澤さんは以前、「女性カメラマンが撮ったものだと評価されるよりも、芦澤明子が撮ったものだと評価されたい」とインタビューで答えられていました。そう意識せざるを得ないほど、個人を見てもらうのは難しいのではないかと想像したのですが。
芦澤:最近は、あまり「女性カメラマン」と言われなくなりましたが、それは年月や実績によるものもあると思います。「芦澤明子の画とは?」と自問自答することもありますが、やっぱり個人として見てもらいたいですね。いまの時代、元気の良い女性監督たちは多少時間がかかろうとも個性を貫いて、常識を弾き飛ばされている方が多いですよね。そういった方々に刺激をもらって、私も頑張ろうと思っています。
─女性監督たちも、いつかその言葉がなくなることを願って、良い作品を世に送り出していると感じます。
芦澤:わざわざ「女性」と冠をつける必要もないですからね。女性に対して母性やあたたかさを感じている人も多いですが、意外と大胆な人が多いようにも思います。だから、私たちに刷り込まれた「女性らしさ」とは違う可能性がありますからね。

気鋭監督との二度目の協働は、「勃起不全のケンカ野郎と伝統武術の達人女性」を描くラブ&バイオレンス映画
─芦澤さんが撮影を担当された『復讐は私にまかせて』は、「勃起不全のケンカ野郎と伝統武術の達人女性が恋に落ちる」という設定と、嵐のような物語の展開に、日本ではあまり見られない生命力の強さを感じました。芦澤さんは台本を読んだ際、どのような印象を持たれましたか?
芦澤:外国人の私にわざわざ頼むので、旅物などやわらかい物語を想像していましたが、アクション映画級にファイトシーンが多い映画でびっくりしました(笑)。私は、あまりこういうジャンルの作品を撮ったことがないんですね。なので「経験がないのですが大丈夫でしょうか」とお話ししたら、まったく問題ないと仰ってくれたので、気軽に引き受けてしまいました。

『復讐は私にまかせて』 あらすじ:1989年、インドネシアのボジョンソアン地区でケンカとバイクレースに明け暮れる青年アジョ・カウィルが、クールで美しく、武術の達人である女ボディガードのイトゥンとの決闘に身を投じ、情熱的な恋に落ちる。じつはアジョは勃起不全のコンプレックスを抱えていたが、イトゥンの一途な愛に救われ、ふたりはめでたく結婚式を挙げるも、幸せな夫婦生活は長く続かない。アジョから勃起不全の原因となった少年時代の秘密を打ち明けられたイトゥンは、愛する夫のために復讐を企てるが、そのせいで取り返しのつかない悲劇的な事態を招いてしまう。 © 2021 PALARI FILMS. PHOENIX FILMS. NATASHA SIDHARTA. KANINGA PICTURES. MATCH FACTORY PRODUCTIONS GMBH. BOMBERO INTERNATIONAL GMBH. ALL RIGHTS RESERVED
─「復讐の女神」が出てくる怪しげなシーンなど芦澤さんらしい奇妙な画のバランスや、光と影の使い方などに引き込まれるものあがりました。
芦澤:嬉しいです。撮影は2020年の始めにスタートして、途中新型コロナウイルスの感染拡大で中断しました。予算のこともありますし、そのときは撮影もほぼ終えていたので、もう現場に戻れないだろうと思っていたんですが、プロデューサーさんが予算を捻出してくださって、私一人現場に戻れたんです。そこで撮れたのが、そのシーンです。
『復讐は私にまかせて』予告編
─エドウィン監督とは短編『第三の変数』(※)以来2度目の共作になりますが、監督の作品の魅力をどのように感じていらっしゃいますか。
※アジアの気鋭監督3名が、ひとつのテーマのもとにオムニバス映画を共同製作するプロジェクト「アジア三面鏡」で製作された2018年の短編作品
芦澤:本人は、こんなにも精神的に変態性の高い作品をつくるとは到底思えない(笑)、温厚で家族思いな方です。だけど、その素顔との矛盾やわからなさが、人間の面白さであり仕事の醍醐味でもありますよね。
彼の仕事ぶりについては尊敬する部分が多々ありますが、思うのは、現場でやりたいことが明確で、ブレがまったくないということ。たとえ大変そうなシーンでも、監督がどっしり構えているのでみんなも安心してついていけますし、作品全体で彼の意思を感じました。
─芦澤さんの撮影スタイルというのはありますか?
芦澤:スタイルというほどでもないですが、監督の意図を汲んで、寄り添って撮影することを心がけています。今回に関しては監督が事前に何度もロケハンをされていて、ある程度決まっていたので、残りの3割を話しながら一緒につくっていきました。

『復讐は私にまかせて』撮影現場にて。芦澤(右)と、武術の達人イトゥン役のラディア・シェリル(左)、イトゥンの幼なじみブディ役のレザ・ラハディアン(中央)
監督との共通点は「変なもの好き」。フィルム撮影でとらえたインドネシアの空気
─監督との会話で印象的だったことは?
芦澤:インドネシアの空気を大事にしてほしい、ということですかね。それならインドネシア人に撮影を頼んだほうがいいのではないかとも思ったのですが(笑)、とくに緑豊かな自然の景色を、フィルムで残すことにこだわられていて私に声をかけてくれたのだと思います。
インドネシアは季節によって雰囲気が様変わりする国で、5月以降になると乾季に入って、緑が寂しくなっていきます。かといって、1年のほとんどは雨季で撮影に向かない。雨季明けの、乾季に入る手前の隙間の季節を狙って、森や緑の多い場所でたくさん撮影しました。
─コダックの16ミリフィルムを採用されていて、ざらついた質感が物語の不思議さや自然の美しさを表現していると感じました。
芦澤:私も撮っていて、楽しかったですね。ただ、フィルム撮影は想像以上に手間がかかりました。現像は日本で行なったのですが、とてもデリケートなので運搬が人の手運びになりました。なので、1か月に4回にわけてプロデューサーが羽田空港まで運ぶことに。政府の許可書や機内持ち込みの申請など、細かいことではありますが、細心の注意を払う必要がありましたね。

『復讐は私にまかせて』 © 2021 PALARI FILMS. PHOENIX FILMS. NATASHA SIDHARTA. KANINGA PICTURES. MATCH FACTORY PRODUCTIONS GMBH. BOMBERO INTERNATIONAL GMBH. ALL RIGHTS RESERVED
─フィルム撮影に対する技術的な知識だけではなく、監督が芦澤さんに期待していたことを、どう思われますか?
芦澤:直接話を聞いたわけではないですが、前作を通じて、いい意味で「変なもの好き」という部分に共通点を感じたように思います。一度監督とのインタビューで、「インドネシア人と撮るものが違うか」と聞いたら「同じだよ」って言われたんです。本当は「違うね」って言ってもらいたかったのに(笑)。
なので、国籍とかそういう問題ではなくて、監督と私の好みが似ているんだと思います。たとえばアップの寄り方は、画面いっぱいではなくて、フレームに余白を持たせるように寄るんです。そうしたら、監督がすごく喜んでくれて。それで「もしかして、こちら側の人間かもしれない」と思いました。
インドネシアの現場では、重要なポジションに女性がついていた
─インドネシアの映画業界は、女性スタッフが活躍していると話を聞いたことがあります。
芦澤:女性はものすごく多かったです。かつ、重要なポジションに女性たちがついていました。それが、性別関係なく、優秀だからそのポジションについているんですよね。本作のプロデューサーのメイスク・タウリシアは、エドウィン監督の右腕として非常に頼れる存在でしたし、チーフ助監督、美術なども頭のキレる女性たちで、ものすごく存在感がありました。平均年齢も若くて、エネルギーに溢れていましたね。

『復讐は私にまかせて』撮影時、芦澤がインドネシア人のスタッフの名前を覚えるために書き出したというメモ。「そこの録音の人、撮影の人とか呼ばれたくないじゃないですか。できるだけ名前で呼びたかったので、これを毎日確認していました」
─どのような部分に優秀さを感じましたか?
芦澤:ちゃんと決断をする人たちでした。相手の話を聞きながら、意見をはっきり言う。国が若いせいもあるかもしれませんが、自主性がすごく強いんです。
考えを表明するのが当然ですし、たとえば政治参加への意識もものすごく高かったです。ロケハン中に、再選した改革派のジョコ・ウィドド大統領が内閣閣僚を決めたという報道があったのですが、保守派のようなおじさんが入閣すると、ごはんを食べるのも止めて「辞めろー!」って騒いでいました。日本で政治に対して大きな声で意見する人って、あまりいないじゃないですか。政治にも情熱を持って声をあげる姿は、ちょっと感動的でしたね。
日本の女性たちも非常に優秀ですし、意見をはっきり言える人も増えてきました。それが希望だと思うので、これからはもっと決断できる主要なポジションに女性がつくようになってほしいと思います。
─労働環境、セクハラ・パワハラ問題など、映画業界は大きな転換点に立たされています。重要なポジションに女性がつくという前例が生まれることで、道が開くことを期待します。
芦澤:そうですね。男女問わず優秀だからこそずっと自分の部下でいてほしいという気持ちはわかるけれど、ちょっと悲しい。かく言う私にもそんなところもありますけど、それは不幸なことだと思います。次の人を育てたり、業界の前提を覆していったりするためにも、優秀な人が評価されてほしいですね。

最初から自分の可能性を決めつけないで、とにかくやってみる
─40年以上映画業界に携わられている芦澤さんより、これから映画業界を目指す人たちにメッセージをいただけないでしょうか。
芦澤:そうですね……まず、労働環境に対する不安な気持ちは、私もよくわかります。私のような映画スタッフはほぼ全員フリーランスで、経済的に不安定。やっぱり賃金が低かったとしても、定期収入を得て安定したいじゃないですか。いまはいろいろな働き方がありますし、人によっては会社に所属した方が才能を発揮できるということもあると思います。
とりあえず業界に入って、周りをよく観察すること。自分の可能性を最初から決めつけないで、情報を分析したり人脈を広げたり、そうやって多面的に「映画業界を楽しむ方法」を考えるのがいいんじゃないかと思います。

─芦澤さんが演出部から撮影部に異動されたように。
芦澤:一度会社に入ると最後までまっとうするのが、昔は普通でした。ですが、行き先を決めつけたり、職種に固執したりしないで、とりあえずやってみることもとても大事だと思います。ダメなら、また次にいけばいいですしね。
それくらいフレキシブルに自分の未来を考えて、良い出会いを自分から見つけられるといいですよね。
─コロナ禍以降、良い出会いを見つけることが難しくなっているようにも感じるのですが……。
芦澤:でも、視点を広く持てばいろいろあるじゃないですか。たとえば学校や大学に入るのも良い手だと思いますし、興味の似た人たちが集まる場所をSNSでチェックして、とりあえず行ってみるのも良い。
検索に慣れている世代のみなさんだと、興味のあるものだけに目を向けてしまいがちかもしれないですね。私の世代は『ぴあ』という雑誌があったのですが、観たい映画のページにたどり着くまでに舞台や音楽といった興味のないページもパラパラ見ることになる。そうやって、知らない世界をチラチラと垣間見たことで、いまの私の興味の広さや意外な出会いがあったのかもしれません。だからとにかく、決めすぎないでやってみよう、と伝えたいですね。

- 作品情報
-
 『復讐は私にまかせて』
『復讐は私にまかせて』
2022年8月20日(土)から全国順次公開
監督:エドウィン
撮影:芦澤明子
出演:
マルティーノ・リオ
ラディア・シェリル
ラトゥ・フェリーシャ
レザ・ラハディアン
ほか
- プロフィール
-
- 芦澤明子 (あしざわ あきこ)
-
東京生まれ。学生時代、8ミリ映画作りが高じて映画制作の世界に入る。中堀正夫氏、川崎徹監督に多くを学ぶ。ピンク映画、PR映画、TVCFなどの助手を経て31歳でカメラマンとして独立。1994年、平山秀幸監督『よい子と遊ぼう』から映画にシフト。以後、黒沢清監督の『ロフト』(2005年)、『叫び』(2006年)、『トウキョウソナタ』(2008年)、『岸辺の旅』(2015年)、『旅のおわり世界のはじまり』(2019年)、沖田修一監督『南極料理人』(2009年)、『滝を見にいく』(2014年)、『子供はわかってあげない』(2020年)、原田眞人監督『わが母の記』(2011年)、矢口史靖監督『WOOD JOB!〜神去なあなあ日常〜』(2014年)、深田晃司監督『さようなら』(2015年)、『海を駆ける』(2018年)、吉田大八監督『羊の木』(2018年)、大友啓史監督『影裏』(2020年)など数々の撮影を担当し、毎日映画コンクール、芸術選奨文部科学大臣賞など多数受賞。
- フィードバック 26
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-