より面白く生きるために、大変な状況を乗り越えるために、ふと何かをつくってみる——そんな衝動が、自分と誰か、自分と新しい世界をつなぐ始まりになるかもしれない。東京都美術館で7月24日に開幕した『つくるよろこび 生きるためのDIY』は、アートの枠組みを超えて、「つくること」と「生きること」の関係を見つめ直す試みだ。
本展では、「DIY (Do It Yourself/自分でやってみる)」という言葉を、大工仕事のような一般的なイメージに限らない幅広い角度で解釈。5組のアーティストと2組の建築設計事務所の活動を通じ、身近な環境を読み替えてみるまなざしから、被災地や路上で生きていくための人々の営みまで、「創造」の多様なかたちが問い直される。そこから浮かび上がってくるのは、個人のDIYが、他者と共に生きるための「場」を開く可能性だ。
今回ゲストに迎えたのは、アートや福祉、コミュニティの現場を横断して活動してきた文化活動家のアサダワタル。自宅などの自分の空間を、表現を通じて他者と共有する「住み開き」と呼ばれる活動でも知られるアサダは、本展のテーマをどのように捉えるのか。展覧会の開催に先立ち、担当学芸員の藤岡勇人との対談で語り合ってもらった。

自分でつくる楽しさから、他者とつながる「余白」が生まれる
—「DIY (Do It Yourself/自分でやってみる)」をテーマにした今回の展覧会は、どのように企画されたのでしょうか?
藤岡勇人(以下、藤岡):東京都美術館では、当館のミッションのひとつ「すべての人に開かれた美術館」を軸に、アートとライフ(生き方、生命、生活)の関係を考える自主企画展を開催していますが、今回は、専門的なアートに限らず、より人々の生活に寄り添う企画にしたいと思いました。
そうしたなか、ちょうど企画を考えている時期がコロナ禍で、みんながマスクを手作りしたり、家で日曜大工的なことをしたりと、立ち止まって生活のあり方を見直す時間が生まれているのを感じていたんです。そこから自然とDIYというテーマが浮かんできました。

藤岡勇人(ふじおか はやと)
東京都美術館学芸員、アート・コミュニケーション係。ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校修士課程修了。文化批評とキュレーションを専攻。2018年から東京藝術大学大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻の特任助教を務め、研究者、キュレーター、映像作家として幅広く文化事業に従事。2021年から東京都美術館のアート・コミュニケーション事業にて超高齢社会に対応 した「Creative Ageing ずっとび」を担当。ミュージアムでの社会的処方 の調査や、認知症の方とその家族を対象にしたプログラムの企画などを行っている。
藤岡:DIYという言葉はもともと、「自助」や「戦時農園(※)」のような文脈から生まれたもので、貧しいなかで自分たちでどうにか生きる態度を指していました。他方、近年ではこの言葉が消費的・政治的に利用される場面も見られます。ただ、今回はそうした背景よりも、「ものをつくることの意味」や「そこにある喜び」に焦点を当てたいと思いました。
※戦争中、食料増産を目的に、庭や公園など、普段は畑として使われない場所につくられた農園のこと。
—自分で何かをつくることそれ自体の、人にとっての意味を問い直す展示なのですね。
藤岡:そうです。例えば、19世紀のデザイナーで思想家のウィリアム・モリスは、産業革命後の状況のなかで、労働やものづくりに価値を見出しました。彼は、「何もしないでも生きていける未来」とは対照的に、手を動かして能動的になることの喜びを大切にした。そういう姿勢と、今回の展覧会には通じるものがあると思っています。
アサダワタル(以下、アサダ):藤岡さんが本展カタログに書かれた文章を読ませていただいたのですが、そのなかで、DIYだけではなく、「DIWO(Do It with Others / 他者と一緒にやってみる)」という言葉に着目されている点が印象的でした。実際、DIYには一見すると他者の要素は感じられませんが、そこには自分で何かをつくるという自助的な側面だけではなく、他者と自分のあいだの余白を試すような側面もあります。本展の出品作家の実践にはそうしたメッセージが強いと感じました。

アサダワタル
文化活動家。アーティスト、文筆家、近畿大学文芸学部准教授、古書・レコード店〈とか〉オーナー。これまでにない不思議なやり方で他者と関わることを「アート」と捉え、全国の福祉施設や復興団地でプロジェクトやワークショップを実施。その経験を著作や音楽作品として発表。2000年代にドラマーやソロミュージシャンとしてキャリアを始め、芸術系NPOに勤めた後、2010年代から市民参加型のアートプロジェクトの演出家として各地で活躍。自宅を創造的に開放し他者とつながりを生むムーブメント「住み開き」の提唱者としても知られる。著作に『当事場をつくる ケアと表現の交わるところ』(晶文社)、『住み開き増補版 もう一つのコミュニティづくり』(ちくま文庫)、CDに『福島ソングスケイプ』(アサダワタルと下神白団地のみなさん名義)など。
—他者と共に生きるあり方を探る視点は、アサダさんが2008年に提唱され、その後、多方面に広がった活動である「住み開き」にも通じますね。
アサダ:そうですね。「住み開き」は、自宅などの自分の空間を、表現や好きなことを介して誰かと分かち合う営みのことです。始まりは、僕が仲間と大阪のマンションの一室をシェアハウス的に使って定期的に開いていたホームパーティでした。当初はただ情報交換やトークイベントをしていたんですが、そこで次第に「家」という空間の特殊性に気づいたんです。
というのも、家では大きな音が出せないといった音の制約があったり、自分で料理をつくらなくていけなかったりと、いろんな手間がかかります。でも、家が要求するその面倒くささや制約が、人とつながる「余白」になるのではないか? つまり、ほかの場所が借りられないから仕方なく家を使うのではなく、家を開くことそれ自体に意味がある。そこで、これを「住み開き」という表現だと捉え、同じように自宅を開いてギャラリーをやったり、音の実験をしたりしている人たちを取材してきたんです。

—手間が人とのつながりをつくるというのは面白い視点ですね。
アサダ:今回の出品作家の活動にも、自分の場所を自分でつくるという、主体性や手間を楽しむ感覚がありますよね。そこで重要なのは、その行為を「人のためにやる」のではなく、「自分が生きやすくなるためにやる」という点だと思うんです。
住み開きでは、家を開くことの楽しさや、空間をお裾分けしている状況が自分の感覚にフィットしているかを大切にしています。「コミュニティをつくるため」ではなく、あくまで出発点は自分の楽しさなんですね。今回の出品作家にも、自分なりの表現や場の開き方、すなわちDIY的な営みが、気づけばDIWO的な誰かも乗っかれる余白になっているという、面白い矛盾のような共通性がある気がします。
つくり方からつくる、道具からつくる。「ままならなさ」からの創造
藤岡:深く読み取っていただき、ありがとうございます。DIYは一見、個人的な営みに見えますが、それがどのようにDIWOに転換していくのか。今回の出品作品のなかには、「利他的であること」が浮かび上がってくる作品も多くありますが、やはり他者が先にあるというより、「自分のセルフケアから始まる」ことが大事だと考えていました。

藤岡:例えば、設計事務所のスタジオメガネの取り組みもそうです。彼らは多摩ニュータウンの商店街に事務所を構え、ベンチを置いたり、事務所の一部を地域に開いたりして、画一的な団地の空間に小さなノイズを取り入れるように活動しています。それは「住み開き」とも重なり、より面白く生きたいという気持ちが自然と他者との関係を生んでいる。そうした始まり方をしている人が、この展示には多いように思います。
一方で、展覧会の始まりに若木くるみさんを選んだのは、「DIYは個から始まる」という出発点を彼女の作品が体現していると感じたからです。ただ、その作品は一見アーティストの自己表現に見えますが、彼女の制作には文房具などの日用品を本来の機能から離れて観察するなど、異なる視点で周囲の環境を捉えることで、世界を開くような感覚がある。それは、スタジオメガネなどの視点とも通じるものだと感じます。

展示風景より、若木くるみの作品
アサダ:「つくり方からつくる」や「道具自体をどうつくるか」という視点は大事ですよね。以前、勤務先の大学で招いたゲストが、IllustratorやPhotoshopを使う時点でつくるものが規定されていると話していて、納得しました。道具が世界の見え方を決めてしまうことがある。
でも、本当にこの道具でいいのか? そこを疑うことがDIYの出発点になる。若木さんもそうですし、彫刻の工程を見直して新しい装置をつくるダンヒル&オブライエンの活動も、まさにそうした問いを投げかけていると思います。

展示風景よりダンヒル&オブライエン『「イロハ」を鑑賞するための手段と装置——またいろは』(撮影:鈴木渉)
—一方、近年は義務教育の図工の授業が「キット化」しているとも言われますよね。均質な材料が与えられて、そのなかで「自由」につくるようになっているとか。
アサダ:そうなんですよね。既製のキットは失敗しないようにつくられているから、ある程度「上手く」いく。他方、道具からつくることは何が起きるかわからない世界に身を投げ出すことでもある。若木さんがやっているのはそういうことで、彼女は身の回りのいろんなものに「版」を見出して、その「でこぼこ」や「ままならなさ」をそのまま受け入れて作品にしている。そういうコントロールしすぎない態度が、ほかの人にも「やってみようかな」と思える余地をつくり、他人と関わるための余白を生み出している気がします。

藤岡:「ままならなさ」という点では、今回の出品作家の多くが活動のなかで何かしらの閉塞感や困難を感じ、そこから現在の制作に至っているんです。若木さんは、美大時代に木版画を専攻しましたが、版画や美術に難しさを感じてパフォーマンス作品を展開するようになりました。それがコロナ禍にパフォーマンス系のイベントが全部中止なったことをきっかけに、身の回りにある日用品や自然を写し取るという自分なりの版画表現を確立していきます。
久村卓さんも、金属彫刻を専攻していたけれど、当時は大学の設備を使わないと制作が難しかった。さらに、あるときヘルニアを患い、重くて固い彫刻がつくれなくなった。そこで「どうするか?」と考え、ホームセンターで買える素材で控えめに造形する現在のかたちに入っていった。
ある種の遠回りをしながら現在の場所にたどり着き、そのプロセスで自分なりのDIYが必要になった出品作家は多いです。社会のなかで個人が感じる「やりづらさ」も、本展の背景にはあるのかもしれません。

展示設営中の久村卓
「つくる」を柔らかくし、美術館を使いこなす。「アート」と「ケア」の交差点
—既存のやり方が上手くいかなくなったり、ルーティンに疑いを抱いたりしたときに、新しいつくり方を模索するなかで、DIY的な姿勢が求められるのですね。
藤岡:そうですね。加えて、美術館における展覧会のつくり方にも、これまでの慣習や蓄積によって、ある種の型や作法がありますよね。それがあるから効率的に成り立つ面もあるのですが、個人的に今回は、「DIY」のテーマを扱うことで、美術館自体にも何か新しい風を吹き込めないかと考えました。
東京都美術館では、2012年から『とびらプロジェクト』が始まり、10代から70代まで多様な背景の市民が美術館に関わる仕組みが育っています。私自身も、『Creative Ageing ずっとび』という高齢者や認知症の方やその家族を対象とした事業を担当してきましたが、そこでも、美術館のあり方をつねに「更新する」視点の必要性を感じてきました。今回の展覧会は、その延長線上にあります。

—美術館を、ただ展覧会を提供するだけの場ではなく、もっといろんな立場の人たちが関われる場とするための、新しい「関わりしろ」を考え直す機会でもある、と。
藤岡:ええ。「つくること」や「創造的であること」は、アーティストだけの特権ではありません。例えば美術館では、認知症の方々が絵を見て感じたり話したりできる鑑賞会を行っていますが、人は年齢や認知症のあるないに関わらず、誰しも創造性を持っていると感じます。そうした力に気づく、あるいは思い出す機会になればと。
アサダ:そのとき、「使いこなす」という視点が、アートとケアとDIYを結ぶ鍵になるのかなと思います。というのも、「つくる」って0から1を生むことだけではないと思っていて。
僕は2017年から福島県の復興公営住宅に通って、その住民の方々に思い出や好きな曲を聞き、ラジオ番組にする『ラジオ下神白』というプロジェクトを行っていました。その放送で流すのは、加山雄三の“君といつまでも”などの既存曲なのですが、面白かったのは、住民の方々が次第に「住民のAさんの“君といつまでも”」と、その人なりの意味づけをするようになったことです。それはまさに、既存のものを使いこなし、新しい文脈を生み出しているということだと思います。

アサダ:こうした光景は、「つくる」ってどこからどこまでなんだろう? と考えさせます。既存のものを別の文脈で使いこなすことにもまた、「つくるよろこび」があるんですよね。
藤岡:久村さんの作品も、まさにそうです。例えば、バリケードに木材を足してベンチにするなど、「なるべく0からつくらない」ことを意識している。DIYというと手を動かすイメージがありますが、彼のように既存のものに少し手を加えることで意味を変える態度も含めて、「つくること」には幅があるんだと感じます。むしろ、それは能動でも受動でもない「中動態的」なあり方かもしれません。

久村卓『One Point Structure 7』(撮影:鈴木渉)
アサダ:そうですね。久村さんがカタログで、「この世界に美術は絶対必要ですが、それが美術ではない方が良い時もあります」と書かれていたのが印象的でした。そして彼は、自身の作品を、「美術」と「美術以外のもの」という制度の境界を行き来するものにしようと意図している、とも書いていました。
「つくる」という概念も、「美術」や「創造」といった強い主体性を感じさせる言葉と結びつけるのではなく、「している」と「させられている」の中間のような、中動態的なものとして捉えることもできる。そうした柔らかい捉え方によって、「つくること」が日常に開かれ、人が関わりやすい場が生まれるのではないでしょうか。
それぞれの立場を溶かし、「当事場」をつくる文化の力
—瀬尾夏美さんも、アサダさんと同じく震災後の東北で、表現することについて考えられてきたアーティストですね。

展示風景より、瀬尾夏美の作品(撮影:鈴木渉)
藤岡:今回のテーマに引き付けると、2011年の震災直後に瀬尾さんが「とりあえず行ってみよう」と東北へ向かった、その行動自体がまずDIY的だと感じます。翌年には現地に移住し、絵を描いたり、人に話を聞いたりしながら、さまざまなものを見つけていった。そこで彼女がずっと向き合ってきたことの一つに、「語ること」や「語れなさ」という問題があります。
「語れなさ」にはいろんな背景があり、いわゆる震災の「当事者」と「非当事者」がそれぞれの立場で心理的なハードルを抱えてしまう。でも、語ること自体が回復の営みになる場合もある。彼女はそうしたなかで、語れないことをどう語るかということを一貫して問い続けています。僕はそれも、広義の「つくる」につながっていると考えています。
アサダ:僕も、福島での活動や、障害がある方とのアート活動のなかで、「語り」の問題に直面してきました。例えば、取材などで、「〇〇として語る」という役割が固定化されてしまうことがよくあると感じています。でも、本当はどうやって立場を崩していくか、という視点こそが大切だと思う。そこには聞き手の姿勢も関わってきますね。
互いの肩書きや立場が少しずつ溶けていくような「時間的な体験」にこそ、語りという営みの本質がある。だから僕は、語りって「場」なんだと思うんです。

—「被災者として語ってください」というように、役割を固定してしまうと、対話のなかから何かを「つくる」ような豊かな語りは生まれない。むしろ、それぞれが自身の立場から離れていくような瞬間や場にこそ、その契機はあるのではないか、と。それで言うと、アサダさんは新刊『当事場をつくる』(晶文社、2025)で、「当事場」という言葉も提唱されています。いまのお話とも関係がありますか?
アサダ:あります。例えば、DIYを語る際、藤岡さんも触れた「自助」という言葉がよく使われますが、この言葉は使いようによっては容易に「自己責任」に結びついてしまいます。僕が関わってきた福祉の現場でも、「自立支援」と称して「できることを増やそう」と言われます。たしかにそれは必要な支援なのですが、そのとき、利用者をどんな社会的規範に合わせようとしているのか、という問いも大切です。
そのように、DIYも、既存の制度に沿った支援も、下手をすると責任や課題を「個人」に帰結してしまう危うさがある気がします。それに対し、僕は、そうした危うさを「かいくぐる」視点をもたらしてくれるのが、文化的なアプローチだと考えています。それは、文化には世界を普段とは異なる視点で見るように促す力があるからです。
音楽やダンス、版画や彫刻などを介すとき、肩書きや、支援と被支援の構図ではない関係が生まれる。僕はそうした場のことを、当事者の「者」を「場」に代えて「当事場」と呼んでいます。今回の展覧会にも、DIYを通して人が居合わせる場をつくろうという意識がある気がします。
予測不可能、ゴールが見えないワクワクを大切に
藤岡:展覧会場でも、さまざまな要素が交差して、ユニークな場が立ち上がっています。例えばダンヒル&オブライエンは今回、原寸大で自宅を再現するのですが、それに合わせて久村さんが自身の展示の位置を決めていたり。また、会場には展覧会ファシリテータの「つくるん」が常駐して、来場者とのコミュニケーションも生まれる予定です。こうした、あえて計画し切らずに予測不可能な要素を残す構成を大切にしています。

展示風景より「DIYステーション」会場(撮影:鈴木渉)
—また、「DIYステーション」と呼ばれる、来場者自身が手を動かして楽しめるスペースも用意されるそうですね。
藤岡:そうです。さきほどのスタジオメガネと、伊藤聡宏設計考作所という、長野県と東京・多摩市でそれぞれいろんな人が交わるパブリックな場を営んでいる2組の設計事務所に、展覧会に来た人が立ち止まったり、余韻に浸ったり、何かを咀嚼する場をつくってもらっています。
若木さんが彫った古材をフロッタージュして彼女の制作手法を体験できたり、瀬尾さんの語りに注目したプロジェクトの一つ「11歳だったわたしは」に関するワークシートがあったり、ダンヒル&オブライエンの作品に触れられたりと、展示とつながる多様な仕掛けを用意しています。また、路上生活者の方々を撮影してきた写真家の野口健吾さんは、被写体の一人の方の手記を展示します。会場を出たとき、自分でも何かDIYしてみようかなと思ってもらえる場になればうれしいですね。

展示風景より、野口健吾の作品
—展示会場が、鑑賞者も手を動かすことで有機的に変化していく場になるということでしょうか。
藤岡:はい。そんなふうに、有機的に場が変化していく展示を目指したいと思っています。
お話ししながらあらためて思ったのですが、最近「利他」や「ケア」という言葉が流行していますよね。僕も普段から使うのですが、「誰かのために」という響きに違和感を覚えることもあるんです。そこで今回は、まず「やってみたい」「つくるのが楽しい」というDIYの個人的な衝動を起点にし、それが徐々にDIWOへと広がっていくプロセスを考えてみたいと思いました。アサダさんの「住み開き」も、そもそも自分の楽しさから始まった活動ですよね。
アサダ:そうなんです。自分がやりたいから始めたことなのに、それが「コミュニティをつくる」という目的にすり替わると、順序が逆になってしまう。表現的な衝動から始まるもののはずなのに、義務感に変わってしまうこともある。
「住み開き」という言葉が広まると、わかりやすい目的として解釈され、利用されることも起きてしまう。「ケア」や「DIY」も同じだと思います。だからこそ、言葉の使われ方と実践を行き来しながら、つねに点検し続ける必要があるんだと思います。

藤岡:わかりやすい成果や目標が先に来て、そのためにDIYという言葉が使われるとすごく怖いなと思います。実際、「自立しよう」「自分でやろう」というスローガンが、ある意味でマッチョな思想のために扇動的に使われることも増えていると感じます。
でも、前のめりで成果主義の草の根運動ではなく、ゴールが見えないDIYみたいな、言葉になり切っていないけど「やってみようかな」という余白こそが大事だと思うんです。つくるプロセスのなかにある喜びや、他者との予測不能な出会いのワクワク感。それを大事にしたい。今回の展示が、そうしたDIYの側面に光を当てるものになればうれしいです。

- イベント情報
-
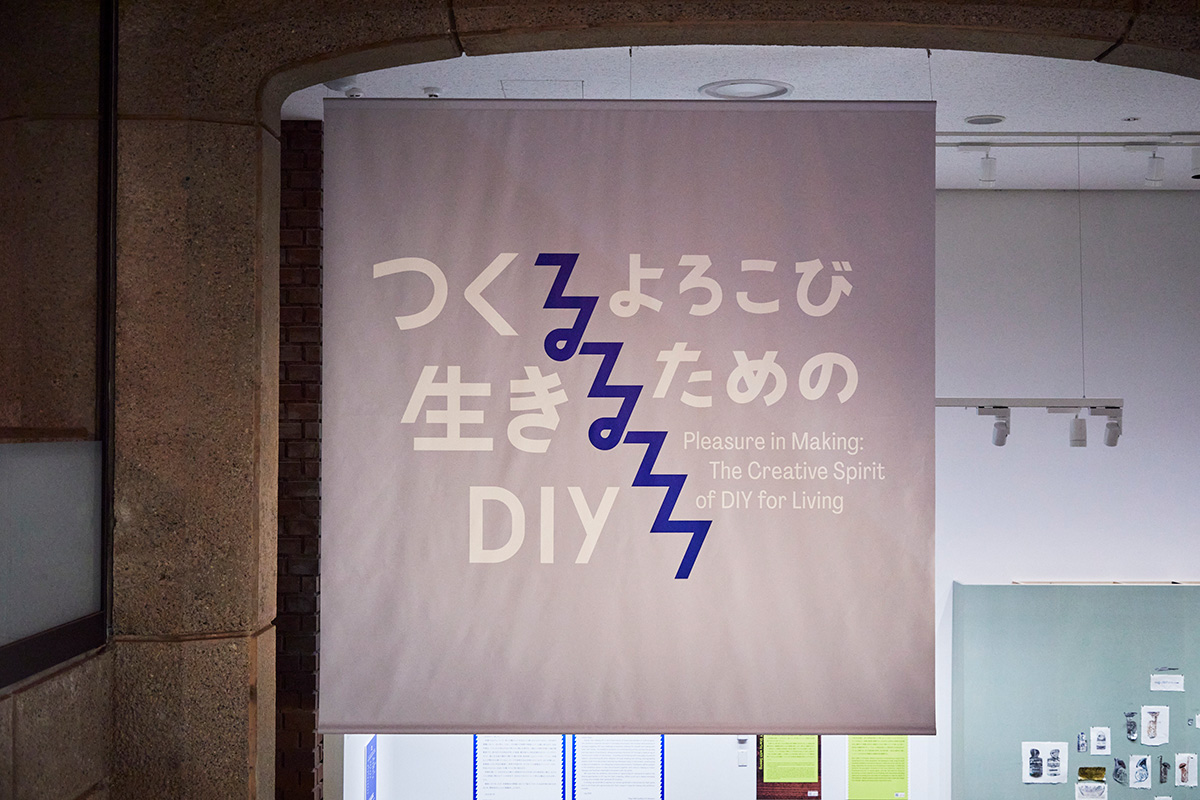 『つくるよろこび 生きるためのDIY』
『つくるよろこび 生きるためのDIY』
2025年7月24日(木)~10月8日(水)
会場:東京都美術館 ギャラリーA・B・C
休室日:月曜日、9月16日(火)
※ただし、8月11日(月・祝)、9月15日(月・祝)、9月22日(月)は開室
開室時間:9:30~17:30、金曜日は9:30~20:00
観覧料:一般 1,100円、大学生・専門学校生 700円、65歳以上 800円、18歳以下、高校生以下無料
- 書籍情報
-
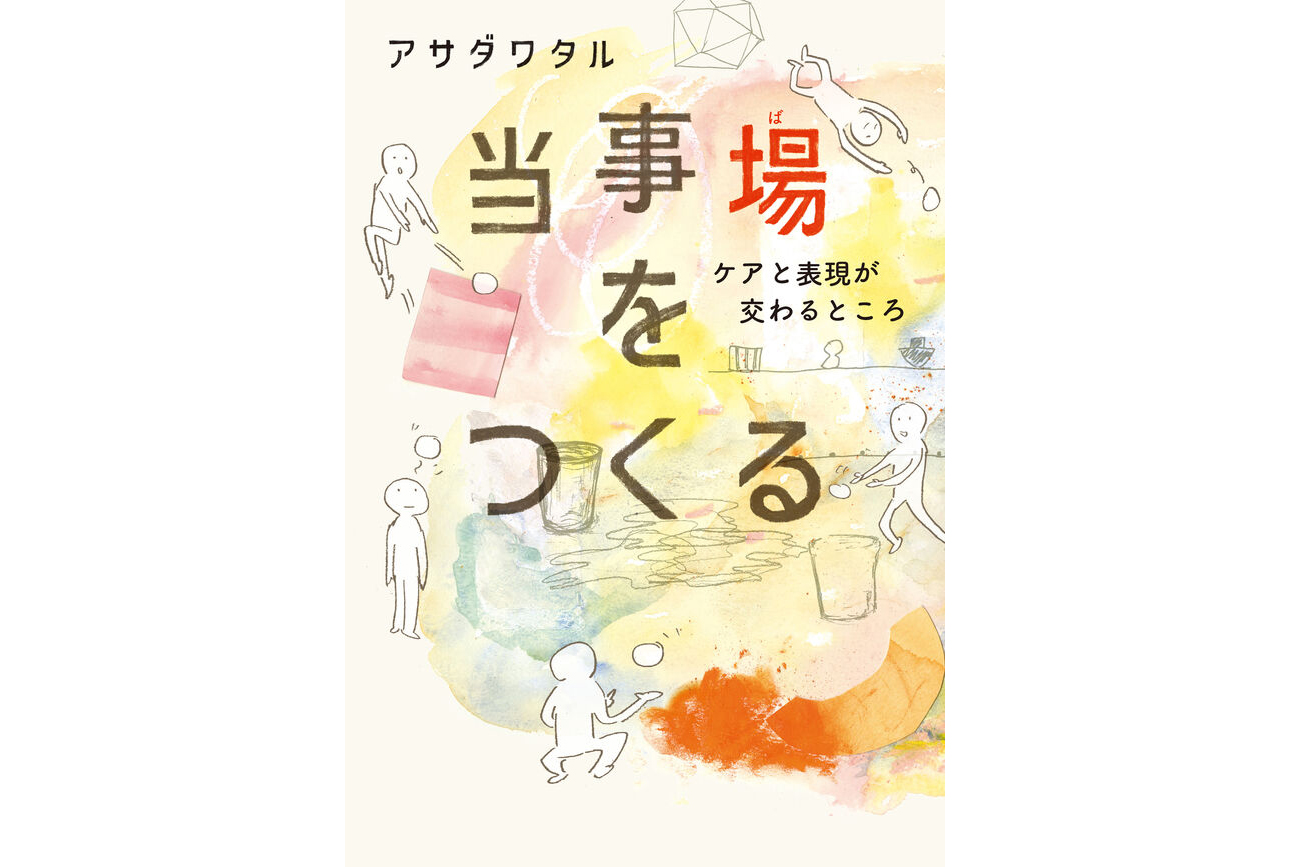 『当事場をつくる――ケアと表現が交わるところ』
『当事場をつくる――ケアと表現が交わるところ』
著:アサダワタル
発行:晶文社
定価:2,200円(税込)
- イベント情報
-
 アサダワタル個展『砕け散った瓦礫の中の一瞬の星座ーリーディング、アーカイブス、ドラテーブルー』
アサダワタル個展『砕け散った瓦礫の中の一瞬の星座ーリーディング、アーカイブス、ドラテーブルー』
会期:2025年8月24日(日)~ 8月31日(日)
時間:12:00~20:00(※関連企画により変動あり)
会場:本と音楽のお店・ときどきゼミ〈とか〉(〒577-0811 大阪府東大阪市西上小阪14-14)
- プロフィール
-
- 藤岡勇人 (ふじおか はやと)
-
東京都美術館学芸員、アート・コミュニケーション係。ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校修士課程修了。文化批評とキュレーションを専攻。2018年から東京藝術大学大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻の特任助教を務め、研究者、キュレーター、映像作家として幅広く文化事業に従事。2021年から東京都美術館のアート・コミュニケーション事業にて超高齢社会に対応した「Creative Ageing ずっとび」を担当。ミュージアムでの社会的処方の調査や、認知症の方とその家族を対象にしたプログラムの企画などを行っている。
- アサダワタル
-
文化活動家。アーティスト、文筆家、近畿大学文芸学部准教授、古書・レコード店〈とか〉オーナー。これまでにない不思議なやり方で他者と関わることを「アート」と捉え、全国の福祉施設や復興団地でプロジェクトやワークショップを実施。その経験を著作や音楽作品として発表。2000年代にドラマーやソロミュージシャンとしてキャリアを始め、芸術系NPOに勤めた後、2010年代から市民参加型のアートプロジェクトの演出家として各地で活躍。自宅を創造的に開放し他者とつながりを生むムーブメント「住み開き」の提唱者としても知られる。著作に『当事場をつくる ケアと表現の交わるところ』(晶文社)、『住み開き増補版 もう一つのコミュニティづくり』(ちくま文庫)、CDに『福島ソングスケイプ』(アサダワタルと下神白団地のみなさん名義)など。
- フィードバック 6
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-





