「難民」という言葉を聞いてどんなイメージを持つだろう? 弱冠25歳の野本監督がつくった映画は、難民についてのドキュメンタリーだった。でもそれは、よくありがちな難民の現状を知ってもらいたい! というような押しつけ的な作品とはほど遠い、ごく個人的な彼の視点でつくられた映画。その個人的な視点が、同世代を生きる人々に多くの共感を生み、不思議と作品がしみ込んでくる。山形国際ドキュメンタリー映画祭や毎日映画コンクールでも受賞した『バックドロップ・クルディスタン』。7月5日からのポレポレ東中野での上映直前に、作品について、そして秋葉原でのあの事件についてなど、野本監督にお話しを伺った。
難民とかクルド人、「なんじゃそりゃ?」って思うじゃないですか?
―『バックドロップ・クルディスタン』を観て、よくある教育ドキュメンタリーとは全く違う印象を持ちました。どういったきっかけでつくったんですか?

野本:そもそも自分の中に、孤独とか不安っていうものが根本にずっとあったんです。今まで生きてきた中で、ニュースで色んな出来事に遭遇するじゃないですか。大きなところで言えば、オウム真理教とか、9.11とか。ぼくと同世代でもある酒鬼薔薇聖斗による事件もそうですね。それで、当然色んなことを感じるわけですけれども、そういった出来事に対して何か自分が関わろうとする。そうすると、何もできないで一瞬にして終わっちゃうんですよ。特に9.11で言えば、あまりに遠い存在で、身近な生活にも何の影響もないから、実感が全くない。
そういう形で色んな出来事が素通りしていく中で、結局自分は社会とつながれないんじゃないか、何ともつながれないんじゃないか、っていう孤独や不安を感じていました。もちろん、それでも生きていくことはできるわけですよ。バイトして、夜は友達と飲んで、って。でも、やっぱり何か残っちゃうわけです。
そんな中、映画学校の卒業制作をつくる時期に、タワレコにフラっと寄ったんです。そしたら、とあるポスターが貼ってあって、「世界にはこんなに難民がいます」とか、「日本は他の先進国に比べてこんなに難民を受け入れていません」っていうのを見たんですよ。「難民」って聞いたら、もうそれはそれはすごい遠いわけです。でも、学校で聞いたような、なんとなくのイメージはありますよね。で、ちょっと調べてみたら、色んな事実を知るわけです。そうこうしているうちに、この作品に出演しているクルド人のカザンキラン一家に出会いました。それで決めましたね。これで作品をつくろうって。
―そういう社会とつながりたい、っていう思いから難民を題材に作品をつくろうという時に、やっぱり彼らの現状をもっと広めたいとか、そういうジャーナリズムというか、正義感のようなものはあったんですか?
野本:正義感なんていうものはまったくなかったですね。彼らが難民として認められないから座り込みをするっていう状況になって、もちろんぼくも人間なので「お腹が空いているだろうな」とか、「不衛生だから大丈夫かな」とか、そういう思いはありましたよ。でも、「難民がこんなにも辛い境遇だからそれを広めたい」っていう衝動ではなかったです。やっぱり「自分は何者なんだ」、「社会と関わることはできるのか」っていう問いからスタートしていて、その問題を軽々とクリアしちゃっているのがあの一家だったんです。もちろん彼らの言動には賛否両論あるとは思いますが、それでも彼らはちゃんと自分が誰であるかっていうことを語れるわけですよ。それがすごく魅力的に見えたんです。自分に足りないものが彼らにあった、だから撮った、そしてそれが難民であった、っていうことなんです。
―なるほど。だからきっと、観る側にとってもすごく遠いものである「難民」を作品を通して見た時に、スっと入ってくる感覚があったんだろうと思います。それが野本さんのドキュメンタリーをつくるスタンスなんでしょうね。
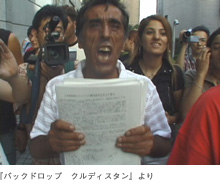
野本:もちろんあの一家とは近い距離にあったとは思います。ずっと一緒にいるわけですから、バカ話しとかもしますし。でも、今まで自分の中にあった難民像と、実際にそこにいる彼らに、やっぱりズレが生じるわけです。「難民」って言ったら、戦争で被害を受けていたり、迫害を受けていたりっていうイメージだと思うんですけど、彼らのバックグラウンドを含めて、ぼくにはわからないことが多かったんです。だから、手放しに彼らを助けるために自分が動くことはできなかった。彼らが難民として主張することが○か×かっていうのは、非常に答えにくいと思うし、ぼくにもわからないんです。この作品を観た知人から、「難民は携帯を使うのか」とか、「難民はテレビを観るのか」とか聞かれましたが、そりゃ彼らだって人間だから携帯も使うし、テレビも観るわけですよ。そういう、「難民」っていうある意味でキレイなイメージと、自分が実際に見たズレを無視はできないし、自分にウソをつきたくなかったんです。
―となると、野本さんがこの作品の中で伝えたかったことっていうのはどういうことになるんですか?
野本:関係することが大事なんじゃなくて、関係し続けることが大事なんだっていうことですね。関係する対象自体は、なんでもいいと思っているんです。やっぱりこの作品は同世代の方々に観てもらいたくて、冒頭に話したような自分が感じた「何ともつながれないんじゃないか」っていう孤独や不安に対して、とりあえずなんでもいいから「やっちゃえ」っていうことなんですよね。難民とかクルド人って聞いて、「なんじゃそりゃ?」って思うわけじゃないですか。その瞬間から関係はスタートしていて、関係し続ければするほど、そこに意味が生まれてくる。そういう感覚を伝えたいと思っています。
秋葉原の事件を知った時に、「何かこの感覚、似てるな」って思った。
―同世代に向けた作品ということで、世代の話しをすると、ぼくも野本さんも、「キレる17歳世代」とメディアから言われてきた世代ですよね。先日の秋葉原での事件、加藤容疑者もちょうど同世代でした。どのようにご覧になりましたか?

野本:これはとてもナーバスな問題だと思うのですが、まず、人を殺すということは絶対にやってはいけないことだし、事件自体は当然否定します。でも、あの事件を知った時に、「何かこの感覚、似てるな」って思ったんです。17歳の頃の感覚に戻った。ぼくはきっと、あの頃感じていたものを消化せずに今まで生きてきたんだな、っていうことに気づいたんです。
まず、彼を特別な人として否定できないわけです。繰り返しますが、人を殺すという行為については当然否定します。今は、ぼくには映画っていう表現手段があるし、こうして話しをしたりできて、社会とつながっている実感を持てている。でも、彼の家族とか仕事とか、詳しいバックグラウンドはわからないですが、それでも彼を特別な人間とは思えないんです。事件そのものは悪だけれども、彼自身は特別ではなくて、ぼくや、ぼくの周りも含めて、たくさん似た感覚を持っている人はいるんじゃないかと思います。
―ぼく自身も当時「キレる17歳」を意識しましたし、今回の事件も加藤容疑者の年齢を見て、ドキっとしました。もちろん、人を殺めることは絶対にしちゃいけないし、あの事件に巻き込まれた遺族の方々のことを思うと、悲しくなります。でも、彼自身を特別な人間として追いやることはできないし、逆にそれをしてしまったら思考停止してしまって、何にもならない。でも、この共通の感覚っていうのは一体なんなんでしょう?

野本:ぼくはこの言葉が大嫌いなんですけれども、「悶々とした気持ち」っていうことなんだと思います。ぼくはそれを形にしたいから作品をつくるわけですけど、やっぱり誰かと関わりたいわけですよ。事件直前までの掲示板での書き込みを見ても、彼が誰かに止めてほしかったことがわかります。きっとギリギリまで可能性を信じていたんだと思うんです。誰かが止めてくれるって。ぼくもそれを求めたことがあったし、今も求めている。止めてもらえなかったからって、あんなことをしていいかと言えばそれは別ですが、あの書き込みを見た時に、ゾッとしましたよ。あの行為だけはやったよな、って。救いを求める行為は多くの人がやっているはずなんです。どうにかしてほしい、っていう信号を出していたんですよね。
―そうですね。きっとその「悶々とした気持ち」は、そもそも社会に対して何かをしたいというバイタリティがなければ生じない不安や寂しさだと思うし、その気持ち自体はすごく大事なことだと思います。『バックドロップ・クルディスタン』でも、その気持ちを表現していらっしゃることが伝わってきました。いよいよ7月5日から公開になるわけですが、公開後、今後の予定は決まっていらっしゃるんですか?
野本:とりあえず劇場公開して、少しでもお金が入って・・・。あ、儲かるわけじゃなくて、制作費が返ってくるだけなんですけどね(笑)。そしたら引っ越しするぞ、とか、犬の散歩しようとか、そばを打つ練習するぞとか、映画以外の雑念ばっかりですね(笑)。でも、次も映画を撮るって言ってまわってます。ウソをつくのはイヤなので、そうなると撮るしかなくなるんで(笑)。
もちろん、次を考えてはいますよ。それは今話していた、自分があの頃に消化できなかった感覚があるんだったら、それを作品を通して消化する、引っこ抜いてやるしかないなっていう。今回は日本人とクルド人っていうことで、良くも悪くも遠かったわけです。だから、もっと近い形でやりたいな、っていうのはあります。前作でリストカットする少女を撮って、今回クルド人を撮って、次は、ぼくの若者論の最終章だと思っているんです。今25歳なんで、若いって言われるのはもうあと2、3年じゃないですか。どんどん大人になっていっちゃうだろうから、今だから撮れるギリギリのものを、自分が積み上げてきたものでつくりたいですね。
―それはやっぱり、ドキュメンタリーですか?

野本:おそらくそうでしょうね。でも劇映画もやってみたいとは思いますよ。とは言え、どちらにせよそれは手段でしかないわけですよ。ほんとになんでもいいんです。カメラが上手ければカメラでもいいし、楽器が上手ければ音楽でもいいし、犬の散歩でいいんだったら、犬の散歩でいいんですよ(笑)。「これで生きているかんじがするぜ」っていうのがあれば。
―では、最後に、この作品を観る同世代の方々にメッセージを(笑)。
野本:いやいや、多くの方々に見てもらいたいですよ(笑)。年齢、性別問わず、お願いします。でも、ドキュメンタリーとか、特に難民を扱っているって聞くと、なんか難しいんじゃないかなとか、無理矢理教え込まれるんじゃないかなとか思うじゃないですか。でも、映画は娯楽ですからね、働いている人であれば土日観に来て、1500円とか1800円とか払うわけじゃないですか。だから、楽しんでもらいたいですよ。この作品を観て難民問題を知ってもらいたいとはあまり思っていなくて、知ってもらえたら「ラッキー、やったぜ」くらいなものですからね(笑)。単純に映画として、エンターテインメントとして観に来て頂きたいですね。観た後は、色々感じたり考えたりしてくださるかもしれませんが、映画だから娯楽として、バカになって観に来てほしいです。『スピードレーサー』の後にでも、是非(笑)。
- イベント情報
-
- 『バックドロップ クルディスタン』
-
2008年7月5日より、ポレポレ東中野にて公開
監督:野本大
プロデューサー:大澤一生
撮影:野本大、山内大堂、大澤一生
編集:大澤一生
2007年/日本/カラー/102分/
配給:バックドロップ フィルム
- プロフィール
-
- 野本大 (のもと まさる)
-
1983年6月生まれ。埼玉県羽生市出身。高校卒業後、日本映画学校に入学。映像ジャーナルゼミに所属し、ドキュメンタリーの制作を学ぶ。 2年次に、自傷癖のある女子高生を撮った「*@17」の演出を務め、卒業制作にはクルド難民企画を提出するもあえなく落選。撮影を続行するため同校を中退し、3年の月日をかけて今作を完成させた。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-


