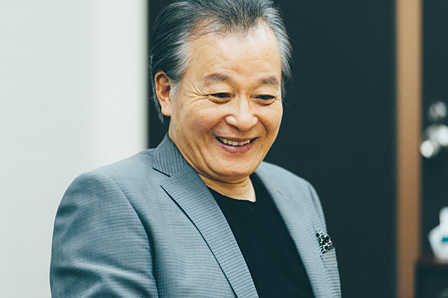大竹まこと、きたろう、斉木しげるから成るシティボーイズは、後世に多大なる影響を与えながらも、若手が簡単には真似できないオリジナルな世界を体現してきた、唯一無二のコントユニットだ。例えば『キングオブコント』のような番組を見ると、シティボーイズから触発されたであろう部分が散見されると同時に、未だに誰も彼らと同じ地平には立てていないことが分かる。そのナンセンスでシュールな芸風は他の追随を許さなかったのである。
そんな彼らが五反田団主宰の前田司郎を作・演出に迎えた公演『シティボーイズ ファイナルpart.1「燃えるゴミ」』のDVDが、10月28日に発売される。公演名に「ファイナル」と銘打ち、ひとつの区切りを迎えた彼らの足跡を、三人の発言を交えながら振り返ってみよう。
演劇につまらなさを感じ、コントの世界に飛び込んだ
シティボーイズの結成は1979年。当初、彼らは劇団「表現劇場」の一員として、俳優の風間杜夫らと演劇活動を行っていた。だが、既成の演劇に退屈を覚えた三人は、徒手空拳でコントの世界に身を投じ、1981年には『お笑いスター誕生!!』で10週を勝ち抜いてグランプリを獲得。彼らの初期の作風を象徴する公演名として、『思想のない演劇よりもそそうのないコント!!』というものがあるが、このタイトルについて彼らは当時をこう回顧する。
斉木:俺たちの若い時は、新劇が盛んで、思想の押しつけ的なものをすごく感じていたんだよ。それに対して冗談じゃないって思っていた。それだったらコメディアンの先輩の方がずっとすごいと思ったわけで。
きたろう:演劇はつまらないという素直な言葉ですよ。僕たちの時代の演劇は、それほど思想のない人が得意気に啓蒙的な芝居をして、何がやりたいんだろうと不思議だったからね。
新劇とはヨーロッパ流の近代的な作風を目指す日本の演劇を指す。だが、芸術志向が強く、時に大上段に社会的メッセージを発する新劇に、彼らは違和感を覚えていたようだ。一方、シティボーイズのコントはいい意味で観た後に何も残らない、という印象がある。思わせぶりな思想的意匠をまとった演劇ならば、くだらないことを一生懸命やるほうがかっこいい、と彼らは思ったのではないだろうか。赤塚不二夫的に言うなら、「真面目にふざける」というスタンスである。

『シティボーイズ ファイナル part.1「燃えるゴミ」』より
36年間、時代を読みながら、他の人がやっていないことを絶えずやり続けてきた
そんな彼らが1983年から開始した舞台公演『シティーボーイズ・ショー』には、当時放送作家だった宮沢章夫が作家として参加した。更には、そこにゲスト出演していた竹中直人、中村有志、いとうせいこうらと共にお笑いユニット、ラジカル・ガジベリビンバ・システムを結成。彼らの笑いは1980年代のサブカルチャーシーンに大きな足跡を残しており、スチャダラパーは彼らの公演『スチャダラ』からグループ名を取っているほどだ。下の世代に様々な影響を与えてきた理由を、彼ら自身はこう分析する。
きたろう:他の人がやっていないことを絶えずやろうと思っていたからじゃないかな。見たことのないことをやってくれたって言われることも多いし。そのかわりメジャーにはなれなかったけど、新しいことが好きな人には好かれたんだと思う。あとはかすかなインテリジェンスが感じられるところかな、若い人に影響を与えられたとしたら。
―シティボーイズがすごいのは、名コントがいくつもあるのに、それを再演してこなかったところだと思うんですけど。
大竹:同時代性の中で常に新しいことをやりたいと思っていたわけで、そのためには同じことをやって笑わせるんじゃだめだったんだよ。コントでも漫才でも、自分の十八番を延々とやり続ける人もいるけど、俺たちはそういうふうになれなかったんだね。作家も宮沢(章夫)、三木(聡)、細川(徹)、天久(聖一)、今回(『シティボーイズ ファイナルpart.1「燃えるゴミ」』)の前田司郎さんと、どんどん変わっていったしね。
きたろう:改めてこれまでやってきたコントを並べてみると、「こんな何本もやってたんだ」ってびっくりしたね。
斉木:同じことやってると飽きちゃうんだろうな。きたろうさんなんかひとつの公演だって初日で飽きちゃうんだから。
―シティボーイズは作家たちにも影響を与えていますよね。
大竹:時代を乗り越えようとする作家たちが、俺たちを「こいつらなら使えるんじゃないの?」って思ってくれるようなことをしてきたからね。そう思ってくれる作家たちとの共同作業がなかったら、全然違うグループになってた可能性は高い。
きたろう:作家を育てたっていう自負はあるよね。
大竹:そうか?
斉木:コントの世界にいる人たちは、素晴らしい才能を持った作家たちのことに気付いてなかったんだよ。そういう人たちとうまく合体できたことは大きい。時代を読んでる人たちとめぐりあえたと思うね。今回の前田くんなんか典型的だと思う。
きたろう:こっちから見つけるというか、寄って来てくれるんだよね、作家が。
斉木:面白いことをずっと続けてるから寄ってきてくれたんだと思う。ずっとやってなきゃだめだった。36年やってきたからね。続けてきたからこそ、だと思うよ。
一流クリエイターからリスペクトを受けるシティボーイズ。16年ぶりに三人だけで芝居に挑む
そう、彼らの周りには常に一流のクリエイターがいた。三木聡、細川徹、天久聖一といった作家が脚本を書き、電気グルーヴや小西康陽やスチャダラパーのSHINCOや高田蓮が音楽を担当。中村有志、ピエール瀧、YOU、五月女ケイ子など、ゲスト出演者も豪華で、多くの実力派が三人の脇を固めてきたのも特筆すべきだろう。だが、今回DVD化される公演は、三人だけで行われた。これはなぜだろう?
きたろう:ファイナルだから、最後はやっぱり三人でやりたいって言ったら、二人とも頑張ってやるよって言ってくれたから。
斉木:大変だったけどね。
きたろう:でも、やってよかった。三人で成り立つことが認識できただけでものすごく嬉しい。
斉木:三人だとね、会話が密なんですよ。三人しかいないという前提のもとに作られた本の方が、会話が妙で面白い。
大竹:それ、今まで参加してくれたゲストに失礼じゃないか。

『シティボーイズ ファイナル part.1「燃えるゴミ」』より
斉木:シティボーイズのコアなファンは「三人でやれ」って言うんですよ。
大竹:でも、三人だと大変だったじゃん。
斉木:大変だったよ。本番中にタバコ1本も吸えないからね。公演中に5分くらいは休憩がとれると思っていたら、出ずっぱりだったから。そんなこと初めてだった。ゲストがいると、自分の休憩が10分くらいあるのが楽しみなのに。
きたろう:すごい楽しみだよね。
斉木:途中休憩は得した気持ちになる。
観客はまだまだコントを見たい。しかし、なぜ三人は終わりを見据えているのか?
今回のタイトル、「ファイナル」と銘打っているものの、「part1」と謳っているのが気になるところ。part1ということはpart2もあるのか? とうがちたくなるのだが、彼らは「同時代性のない表現には興味がない。だから歳をとった俺らはもう終わりなんだ」と言う。ファンからすると、歳を重ねたらこその円熟味というものもあるのではないか? と思ってしまうのだが、それは否定されてしまった。
―コントをやる上で、歳を重ねたことがプラスに作用する面もあるのではないでしょうか?
きたろう:ないね。
斉木:あまりない。
大竹:歳とったらだめだよ。コメディアンだからさ。役者さんなら歳とってよくなってくる人もいるだろうけど。あと、ボケはいいけど俺みたいなツッコミはねえ。キレだから、ツッコミは。間をひとつ間違ったらおしまいなんだよ。若い時の方がいい加減でもなんとかなった。
―衰えてもやる姿をお客さんに見せることは何かしら意義があると思いませんか?
大竹:そこがわからないところで……。コメディアンは時代と添い寝するものだから、ある時代とともに終わっていくのが当たり前でさ。自分が時代とずれてきてるんじゃないかっていう恐怖がすごいあるわけね。同じツッコミでも間がワンテンポ遅れたら、ああもうだめなんじゃないかって思っちゃう。だからこそ、余計に今回の最後の舞台は愛おしかった。もうあとがないのが分かってるからね。前は「このセリフは適当でも乗り切れるだろう」くらいに思ってたところもあったけど、近頃は一つひとつのセリフをああでもないこうでもないって頭の中でひねってみたり、色々なことしちゃったね。終りが近いせいか、追い詰められながらも楽しめたというか。要するに、まだ許されるだろうっていうギリギリのところでやってたから。
―「ファイナルpart.1」となっていますが、「part.2」はあるのでしょうか?
大竹:うーん……70才とか80才になって、すごい芝居ができるという希望があれば別だけど、ただ衰えていく姿を晒すだけじゃ老害だろうっていう気持ちが強いよね。
斉木:笑いは客観的視点を持っていないと表現できないと思うけど、同時に今という時代を切り取る感性が必要ですからね。
きたろう:かっこいい時にやめたいっていうのはどうしてもあるよね。もっと観たいという人もいるけど、老いて情けない姿を見てお客さんが喜ぶとはあまり思えない。
斉木:歳とった役者で、すごい人いるけどね。
きたろう:だから役者は違う。
斉木:役者はいいのか。
きたろう:そう。別に役者やめるって一言も言ってないから。
大竹:役者とコメディアンは違うからな。役者は日常を晒さずに生きようと決めればそれが出来るけど、コメディアンは無理。時代の中で生きていくものだからさ。
作・演出を担当した前田司郎による、シティボーイズの細かい分析
三人が同時代性を追求し続けていることは、『シティボーイズ ファイナルpart.1「燃えるゴミ」』の鮮度の高さとキレの良さを見ればはっきりと分かる。そして、その大きな要因と言えるのが、劇作家で小説家の前田司郎を作・演出に起用したことだろう。前田は五反田生まれ五反田育ちで、現在も五反田に劇団の本拠地を構える生粋の東京っ子だが、そうした彼の出自はシティボーイズの洒脱でドライな芸風と見事にマッチしている。
―前田司郎さんに脚本・演出をお願いすることになった経緯は?
きたろう:前田くんの本を読んだりお芝居を観たりしていて、この人は笑いが書けると思ってたの。特に『岸田戯曲賞』を獲った『生きてるものはいないのか』、あれがおかしかったの、俺にとってはめちゃくちゃ。で、たまたま飲み屋で話す機会があって誘ったら、ぜひやりたいって言ってくれて。彼は最初からやれるって自信があったんじゃないかな?
大竹:たまたま会ったの?
きたろう:打ち上げでね。たまたま隣りに座ってたから、「シティボーイズ興味ある?」って聞いたら、「あります」って。
大竹:俺らのこと、ちょっとは知ってたの?
きたろう:めちゃくちゃ知ってるんだよ、実は。忙しい人なのに、「スケジュール空いてる?」って聞いたら「全然空いてます」って即答してくれちゃって。
大竹:忙しいだろう。稽古中に『向田邦子賞』(東京ニュース通信社が主催する脚本賞。連続ドラマ『徒歩7分』で受賞)まで獲っちゃったもんな。
―前田さんはみなさんの雑談を聞いて、それをヒントに脚本を書かれたそうですね。
きたろう:雑談というか、各々の人間性を見てたんだよね。
大竹:ずっと見てたね。脚本もそれぞれのキャラ通りになっていて、よくこんなに観察していたなって思った。
斉木:俺たちがしゃべっている会話の内容を元に脚本を書くのかなと思ったら、そうじゃないのね。むしろ見ていたのは、それぞれの個性。どういうしゃべり方をしていて、どういう癖があるか。そういうところずっと見ていたみたい。
きたろう:稽古場で俺と大竹がべらべらしゃべっていて、斉木が黙っているとか、そういう関係性を見てたんだよね。

『シティボーイズ ファイナル part.1「燃えるゴミ」』より
―台本を読んでみて、自分たちのしゃべり方の癖にあらためて気付いたこともありますか?
きたろう:倒置法をよく使うんだよ、前田くんは。俺はこういうしゃべり方をしてないぞって最初は思ってたんだけど、実は意外とそういうしゃべり方してるのね。
大竹:みんなで蕎麦食いに行った時に、「普段からこういうしゃべり方してないぞ、俺たちは」って言っちゃったの、きたろうが。
きたろう:「俺たち」が後ろに行っちゃうしゃべり方をするんだよね、俺は。
大竹:舞台とかテレビの台本は倒置法になってないけど、普段しゃべってる時は割とみんな倒置法を使ってるんだよ。前田さんはそういうことを分かっていた。
作家が変わっても「俺たちがやるとみんな同じになる」
先ほど、シティボーイズのコントは既成の演劇の否定から始まった、と述べたが、DVDを見ると、実は演劇的要素もちらほらと垣間見える。例えば三人は、しゃべっていない時でも相手の発話にちゃんと反応している。観客はしゃべっている人間を注視しがちだから、サボろうと思えばいくらでもサボれるのだろうが、皆、その場に相応しい反応をして笑いを倍加させているのだ。こじつけかもしれないが、これは彼らが演劇からスタートしたことと関係あるのではないか。そうした彼らの役者っぽさは、前田の脚本と相性がよかったのだと思う。
―前田さんのセンスは、これまで脚本を書いてきた三木聡さんや宮沢章夫さんや細川徹さんと比べてだいぶ違いを感じましたか?
斉木:もちろん違うね。
きたろう:違うけど、俺たちがやるとみんな同じになるね。
大竹:例えば、細川が書いた本はアドリブでぶっ壊すのが平気なのね。アドリブを言って笑いを取ることができた。でも、前田さんの本はそういうことが通用しなかったね。アドリブがきかないコントというか、つまり演劇チックという意味だよね。コントチックだったらアドリブの入る余地が残ってるけど、演劇寄りだとそうはいかない。
きたろう:よく書いてるんだよ、一言一言。
斉木:そう。だから、俺も本番中に「そのせりふはこういう風に言ってください」って指摘されたことがあって。語尾のトーンが違っていたみたいなんだよね。で、指摘された通りに言い直したら途端にウケたもんね。
「俺たちがやるとみんな同じになる」というきたろうの発言は、一見謙遜した言葉のようでいて実に的を射ている。それじゃあ誰と組んでも同じなのか? という声が聞こえてきそうだが、それだけ三人が集った時の空気は独特なのだ。インタビューでも、三人の当意即妙のやりとりがまるでコントのように聞こえて驚いた。その場でエチュード(即興の芝居)を見ているようなのだ。作家やゲスト陣は入れ替わっても、三人がいれば揺ぎないものができる。そうした自信と自負が彼らにはあったのではないか。だからこそここまで続いたのだ、とも。ファイナルということで、これで終わりかと惜しむ声もあるが、1989年から毎年、ゴールデンウィークに決まって公演を続けてきたこと自体驚異的だ。その理由を最後に述べてくれた。
―これで終わりかと惜しむ声もありますが、逆にここまで続けてきたことがすごいと思います。
斉木:それは、新しいことを常にやってきたからだね。惰性やマンネリを感じた瞬間に、もう止めてるよ。
きたろう:自分たちが面白いと思うことをやる、というのが第一だったからね。客がそれを面白いと思うかは二の次でさ。要するに学生のようなモチベーションを持ち続けたことが続いた理由だと思うね。
- リリース情報
-

- 『シティボーイズ ファイナル part.1「燃えるゴミ」』(DVD)
-
2015年10月28日(水)発売
価格:5,076円(税込)
COBM-6807[収録内容]
・舞台本編映像
・舞台特別映像
・シティボーイズスペシャルインタビュー
- プロフィール
-
- シティボーイズ
-
大竹まこと、きたろう、斉木しげるによるコントユニット。1979年結成。1981年から『お笑いスター誕生!!』に出場し、10週勝ち抜きでグランプリを獲得する。1980年代から定期的にコントを上演してきた。定型に陥ることを周到に避け、コントに新鮮な風を送り続けてきた彼ら。まさに、コントをアートにまで高めたといっても過言ではない。
- フィードバック 23
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-