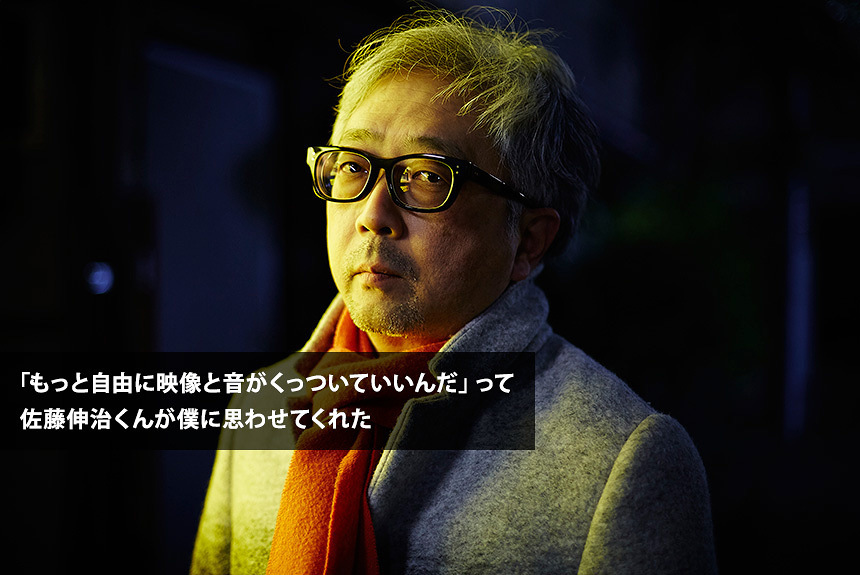スペースシャワーTVが開催する、音楽とカルチャーの祭典『TOKYO MUSIC ODYSSEY 2017』。そのプログラムのひとつとして『MOVIE CURATION~特上音響上映会~』が、3月6日に開催される。渋谷WWWを会場に、『Fishmans in SPACE SHOWER TV』『Cornelius performing Fantasma USツアー』『The Documentary DEV LARGE/D.L』という3作品が上映され、臨場感のある音響によって、3組のアーティストの魅力はもちろん、それぞれが活躍した1990年代の雰囲気を体験することができるだろう。
イベントの開催を記念して、“ナイトクルージング”以降のフィッシュマンズのすべてのミュージックビデオやライブ映像を手掛け、映画『THE LONG SEASON REVUE』では監督も務めるなど、バンドとなじみの深い映像ディレクター・川村ケンスケにインタビューを実施。今も音楽ファンを魅了し続けるフィッシュマンズの秘話に加え、90年代という時代が持っていた熱量、そしてこれからの作り手へのメッセージまで、幅広く語ってもらった。
「もっと自由に映像と音がくっついていいんだ」っていうのは、佐藤伸治くんが僕に思わせてくれたことだった。
―川村さんとフィッシュマンズの関わりは、どのようにして始まったのでしょうか?
川村:最初に仕事をしたのは“ナイトクルージング”(1995年)のビデオです。当時はドラマの主題歌(1992年に発表された“100ミリちょっとの”が、フジテレビ系列『90日間トテナム・パブ』に起用されていた)で存在を知ってるくらいだったんだけど、レコード会社のポリドールの宣伝の人から「川村ちゃんが向いてると思う」って言われて。
ただ、「佐藤伸治は相当気難しい人です」みたいなことを言われたし、“ひこうき”(1991年、デビューシングル)のビデオは最初全然気に入らなくて、何度もやり直したみたいな都市伝説めいたものも聞いていました(笑)。でも、「とりあえず、音ください」って言って、“ナイトクルージング”を聴いたら衝撃を受けて。
―どんな部分に衝撃を受けたのでしょう?
川村:そのあたり、日本では渋谷系が流行っていて、海外だとBECKとか、デジロックとかも出てきていたなかで、「当時の周りのミュージシャンとは違う、こんなに変わった音楽が日本でもできるんだ」って。すごく感動して、何回も何回も聴いた記憶があります。
普段、ビデオを撮るにあたっては、そんなに聴き込まないほうで。撮る前に聴いた第1位が“ナイトクルージング”。ちなみに、第2位は“美しく燃える森“(東京スカパラダイスオーケストラ)でした。そういえば当時って、CDが発売されてからビデオを作ることも珍しくなかったんですよ。今だと考えられないでしょう?
―YouTubeで先行公開されたり、もしくはCDの発売日前後に販促として公開されることが普通ですもんね。
川村:今は曲ができてないのにビデオを作らされることもあるからね(笑)。某ガールズグループとか、「デモ音源でビデオを作れ」みたいなことがあるわけですよ。むちゃくちゃだなって思うんだけど、90年代はある意味もっともっとむちゃくちゃで、「CD出てからでもいい」という考えだったんです。アグレッシブでしたね。
―“ナイトクルージング”のビデオを撮ることになって、実際にメンバーと会ったときはどんな印象でしたか?
川村:あんまり覚えてないんですけど……前もって「どんなものを撮ろうか」みたいな話は全然していない気がします。“ガッツだぜ!!”(1995年発表、ウルフルズの楽曲)みたいなビデオが注目されて、ちゃんと打ち合わせをして作られるビデオが増えたタイミングだった気がするんですけど、その頃もそうだったし、未だに僕は、「そんなに『ちゃんと』する必要ない」と思っているんです。
―ミュージックビデオは、撮影の前段階で、企画上作り込む必要はないと。
川村:なんの確信もなかったけど、特に“ナイトクルージング”は「この部分にはこの画」みたいな感じにしなくてもいいと思って。とはいえ、当時は音楽ビデオを作り始めてまだ3年目くらいで不安もあって、しかも曲も長かったから、とにかくいろいろなシーンを撮りました。回るジャングルジムだったり、ボートに乗ったり、レインボーブリッジの下で歌ってもらったり、1日半使ってアナログのビデオの30分テープで10本分くらい撮ったかな。
―結果的には、トランポリンを使ったシーンがメインで使われていますよね。
川村:唯一「トランポリンがいいかもね」っていう話は事前にしてたかも。ただ、仮編集の段階では、トランポリンのシーンはもうちょっと少なくて、いろんな画を使っていたんです。でも、「あれ(トランポリン)だけでいいんじゃない?」って、佐藤くんから話が出て。で、全部編集やり直したんですよ。「確かに、これでいいかも」って思えたことが、衝撃だったんです。
―というと?
川村:「こういうことでいいんじゃないか」って薄々思ってはいたんですけど、ホントに「それだけでいい」って言ってくれた人はいなかったんですよね。つまり、ポップスは基本的に「イントロ、Aメロ、Bメロ、サビ」みたいな構成があるから、音楽ビデオもそれに合ってないといけないと思ってたけど、“ナイトクルージング”はそういう決まった構成の曲じゃないから、そんなにちゃんと合わせる必要がない。
その背景としては、BOREDOMSがいたり、ダムタイプがいたりもあったんだけど、「もっと自由に映像と音がくっついていいんだ」っていうのは、佐藤くんが僕に思わせてくれたことだったんです。彼自身が音楽のことをそう捉えてたということだと思います。
―なるほど。
川村:さらに言うと、あのビデオは『THREE BIRDS & MORE FEELINGS』(ミュージックビデオ集。1999年にVHSが発売、2000年にDVDが発売)でDVDになったときに、さらに編集し直して、ほとんどトランポリンのみの映像になってるんです。当時はリミックスが流行ってたので、「ビデオでもリミックスだ」みたいな感じで作ったんですけど、結局そのバージョンが一番完成形に近いと思ってるんですよね。
「前はこうだった。では今はこうなってる。それはなぜなのか?」ということを、もっと考えなきゃいけない。
―“ナイトクルージング”以降、川村さんはずっとフィッシュマンズのビデオを手掛けられていますが、どのビデオが印象深いですか?
川村:“MAGIC LOVE”(1997年)は『COUNT DOWN TV』(TBS系列)のエンディングテーマに使われたこともあって、最初ポリドールの人から「TBSのスタッフに撮らせたいんです」って言われたんです。そのときは「わかりました」って言ったんですけど、だんだん腹立ってきて(笑)。
その前に撮った“SEASON”(1996年)はいいビデオができたと思って、自分的には達成感もあったのに、その次のビデオでそんなこと言われてホント頭にきて……なにかやってやりたいと思ったから、勝手に撮ることにしたんです。
―勝手に、ですか?(笑)
川村:レコード屋の店頭で流すコメント動画を撮る機会があったときに、「今から“MAGIC LOVE”のビデオを撮りに行きます」って言って。メンバーは「え?」って感じだったけど、2~3時間でバーッと撮って。で、これは今でもよく覚えてるんだけど、まあ、もう時効ということで……たしか小野正利さん……メルダックというレコード会社のアーティストの仕事で、編集室で彼の音楽ビデオを作った後に、朝までかかって“MAGIC LOVE”を「勝手に」編集したんです。
初めの気持ち通り、あまりにも悔しかったから、最後に手書きのポリドールのマークを入れたりしてね(笑)。それをポリドールに持っていって、「どちらを使うかはあなた次第です」って渡したら、結局僕が作ったものが正式なビデオになって、『THREE BIRDS & MORE FEELINGS』にも収録されているんですよ。
―すごい話ですね……。
川村:ただ結果的に、TBSスタッフが作ったバージョンは『COUNT DOWN TV』だけで流れていたから、「幻のバージョン」みたいになって、価値が上がっちゃったんだよね。ホントは逆になる予定だったんだけど、そこは読み違えたなって(笑)。
まあ、当時はそのくらいむちゃくちゃなこともありました。90年代は音楽ビデオが一番自由な表現ができるメディアだったと思っていて、僕らより前の世代はもっと自由だったと思う。たとえば、フリッパーズ・ギターのビデオなんて、ホント適当だけど、それがかっこよかったんですよね。なにかを狙って作るんじゃなくて、「こういうのを作りたいから作る」っていう感じがあったんじゃないかな。
―YouTubeの時代になってからは、マーケティング的な目線で作られた、ある種定型化されたビデオも増えましたもんね。
川村:そこには抵抗しないといけないんじゃないかと思います。もちろん、「昔は自由でよかった」って話ではなくてね。ただ、そういう時代があったのは事実だし、今と昔を比べることは必要かもしれない。それはいい悪いの話でもないし、ノスタルジーでもなく、「前はこうだった。では今はこうなってる。それはなぜなのか?」「なにが変わって、なにが変わっていないのか?」ということを、もっと考えなきゃいけないんじゃないかと思いますね。
「変わった!」ってことがわかるには、「変わる前のこと」、簡単にいうと「過去」のことを知って、その上で「今」のことを感じる必要があるはず。その際に、「過去」を知ることを、一般的には「勉強」と呼ぶのだろうと思います。だからこそ、映像を作っていくためには「勉強」をしなければいけなくて。
あらゆる芸術表現や文学やなんかは、そういうふうであると思いませんか? そういう意味で、最近「おすすめ音楽ビデオ」っていうブログも書き続けていて、そこで音楽ビデオのことをいろいろ書いています。弊社社員には「必読!」と言っているんです。うざいっすね(笑)。
自分が思う「抵抗」をフィッシュマンズの音楽に乗せて実現しようとしていたのかもしれない。
―今おっしゃった言葉を使うと、90年代の川村さんとフィッシュマンズはある種の時代に対する「抵抗」の感覚を共有していたと言えるのでしょうか?
川村:僕からすると、フィッシュマンズを利用してというか、自分が思う「抵抗」をフィッシュマンズの音楽に乗せて実現しようとしていたのかもしれない。一般的には、それを「実験」と言うのかもしれないけどね。
『MOVIE CURATION~特上音響上映会~』で上映される『Fishmans in SPACE SHOWER TV』のなかには、『LONG SEASON THE VIDEO~Quiet Version~』というのが入ってるんですけど、あれはスペシャから番組を作ってくれって言われたときに、「風景だけでどこまで映像を成立させられるか」をやったものでした。そうしたら、当時フィッシュマンズのBBSに「あれは映像の専門学校の課題みたいなもんだ」って書いた人がいて、僕はそんなふうに思ってなかったから、「どこがそうなのか言ってくれ」って書いて。偉そうに言われるのが嫌だったんだろうね(笑)。
―(笑)。
川村:なんでそう書かれたのかを考えると、途中の話にも通じるんだけど、その人は「イントロ・Aメロ・Bメロ・サビ」が音楽ビデオだって思ってたんだと思う。でも、当時の僕は「そんなのはクソだ」と思ってたし、そもそもアーティストがあんまり映ってないビデオが好きだったから。その感じがフィッシュマンズの音にも合うと思ったんです。
当時『Qucik Japan』のインタビューで、佐藤くんかzAk(フィッシュマンズのライブ音響、レコーディングエンジニアを務める)かが、「ゼロである音楽ってなんだろう?」みたいな話をしていて。歌詞でも言ってるように、なにもないんだと。「じゃあ、なにもない映像っていうのもあるのかもしれない」と思ったんですよね。それを当時の表現のコード、規範のなかでやろうとしたんだと思う。極力意味も意図もないものができないかって、そういう実験だったのかもしれない。
―音楽はときにメッセージ性や自意識の部分が取り沙汰され過ぎるけど、音楽は音楽であるだけでいいと言うか、「なにもない」ということに価値があるんだっていう、そういう提案でもあったというか。その意味では、川村さんとフィッシュマンズによるスペシャのステーションID(2001年)がすごく印象に残っていて、あれも「なにもない」映像でしたよね。
川村:「渋谷のハチ公前で待ち合わせしよう」って言ったときに、僕の頭のなかのハチ公前って、誰も人がいないんですよ。つまり、抽象化されたハチ公前が頭のなかにある。地図を見てるみたいな感じというか、記号としてその場所がある。そういう街を映像化したら、フィッシュマンズの音に合うんじゃないかって、いつも一緒に仕事をしていたカメラマンの方と、よく話をしていたりして。
それで実際に人がいない場所だったり、いたけど消しちゃったり、人の気配がありそうなんだけどそこには誰もいない、といった映像を1分くらいにまとめたんです。「なにもない」の理想に近づけると、ああなったという感じですね。
今でも一部のアーティストはお金かけて作ってるけど、僕からすると「もっと違うやり方あるんじゃないか」って思うことが多いかな。
―『MOVIE CURATION ~特上音響上映会~』はフィッシュマンズ以外に、CORNELIUSとDEV LARGEの作品が上映されるので、1990年代後半の雰囲気が味わえるイベントになっています。近年は若い人の間でも、90年代リバイバル的な空気があるように思うのですが、川村さんの思う90年代ならではの熱量というのは、どんな部分にあったと思われますか?
川村:音楽ビデオが一番ピークを迎えた時代が90年代後半だったんじゃないかとは思います。お金もあったし、時間もかけられた。今の人たちがその時代に憧れているとしたら、そのちょっと浮かれた感じの熱っていうものに憧れるのかもしれないですよね。
変なものも存在できたというか、傍流が傍流にならずに、メインストリームに投げ入れられた。クオリティーさえ高ければ、マーケティングを無視してもちゃんと注目される、そういう時代だったんじゃないかな。
だって、『FANTASMA』(1997年発売、CORNELIUSのアルバム)がマーケティングを基に作られたとは思えないでしょ? 「誰かに向けて」ってこともなかっただろうし……ディズニーに向けてはいたかもしれないけど(笑)、ディズニーに来る人に向けて作ってたわけじゃないよね。なおかつ、それが個人のレーベルで成り立っていた。そういうことに対して、今の人たちが憧れるっていうのはあるのかもね。

『MOVIE CURATION ~特上音響上映会~』(サイトを見る)
―確かに、そうかもしれないです。
川村:僕がCMをやり始めたのも90年代の終わりで、お金とクリエイティブが一番いいバランスだったのかもしれない。バブル期は、お金はあったけど、テクノロジーは昔のままだった。でも、90年代はお金もまだあったし、デジタル時代の始まりでもあったんです。
たとえば、80年代にいすゞのジェミニという車のCMがあって、2台のジェミニがギリギリの距離でダンスするように走ったりジャンプしたりするんだけど、それは合成じゃなくて、人力なわけ。でも、90年代になるとそれが合成でできるようになって、さらには音楽ビデオですら「アメリカに行って色調整しようか」みたいな。あ、これは“ピンクスパイダー”(1998年発表、hide with Spread Beaverの楽曲)のことですが(笑)、簡単に言ってしまうと「バブル」な感じ……そういう時代だったんですよね。
―今ではありえない話ですね。
川村:でも、今でも一部のアーティストはお金かけて作っててさ、そのなかでいいものもあるんだけど、僕からすると「もっと違うやり方あるんじゃないか」って思うことが多いかな。「それ一回やったじゃん」っていうものだったり、今やる必要はないんじゃないかって思っちゃうものだったりね。
今って、ある意味YouTuberが音楽ビデオを超えちゃってると思うんですよ。
―過去の焼き直しではなく、今だからこそできる表現をもっと見たい?
川村:そう思うんだよね。「じゃあ、どんな感覚の映像がいいのか」というと、僕はやっぱり「なにもない映像ってなんだろう?」という話に戻ってきて、こればっかりはもうテクノロジーの問題ではなくて、「考え方」の問題だからさ。
で、これを小難しい言葉でいうと、「思想のある映像かどうか」という話になる。今、思想がある映像がどれだけあるのかって考えると、あんまりないような気がするんですよ。
―川村さんの考える「思想のある映像」を、具体的に挙げていただくことはできますか?
川村:これは映像に限った話ではなくて、それこそまた小山田くんの話をすると、5.1chのサラウンドでCDを作るときに、音の配置ですごく悩んだ結果、バスドラをリスナーの位置に持ってきた。僕はこういう発想自体が「思想」だと思うのね。新しいフォーマットが出てきたときに、それに見合った最適なやり方を考えるっていうかさ。
今の映像はそれができてなくて、だからみんなアナログのレンズとかに走ってるんだと思う。そうじゃなくて、もっと考えてやれることがあるんじゃないかな。それをやるのは僕ではなくて、もっと今のテクノロジーにどっぷり浸かってる下の世代であるはずで。なんでそれをやらないのかっていうのは、「なにもない映像」を標榜する僕としては、すごく思うかな。
―YouTubeだったらYouTubeだからこそできる、思想のある表現方法がもっとあるのではないかと。
川村:今って、ある意味YouTuberが音楽ビデオを超えちゃってると思うんですよ。YouTuberが「この曲いい」って言った方が早いんじゃないかって思っちゃう。
だって、はじめしゃちょーとかは1日200万回とか再生されるわけでしょ? そんな音楽ビデオごくわずかだし、しかも彼らはリビングルームでパッとやって200万回だったりする。今、音楽ビデオはそこと同じフィールドにあるわけだから、やっぱり昔と同じことをしてる場合ではなくて、頭使って違うことを考えないと。
―その意味では、やはりアーティストと映像の作り手との関係性が重要で、川村さんとフィッシュマンズのように、相互作用から思想のある映像が生まれるのかなと思います。
川村:音楽と映像が対等だからこそ、お互いに見合う音楽であり映像を作らないといけなくて、たぶん今はそれができてないから、YouTuberに負けちゃってる。それはすごい悔しいなって思うんだよね……まあ、これが一般的に言う、愚痴ってやつですけど(笑)。
―いやいや、これから映像作家を志す人はもちろん、なにかを表現したいと考えている人に向けてのメッセージになったと思います。
川村:そういうふうに思ってもらえると嬉しいですね。さっきも言ったように、自分は自分で今のやり方をやろうと思って頑張ってるんだけど、やっぱり若い人がやるべきだと思うから。今はもうバンドをやるのにギターが弾ける必要ないし、映像作るのにカメラと三脚持って朝早く集合しなくてもいいわけだからさ、After Effects(映像のデジタル合成やモーショングラフィックスなどを制作できるソフト)とか使えば(笑)。どんな形であれ、やれることがあるんじゃないかって思うんだよね。
- イベント情報
-
- 『MOVIE CURATION ~特上音響上映会~』
-
2017年3月6日(月)
会場:東京都 渋谷 WWW『Fishmans in SPACE SHOWER TV』
上映+トークショー
トークショー出演:
川村ケンスケ
角舘健悟(Yogee New Waves)『「Cornelius performing Fantasma USツアー」密着ドキュメンタリー・完全版』
上映+トークショー
トークショー出演:
堀江博久
あらきゆうこ『「The Documentary DEV LARGE/D.L」SPECIAL EDITION』
上映+トークショー
トークショー出演:
CQ(BUDDHA BRAND)
GOCCI(LUNCH TIME SPEAX)
GO(FLICK)
ダースレイダー料金:各公演 1,800円(ドリンク別)
※毎回入れ替え制
-

- 『TOKYO MUSIC ODYSSEY 2017』
-
『TOKYO MUSIC ODYSSEY』とは、「都市と音楽の未来」をテーマに、東京から発信する音楽とカルチャーの祭典です。素晴らしい音楽と文化の発信、新しい才能の発掘、人々の交流を通して、私たちの心を揺らし、人生を豊かにしてくれるアーティスト、クリエイターが輝く未来を目指します。2017年は3月2日(木)~8日(水)の一週間にわたり、様々な企画を展開。
- プロフィール
-
- 川村ケンスケ (かわむら けんすけ)
-
1965年生。東京外国語大学外国語学部英米語学科卒。CM、PV、ライブ映像など数多くの映像作品を手掛ける。初演出のCMは、サントリーリザーブ・シェリー樽仕上げ(出演:木村拓哉)のCM。以降、100本以上のCMを演出。MVの主な作品には、サザンオールスターズ、フィッシュマンズ、嵐、倖田來未、安室奈美恵、ゲスの極み乙女。、GLIM SPANKYなど多数。インディーズ音楽支援サイト『kampsite』のディレクションも手掛ける。
- フィードバック 3
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-