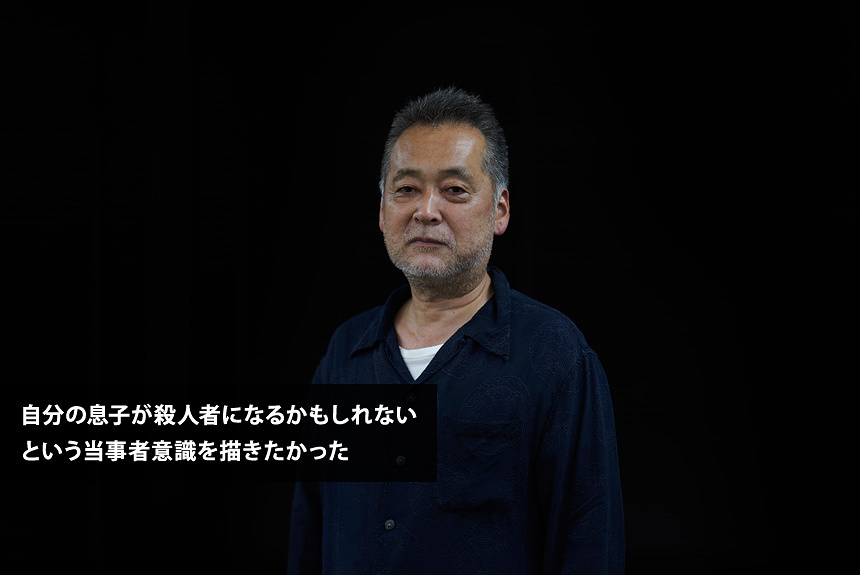映画『64 -ロクヨン-』など知られる監督・瀬々敬久が2010年に生み出した、全9章合計4時間38分という巨編映画『ヘヴンズ ストーリー』。その後、『ベルリン映画祭』で「国際批評家連盟賞」と「NETPAC賞(最優秀アジア映画賞)」を受賞したのをはじめ、国内外の映画祭などで高い評価を受けつつも、今日に至るまでソフト化されていなかった本作が、公開から7年の歳月を経た今、遂にパッケージ化される。
1990年代に世間を騒がせたいくつかの事件をモチーフに、「21世紀の『罪と罰』」とも称される、壮大かつ密度の濃い人間模様を描き出したこの映画が、公開当時の世の中にもたらせたインパクトとは、どんなものだったのだろうか。そして、「世界が憎しみで壊れてしまう前に。」というキャッチコピーをはじめ、今の時代においても、いまだ強烈なインパクトを放ち続けている本作の「凄み」とは、果たしてどこからきているのだろうか。製作当時の心境を振り返ってもらいながら、瀬々敬久監督自身に、本作が持つ意味と効力ついて、改めて語ってもらった。
この4時間38分という時間を「体験する」ことが、一番この映画らしいなって思っていたので。
―7年の歳月を経て、映画『ヘヴンズ ストーリー』が、遂にパッケージ化されます。まずは、公開当時の様子から、現在に至るまでの経緯を振り返っていただけますか?
瀬々:もともとこの映画は、東京渋谷のユーロスペースで公開したのですが、初日は満員にならなかったり、興行としては思った以上に芳しくなかったんですよ。で、そのあと連休があったんですけど、そこで初めて満員になった。ユーロの支配人も、これはもう興行者冥利に尽きると言ってくださって……「初日に満員じゃなくて、途中で満員になったのは、自分も初めてだ」と。
―まさしく「口コミ」で広がっていったわけですね。
瀬々:そんな中、毎年、新宿K's Cinemaでアンコール上映をやるようになったのですが、リリース記事のためにコメントを書くときに、「当面のあいだ、DVD化の予定はありません。劇場のみの公開です」と書いたんですけど、みんなの頭の中でその「当面のあいだ」っていうのが、いつの間にか抜けて、DVDにはしない、という言葉が一人歩きしたところもあります。
―ああ、これはもう、DVD化しないんだと、勝手に解釈してしまうというか。
瀬々:そうなると、なかなかDVD化もできないですよね。みんなが、もうDVD化はしないと思って劇場に駆けつけてくれる中、「いや、そのうちDVD化するよ」とは、やっぱり言えないですから(笑)。
―まあ、そうですよね(笑)。
瀬々:多少冗談めかして話しましたけど、そういう理由がまずひとつあったのと、あとはやっぱり、この映画は非常に長い映画なので、家で見るのにはあまり向いていない。やっぱりまずは映画館という場所で、みんなと一緒にこの4時間38分という時間を「体験する」ことが、一番この映画らしいと思っていました。そういう意味で、映画館の上映というものにこだわってきたというのは、確かにあったわけです。
―なるほど。それがなぜ今になって、パッケージ化しようと思われたのでしょう?
瀬々:今って、ネット配信の時代になってきているじゃないですか。特に、この1~2年の勢いってすごいと思うんです。配信で映像を見ることが主流になりつつあるし、レンタルDVD屋さんはちょっと厳しい状況になりつつある。映画産業としても大きな変わり目に来てると思われます。
そういう中で、映画をパッケージとして所有する時代はもう終わってしまうんじゃないかという危惧もあって、パッケージ化することにしました。この『ヘヴンズ スト―リー』という映画が、モノとして個人の方々に所有していただくのは、ひょっとすると今が最後のチャンスかなと。

『ヘヴンズ ストーリー』ジャケット(Amazonで見る)
次の撮影ではこう変化させようとか、撮りながら脚本を変えていったら、どんどん長くなっていったという(笑)。
―公開当時から、この映画の尺の「長さ」と内容の「濃さ」は話題になっていましたが、そもそもなぜ、そういうものを撮ろうと思ったのでしょう?
瀬々:僕はもともとピンク映画の出身で、1989年に監督になっているんですけど、それから10年ぐらいピンク映画をやって、そのあと一般映画を撮るようになって……それから5年ぐらい経った頃ですよ。この映画を作ろうと思ったのは。
―何かきっかけがあったのでしょうか?
瀬々:ピンク映画というのは、予算は無いけれど、男女のセックスシーンがあれば、あとは自由にできるみたいなところがあったわけです。だから、やっぱり一般映画とピンク映画の自由度は違うし、このままこうやってて良いんだろうかという気持ちもあった。であれば、もう一回自主映画的なものを何かひとつ作ってみようと思ったんです。
―なるほど。この作品は、実際の事件をモチーフにしていますが、それはなぜだったのでしょう?
瀬々:それまでも実際の事件をモチーフにした映画は結構やっていたし、もともとそういうところに興味はあったんですよね。で、それをこの機会にひとつの大きな物語として作れないかと思って。
大きな物語を作りたいんだから、まあ長い映画でもいいだろうと。と言っても、最初の脚本の段階では、大体3時間ぐらいの映画になるはずだったんですけど……。
―最初は、普通の映画よりも、ちょっと長いぐらいのイメージだったんですね。準備期間も時間はかかりましたか?
瀬々:この映画の企画自体は、撮影の数年前から温めていて脚本も用意していました。で、主人公のサト役を演じた寉岡萌希さんに最初に会ったのが、確か彼女が中学二年生ぐらいの頃だった。ただ、こういう映画なので、自分たちでお金を集めようとしても、なかなか集まらないわけです。で、そうやっているうちに、中二、中三、高一と、彼女はどんどん大人になっていって……だから、高二ですね。彼女が、高二の夏に、もうギリギリだと思って、ようやく撮影に入ったという。
―実際の撮影に入るまでのあいだに、そんなに準備期間があったんですね。
瀬々:彼女はもう3年ぐらい待っているわけですよ。で、この時期を取り逃したら、完全に大人の女になってしまって、この映画で描かれているような少女の純粋さが描けないと思ったので、お金も大して集まってなかったけど、撮影に突入したんです(笑)。
で、一年半あった撮影期間を5期ぐらいに分けて撮っていて、1期終えるたびに編集をしながら、次の撮影のことを考えるわけです。このままだと、ちょっと脚本に足りないところがあるから、次の撮影ではこう変化させようとか。そうやって撮りながら脚本を変えていったら、どんどん長くなっていったという(笑)。

『ヘヴンズ ストーリー』場面写真 ©2010ヘヴンズ プロジェクト

『ヘヴンズ ストーリー』場面写真 ©2010ヘヴンズ プロジェクト
―結果的に、4時間38分という尺になったわけですが、商業映画としては、ある意味大胆というか無謀というか……。
瀬々:まあ、そうですよね(笑)。ただ、これはあくまでも自主映画ですから。自分たちで企画して、自分たちでお金を集めて作った映画ですから、すべての責任は、自分たちにあるわけです。そういう意味で、さっきも言ったように、とにかく自由に作りたいっていう欲求があったんでしょうね。
1990年代って、オウムや酒鬼薔薇事件があって、何か時代の鬱屈とした空気感と事件性が、非常に密着した感じがあった。
―先ほど、「実際の事件をモチーフとした映画」という話がありましたが、瀬々監督は現在に至るまで、そういった作品を数多く撮られていますよね?
瀬々:そうですね。それは、もうかなり早い段階からあって……というか、自分が映画を好きになったときから、高校生の時に『青春の殺人者』(1976年、長谷川和彦監督)を見てやられてしまって。これこそ映画だと。そう思っていたところがあるんです。
―監督のピンク映画時代の代表作『黒い下着の女 雷魚』(1997年)も、実在の事件をモデルにしていましたよね。
瀬々:だから、自分にとっては、『ヘヴンズ ストーリー』の前から、そういう実際の事件をモチーフに作るのが映画なんだと刷り込まれていたんですね。でも『雷魚』を作った1990年代って、オウムがあって、酒鬼薔薇の事件があって、神戸の震災があって……何か時代の鬱屈とした空気感と事件性が、非常に密着した感じがあったと思うんです。みんなどこか生きづらそうだったじゃないですか。いきなり不景気になって……空白の10年とか言われていますけど。
―バブルが弾けたあとの10年ですね。
瀬々:そう、バブルが弾けて、もうみんな何をしていいかわからないみたいな。みんなすごく鬱屈として、もう世の中、あんまりいいことないんだろうなって思い始めていたというか。1990年代って、そういう時代だったと思うんです。黒沢清さんの『CURE』(1997年)なんか、まさにそういう時代感みたいなものを、すごく反映していましたよね。
―ああ……わかります。
瀬々:だから、そういう時代背景の中で、ああいった事件が起こってくるということに、何か同時代性は感じていたわけです。自分もその頃はピンク映画を撮っていて、生活するのがやっとだったし、鬱屈としていたところもあって。もちろん、事件そのものにシンパシーは湧かないですけど、何か同時代を生きている感覚はあったわけです。ああ、今の時代を反映している事件だなって。そういう親和性みたいなものを感じていたというか。
ただ、それが2000年以降になると、世の中は割と、金融資本主義とか新自由主義とか、また拝金主義的な時代になっていくわけですよね。そういう中で生きていて、何か違和感があったというか。そういう意味でも、「殺す / 殺される」とか、「被害者 / 加害者」みたいなものも含めて、ものすごいごっつい物語を作って提示してみたいという欲望が生まれてきたのかもしれないですね。

『ヘヴンズ ストーリー』メインビジュアル(公式サイトで見る)
かつては、みんなの希望の証だったような集合住宅が、今は凋落してしまっている。
―この映画は、ロケーションがすごく印象的でした。
瀬々:そう、岩手のほうの鉱山廃墟なんですけど、ここを初めて訪れたときのショックが忘れられずにいて。いつかここで本格的に映画を作りたいと思っていたのは、ひとつ動機としてあったんですよね。
―もう一か所、海辺の集合住宅も、象徴的な場所として繰り返し登場しますよね。
瀬々:あれは、浦賀の「かもめ団地」。ただ、そこは外観撮影だけで、集合住宅の内部や敷地内は、茨城県の高萩市で撮っています。
―いずれも、高度経済成長期に建てられた集合住宅ですよね。
瀬々:そうですね。この映画を作ろうと思ったときに、いろんな団地を見に行ったんですよ。たとえば今、都内で有名なのは、多摩ニュータウンとかですよね。で、この映画の準備期間に多摩ニュータウンに行ってみたら、それこそ老人と子どもしか目につかないわけです。若者の姿が見られないという。
かつては華やかなりしニュータウンが、今はある意味、限界集落みたいになって。何か時代の変化みたいなものを、すごく感じたというか。かつては、みんなの希望の証だったような集合住宅が、今は凋落してしまっているという。そういうものをあちこち見てまわったのは、実際この映画を作る上で、ひとつ大きな影響を与えられたとは思います。
1990年代だったら、廊下ですれ違った青年が殺人者かもしれない恐怖が日常だった。2000年代に入って、自分の息子が殺人者になるかもしれない恐怖に変わった。
―改めて今この映画を見て、監督自身は、どんなことを感じましたか?
瀬々:この映画でやりたかったのは、被害者と加害者の関係性……被害者も個人、加害者も個人であるというか、個人と個人がぶつかり合うことだったんですよね。この映画では、あえて司法や国家の問題を描いていないんですが、そうではなくて、個人対個人という二者のあいだで、どう気持ちを解決していくかを描こうと思ったんです。個人が個人としてどう発言し、どう対応するのか。そこを最終的に問おうと。
ただ、そういうものが、最近は個人が発言しにくい時代になってきましたよね。SNSはもちろんのこと、記者会見とかを見てもそうじゃないですか。
―ある意味、個人であることが非常に難しい時代になっているというか。
瀬々:はい。誤解を招きかねない言い方で申し訳ないのですが、たとえば、かつての秋葉原の通り魔事件とかって、匂いとしてすごく個人として屹立していますよね。変な話、ああいう個人が屹立する犯罪って、最近あまり起こってないような気がして。そういう意味で、何か気持ち悪い時代になっているというか、個人の声が消されてしまうような世の中になっているんじゃないかと思うんです。
―そんな中で『ヘヴンズ ストーリー』は「個人」を撮っている。
瀬々:ひとつの方法論として、その渦中に入って、そこにいる「個人」を撮りたいと思ったんです。だから、僕たち映画を作る人間も、その渦中に入ったような気分でやっていたんですけど、「個人の声」が打ち消されようとしている今、同じような事件を同じような取り組み方で撮れるかっていうと、わからないですよね。時代とかいろんなものが見えてこないのかもしれないし。
―なるほど。
瀬々:それと同時に、この映画は、当事者であるということを、すごく問題にしたいと思ったんですね。自分たちを当事者として描いていくという。例えば、1990年代だったら、アパートの廊下ですれ違った青年が、ひょっとしたら殺人者かもしれないとか、そういう恐怖が日常だった。で、それが2000年代に入って、自分の息子が殺人者になるかもしれない、自分の奥さんが被害者になるかもしれないという恐怖に変わって……それは映画だけではなく、当時の社会って、そんな感じがあったような気がするんですよね。
―この映画を今の人たちに、どんなふうに見てもらいたいですか?
瀬々:まあ、4時間38分ある映画で、こういう内容に慣れていない人にとっては、ちょっときついとは思うんです。けどやっぱり、価値観っていうのはひとつだけではないと思うんですよね。いろんなことが存在していいし、いろんなものがあっていい。自分の趣味や嗜好、意見と違うなと感じることもあるかもしれないけど、そういうものも存在するし、そういうものに触れたときに意外にハマったり。
なので、この長さや内容にへこたれることなく、この世界に触れてみてくださいという感じですかね。この映画には、老若男女、いろんな世代の人が出てくるから、きっと自分に近しい世代の人物を発見することができると思うので……そういう意味では、見ていて楽しいというか、見ていて飽きるということはないと思います(笑)。
- リリース情報
-

- 『ヘヴンズ ストーリー』(Blu-ray)
-
2017年12月6日(水)発売
[封入特典]
価格:6,264円(税込)
PCXP-50532
・特製アウターケース
・60Pスチル写真集ブックレット
[映像特典]
『ヘヴンズ ストーリーの10年』 (瀬々敬久 構成・演出映像作品 / 42分)
-

- 『ヘヴンズ ストーリー』(DVD)
-
2017年12月6日(水)発売
価格:5,184円(税込)
PCBP-53669[封入特典]
・特製アウターケース
・60Pスチル写真集ブックレット
[映像特典]
『ヘヴンズ ストーリーの10年』
(瀬々敬久 構成・演出映像作品 / 42分)
- プロフィール
-
- 瀬々敬久 (ぜぜ たかひさ)
-
1960年生まれの映画監督。京都大学在学中に『ギャングよ 向こうは晴れているか』を自主制作し注目を浴びる。その後「ピンク映画四天王」として日本映画界で独特の存在感を放つ。以後、大規模なメジャー作から社会性を取り入れた作家性溢れるものまで幅広く手がけ、国内外で高く評価されている。『雷魚』(1997)、『HYSTERIC』(2000)、『MOON CHILD』(2003)、『感染列島』(2009)、『アントキノイノチ』(2011)などの劇場映画作品からテレビ、ビデオ作品まで様々な分野で発表。近年は『なりゆきな魂、』(2017)、『8年越しの花嫁』(17年12月16日公開)、また公開待機作に自身の企画の『菊とギロチン-女相撲とアナキスト-』(2018年夏公開)や『友罪』がある。
- フィードバック 2
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-