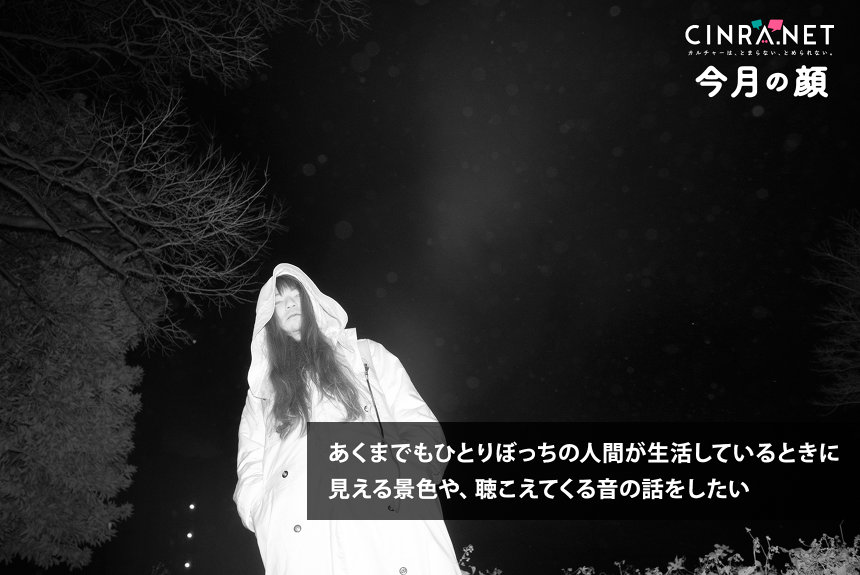2019年9月と10月の『全感覚祭』で何かが変わった。GEZANとその仲間たちによるあの祭りが何を変えたのか、今はまだはっきりとはしていないけれど、あれ以降で都市の風景が一変してしまったように感じる。入場料は投げ銭制、フードフリーを実現した9月の『全感覚祭』大阪編。満身創痍のなか挑んだ千葉・印旛医大前での『全感覚祭』東京編は台風19号の直撃により中止に。だが、その翌日には渋谷各所のライブハウスで『全感覚祭』渋谷編を緊急開催。あの混乱と熱狂の夜、確かに何かが変わったのだ。
その一方で、GEZANの4人は内田直之をレコーディングエンジニアに迎え、密かに新作の制作を進めていた。完成したアルバム『狂(KLUE)』には、ここ2年の混沌と怒りが渦巻いている。バリ島の男声合唱ケチャを思わせるプリミティブなコーラスが多用され、アボリジニの伝統楽器であるディジュリドゥがヘビーな低音を鳴り響かせるその音楽世界には、GEZANが世界に対峙することで掴み取った生々しい感覚が息づいている。
マヒトゥ・ザ・ピーポーはこう歌っている――<前半ではこの世界の破綻の詳細と奮起を、後半では希望という癌について、反抗に対する再定義について>(“狂”)。だが、このアルバムはそうした言葉を凌駕するほどの広大な世界観を持ち、私たちに「何か」を叩きつける。一体それは何なのだろうか。大石始(ライター)による前半、矢島大地(CINRA.NET編集部)による後半と、2回のインタビューによって2020年最初の問題作に迫る。
無菌の部屋みたいなところで「研ぎ澄まされた風のもの」だけを扱っているような今の東京に違和感がある。
―前作『Silence Will Speak』から、ここ2年ほどのGEZANの活動はかなりハードでしたよね。バンド内のテンションはどんな感じだったのでしょうか。
マヒト:自分の生活にすべてが侵食してきちゃってる感じでしたね。モードを切り替えることができないというか。『全感覚祭』に向けてWEB上などで書いてきた言葉も、自分より少し前を走っている誰かの言葉という感覚で。本当だったらもっと綺麗に整理して進めることもできたんだろうけど、そんなに器用じゃなかった。
―台風直撃による中止を受けて渋谷で急遽行われた『全感覚祭'19』(10月12日に開催予定だった『全感覚祭』の中止を受け、急ピッチで渋谷7会場での開催に振り替え。10月13日の深夜に『SHIBUYA全感覚祭 –Human Rebellion−』が行われた)をやってみて、どんなことを感じました?
マヒト:台風という自分たちがコントロールのできないものによって渋谷でやることになるというのも、自分たちらしいなと思いましたね。今後は気候の変化も世界的にどんどん加速していくだろうし、フェスをやる意味も変わってくると思う。夏フェスっていうと雲ひとつない晴天のイメージに直結するかもしれないけど、考えてみると、今まで『全感覚祭』をやってきて晴天だったことって一回もなくて。

GEZAN
2009年、大阪にて結成。自主レーベル「十三月」を主宰する。2018年に『Silence Will Speak』をリリースし、2019年6月には、同作のレコーディングのために訪れたアメリカでのツアーを追ったドキュメンタリー映画『Tribe Called Discord:Documentary of GEZAN』が公開された。2019年10月に開催予定だった主宰フェス『全感覚祭』東京編は台風直撃の影響で中止となったが、中止発表から3日というスピードで渋谷での開催に振り替えられた。そして、1月29日に『狂(KLUE)』をリリースする。
マヒト:そういうことも引き受けていくのが2020年のあり方なんじゃないかなって気がしてるんです。人ができることの限界もあるけど、人間の創造力も捨てたもんじゃない。『全感覚祭』をやってみて、そういうことを実感しましたね。それに、普段から渋谷にはいますけど、今はより渋谷を自分の街って呼べるような景色に変わった感覚があって。それは自分でも驚きなんですけど、そういう意味で、前と違うかもしれないですね。
―以前CINRA.NETのインタビューでマヒトさんは「政治とか活動家みたいな人って『構造』を変えることはできるんだけど、芸術や音楽は、そういう問題を体験に変えられる可能性を持っている」と話してましたよね(参考記事:GEZANマヒトが我々に問う。新しい世界の入り口で社会を見つめる)。『全感覚祭』は各地の農家の協力のもとフードフリーを実現したわけですが、食の問題に取り組むというのは、「社会の構造を変える」試みでもあったんじゃないかと思うんです。
マヒト:自分たちからはあんまり訴えたくないんだけど、確かにそういう面はあったと思いますね。でも、自分は活動家という意識はまったくなくて。かつては海で魚を捕ってくる人がいて、着るものを編んでる人がいて、それぞれに得意なことで生きてきたはずですよね。でも、今はお金が真ん中にあって、あらゆることが均一化されている。
その均一化が、音楽みたいに自由であるべきものの中にも侵食してきている感覚があるんですね。だけど俺の場合はーーこれは単純に人に触れて生きることや『全感覚祭』への道にも通じている感覚だと思うんですけど、ちゃんとそのものが生きていること・存在していることを尊重してくれる音や人や場所にすごく心地よさを感じるんです。だからこそ、完全に無菌の部屋みたいなところで「研ぎ澄まされた風のもの」だけを扱っているような今の東京にはすごく違和感がある。人も、そのベルトコンベアに乗せられているだけみたいな感じがして。
―はい。
マヒト:お金によって社会を縛ろうとする人たちにとっては100人がひとつの答えでまとまっていたらすごく便利だけど、そういう人たちや資本主義的な流れにとっては、オリジナルな価値観で生きている人たちってすごく面倒な存在だと思うんですよ。もちろん自分もベルトコンベアに乗せられて生きてる部分もあると自覚してるし、ファストフードを食べることももちろんあるんだけど、そういう状況に対する問題提起という感覚はあったかもしれない。

―「構造を変える」といっても、あくまでも日々の暮らしのなかで何を考え、何を実践していくか。そういう地道な感覚が根底にある?
マヒト:そうですね。自分たちの場合、あくまで生活という軸からは逸脱しないでやっていきたいんです。切り取り方によっては『全感覚祭』の活動も政治的と取れるだろうし、アクティビストがやってることとも共通しているのかもしれないけど、あくまでもひとりぼっちの人間が生活しているときに見える景色や、聴こえてくる音の話をしたい。
それぞれに役割があっていいのですが、自分の場合、政治というひとつのジャンルで語ると連帯は強くなるけど、それは同時に何かを拒絶することにもなりかねないと思うんです。だからこそ、一つひとつの体験が大切なんじゃないかって。そういう意味でいえば、台風というのも圧倒的な体験だったし、環境問題が生活のレベルまで侵食してきたことを実感させられましたね。
―今回のアルバムには、そういった実感や気づきが反映されていると思うんですが、一聴して感じたのは、ディジュリドゥやケチャ的なコーラスが多用されていたりと、今までにないプリミティブな匂いが充満してますよね。こういった要素はどこから出てきたものなんでしょうか。
マヒト:自分のなかでは「生きている音・呼吸している音」を求めているところがずっとあって。アルバムに入っている音にしたって、究極的にいえば、MPCに全部入れてボタンを押せば鳴らすことはできるんですよ。でも音楽の作り方がそうなっていけばなっていくほど、むしろ呼吸している音の価値が高まっている気がするんです。体温のある音というかね。今回のアルバムにはそういう音が多くなったと思う。
普段自分たちが見ているものがいかにレタッチされているのか実感した。そういう世界に対してのアンチテーゼみたいな気持ちはあったかもしれない。
―何か具体的にインスパイアされるものはあったんですか。
マヒト:具体的な音というより、普段の体験からインスパイアされるほうが多いかな。たとえばセックスだってそうだと思う。このあいだ山口小夜子さんの写真を見る機会があったんですけど、そのなかに口元のアップの写真があったんですね。ものすごく肌が立っていて、産毛まで写っている。それがすごく生々しくて、ドキッとしたんです。逆にいうと、普段自分たちが見ているモデルさんの写真がいかにレタッチされているのか実感して。

マヒト:そういうことって音楽でもいえると思うんですよ。むしろ余分とされている部分や余白にこそ、やっている人のオリジナリティーや存在感があると思うんですけど、それを尊重できない世界になってるんじゃないかって。いかに最短最速で成果を出すかという資本主義的な評価軸が当たり前になって加速しているけど、それを当たり前に受け入れていくのは危険だと思うんです。
何においても一番綺麗とされるものを最短で見せるのが当たり前になっている中で、足を止めて考える時間すらない。これを当たり前に受け入れていったら、本当にAIとかにとって変わられると俺は思うし。そこで呼吸して渦巻いているものがクロスしていく感じを音楽にしたいっていうのは、そういう世界に対してのアンチテーゼみたいな気持ちだったかもしれないですね。
―今回のアルバムに入っている“狂”という曲のなかに<前半ではこの世界の破綻の詳細と奮起を、後半では希望という癌について、反抗に対する再定義について>という歌詞がありますが、「反抗に対する再定義」というのは、いわばレベルミュージックの再定義でもあると思うんですね。
マヒト:社会の景色があまりいいものだとは思えないんですよ、やっぱり。音楽が扱われる環境もそうだし、この先もっといろんなものが散らかっていくと思うんですね。現状維持のために麻酔を打っている状態で、破綻してしまったものをあたかも破綻していないかのように見ない振りをしている。それをただただ肯定する音楽がまったく心地よくなくなってしまったし、現状に対して疑問を持ち続けること以外に方法はない気がしていて。アルバムのなかでも自問自答しているところはあると思います。


―ただ、今までのGEZANは「レベル」という言葉を避けてきたところもあるんじゃないですか。そこを今回はあえて打ち出してきたことに驚きました。
マヒト:もともとバンドのなかに(聴き手の)入り口を狭めたくないという感覚があったんですよ。それもあって、自分たちが何かを背負っているというイメージを持たせないようにしてきたところがあったんだけど、「もうブッ壊さないとシャレになんないぞ」という意識が出てきて。
―イメージのことを気にしてる場合じゃないと。
マヒト:そう、それは思うっすね。今までは「自分たちではこういうものを提示するから、あとは勝手に解釈してくれ」という感覚だったけど、もう少しこちらでイニシアチブを持ってやっていくというか。髪の毛を掴んで「おい、コラ!」とやってる感じ(笑)。
―それぐらい危機感が高まっている。
マヒト:そうです。2020年はどんな一年になるか想像もつかないし、そんな時代に対する「反抗のサウンドトラック」という感覚があって。だからこそ2020年の最初に出したかったんです。自分を奮い立たせるための武器というかね。
―“赤曜日”のなかに<反抗のサウンドトラック / Tribal Scream>という言葉があったり、2018年の『全感覚祭』のテーマが「Tribal Scream」だったり、GEZANのアメリカツアーと、ネイティブアメリカンとの出会いを追った映画『Tribe Callerd Discord:Documentary of GEZAN』があったりと、近年のGEZANの活動のなかで「トライブ(部族)」という言葉がよく出てきますよね。この「トライブ」という言葉に込められているものとは何なのでしょうか。
マヒト:たとえばSNSを開くと、みんな自分が「どっち側の人間なのか」を自然と分類している感じがするんだけど、そもそも身ぐるみを剥いじゃえばただのケモノなわけだし、皮を剥がせば肌の色も分からなくなるわけで。人間は生きていくうちにそれぞれの歴史を背負いながら自分という人格になっていくわけだけど、本来誰もが言葉にできない叫びみたいなものを持っているはずなんですよね。
赤ちゃんだって、叫びながら生まれてくるわけじゃないですか。電車のなかで赤ちゃんが泣いてるところを目の当たりにすると、すごく格好いいと思うんですよ。でも、人間は成長していくなかであの感覚を忘れていってしまう。自分の属性を越えたところにある、血液みたいな叫びというか、命を鳴らすということ。
マヒト:「自分」という存在は本来ひどく曖昧で、それ以前に生き物であるということのほうが強くて。俺なんかもマヒトゥ・ザ・ピーポーというふざけた名前で24時間生きているような気持ちになってるけど、たとえば盆踊りで櫓(やぐら)の周りをずっと回っていると、自分も含めたおのおのの人格が溶けていくような感覚になってきて、「マヒトゥ・ザ・ピーポーなんてどこにもいない」ということを知るんです。だって、盆踊りで踊ってるときって、何か目的を持ってることってあります?
―踊ってる瞬間は消滅しちゃいますよね。余計な考えが消え去って、黙々と踊ってしまう。
マヒト:俺もただ気持ちいいだけなんですよね。アルバムに入っている言葉のなかには論理的に組み上がってところもあるとは思うんだけど、目指しているのはすごく抽象的で自由で温かい場所。その点は盆踊りやクラブで踊っているときの高揚感とさほど変わらないんですよ。
何をそこから持ち帰ろうとか、それを家に帰ってからどのように提示しようとか、そういう感覚はほとんどなくて。むしろその感覚がまったく入ってこないところが気持ちいい。このアルバムでやっているのも、用意された「自分」よりももっと深いところに声を与えていくということなんだと思う。

祭りのなかで独特の連帯が生まれて、それぞれの場所に散っていく。カテゴリーで縛る限界がきてフラットになった時代の、一瞬の連帯と一瞬の解散というか。
―「自分なんてどこにもいない」というのは、社会的な枠によって決定された自分じゃなく、もっと本来的な自分の感覚に立ち返るということですよね。ふだんは押さえつけられている生物的な衝動を解放する感覚に近い。『全感覚祭』や今回のアルバムには確かにそういう感覚が漲っていて、そこから新しい「トライブ」が生まれつつあるんだと思う。今回築かれた各地の農家とのネットワークなんて、まさに部族的ですよ。
マヒト:ステートメントを出すまではまったく関わりのなかった農家の方々が反応してくれて、『全感覚祭』の場で繋がったことはすごく大きかったんですよ。2、3回しか会ったことがないのに、ある部分を共有した未来像をイメージできるようになった。今自分たちの周りで生まれつつある「トライブ」の場合、これまでに使われてきた「シーン」という言葉が適用できなくないと思うんです。そこに新しさがあると思うし、『全感覚祭』の前と後で何かが変わったかというと、そういう繋がりが実感できるようになったということはあるんじゃないかな。
―その繋がりって、どういうヴィジョンを共有しているものなんですか。
マヒト:トライブといっても国籍や民族で縛ってるわけでもないし、明確なカテゴリーが存在するわけでもない。祭りのなかで独特の連帯が生まれて、それぞれの場所に散っていく。「新しいトライブ」とは、そういう感覚を共有している人たちのことなんだと思います。いろんな知識を持つ人たちだけで集まったときに生まれる選民意識とは関係なく、『全感覚祭』はその感覚を自覚するプロセスになればいい。

―あくまでも自分たちの「トライブ」以外を排除するものではない、と。
マヒト:うん、そうですね。ある定義のもとに使うと、「トライブ」というのは危険な言葉だとは思いますし。実際、世の中を見てみてもカテゴリーで縛り付けていく限界もきてるし、どうでもよくなっている。そういうものがフラットになってきた時代の一瞬の連帯と一瞬の解散というか。
―実際、『全感覚祭』をきっかけに作られた連帯もミュージシャン同士だけじゃなく、より大きな意味での「表現者」との連帯ですよね。
マヒト:もっともっと出会うべき人がいるんだろうし、そう思うとすごく楽しくなってくるんですよ。誰かのアンテナにひっかかるように言葉を研ぎ澄ませていかなくちゃいけないと思ってますね。「生きる」というすごくプリミティブな行為の一環として問題提起をしてるので、フィールドは違っていても同じ意識で活動している人はたくさんいると思う。自分の身体と向き合って、2020年にそれぞれの街に立って考えていったら、ちゃんと答えを出せるはずなんですよ。
―僕からは最後の質問です。GEZANのレベルミュージックが破壊したあとの新しい世界は、どんな形をしているんでしょうか。マヒトさんはどういうイメージを持っています?
マヒト:極論かもしれないけど、少なくともレベルミュージックが必要とされなくなる世界が理想ですよね。このアルバムを聴いても何も感じなくなるというか。逆にいえば、レベルミュージックが必要な世界になっちゃってるんですよ。
実際、今の東京はすでに壊れてると思ってるんですよ。Photoshopを使って街をトリミングし、レタッチして2020年のイメージを作り上げている。だから、本当はネオトウキョーみたいな「新しい世界」はこなくて、だらしないままの東京が続いていくだけな気がしていて。自分はこれまで「新しい世界」って言葉を使っていろんな価値観が更新されると歌ってきたけど、今は「本当の世界」のほうが言葉としてはしっくりきてるんです。
―よりプリミティブな世界になる、より本来的な自分の声に気づいていくというか。
マヒト:そうですね。そのための反抗がこのアルバムなんだと思う。
山元(CINRA.NET編集部):僕もこのアルバムを聴いて何かが変わってほしいし、変わらないとおかしいと思っています。ただ、マヒトさんはオリジナルの神様を一人ひとりが持つということの大切さを前から訴えていたけど、それって現状を考えると結構難しいんじゃないかと思っていて。
マヒト:まずは疑問を持つということが大事なんだろうね。ただ、知らずにどこかへと運ばれてるほうが幸せなんじゃないかって考えるときもあって……俺らができるのはいい匂いのする場所やモノを作って、引き込むことぐらい。なぜそれが心に響くのか、各々が考えることがスタート地点という気もしてる。
何か大きなものを切り崩すというのは難しいかもしれないけど、ひとりひとりが変わることはできるはずで。自分で自分のことを大切にして、尊重し、間違ってることを認めつつ、誇りを持った生き方をして、勇気を持って……アンパンマンみたいな話になってきたけど(笑)、でもそれが大事なんだよね。そういうことが「革命」なんだと思う。

- リリース情報
-

- GEZAN
『狂(KLUE)』(CD) -
2019年1月29日(水)発売
価格:3,080円(税込)
JSGM-341. 狂
2. EXTACY
3. replicant
4. Human Rebellion
5. AGEHA
6. Soul Material
7. 訓告
8. Tired Of Love
9. 赤曜日
10. Free Refugees
11. 東京
12. Playground
13. I
- GEZAN
- イベント情報
-
- 『十三月presents GEZAN 5th ALBUM「狂(KLUE)」release tour 2020』
-
2020年2月13日(木)
会場:北海道 札幌 BESSIE HALL2020年2月17日(月)
会場:青森県 弘前 Mag-Net w / 踊ってばかりの国2020年2月19日(水)
会場:山形県 酒田 hope2020年2月20日(木)
会場:宮城県 仙台 LIVE HOUSE enn 2nd2020年3月18日(水)
会場:大阪府 梅田CLUB QUATTRO2020年3月19日(木)
会場:愛知県 名古屋 APOLLO BASE2020年4月1日(水)
会場:東京都 恵比寿 LIQUIDROOM
- プロフィール
-

- GEZAN (げざん)
-
2009年、大阪にて結成。自主レーベル「十三月」を主宰する。2018年に『Silence Will Speak』をリリースし、2019年6月には、同作のレコーディングのために訪れたアメリカでのツアーを追ったドキュメンタリー映画『Tribe Called Discord:Documentary of GEZAN』が公開された。2019年10月に開催予定だった主宰フェス『全感覚祭』東京編は台風直撃の影響で中止となったが、中止発表から3日というスピードで渋谷での開催に振り替えられた。そして、1月29日に『狂(KLUE)』をリリースする。
- フィードバック 2
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-