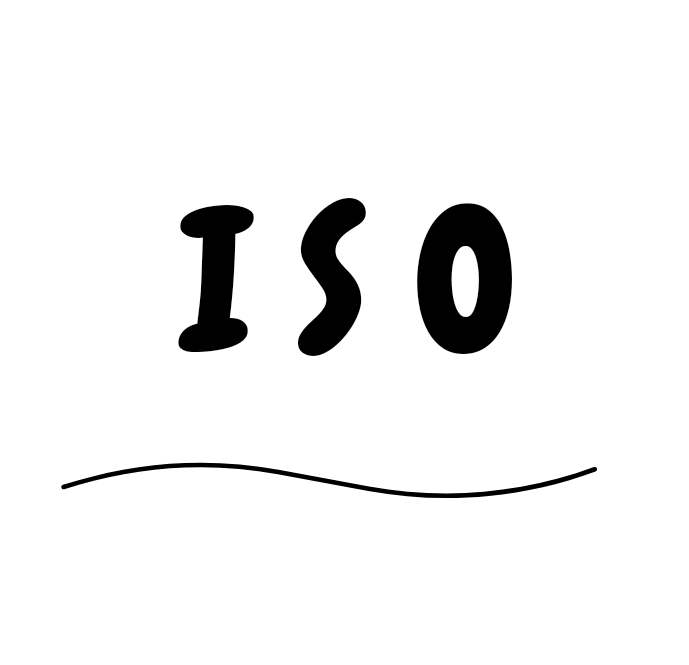『第30回釜山国際映画祭』で北村匠海、林裕太、綾野剛が最優秀俳優賞に輝いた映画『愚か者の身分』。闇ビジネスや貧困といった社会の周縁で生きる人々を描いた本作は、西尾潤による小説を原作に、永田琴監督が向井康介を脚本に迎えて映画化した意欲作である。
5人の視点から描かれた原作を3人の男性に絞り込み、約2時間の作品へと大胆に編集。エンターテイメント性と社会性を両立させた絶妙なバランスは、永田監督のこれまでの経験の集大成といえる。本インタビューでは、3人集まるのは取材日が初めてだったという監督、原作者、脚本家の3人が、映画化に至る経緯から制作の裏側、印象的なシーンの数々について語り尽くす。
新宿を舞台に、闇ビジネスの世界で生きる3人の男たちを描く群像劇。戸籍売買に手を染める若者タクヤ(北村匠海)、彼に拾われた過去を持つマモル(林裕太)、そして元ボクサーで運び屋を生業とする梶谷(綾野剛)。貧困や少年犯罪といった社会の周縁で繋がった彼らは、犯罪の連鎖から抜け出せずにいた。それぞれが過去と未来を映し合うように交差しながら、やがて決断の時を迎える。果たして彼らは闇から抜け出すことができるのか。北村匠海、林裕太、綾野剛が熱演し、釜山国際映画祭で最優秀俳優賞を獲得した社会派エンターテイメント。
『釜山国際映画祭』で3人同時受賞の快挙ーー「本当に生きていて良かった」
—まずは『釜山国際映画祭』での最優秀俳優賞受賞おめでとうございます。作品を観ると北村匠海、林裕太、綾野剛さんが揃って評価されたのも納得でしたが、釜山での反響はいかがでしたか?
永田琴(以下、永田):めちゃくちゃ嬉しいです。釜山ではたくさんの人が「あなたの作品はコンペに出品されているよね」って声をかけてくれるんですよ。それで今年新設されたコンペティション部⾨に対しての注目度がすごく高いことを現地で実感しました。マーケットを含めヨーロッパから来ている人もたくさんいたんですが、皆さんコンペ作品に対するリスペクトがすごいんです。
たしかにコンペ作品を見渡すと、『ロカルノ国際映画祭』で最高賞を取った三宅唱監督の『旅と日々』や『カンヌ国際映画祭』のコンペに入ったビー・ガン監督の作品とかが揃っていて。そのなかで賞をもらえるなんて考えていなかったんですが、それでも何かあるんじゃないかという予感はしていたんですよ。

永田琴監督
西尾潤(以下、西尾):映画祭開幕の夜にパーティがあって、私も招待していただいたので遊びにいったんです。その時にプロデューサーの森井(輝)さんが「他の作品もすごいけれど、うちらにも勝算はある気がする」って言っていたのを覚えています。
永田:森井さんも思ってたんだ。でもまさか3人揃って受賞というかたちだとは思っていなかったので感動もすごくて。審査員のレオン・カーフェイさんが受賞作の書かれた封筒を開封するとき「1人じゃないの⁉︎」みたいな小芝居もしてくれたんですよ(笑)。びっくりしましたが、1人じゃなく3人で賞をもらったことでこの作品の感度が上がった気がしますし、だからこそ本当に嬉しかった。
みんな(林)裕太のところに来て「写真撮ろう!」って言ってくれるんですよ。プレゼンターとして来ていたジュリエット・ビノシュさんも私たちの顔を見た瞬間「おめでとう!あなたたちとは写真を撮らなきゃ」って言ってくれて、本当に生きていて良かったです。
向井康介(以下、向井):僕は受賞をニュースで見たんですよね。俳優が賞を獲ることって、たぶんその人を演出した監督が一番嬉しいと思うんです。だから3人で受賞と聞いて、「永田さんは本当に嬉しいだろうな」と遠くから思っていました。

脚本・向井康介さん
西尾:この企画が始まるときに、琴さんが「いろんな作品を撮ってきたけど、私の代表作として映画祭に出品できるような映画を撮りたいと思っている」って話していたんですよ。それを思い出したら本当に泣けてきて。しかも3人同時受賞と聞いてことさら感動しましたし「持ってるな永田琴!」って思いました。
永田:ゲッターズ飯田さんの占いで、私と森井さんは「銀のインディアン座」っていう同じ星座タイプなんですよ。で、「銀のインディアン座は今年最高の運気」とあったので、森井さんにも「私たちは今年最高だから!ダブルで最高って思ってやろう!」ってつねに言ってたんです。それが良かったのかも。
原作5人から3人への大胆な再構築。「この3人は実は1人の人間のようなもの」
—そもそも西尾さんが「闇ビジネスとそこから抜け出せない人々」という題材に着目し、初めての小説で連作短編集として描いた理由は何だったのでしょうか?
西尾:『大藪春彦新人賞』という作家の登竜門となる賞がありまして、それに応募しようと決めたのが出発点でした。大藪春彦さんはハードボイルド小説で有名な作家なので、ハードボイルドを書こう思ったことに加え、もともと犯罪などのノンフィクション小説に興味があったんです。その頃ちょうど世間では闇ビジネスや半グレといった問題が話題でした。ただ、ハードボイルドはジャンル的に少し読みづらいと感じることがあったので、もう少し女性が読みやすいようなライトなハードボイルドを書きたいと思ってい、女性を主人公に闇ビジネスの物語を書き始めました。だから元々は、山下美月さんが演じる希沙良ちゃんがこの物語の始まりなんです。
小説は第2回の『大藪春彦新人賞』で受賞しているんですが、実は第1回にも応募していまして。それは希沙良ちゃんが主人公の『ビッチ』というタイトルの小説でした。第2回は別の話を……とも思ったんですが、締め切り直前まで仕事をしているから全然思いつかなくて。その『ビッチ』に、タクヤが「マモルから連絡がないから会いにいく」という場面があったので、そこからいろいろ想像していってマモルの章が生まれて、それを応募したら受賞したという流れです。
—原作小説の第二章がすべての出発点だったんですね。小説に掲載されている希沙良パートは『ビッチ』そのままなんですか?
西尾:少しは直していますが、基本的にはそのままですね。その希沙良ちゃんとマモルの章があって、それだけだと単行本でデビューするには足りないなということで残りの三章を書き足していきました。
—その原作小説を初めて読んだときの感想はいかがでしたか?
向井:僕は永田さんから脚本のお話をいただいて、映画化前提で読み始めたんですよね。しかも連作の群像劇なので、「これを2時間くらいに収めるにはどうすれば良いんだろう……」というのが正直な感想でした。
永田:仕事として読んでるから純粋には楽しめないよね(笑)。
向井:でも自分は負けた人の物語が好きということもあり、いろいろと負けた過去のある梶谷の章に共感する部分はありました。だからこの人は外したくないなというのは読みながら考えていましたね。
永田:向井さんに脚本をお願いしたとき、最初「これを2時間に収めるのはちょっと……」ってやんわりお断りされたんです。ただその瞬間に「この人は絶対離しちゃだめだ!」とビビッと来て、私のなかで考えていた「3人の男を主軸にする」というアイデアを出したんですよね。そしたら「面白そうだしできるかも」と受け入れてくれて。
—5人の視点だった原作を3人に絞ったのは監督のアイデアなんですね。
永田:私もどこか切らなきゃいけないなとは思っていましたし、この3人に委ねれば私が描きたい世界を引っ張ってくれるだろうなと思っていたので。向井さんから「この登場人物の多さは失敗しちゃいますよ……」みたいな空気を感じましたし。
向井:そんなこと思ってないですよ(笑)! もしフォーマットが変わって、たとえばリミテッドシリーズで放送されるということなら1話につき一人というかたちで全然成立すると思うんです。ただ映画となると2時間で何を見せるのかを考えないといけない。
監督が言っていたのは「この3人は実は1人の人間のようなもので、タクヤの過去がマモルで未来は梶谷。闇ビジネスに堕ちていくけれど、どこかで連鎖を止めたいと思っている各々の視点がある」ということ。かつ最初にお会いしたときに「少年犯罪や貧困を描きたい」という話をしていたので、その視点も外しちゃいけないなということで焦点を絞っていきました。

初対面の脚本家を口説いた監督の行動力と、「2時間35分」からの格闘
—永田監督と西尾さんはかねてより親交があったとうかがいました。監督自ら映画化の企画を進めたとのことですが、その際お二人はどのようなお話をされたのでしょうか?
西尾:あんまり話してないですよね。これは大きな変更点だから言っといたほうが良いかなと思ったら教えてください、という感じで全面的にお任せしていました。だから仲道という原作に出てくる探偵がいなくなったことは事前に教えてもらいました。やっぱり小説は小説、映画は映画で違いますし、映画は永田さんの作品だと思っていたのでどう変わっても私としてはイエスでした。
永田:特にリクエストなどもなく「好きにやってもらって」と言ってもらえたのでホッとしましたよね。
向井:打ち合わせで「こんなに変えて本当に大丈夫?」って何度も何度も聞きましたが、監督はいつも「大丈夫だから」って言ってましたね。

—永田監督がこれまで組んだことのなかった向井さんに脚本を委ねようと思った理由は何でしょうか?
永田:これは男性の物語じゃないですか。その世界を描くときに、小説に書かれた以外の台詞も出てくるわけですし、その空気感をつくってもらうために男性脚本家が良いなと思ったんです。私は男性脚本家とほとんど仕事をしたことがなかったんですが、青春映画から『愚行録』のようなサスペンスまで書かれている向井さんだったら上手くいくと勝手に思いまして。
面識もなかったんですが、向井さんの同級生で以前飲み仲間だった方がいたので即座に「紹介して」とお願いしました。で、向井さんの連絡先を教えてもらってすぐ「ご飯食べにいきましょう! いつ空いてますか?」って。
—すごい行動力! でも最初は仕事ではなくご飯のお誘いだったんですね。
永田:すごく変わった人だったら仕事するのも難しいじゃないですか(笑)。だから最初は仕事の話をせずに、「どんな人なのかな」ということを知りたくてご飯を食べることからスタートしました。
向井:僕も「どんな人なんだ……?」と思いながら会いにいきましたよ。ただ大学の同期の紹介だからそんな変な人ではないだろうなとは思っていましたが。
そんな細かいところで登場人物の生き様を表現? ディテールにこだわった脚色
—闇ビジネスなどの題材について書くうえでどのようなリサーチをされたのでしょうか?
向井:本作の戸籍売買という題材は『ある男』(2022年)でも扱っていたんですよね。もちろん内容は全然異なるんですが、そのときにある程度調べていたというのはあります。あと事前に永田監督が調べてくれていたものを参考にさせてもらったり、原作にあるものをそのまま落とし込んでいったりしました。
—貧困や闇ビジネスから抜け出せない人々など、社会の周縁の人々を描くうえで意識したことはありますか?
永田:一番に意識したのはタクヤとマモルの関係や人物像、そこに陥った過程というものをリアルに描くことでした。こういう世界に生きている人が本当にいることを知ってもらいたいという気持ちがとても強かったので、そこをねじ曲げないようにしたいなと。
—主要人物を3人に絞るだけでなく、構成や登場人物の関係性においてもさまざまな脚色がなされていたかと思いますが、本作の脚色をするうえで意識したポイントを教えてもらえますか?
向井:前提にあるのは、できるだけ原作を壊さずどう映画的にまとめていくかということ。脚色というのは9割9分が「どこを削るか」という作業なんですよ。やはり時間も情報量も限られるので、2時間ノンストップで見せ切るためにどう切り取っていくかをひたすら考えていきました。ただ監督の「3人は実は1人の人間」という手引きがあったので、書き進めるうえでそれほど迷いはありませんでした。脚本チームとしてプロットライターの方々も参加して、優れたアイデアを出してくれたので、それをまとめていったという感じです。
—些細な仕草で描かれない登場人物の背景がわかる描写が巧みでしたね。たとえばタクヤがハイタッチしようと上げた手に怯えるマモルのシーンだったり。そういう部分はどのようにつくりあげていったのでしょうか?
向井:あのシーンやマモルの箸の持ち方がちょっと間違っているなどのアイデアは打ち合わせで出ましたよね。ただでさえ群像劇で時系列が前後するなかで、さらに過去に遡って彼らの生い立ちを描くのはしんどい。なのでどう育ってきたのかを今の状況から描けないかと試行錯誤していきました。そもそも回想があまり好きではないので、入れたくなかったということもありますが。

永田:それでも私が回想を入れてほしいと追加で書いてもらったところがあるんですが、結果的に編集段階でほぼ切りました(笑)。私が一番最初に満足いくかたちでつくった尺が2時間35分だったんですよ。ただ森井プロデューサーに怒られて最終的に2時間5分に収めたんですが、30分削るにはガッツリ切らないといけなかったんですよね。
回想でタクヤが梶谷と最初に出会った瞬間も描いていたんです。本作ではそれぞれの身分証明書を出したかったんですが、梶谷のものは出てないんです。実はその回想シーンで梶谷がボクサーとしての証明書を落として……という描写があったんですが、そこはもうガッツリ切っちゃって。すごく良いシーンだったんですけどね。期限切れの証明書を未練がましく持っている梶谷の心情を表していて。
向井:ただでさえ140分の脚本になっていると感じてはいたんですよ。撮影終了後にみんなでご飯を食べているときに編集中と言っていたので、状況を聞いたら「2時間半ある」と言ってて。正直「ですよね……」と思いました(笑)。事前に言っておいたら良かったなと反省した部分でもあります。
永田:最初に編集したものは、森井さんに「話になんない! この尺だとビジネスにならないよ」って鬼みたいに言われて(笑)。それで2時間20分にしたものを自慢げに見せたら「まだラインに乗ってないよ」って突っぱねられて。
向井:長くて良い映画と長いとダメな映画ってありますもんね。でも編集は宮島(竜治)さんだったから、宮島さんなら綺麗に切ってくれると思ってましたよ。
永田:宮島さんも途中で「もう切れないんじゃない?」って言ってくれたんだけど、私は「今意欲に燃えてるからあと少し切る」って意味不明な意気込みで切っていきました。でも宮島さんがいてくれたおかげで本当に大事なシーンは残せました。
エンタメと社会性の綱渡り。「辛気臭いものにならなかった」原作の力とは
—扱っている題材は描き方次第では重々しく取っ付きにくいものにもなり得たと思います。ですが本作は社会派の側面もありつつ、娯楽性を追求した内容になっていたと思うのですが、作品全体のトーンはどのような指標で決めていったのでしょうか?
永田:アート映画的に撮るつもりはもともとなかったです。監督という立場上、興行収入の面でも失敗できないので、まずかたちとして観やすいエンターテイメントにするという指標はありました。ただ、エンタメのなかで自分が示したい社会性をどう表現するかはすごく考えましたし、そのためにも登場人物をしっかり描かないと、とつねに意識していました。だから編集でも、人物描写に関わるささやかな仕草に対して「ここ長くない?」と言われても「長くなーい!」ってどしっと構えてました(笑)。
糸井重里さんにも「不思議なバランスで成立してる映画だな。何人かで撮っているように見える」って言われたんですよ。それは今まで私がラブコメやサスペンスなどいろんなものを撮ってきた経験が集約されたものだったからじゃないのかなって。
でも本作がエンタメになり得たのはやはり原作の力も大きいと思います。同じ題材でも私が脚本を書いたら、日の目を見ない辛気臭いものになったでしょうし、自分のなかにないものがこの原作にはあったので。だからやっぱり『愚か者の身分』の魅力はこの2人がいてこそ生まれたものだなと思いますね。
—原作者である西尾さんは完成した作品を観ていかがでしたか?
西尾:最初に観たときは理解が追いつかなかったです。自分の書いた物語が映像になっていること自体がすごいし、スクリーンに映っている一つひとつの物事にいちいち感動しているから客観視できなかったと言いますか……。「そう、最初は神田川から始まって……え、この場面がこんな風になってるんや! う、うわー!」って感じで。内容がちゃんと入ってきたのが2回目で、そのときは序盤から号泣でした。気持ちがグッと入りすぎちゃって。それで3回目にやっと全体像が見えるようになって、「タクヤはこんな服着てたんだ」とか「刑事の存在はこんな風な描き方になったのか」といった細かいことを思ったり。

西尾:それぞれのキャラクターもバッチリで、正直イメージを超えてきました。原作での梶谷は30歳前後くらいの設定で、もう少しもっさい感じなんですよ。乗っている車も映画とは違っていましたし。でも綾野さんが演じてくれたことで、とても素敵な梶谷になったなと感動しました。原作では地下格闘技に身を投じて、悪い友達とつながって捕まった挙句に闇ビジネスに手を出してしまうんですよね。そこで戸籍売買もやったことがあるけど、今は疲れて運び屋をやっている……という人間。だけど綾野さん演じる梶谷はすごく格好良くって。
永田:ダメな男としてダメに描いているんですけどね(笑)。でもたしかにこれまでの綾野くんで一番格好良かったと言ってくれる人もいて。「演技が上手いと思ってたけどこれほどとは……」って感想もあったし。
西尾:北村さんと林さんが演じるタクヤとマモルは、もうそのものでした。演技をしている感覚がないというか、イメージしていた人物がそのままスクリーンのなかに生きているようで。だから今もどこかで暮らしている姿も想像してしまうんです。改めて役者さんのすごさを思い知りましたし、監督の演出も素晴らしかった。だからこその俳優賞なんでしょうね。
永田:匠海君に関しても「こんなに芝居が上手いなんて」とか「北村匠海がこういう役者だと知って驚いた」という反応がたくさんあって。それぞれの良いところが引き出せたならすごく嬉しいですよね。

—向井さんは完成品を観た感想はいかがでしたか?
向井:ちゃんと舞台である新宿区の姿が撮れていたというのがすごく良かったですね。歌舞伎町や神田川、大久保通りや百人町、東中野へ向かう感覚とか、そのあたりのリアリティが出ていて作品の質感に貢献しているなと。もともと歌舞伎町で撮れるかどうかという議論もあったんですが、監督が「こう撮ればいけるはず」というように歌舞伎町で撮ることに最後までこだわっていて、その粘りが映像に映っていると観ながら感じていました。特に雨の歌舞伎町のシーンは良かったです。
永田:私は助監督経験から「ここをこうすればこの場所でも撮れる」という段取りを理解している。でも歌舞伎町の通りを裕太の服を変えて4回撮影するというのは、みんなに「絶対無理だからやめてくれ」と大反対されて。でも私は「絶対できる!」としつこく言い続けて譲らなかったんです。結果自分を貫いて撮影をして良かったなと思えるシーンができたと思っています。
「かすかな光はほしかった」原作者がラストへこめた想い
—それぞれが印象に残っているシーンはどこですか?
西尾:さっき少し触れていた「タクヤが上げた手に怯えるマモル」のシーンが一番印象的でした。あそこを観たときに映像の力のすごさを実感したんですよね。もし文字で書こうとするとすごく長くなると思うんですが、それを一瞬で表現できるのは映像ならではだなと。あとご飯を食べているシーンも印象的でしたね。小説を書いていたときは最初から「ラストは白米を黙々と食べているシーンで終わろう」と決めていたんですよ。
犯罪者を描こうと思うと、オチがハッピーエンドにならないだろうなって大体わかるじゃないですか。でもこの物語の人々は決心してヤクザになったような人じゃなく、何かにだまされたり巻き込まれたり、社会の周縁で必死につながった関係から犯罪に関わってしまった人なんです。もちろん犯罪に加担したということでハッピーエンドにはできないけれど、かすかな光はほしいと思いました。ご飯を食べるというのは生きる力を感じる行動だし、そういう意味で黙々と白米を食べるシーンで終わる物語が良いなって。だからその思い入れのあるシーンが映像になったことにとても感銘を受けました。あとは梶谷がタクヤの血のついた髪を洗ってあげるシーン。書いているときから美しい場面だと思っていましたが、やっぱり素晴らしいシーンになっていてとても素敵でした。
永田:入浴のシーンはもっと長く撮っていてそれもすごく良かったんですが、編集で泣く泣く切ったんですよね……。
向井:個人的に印象に残っているのは木南晴夏さんが演じる由衣夏まわりのシーンですね。原作でもそうですが、賞味期限切れの牛乳の話とかで緊迫感あるなかでちょっと砕けるというか、ホッとするじゃないですか。木南さんは大阪弁でそれを的確に演じられていてすごく良かったなと。
西尾:大阪弁にしたことで、小説を読んだ人みんなに「この女は最後に絶対裏切ると思った」って言われたんですよ! 大阪弁話す人は悪いことをしそうみたいなアンチ大阪弁的な風潮あるじゃないですか。まあ佐藤には大阪弁を喋らせちゃったんですが……。ともかくそういう風潮があるなかで由衣夏は善人でいくって決めてて、逆に絶対裏切ってやんないぞって書き切った役なんです。
向井:僕も脚本を書くときにちょっと「この人は裏切るんじゃないか」と思わせようかなという気持ちが最初ちょっとありました(笑)。
永田:私は由衣夏は彼らのオアシスって決めてたから、原作の通りこの人は裏切る必要がないって考えていました。それで安心感のある関西弁を喋ってもらうためにも、関西出身の木南さんをキャスティングしたんですよ。あのほんわかした味わいのある関西弁は関西人じゃないと出せないかなと思って。ため息混じりの「そやんな」って相槌とかね。
一方で佐藤を演じる嶺豪一さんは関西圏出身ではないですが、私直伝の関西弁でめちゃくちゃ練習されてましたね。役柄に反して嶺さんは本当に良い人なんですよ。毎回「こんな感じで大丈夫ですか?」って聞きにきてくれたり。
西尾:でも映画の中じゃめっっっちゃくちゃ憎たらしい奴でしたよね。
永田:そうそう。北村くんも役に入り込んでるから本気で嫌っていて(笑)。
西尾&向井:あはは!
永田:マモルと梶谷の関係性はすぐに掴んだそうなんだけど、「佐藤のシーンはどういう顔をしたら良いんですかね?」って相談されたんですよ。だから「佐藤のことは嫌いで大丈夫。ただ嫌いでも生きていかないといけないし、マモルを守る必要もある。だから表面上は仲良くして何かあったら見捨てるというビジネスライクな関係で良いよ」って話をしました。ステーキハウスでパフェを食べるシーンを撮影しているときも「マジで嫌いです……」って。
西尾:たしかにパフェのところが一番憎たらしいかも。さくらんぼの種を飛ばしたりね。
永田:でも嶺さんはずっとめちゃくちゃ優しいし、すごく真面目なんですよ。佐藤を演じるために10キロ太って腹が出るよう頑張ってくれましたし。すぐ痩せる体質だそうなので、撮影中も「いっぱい食べなきゃ」って。本当に良い人でした。
観終わった後、映画について話してくれるだけでいい
—佐藤の役が強烈すぎて嶺さんに怖いイメージがつきそうだったので、そのお話を聞けて良かったです(笑)。では最後に、本作を観る人がどのような会話や楽しみ方をすることを期待しますか?
永田:私はもう、観終わった後にこの映画について話してくれるだけで良いです。劇場に行って映画館を観終わったすぐあとに、横で「じゃあなに食べに行こうか」って言ってるのを聞くと、その映画が失敗しているようでつらくなるんです。本当に衝撃を受けたり良いなと思った作品ってみんな黙りこくって席を立たないとか、興奮気味に作品について話し合ったりするじゃないですか。だから『愚か者の身分』もそんな映画になってくれたら良いなって思います。
西尾:自分はヘアメイクの仕事をしているとき、撮影って「祭りだな」っていつも思うんです。丹念に計画して、準備して、いろんなことを経て、ついにその瞬間を迎えるという意味で。ヘアメイクだと関わるのは撮影までですが、今回はひとつの作品が生まれて、みんなのもとに届けられるまでを見守っています。そうみると「作品は、監督や脚本家、プロデューサーや俳優と、いろんなスタッフが集結して生まれた宝石みたいだ」と実感するんです。宝石って上から見ても横から見ても、触ってみても飾ってみても良いじゃないですか。それと同じでこの作品もいろんな角度の見方、楽しみ方があると思います。だからそれぞれが好きな見方で、一回と言わず何度でも観て楽しんで頂けたら嬉しいですね。
向井:何よりも役者の御三方はぜひ観てほしいですよね。北村くんと綾野さんはもうベテランの域に入っていると思いますが、その間でこれからの俳優である林くんがすごく良い芝居をしている。まだ24歳ということで、「初期の林くんを知りたいならこの映画を観ればいいよ」とみんなが言ってくれるような作品になれば良いなと思います。
- 愚か者の身分
-
 監督:永田琴
監督:永田琴
原作:西尾潤
脚本:向井康介
出演:北村匠海、林裕太、綾野剛、山本美月、矢本悠馬ほか
配給:THE SEVEN , ショウゲート
- フィードバック 53
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-