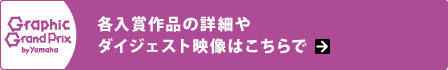審査委員長に日比野克彦を迎え、約半年にわたって開催してきた新たなグラフィックコンテスト『Graphic Grand Prix by Yamaha』(以下、『GGP』)が終幕した。いまから30年前の1982年『第3回日本グラフィック展』において「平面作品に限る」という応募規定のなか、段ボールを重ねるというウルトラCで大賞を獲得し「平面グラフィック」に問いを投げかけた日比野は、今回のコンテストを通して、いまグラフィックの未来に何を見ているのだろう。『GGP』の最終審査および表彰式のなか、日比野が掲げた「存在」というテーマについて、そして最終審査に大きな影響を与えた「言葉」について、個性的でまるで似ることのない、それぞれの受賞者の作品を見ながら、その未来や可能性について考えた。
「平面」かつ「デジタル」で「存在」感のある作品による、異種格闘技戦
「存在」とはそもそもどういう意味なのだろうか? そんなことをずっと考えさせられる時間だった。楽器の製造を主とするヤマハ株式会社、モーターサイクルを中心とするヤマハ発動機株式会社、感動を企業目的に掲げる2つの「ヤマハ」が共催し、今年6月にスタートしたグラフィックコンテスト『Graphic Grand Prix by Yamaha』(以下、『GGP』)の最終審査および表彰式が、12月14日に新宿パークタワーホールで行われた。

会場風景
今回が初開催だった『GGP』だが、ルールは簡単なようで奥が深かった。作品の応募規定は「1,200×1,200px以内のjpegファイル」ということのみ。応募作品は額面通りのデジタルアートでもよければ、油彩画をスキャンしたものでも、立体物を写真に撮って二次元に変換したものでも構わない。唯一作品性を縛るものがあるとするならば、コンテストのテーマとして設けられた「存在。」というキーワード。これに対して応募された作品は1,585点。それぞれの作家が考える実に様々な「存在。」が集まった。審査員を務めたヤマハ株式会社デザイン研究所所長の川田学が、「異種格闘技みたいになっちゃって、どう比較すればいいのか難しかったし、こちらも試された」と振り返った事前審査、一般からの反応も加味した公開審査、そして二次審査を経て、最終審査までに7つの作品が残った。
デジタル作品だからこそ、身体性から放たれる魅力を求めた
この最終審査では7人のノミネート作家全員がステージに登壇し、審査員を務めた日比野や両ヤマハ社長、4名のヤマハデザインセクションメンバーの前で作品について語る場が設けられた。応募段階でも作品そのものだけでなく、その閲覧環境および展示方法の解説が任意で求められていたが、ここで7人は改めて作品を制作した背景や意図を審査員に伝えたのである。今回、最終審査で作品に対する説明を求めた理由について、表彰式後の日比野に尋ねたところ、次のように話してくれた。

日比野克彦
日比野:グラフィック、そしてデジタル応募という形態だったからこそ、逆に身体性を求めたくなったんですよね。「誰が?」とか、「なんで?」とか、すごく子供じみた質問をしたくなる。これからは誰とでもすぐコネクションできる世界になっていくからこそ、面と向かって会うとか、自分の足で歩いて移動するとか、そういうことが重要になっていくと思うんです。山ほど情報があふれ、山ほどグラフィックの種類も増えていくなかで、こういうコンペティションの役割は、1枚のグラフィック作品だけじゃなくて、それを発信する人間を含めてきちんと評価していくことだと思います。だから、入口は当然グラフィックで審査しましたけど、最後の部分では作品や作家のあり方をふくめた広い意味での「身体性」を元に決めさせてもらいました。

ヤマハ株式会社 デザイン研究所所長 川田学
もし目が見えなかったとしたら、グラフィックアートって何なんだろう?
最終審査直前まで、「どれがグランプリになってもおかしくなかった」と舞台裏を話した日比野。最終的に、グランプリは楠陽子の『触覚の視覚化』が受賞。また、日比野克彦賞に森未央子の『フランジ』が、一般からの反響を対象としたオーディエンス賞に松田雅史の『9,332km遠くの人 15.09.2012~15.08.2012""』がそれぞれ選ばれた。なかでも、グランプリを受賞した楠が、最終審査で語ったスピーチは見事だった。以下はその楠のスピーチであるが、できる限りそのまま再現して記載した。凛とした表情とはっきりとした口調で語られたものである。

グランプリ 楠陽子
楠:私は、目の見えない人にとって、グラフィックアートって一体何なんだろう? というところから作品制作を始めました。それは、そこに何か「存在」のヒントがあるのではないかと思いました。なぜ存在のヒントがあるのかと考えたかと言いますと、例えば、いま、目をつぶってください。カメラの音が聞こえます。それであったり、普段の私の実感なんですが、田舎町に住んでいて、目を閉じると海の音が聞こえてきたり、近所のお姉さんかおばさんかわからないんですが、ピアノの練習の音が聞こえてきたり、目を閉じることで音であったり、匂いであったり、いろんな感覚がすごく刺激されるというか、そこにすごく存在を感じる、美しさを感じると思いました。そこで、今回は触覚の視覚化という形でビジュアルアートというものを表現しました。これは私が美しいと思った表現になります。

グランプリ『触覚の視覚化』楠陽子
彼女が「目をつぶってください」と言った瞬間、その言葉にどれほどの人が引きこまれ、カメラのシャッター音が聞こえた瞬間に、どれほどの人が「存在」というものを感じたことだろうか。彼女は自らの言葉で作品の持つ力をさらに輝かせ、この場にいた人たちに彼女の作品の「存在」を、そして彼女自身の「存在」を強く印象づけたのである。審査員を務めたヤマハ株式会社デザイン研究所の竹井邦浩は、グランプリの選考理由をこう話した。
竹井:最初は作品から読み取れることだけで決めたいねと話していたんですけど、やはり作者本人のスピーチを、それぞれ改めて聞くことで、より深く考えさせられることも色々とありました。もちろん作品そのものの評価があってのものですが、言葉の力やその人の考えを知ることが、ときに強い力を持つということは、自分にとっても衝撃でした。

ヤマハ株式会社 デザイン研究所 竹井邦浩
表彰式後の楠に話を聞くと、受賞した『触覚の視覚化』という作品は、どの素材を使って、どの構図で撮影するのかなど、どうすれば最も「存在」が際立たせられるのか何度も検証作業を重ねたという。彼女がスピーチの場で言った「これは私が美しいと思った表現になります」という言葉も、そうした背景があったからこそ、作品を強く印象づけるものになったのではないだろうか。
「どうしてこうなってしまったの!?」と思わせる作品を目指して
思わず「なるほど!」と納得させられた楠のスピーチに対して、日比野克彦賞を受賞した森未央子のスピーチもまた、別の意味で印象的なものとなった。彼女の応募作である『フランジ』は、「どうしてこうなった!?」と疑問を感じずにいられないほどインパクトの強い絵(ちなみに実在するオランウータンをモチーフにした作品)であったが、その反応はまさに彼女が狙ったもの。彼女のスピーチを要約すると、「例えば尋常じゃない大きさのかぼちゃの写真だったら存在として扱うけど、イラストだったら、ただのファンタジーとして消化されてしまう。だから、『作者はなんでこういうふうに描いてしまったんだろう?』って思わせるくらい極端なものを作ろうと最後まで意識して制作しました」ということだった。審査員の中で、特に彼女の作品を強く推していたというヤマハ発動機株式会社デザイン本部の一色知行は、感銘を受けた理由をこう説明した。

日比野克彦賞『フランジ』森未央子
一色:普段の仕事では、デザインの理由をかなり細かいところまで言葉で説明しているんですが、みんなが言葉で理解できるようなデザインにすると、ありきたりなものになりやすいんです。だから期待を超える感動を生むためには、今回の森さんの作品のように、「なんだろうこれ!?」っていう衝撃を与える気持ちを常に持っておかないといけないんですよね。そういった意味で彼女の作品からは、言葉の限界。すなわち、グラフィックのクリエイションは言葉を超えて迫るものを伝える、そんな大事なことについて、我々も改めて気付かされる作品でした。

ヤマハ発動機株式会社 デザイン本部 一色知行
- 次のページへ
存在とは、発信、受信することで生まれていくもの?
存在とは、発信、受信することで生まれていくもの?
コンテストを終えた日比野に、自身にとっての「存在」とは、どういう意味を持つものなのか、改めて尋ねてみた。
日比野:表現者における「存在」というのは、五感から受けたものを、一番器用に動く手先などを使って、その運動による軌跡が残って、視覚なり触覚なりで人に伝えていくことの繰り返しだと思うんですね。その繰り返しによって、「おれはここにいるんだ」ということがわかる。だから発信しなくちゃいけないし、受信しなくちゃいけない。そうすることによって自分の「存在」がわかる、相手との距離感がわかるっていうことなんだと思います。

日比野克彦賞 森未央子
例えば、今回の応募作品が人知れず描かれ、家の中に眠ったままだったとしたら、物理的には存在しているかもしれないが、作者以外の人にとっては存在していないも同然だっただろう。仮に誰かの目に触れたとしても、記憶から忘れ去られてしまえば、それも存在していなかったことと同然となる。「存在」が誰かに記憶されることで初めて意味を成すものであるならば、新たな情報が増え続ける現在の社会において、日比野が言う発信・受信を繰り返すことは、存在し続けるために最も大切なことなのかもしれない。
一方、インターネットを通じることで、物質感がどんどん失われていっているいま、Skype(インターネットのテレビ電話)のキャプチャ画面を重ねた作品で、新しい時代の「存在」を表現し、オーディエンス賞を受賞した松田雅史も興味深い答えをしてくれた。

オーディエンス賞 松田雅史
松田:作品において、物質感を取っ払ったときに、どういう可能性があるんだろうっていうことを考えなきゃならなかったので、その問題をもう一度考え直すいい機会でした。あと、やっぱりインターネットが関わってくると、本当に自分の考え方、アイデア次第でいろんな表現が生まれる可能性がある。でも、いまの時代はこうですけど、何十年後かにはもっと違う表現ができているんじゃないかなと思います。

オーディエンス賞『9,332km遠くの人 15.09.2012~15.08.2012""』松田雅史
足りない情報を補おうとするイマジネーションによって広がる作品力
今回、最終選考に残った作品はどれも、いまあえてグラフィックだからこそ表現できた作品だったように思う。作品の募集に先駆けて公開された「あらゆるグラフィック作品に募集範囲をした理由は?」という動画の中で、審査員の竹井が次のように述べている。
竹井:グラフィックと言ったら二次元ですよね。二次元っていうのはある意味、情報不足なんですよね。三次元でモノを見せるっていうのは、それはそれで魅力があるんだけど、ある意味ちょっと語りすぎで、見る人にストレートすぎる。逆にグラフィックにする、二次元にするということで、情報不足なところを見る人は自分で補おうとする努力をする。その努力とか、どうしてこの人はこう思ったんだろうと模索することが、逆に自分の心の中で作った何か、自分で作ったリアルな感情を持つことができると思うんですよね。(中略)情報が足りないんだけれども、(平面グラフィックは)逆に見る者に喚起するひとつのトリガーを持っているような気がします。
人間の体とはよくできているもので、足りない情報を前にすると、脳がこれまでの経験などを用いて、不足した情報を勝手に補うように働き、それはときとして現実以上に「存在」というものを強く感じさせるのである。この先、ますます物質感が失われていくであろう社会において、グラフィックはこれまでと異なる存在意義を持つようになってきているのかもしれない。それはきっと、30年前に日比野が、段ボールという事実上の立体を持ち込んでグラフィックの概念を変えたように、常に時代の流れに合わせて変わっていくものなのだろう。今回の『GGP』は、その参加者や、関係者たちによって、今連載のタイトル通り、「GRAPHIC IS NOT DEAD」ということを改めて示したコンテストでもあったといえるのではないだろうか。
- 次のページへ
応募者の姿が、プロのデザイナーに与えた影響
応募者の姿が、プロのデザイナーに与えた影響
なお、最後になってしまったが、受賞者に贈られたオリジナルトロフィーについても触れておきたい。今回、両ヤマハの共同デザイン、制作によって作られたトロフィーは、コンテストのテーマである「存在」と、デジタル応募というバーチャルな要素を掛けあわせたハイブリッド仕様。バイクなど様々な機械の素材に用いられる真鍮製の台座、アコースティック楽器に使われるローズウッド製の胴体、上部にはバーチャルの存在感を表すシンボルとしてガラスプレートがセットされ、胴体背面にはSDカードが挿入されている。このSDカードには、3DCGで作られたバーチャルトロフィーのデータが入っており、受賞者は自身のパソコンで見ることができるのだ。物理法則の制限から放たれたバーチャル世界で自由にデザインされたトロフィーを、ライティングを変えながら、拡大・縮小して見ることはもちろん、カードによって持ち運びも可能とした革新的なものだった。

「応募者の作品に負けないように、両ヤマハのデザインチームが必死の覚悟でデザインした」という一色のコメントからもわかるように、このコンテストがヤマハという会社に与えた影響も大きかったようだ。実際、表彰式後に審査員を務めたデザインセクションメンバーの4人に話を聞いた際も、誰もが興奮を隠し切れない様子で、コンテストの感想について饒舌に語ってくれた。最後に、ヤマハ発動機株式会社デザイン本部デザインディレクターの吉良康宏の熱い決意を紹介したい。
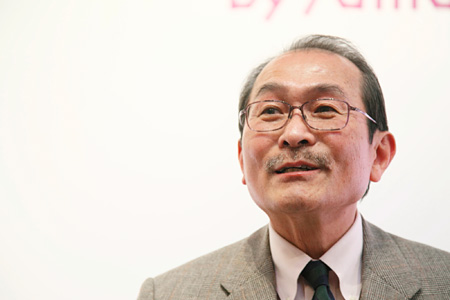
ヤマハ発動機株式会社デザイン本部デザインディレクター 吉良康宏
吉良:デザインっていうのはそもそも感性の領域なんだけど、会社の中ではやっぱり「そんなもんに金を使ってなんの役に立つんだ」って言う人もいるわけですよ。でも、そうじゃないと思うんですよ、もの作りって。やっぱり人に訴える力があるから。今日のプレゼンテーションでも、「あっ、こんなことまで考えてたんだ!」って訴えられたことで、審査への影響もありましたからね。そういう力がデザインにはあるなと思って。それをヤマハとしては、いままでやってきたんだし、これからも続けていきたいなと思いますね。
今回受賞した7人の作家たちの未来、そして両ヤマハの今後についても期待して、次回『GGP』開催の報が届くことを待ちたいと思う。
- イベント情報
-
- 『Graphic Grand Prix by Yamaha』
-
応募期間:2012年6月29日(金)〜9月30日(日)
テーマ:「存在。」
審査委員:
日比野克彦
梅村充(ヤマハ株式会社代表取締役社長)
ヤマハ株式会社デザインセクションメンバー
柳弘之(ヤマハ発動機株式会社代表取締役社長)
ヤマハ発動機株式会社デザインセクションメンバー
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-