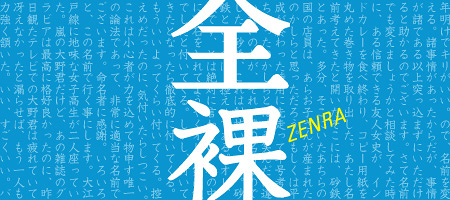vol.273 「上から目線」序説(2010/5/10)

よく、上から目線だよねと言われる。2点ほどさっさと議論をふっかけておこう。まず1点。そう言ってくる君は何から目線なのか。唐突にその人の立地・アングルを決定付ける行為、それこそ上から目線ではないのか。もう1点。上から目線は、どうして悪いものとして扱われるのか。斜め目線とか、下から目線とか、一緒だよね目線とか、いろいろあるんだろうが、その中で上から目線だけがそれはちょっといかがなものかという扱いに追いやられることに、納得できる説明が欲しい。
冷静な分析と偏った分析のどちらかに押し込む作法をそろそろ止めにしたらどうか。分析する当人も、これは2つのうちのどっちだと理解した上で発しているようで気色悪い。つまり、自分の引き出しには2種類あって、「ああこれはそうだよね」という冷静、「ちょっとそれ許せない」という異議、この2種だけを使い分けている。自分に甘い・優しいというのはその人なりの身のこなしだから問いつめる事なんて出来ないけれども、この、自分の分析力への緩慢については、近辺でうろつく知人群にそれなりの危害を加えている事に、そろそろ気づいてくれないだろうか。
人であろうが、消防車であろうが、バナナであろうが、そこへ向かう分析というのは、冷静でもあり偏ってもいる。混在するのが常だ。頭の中に、NHK(1 チャンネル)と2ちゃんねるが合わさっているのが常態であるべきで、それを区分けして、公的な発表と私的な野次に変換するのは、白スーツの蓮舫もさすがにビックリの仕分けであろう。しかし、それに気づこうとする気配はない。これはこういうことだからと涼しい顔をして、次の日にちょっとこれはどういうことと青筋を立てている。それは混ざろうとしない。
どちらかが際立つと重宝される。ワイドショーのコメンテーターを見ていれば分かる。絶対に冷静か、絶対にキレているか、どちらかだ。そういう人が、キャラクターとして認知される。逆に言えば、簡単に特徴付け出来なければその位置にはいられない。それはテレビの中の話。外で同様のアプローチを踏襲する必要は無い。それなのに、踏襲する。
上から目線だよね、というのは、両極のどちらかに何もかもを置いておきたい人が議論を放り投げたい時に使われる言い方なのかなと思えてくる。冷静か偏屈のどちらもなく混色している意見を見つけると、「知りもしないくせして俯瞰しやがって」という見方で、上空へと排他する。困ったものだ。
ある対象に向かって、イラッとして、理解して、憤怒して、許す。万事は、こうやってグラグラと揺れていくんじゃないのか。その後で意見を発すると、どうしても俯瞰した言い方になる。それを、上から目線だと片付けられる。何なんだよそれは。彼等なりの定義では、上から目線とは「何もかも知ったかのように物事を決めつける」ことのようだ。最後に冒頭の復習。人の発言を上から目線だとするその行為こそ、君の言う「上から目線」の定義にピッタリあてはまると思うのですが、そこのところ、いかがでしょうか。
vol.274 国民の声はどこから聞こえるのですか(2010/5/17)

数日ほどネットも新聞も見られない環境にいて、ようやっと見られるようになったと斜め読みで振り返りにかかると、そこでは谷亮子が既に出馬することになっていた。なんだこの前提は。一昨日から四国がオーストラリアです、と言われたくらいの前提だ。谷亮子の出馬を知る、という希有なタイミングを皆と分かち合えなかったのが悔しい。「地球を覆うほどの愛で」と奇怪なスケールを持ち出せば、「小沢先生には田村亮子時代からずっと応援をしていただいて」とお得意の過剰な自己認識のプレゼンが始まる。自分で、田村亮子時代、である。「前人未到の四連覇です」と自ら言ってしまうアレは健在だ。
谷亮子について話せば長くなる。別の機会に譲ろう。気にしたいのは、国民の声、というやつだ。インスタントに仕上げるには格好の的である「街を歩く国民の声は……」というお馴染みのアプローチ。「片手間でやられちゃ困るんだよね」「受かってから勉強しますじゃ遅い」「あんなの客寄せパンダ」と予想通りの非難が飛び交った後で、わずかな賛同者として若い女性が言った。「スポーツ選手なら、政治家と違って市民の目線が分かるはず」。
市民の目線って、なんなのだ。だれなのだ。どこなのだ。この人は、それを明確にせずに断言する。僕はこう思う、市議会議員から県議会議員になってようやく国会議員に辿り着いたとか、国会議員の秘書として引っ付き回り、ようやく先生から独り立ちを目指す許可を得たとか、こういう人のほうが絶対的に市民の目線を知っているはずだ。二世議員を嫌がる世論には賛同するものの、政治に向かってくる市民からの声を聞いてきた人かどうかだけを問えば、よほど二世議員はその声を聞いてきただろう。
今いる政治家と違って……、というような言葉をどうしてすぐに発してしまうのか。中がダメだから外から連れてくれば良くなるかもね、という即断が、結局、中を更にダメにしていく。次回もまた、今の政治家はダメだから、なんて繰り返し言うのだろう。今の政治家を誰が選んだのかをどうやら振り返れないらしい。おそらく頭が悪いのだろう。再び、私たちの目線を分かってくれる人を、と繰り返す。
主婦の井戸端会議はあくまでも主婦の目線だし、会社の給湯室での雑談はあくまでも労働者の目線だ。だから、どこだ、どこにあるのだ、その市民の目線というのは。
そんなものはない。誰かの目線は誰かだけの目線だ。政治家は国民に選ばれて政治を代行する。ならば、その目線の種類を沢山浴びて沢山知っている人に託すべきだ。分かってくれそう、ではない気がする。そう考えるとスポーツ選手というのは、均一に揃った目線ばかりを浴びてきた人だ。勝てば熱く、負ければ冷たい目線。それは、浴びた者にしか味わえない特別な目線かもしれない。だけども、それと、そこから離れた誰かだけの目線の集積は、目線として最も離れた所にあるんじゃないのか。
差し向けられたマイクに向かって「スポーツ選手なら、政治家と違って市民の目線が分かるはず」なんてひとまず放ってしまう個人と、それを賛成意見の骨子として流してしまう大衆、その隙間の数多を気にしないから「地球を覆うほどの愛」を受け入れてしまう。これは恐い。族議員と二世議員による利権政治より恐いかもしれない。何が悪いかが見つけようとせず何となく良さそうに見えているという状態、例えば自分の友人との付き合いなんかに準えれば分かると思うけれど、それが最も脆いのは間違いないじゃないか。
vol.275 がっている(2010/5/24)

チューしちゃったの、と終電一本前に飛び乗った女子大生が早速友人に電話をかけている。どうしようどうしよう、と慌てている。どうやら互いに別に付き合っている人がいるのに、雰囲気でそうなってしまったのだという。電話口の相手が正式な返答をする前に、彼女は言い訳を繰り返す。いい雰囲気だったんだもん。千恵美にはわからないと思うけど、と相手に何となく失礼な発言をつないでいく。でもね、あのままだとそれ以上のことになってしまいそうだったの。もうどうしようどうしようねぇどうしたらいい。
この人は、慌てているのではなく、慌てたがっている。電話がルルルと呼び出したときから、慌てていこうと決め込んでいる。慌てて、戸惑って、どうしたらいいか分からないという思いを一方的に伝えよう。こういう「がっている」がやっぱり苦手だ。泣きたがっている、怒りたがっている、寂しがりたがっている。この手の、自分の感情を自分の手で手繰り寄せていく企みには一切付き合いたくない。そのかわり、泣いてしまった、怒ってしまった、淋しくなってしまった、には懸命に付き合うべきであって、その差の見極めを正確にしていかないと、自家栽培した感情に振り回されてしまう。んなのは、ご免だ。
彼女は、チューしてしまった彼に、よく恋愛相談を持ちかけていたのだという。それを彼が後日、別の女友達に、アイツがしょっちゅう恋愛相談を持ちかけてきて正直ウザいんだよと言っていたことを知り、それについて怒っているのだという。そういうのってヒドくない、と電話口に問いかけて、返答をする間を与えずに、ヒドいよねと連呼している。ドラマは「予定通り」急転する。それでも彼と会っていると、何だか気を許してしまうの。だから今日もチューしてしまったの、分かるかな、と聞いている。今度は答える間を与えている。
この場合、相手は曖昧ながらも肯定の方向の返答をするしかない。この5分くらい、この女性は、自分で慌てる為の外堀を固めてきた。どうしよう、と思いたいのだ。分かるかなと問いかけて、その答えとしてもらいたいのは、まあその気持ちは分からなくもないけども、である。おそらくその手の返答をしたのであろう、女性は更なる加速で慌てふためいている。そして、どこか満足げである。
感情が先走るのは致し方ないことだ。でも、感情が先に用意されているのは、それとは大きく違う。こうすればこうなれるだろうという心の調整に付き合うのは億劫だ。占いなんてもんを一秒も信じないが、人はどこそこの占いが当たるのとウルサい。でもあれは、こうなるという予想ではなくって、「こうなりたがっている」という現在の自分とのリンクだから、そこまで劇的なものではないのである。それこそ「がっている」信号をキャッチすればいいのだ。
自分が降りるころになっても、彼女の話は延々と続いていた。話が明らかにループしている。混雑するも静かな車内に、チュー、ウザい、でも、どうしよう、チュー、がこだまする。それなりに有益だった一日が、彼女の感情強制整理サイクルに付き合わされたことで霞んでいく。小腹が減っていたので駅前のコンビニでおにぎりでも買って食いながら帰ろうかと思ったがどうにもそんな気になれず、野菜生活を吸いながら、とぼとぼ帰路についた。
vol.276 なう・あんど・ぜん(2010/5/31)

シューカツの履歴書を覗くと、趣味・自己PRの欄にとりわけ目立つようになったのが「1人カラオケ」と「散歩」なのだという。かつては「100人規模のサークルをまとめた」「海外放浪旅で様々な現地の人と交流を持った」だったと考えると、途端に個体だけでどうにかする動きが強まったということか。僕がいればこれくらいのことが出来ます、ではなく、僕は僕のことを誰にも迷惑かけずに僕だけでやり遂げます、ということなのか。大きく出るよりも、小さく完結出来る人間を求めるようになったのか。別にどうでもいいけれど。
確かに、「1人カラオケ」が好きだ、と漏らしてくる人間に何人も出会う。しかし、それは厳密に言うと1人カラオケではないのではないか、といつも思っている。1人でカラオケに行って、歌って、そのことは自分以外誰も知らない、という形を守り抜けなければ、それは1人カラオケではない、としたい。なぜならば、昨日1人カラオケ行ってたんだよね、という報告は、目の前で半端な熱唱を聴かされるカラオケボックス内の違和感と、大小の差はあれど同様の質感だから。
え、1人で行ったのー、というお決まりの返答をしてはならない。何歌ったのなんて間違っても聞いてはならない。報告を受けたならば、そうなんだぁ、昨日は夕方から小雨がパラついたよね、雨には降られなかったかな、と返してやればよい。相手はポカンと口を開けるだろう。本当は「1人なのにリンダリンダをジャンプしながら熱唱しちゃった(笑)」とか、「バラードをしっとり歌い上げていたら店員が入ってきて何も言わずに烏龍茶を置いて去っていった(笑)」とか、自分なりに振り絞った笑い話をかましたいのだ。申し訳ない、面白くないんだ、その話。
本人がイレギュラーなつもり、でも、聞くこちらにとっては完全にレギュラーとなっている案件について耳を傾けるのは、本当に苦痛だ。逆に言えば、話なんてのはそこを逸らせばすぐに面白くなる。サークルで100人をまとめたけれども101人目に難航したとすれば、その話を聞きたい。その話は絶対に面白い。 100人乗ってもダイジョーブなイナバ物置に、もう1人乗ったら音を立てて壊れてしまった。こういう話こそイレギュラーなのである。
個性は英語でイレギュラーと訳すんでしょうかというような昨今ではあるのですが、世の「変わってること」って、とりわけ変わったことなんかじゃありませんですわよね、と日々思う。例えば、いや実際にあるのだと思うけれども、「1人カラオケなう」というつぶやき、この手のはた迷惑なジャイアンリサイタルまがいのアピールに、うわぁキミ変わってるね、個性的だね、と褒め称える人事部なんてのがいるんだろうか。いるんだろうな。
誰にも言わず1人カラオケに勤しんでいる人がいたら、僕はその人のことがとても好きだ。その人は、『世に蔓延る「エセ1人カラオケ好き」が吐き出すことで築き上げられる1人カラオケの安っぽいイレギュラーの形成』に頭を抱えているに違いない。どうしたって見つけることが出来ないその本家の存在を信じつつ、 1人カラオケ好きの戯言に耳を傾けない運動を自主的に推進していこうと思っている。
- フィードバック 0
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-