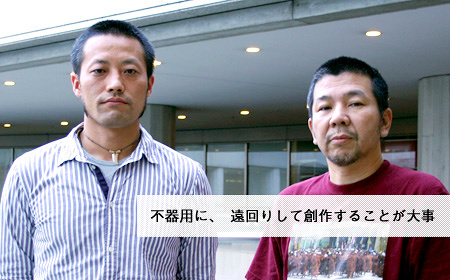7月23日から8月1日まで、埼玉県川口市で開かれる「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2010」。2004年より、世界中から「エンターテインメント性とデジタルの新たな表現の可能性を感じる」作品を公募し、次代を担うクリエイターの発掘を目的に毎年開催しているイベントで、今年も多くの優れた作品が集まっている。 このたび、その長編部門(国際コンペティション)に『未来の記録』を出品した岸建太朗監督と、岸さんが師事し、影響を受けてきたという「遊園地再生事業団」主宰の宮沢章夫さんに対談を行なっていただいた。映画や演劇、小説、そして眠りや「場所」といったテーマを軸に、さまざまな話題を自在に行き交う刺激的なお話を、ぜひご一読いただきたい。
(インタビュー・テキスト:小林宏彰 撮影:安野泰子)
100年前も、100年後も「変わらないもの」
―まずは宮沢さんに、岸監督の『未来の記録』をご覧になった感想をお伺いしたいと思います。
宮沢:これ、すごく時間をかけてつくった作品だよね。
岸:3年半かけてコツコツつくってました。
宮沢:そうなんだね。当然だけど、制作に時間かけることの良さと、一瞬でつくりあげる良さの両方がある。まあ、僕なんかは瞬発力でやっちゃうほうです。長くやっていると飽きちゃうから(笑)。
ただ、表現するメディアによって違いがあると思っていて、映画の場合、撮影に時間をかけると映像の雰囲気がだんだん変化していくでしょう。登場人物が映画のなかで年を取っていっても面白いだろうしね(笑)。

『未来の記録』より
―岸監督が『未来の記録』を撮り始めたきっかけは何だったのでしょう?
岸:何かを継続していく過程で、技術力が向上して以前よりも上手になった実感を持った時、人は何も喜ぶばかりではなくて、やっていることをイチから考え直そうとすることがあると思います。当時の僕もそうした壁にぶち当たっていました。確かに上手くなったかも知れないけれど、「このままでいいのか」という気持ちが高まっていたというか。
そこで思いを馳せたのが、最初に映画を撮った人、リュミエール兄弟のような人でした。彼らがどんな目線で映画を眺めていたのかということを想像したんです。今とても便利な世の中になったけれど、映画の創世期とまるで「変わりようがないこと」があるとしたらそれは何だろうと。例えば「カメラがあって被写体がいる」という、映画の基本的な関係は少なくとも変わってないんじゃないか。
でも、それについて何を知っているのかと考えると、やっぱりたくさんの疑問が残った。むしろ自分への疑いのほうが強かったんです。だから分かった気になっていることに対して「本当に?」という疑問符を投げかけることから始めました。とにかくその場所に行って、この目で見て、直に触れることだけは確かな気がしたので。でもいちいち合理的に進まなかったから、普通はあり得ないような間違いもたくさんしたと思います。
「合理的」につくられた作品は、本当に面白い?
宮沢:台本は、きちんとつくって撮影したの?
岸:一応ありましたが、状況に合わせてその都度つくり変えていきましたね。即興でつくられたシーンとそうでないシーンが、自然に共存するにはどうしたらいいのかが当面のテーマでした。

宮沢章夫
宮沢:ジャン=リュック・ゴダールが『勝手にしやがれ』を撮ったときもそうだったけど、「即興を活かして映画を撮る」という方法は確かにありますね。演劇にしてもそうで、制作するのに最も合理的な方法とはどんなものか、これまでも長い時間をかけて映画史にしろ、演劇史にしろ、方法が蓄積されてきたけれども、そうして出来上がった「型」にはめて作られた作品が本当に面白いのかと。そのことを、あらゆる作家は考えてきたと思うんです。
岸:出来上がった「型」の中でつくることはある意味ではとても楽なんですけど、そもそも楽をしていいのか? っていう気持ちが強かったんだと思います。先人たちは何も無いところからアイディアを絞り出したんじゃないだろうか、という想像がまずあって、できれば自分達もそうありたいし、そうあるにはどうしたらいいのか? ってことを強く求めました。幸運なことに『未来の記録』は自主映画であったし、金銭面を除けば商業的な作品よりフットワークも軽いですから、手法や構造をイチから疑ってみたり、何よりやってみることができたんです。
『未来の記録』では俳優とスタッフを兼任している人が多いんですけど、役職とか役割も疑ってみようとしたんです。撮られる人は、むしろ撮ることから学べるんじゃないかという。だからこの人はこの役割、ということをあえて限定しなかったんですね。そしたらもろもろの担当がハッキリしていないものだから、本番に小道具を持ってくるのを忘れちゃったりして(笑)。
宮沢:それ、ダメじゃん(笑)。
岸:はい。役職が決められた意味が実感できました(笑)。

『未来の記録』より
宮沢:岸とは、舞台の映像なんかで一緒にやってそばで仕事を見てきたけど、すごく不合理というか、計算してないっていうか(笑)。だから半分くらいの期間で撮れたのかもしれないよ(笑)。
岸:これは自分の傾向でもあるのですが、僕、編集ソフトとか機材のマニュアルを最初に読まないんですよ。いつも実際に触ってゆく内にだんだん理解してゆくんでけど、その分デタラメに覚えてしまうことも沢山あって(笑)。でも、何かを「覚える」と言うとき、実はその過程が一番面白いんじゃないかと思っているんです。ついつい回り道を選んでしまうのはそういう理由があるかも知れない。そういった、過程を積み重ねながら少しずつ溜まってゆく感触や実感があるなら、それに費やした時間そのものだって「いつか画面に映り込んでくるんじゃないか」という、何かロマンのような気持ちがあったんです。
宮沢:合理的ではない方法でつくることの魅力も、もちろんあると思うんだよ。それぞれの作家自身が、自分の資質に合ったつくり方をしていれば自然に個性は出てくる。そして、観客が魅力を感じるのって、そうした作家の個性が隠しても出現してしまう作品だと思いますね。
睡眠異常から発想した、「眠り」から現代を描く新作
―撮影期間中、岸監督は10日間も眠らなかったことがあるそうですね。それはなぜだったんでしょうか。
岸:単純に眠っているヒマがなかったこともありますが(笑)、それは実験めいた、ある種の儀式めいた意味合いもありました。撮影者が自分の限界を遙かに超えた状態で撮った映像があるとしたら、それは一体どんなものなのか、僕自身が見てみたかったという。これも映像を「撮る」ことの原初から映画を眺めてみたいという意識と通じていると思います。

岸建太朗
―宮沢さんも、今年の10月に公演を予定している新作『ジャパニーズ・スリーピング』では、「眠り」をテーマに据えていらっしゃいますね。
宮沢:僕は睡眠異常なんですね。だいたい3時間ほど眠ると目が覚めてしまうんです。それはなぜなのか? という疑問から睡眠に興味を持ったんですが、結局人が生きる仕組みとかなり深く関係しているのではないかと。そこから、眠りを通じて「現在」について何か描けないかと思ったんです。そもそも、近代以降でしょう、8時間睡眠が当たり前になったのは。睡眠は当然、産業と結びつくんだけど。
あるいは100年前と現代では、夢の持つ構造じたいは変わっていないけれども、夢に携帯電話が登場したりする枝葉の部分には現代性があらわれている。その「変わるもの」と「変わらないもの」を見ていくことで、「現在」をなにか別の姿で描くことが出来るかもしれない、と。
―宮沢さんが、その100年も変わらない「眠り」や「夢」を、改めて今取り上げる理由とは何なのでしょう。
宮沢:その「変わらない」ことが、我々を拘束している部分もあると思うんです。自分たちは現在、豊かな時代に生きていると思っている。確かに一面ではそうです。ただ新しい種類の貧困もまた確実に層として出現している。例えばフリーターやニートが社会問題になるとか、それこそ現在的な貧しさの象徴でしょう。それをどう描くか。通りいっぺんではつまらない。「夢」や「眠り」を通して描けないかと思うんです。
新宿、渋谷、秋葉原…変わり続ける東京の「象徴」
―東京の街から受ける「貧しさ」とは、具体的にどういったことなのでしょうか。
宮沢:そうですね、僕はしばしば、新しくて刺激的な文化が出現する場所はどこなのか、と考えるんです。その際に、何というか今までの枠組みとは違った考え方をする必要があるんじゃないか、と思っていて。
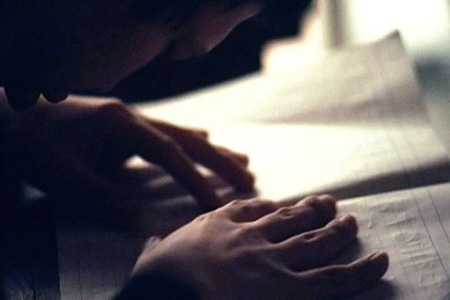
『未来の記録』より
―「今までの枠組み」とは?
宮沢:ある時代の新宿や、ある時代の渋谷というひとつの大きな盛り場は、その時代を「象徴」していました。でも、その「象徴」している、ということには、今の若者はリアリティを覚えないのかもしれない。
では、若者にとっての秋葉原はどうなのか? 2年ほど前に加藤という男が秋葉原で無差別通り魔殺人を起こしたわけですけど、そのとき彼は、東名高速道路の御殿場あたりから来て、横浜あたりで降りるんです。そのあと国道246号で秋葉原を目指すわけですが、その途中で渋谷を通過する。渋谷で渋滞したことに対して腹を立てる。その模様を逐一ネットの掲示板に携帯電話で書き込んでいる。それではなぜ、事件を渋谷で起こさなかったのか?
もちろん、彼の行動を肯定するわけでもないし、殺された人たちに対して許しがたい犯罪行為であると思うけれども、不謹慎な言い方をすれば、秋葉原の交差点にトラックで突っ込むよりも、渋谷のスクランブル交差点に突っ込んだほうがより多くの人が亡くなったかもしれない。だけど今、ある憎悪を抱えた者がそれを解消しようとする場所が秋葉原であったことの意味を改めて問い直すことは、すごく興味深いことだと思っています。そしてその背景には、さっきも少し話した非正規雇用を含めた労働状況、それから2000年代に入ってからの小泉内閣以降の新自由主義を背景にした、この国に新たに登場した「貧困」や「格差」があるでしょうね。
- 次のページへ:
4/4ページ:ものすごくゆっくりと「見る」。それが大事
「祈る自由」すらない場所
―岸監督も、「場所」から想像力を喚起していく作家ですよね。『未来の記録』は、ある部屋で起こった出来事の記憶をきっかけにドラマがはじまります。この筋立てに影響を及ぼしたのは、どんな「場所」だったんでしょう?
岸:宮沢さんの『ニュータウン入口』という作品のリーディング公演を観に行ったとき、僕は深い感銘を受けてイスラエルに行こうと決意したのですが、劇場を場所として考えたとき、一人の若者に海を越えさせてしまう力が働くことがあるのだと思います。場所が誰かの想像力を喚起させて、思いも寄らぬ行動を起こさせるというか。『未来の記録』の着想もそれととても良く似ているんです。
『ニュータウン入り口』の観劇後、僕は本当にイスラエルに旅立って、エルサレムを拠点にパレスチナを回っていました。ある小さな農村に立ち寄った時のことですが、その村には村民たちが自営するフリースクールがあって、多くの戦傷孤児たちが生活していました。僕は子供たちとサッカーしたり遊んだりしたあと会食に招かれて、「あなたにとって自由とは何か?」というテーマで村人たちと話し合いました。そこである一人の村人が、「我々には祈る自由すらない」と言ったんです。
その言葉が僕の中にずっと残っていて。だって「祈る場所がない」って相当なことだと思うんですよ。僕はそのとき、返す言葉が見つからなくて黙っていたんですが、ずっと彼の訴えに何か返信したいという思いがありました。おこがましいことかも知れませんが、そういう気持ちが『未来の記録』をつくらせたんじゃないかと思っています。

ものすごくゆっくりと「見る」ことの大切さ
―「場所」からインスピレーションを受けてきたお二人ですが、他にも最近の関心事があれば教えてください。
岸:小説家の中上健次さんが『現代小説の方法』という講演のなかで、アフガニスタンに旅行されたときのことを書かれているんです。現地でガイドと待ち合わせしていたらその息子が来て、父親から「明日改めて連絡をする」と伝言があったと。で、安心して待っていたんだけど翌朝も父は現れなかった。息子はまた探しに行くと言うんだけど、そもそもの探し方が非合理で、翌朝も人が溜まる場所に行ってみるというだけだったそうなんです。見かねた中上さんは、こちらから父親に電話を掛けるとか、何か合理的な解決法を教えてあげようとしたのですが、そのときにふと、「これは現代小説の問題なんじゃないか」と気づいたという一節があるんです。
だいたいの小説は、密室で電話連絡を待っているような状況から始まるのだと中上氏は言います。そういった移動のない状況を小説で書こうとすることーーそれは心理劇なんだと中上氏は続け、「小説を阻害するもの」と仰っているのですが、僕はそのことを「映画を阻害するもの」と言い換えて捉えました。
僕の制作の仕方は、実際にそこに行って、見たり触れたりしながら実感したことをヒントに物語を紡ぐものだったので、プロの方から見れば随分無駄の多い現場だったと思います。でも良い悪いは別として、思いも寄らぬ方向に映画が進んで行った感触があって、今考えると何か不思議なんです。自分がつくった映画ではない気さえして。
宮沢:その中上健次の文章は僕も読んでいますが、非常に感動的なんです。「すぐに手に入れられるものを小説として書いて良いのか」という問題を、近代小説の思考の枠組みのなかで改めて問い直す必要があるんじゃないか、という提起だと思うんですね。
小説という表現のジャンルは何を書いてもいいメディアとして出現し、そのことの自由の中で育ったと考えられます。でも、それでも失われていってしまうものはある。中上健次は、小説について語りつつ、我々が当たり前だと思ってしまっている、日常における「人とのコミュニケーションの問題」を問い直したんでしょう。これは映画でも演劇でも同様の問いが立てられる。電話を使えば簡単にできてしまうことを、ゆっくりと時間をかけて行う。
で、これまでの話を聞いていて分かったのは、岸建太朗は不器用だということです(笑)。人が5分でできることに、1時間もかかってしまうという。でも、これはすごく重要なことなんです。普通はサッと通り過ぎてしまうものを、ものすごくゆっくり見ているわけですから。
不器用な人は、目的を達成するのに時間がかかる。でも、時間がかかった分、きっちり自分の血肉にしている。それは作家としてとても大切なことだと思うし、それこそが中上健次が言おうとしていた、芸術作品が本来持っているべき力なんじゃないかと思います。
- イベント情報
-
- 『SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2010』
-
2010年7月23日(金)〜8月1日(日)
会場:SKIPシティ 映像ホール・多目的ホール他(埼玉県川口市)『未来の記録』上映
2010年7月24日(土)17:00
2010年7月28日(水)11:30
上映時間:91分
- プロフィール
-
- 宮沢章夫
-
1956年生まれ。劇作家、演出家、小説家。多摩美術大学中退。中退後、24歳でさまざまな種類の執筆業をはじめる。1980年代半ば、竹中直人、いとうせいこうらとともに、「ラジカル・ガジベリビンバ・システム」を開始。その作・演出をすべて手掛ける。1990年、「遊園地再生事業団」の活動をはじめる。その第2回公演『ヒネミ』で、1993年、岸田國士戯曲賞を受賞。その後、舞台作品多数を手掛け、ほかにもエッセイをはじめとする執筆活動、小説発表などで注目される。2000年より、京都造形芸術大学に赴任。現、早稲田大学教授。
-
- 岸建太朗
-
1998年、劇作家宮沢章夫氏に師事し、演出助手に従事する。2002年より「演劇映像実験動物黒子ダイル」を旗揚げし、数本の自主映画、PV、ネットドラマ、演劇の劇中映像などを制作。2007年、ヨルダン川西岸の都市ラマッラーに訪れた時、突然『未来の記録』の基になるビジョンを得る。帰国後、ワークショップ「WORLD」を繰り返しながら『未来の記録』を制作。また俳優としても、映画、演劇、TVドラマなどに多数出演している。
-
- {映画『未来の記録』ストーリー
-
新しい学校を始めようと、幸と治はかつてフリースクールだった古い家屋に住み始める。やがて1冊のノートを手に大勢の生徒たちがやってきた。ノートには、「思い出を残そう」という言葉。やがて過去と現在が交錯し、未来に向かって流れてゆく。時空を越えて物語が展開し始める。
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-