新型コロナウイルスの流行は、生活様式や労働形態、娯楽のかたちなどにさまざまな影響を与えている。オンラインを活用したコンサートや配信による映画公開も、文化の新しい反応の一つだろう。
国際交流基金が主催する『11 Stories on Distanced Relationships: Contemporary Art from Japan(距離をめぐる11の物語:日本の現代美術)』も、そんな反応の一つである。主に新作を発表する10人の現代美術作家、1人の物故作家の旧作によって、「距離を翻訳すること」をテーマに、映像配信というかたちでのオンライン展覧会を開催するという。
そのキュレーションを担当した木村絵理子(横浜美術館主任学芸員)、野村しのぶ(東京オペラシティアートギャラリー シニア・キュレーター)、桝田倫広(東京国立美術館主任研究員)の3名(本展にはもう1名、森美術館シニア・キュレーター近藤健一も担当しているが、本取材では都合があわず不参加)と、出品アーティストで現在はベルギーを拠点とする奥村雄樹を招き、同展について聞くことにした。
本来キュレーターとアーティストの役割は明確に分かれているが、今回は奥村のユニークなアイデアによってその関係性は大きく揺らいでいるという。オンラインという新しい空間で行われる実験とはいったい何か?
(メイン画像:左上から時計回りに、木村絵理子、桝田倫広、野村しのぶ、奥村雄樹)
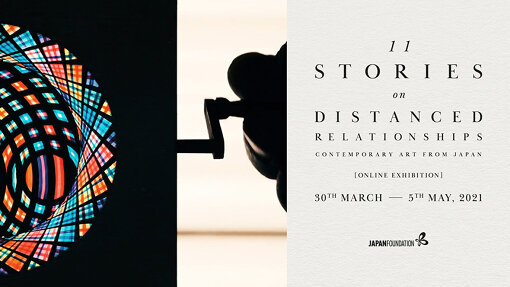
言語や文化の違いによる距離感、コロナ禍のソーシャルディスタンス──「距離」もその人の意識次第で解釈が変わりうる
―『11 Stories on Distanced Relationships: Contemporary Art from Japan(距離をめぐる11の物語:日本の現代美術)』は、日本の現代美術作品を映像配信で紹介するオンライン展覧会です。どんな経緯で企画されたのでしょうか?
木村:主催は国際交流基金なのですが、同基金はこれまでも日本の芸術文化を海外に紹介する取り組みを継続しており、現代美術の分野でも定期的に海外での展覧会を企画してきました。けれども昨年来の新型コロナウイルス感染拡大の影響で、実際にアーティストやキュレーターが外国に行って展覧会を行うことが難しくなってしまっています。
そこで我々4名(この日は不参加だった森美術館シニア・キュレーター近藤健一を含む)がキュレーターとして指名され、映像を主体としたオンライン展覧会を作ってほしいという依頼があったんです。
それが昨年の夏の終わりぐらいでしたが、コロナ禍の状況が比較的落ち着いているタイミングでもあって「もしかしたらリアルな展覧会も行えるのでは?」「オンラインで展覧会をやるとして、観客にどう受け止めてもらえるだろうか?」といった議論や疑問もたくさん浮かび、さらに「映像を主軸に考える際に、たとえば映画のような表現は入れるのか?」と自問自答するようになったんですね。

横浜美術館・主任学芸員 Photo:KATO Hajime
―コロナ禍のなかで、現代美術のキュレーターのみなさんも悩まれたんですね。
木村:そうなんです。企画が立ち上がった初期は、映像に限らず、いろんなメディアを取り込んだオンライン展覧会のあり方を考えてみたりだとか、そもそものフレームについて議論することにかなりの時間を割いてしまいました。
結果としては、コロナも現在のような状況が続いていますから映像メインの内容に落ち着きましたが、現代美術ならではの、映像的な概念に限定されないアプローチを選択することになり、そういったアイデアを実現できるアーティストにお願いしようということになりました。
野村:「距離」というキーワードは、早い段階から出ていましたよね。そして奥村さんからは、展覧会のタイトルが決定するまでの過程を作品にしたい、ついては議論の内容を共有してほしいというリクエストがありました。「私たちが話すことが全部、筒抜けになってしまうのか!」という緊張感を持ちながら企画会議を進めることになりました(苦笑)。

東京オペラシティアートギャラリー シニア・キュレーター Photo:伊丹豪
―そのアイデアも面白いですし、キーワードになった「距離」も非常に今日的で興味深いです。
野村:国際交流を前提とした企画ですから、言語の違い、文化の違いの距離感は常に議論されてきました。さらにソーシャルディスタンスが意識され、行動制限で海外に気軽に行けなくなった状況は、まさにコロナ禍以降の新しい制約ですね。
同時に、こうした制約はネガティブに思えるけれど、本当にそれだけなのだろうか? という話もありました。現在のようにリモートで簡単に会話できなかった頃も遠くに住む友人との友情は薄れませんでしたし、気軽に会えないからこそ思う気持ちが強くなることだってありました。つまり「距離」も、その人の意識次第で解釈は変わりうる。
さらにこの問題は、奥村さんが作品のなかでたびたび扱ってきた「翻訳」にも生じるものでもあります。翻訳するプロセスでは、翻訳者の解釈、その人の主観が入ってくるわけですから。
桝田:そういったテーマに関する長い議論があって、その後、急いで各アーティストに参加依頼をしていきました(苦笑)。

東京国立近代美術館・主任研究員
奥村:僕のところに依頼があったのが、たしか11月中旬だったはず。じゃあ、そのときには距離や翻訳のテーマはある程度決まっていたんですね。
桝田:そうですね。制作期間が短い点、オンライン展覧会のために新作を作るという点でも、かなり厳しい依頼をアーティストにお願いしていると自覚しつつ……。でも、みなさんから快くお返事いただいて心強かったです。
本展キュレーター4人による展覧会づくりのプロセスを映像作品化した奥村。4人を一つの人格のように統合
―そういった状況を踏まえて、奥村さんは新作のための準備を始めたわけですね。事前に作品映像を見せてもらいましたが、とても奥村さんらしい、キュレーターに対してちょっといじわるな内容だと思いました(笑)。
奥村:オンラインで作品を見せるってけっこう難しいですよね。パソコンで閲覧していると、5分ぐらいしたら「メール見ようかな」とか「YouTube見ようかな」っていう誘惑が頭をもたげてくる。

1978年、青森県生まれ。現在、ブリュッセルとマーストリヒトを拠点に制作活動を行う。奥村は、ビデオ、インスタレーション、パフォーマンス、キュレーション、翻訳など多岐にわたる実践に取り組んできた。 Photo:Yuki Naito
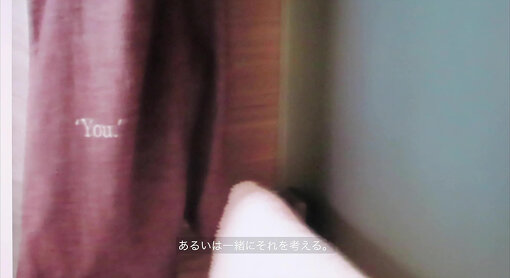
奥村:美術館みたいに没入して鑑賞できる環境とは言い難いですから。それを逆に利用して、それこそCINRA.NETみたいなウェブ記事のフォーマットで複合的な作品に取り組もうと最初は考えたんですが、僕のなかでうまく歯車が噛み合わなかった。
そこで、オンライン展という枠組みとは別のところにフォーカスを移しました。むしろキュレーターが4人いて、一つの展覧会をキュレートするという構造に面白さを感じて、展覧会の英語タイトルが決定されるまでのプロセスを映像作品に変換することにしました。
―作品、奇妙な構成ですよね。4人のキュレーターが1人の人格であるかのように再統合されていて、それをまた別の人の声が物語り直すという。ナレーションはライターのアンドリュー・マークルさんですね。
奥村:もともと僕はインディビジュアリティー(個別性、個人性)に興味があるんです。個人という枠組みって、基本的に肉体の個別性で分けられてると思うんですけど、それを他の基準で分け直せないだろうか、とか。そのために通訳や翻訳の手法を手がかりにしてきました。
今回であれば、4人のキュレーターの言葉を1人の通訳者にすべて訳してもらうことで、複数人による議論だったものを、一つの人格が脳内で自問自答してるように置き換えてみようと思いました。

「冒頭に、ボートを漕いでいるシーンがあるじゃないですか。あの風景はまさに私たちだったな、と思いました」(野村)
―実際にキュレーターの方々の間で行われたタイトルを決定する会議の音源をもとにしているんですよね?
奥村:はい。Zoom上の議論を一旦テキストに書き起こしして、それを再構成しました。スクリプト(台本)というよりも一種のスコア(楽譜)ですね。
もちろん日本語なんですが、アンドリューにはそれを黙読しながら、即興で英語に「通訳」してもらいました。さらに彼の声を日本語字幕にするため、アーティストで小説家のミヤギフトシさんに再翻訳をお願いして。2人には基本的に自由に訳してもらったのですが、人称代名詞に関してはインストラクション(指示)もあったり。
―ややこしい(笑)。
奥村:スコアの段階では、もちろん人格はバラバラのままですが、どれが誰の発言であるかは明らかにしていないんです。いちおう改行で話者が切り替わったことはわかるんだけれど、それぞれ誰かはわからない。
そうするとアンドリューの解釈によって複数の話者が1人のように繋がったり、1人が複数に分かれたりする。ミヤギさんの翻訳でも同じようなことが起こる。声によって人格を統合するといっても、どうしても多重人格性が残るんですけど、その多重性の境目もオリジナルからずれていくわけです。
野村:さらに作品のための映像を撮ったのがアーティストのリー・キットですからね。冒頭に、ボートを漕いでいるシーンがあるじゃないですか。あの風景はまさに私たちだったな、と思いました。4人の異なる人格を持った人物が一生懸命スワンボートを漕いでいるんですが、何処に行ってしまうのかわからない(笑)。

奥村:(笑)。以前、アンドリューによるキットのインタビューの和訳を僕が担当したんですよ。アンドリューの提案で、キットの頭の中に響く複数の声にフォーカスして訳したのですが、諸事情でお蔵入りになった。だから今回の人選は、僕のなかでは必然的なんです。
映像に関しては、キットに「自問自答するときに眺めている景色や繰り返している行為について」というお題を出して、あとは丸投げです。編集済みのクリップをいくつか送ってくれたのですが、スワンボートも予想外だったし、海のシーンも「長っ!」ってびっくりしました。とにかく今回の作品は、3人がそれぞれリモートで進めてくれた仕事を、最終的に僕のところで合体させた結果なんです。
奥村によるキュレーションへの「介入」。キュレーターは作品制作を依頼した自分と、作品との適切な距離が取れない感覚にも陥った
野村:これは奥村さんの意図かはわからないのですが、この作品は展覧会が作られるときのプロセスや関係性に介入していくベクトルも持っていますよね。今回のように11組ものアーティストが参加する展覧会では、大きなテーマはキュレーターが事実上密室的に決めていくのが一般的ですが、奥村さんはそれを盗聴して作品にしているようでもある。
奥村:録音してくれたのは僕を担当している桝田さんですから、桝田さんがスパイ=内通者です(笑)。でも、音源をイヤフォンで聞いていて、たしか野村さんだったと思うんですけど「奥村さん、今これを聞いてるよね?」と急に言われてびっくりしました。「時空を超えて頭の中に語りかけられた!」と。
一方的に介入するつもりが、思わぬタイミングで仕返しされたみたいで楽しかった。そのときの問いかけには後日メールで答えましたけど、その経緯も作品に入ってます。だから語り手の人格には「ユウキ」という他者もちょっと侵入しちゃってる。
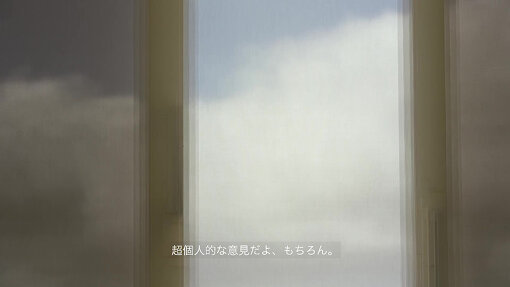
奥村:それに関連して聞きたいんですが、僕が送ったメールはみなさんの暫定的な結論に異議を唱えるもので、それが最終的な展覧会タイトルにも波及したと思うんです。それについてはみなさんどう思いますか? まさにキュレーションへの介入になったのかなあと。
木村:キュレーションって、そもそもキュレーターだけでやるものではないんですよね。アーティストとの会話によって内容はどんどん変わっていくし、アーティスト以外の人たちの言葉にも影響されていく。
今回であれば、作品について私たちが書いた日本語のテキストをイーデン・コーキルさんに英訳してもらっていて、イーデンさんからの反応も私たちの思考に影響しています。
―特に海外だとスターキュレーターみたいな存在がいるから、展覧会の人格がキュレーター個人とイコールに思われるような時もあります。でも、実際にはもっと複合的なものであるわけですね。
木村:もちろん分化してるところも多くありますが。今回の奥村さんのアプローチで面白いのは、キュレーション全体ではなく、タイトルを決めるという部分に限定されてることだと思っています。
それによって議論の方向性が集約されたと感じます。キュレーター的な発想だと、タイトルを決めるときも、広報的なアピールや、全体的なフレームとの照らし合わせなど、いろんな要素を同時に考えていくので、しばしば議論がまとまらない(笑)。奥村さんの介入によって、逆にうまくまとまったところがあるかもしれない。
桝田:奥村さんの作品を見て私はけっこう戸惑ったんですよね。というのは、自分が喋った、自分が聞いたと思っている記憶と、作品内で語られていることがちょっとだけずれているように感じたからです。
そのことを作品解説に書いたら、奥村さんから「原文に創作は含まれていません。みなさんのZoomでの議論やメールからすべて抜いています。」と返事がありました。でも、私の主観からすると、文脈が変わり、声が変わり、文字が変わったことで、少しだけ別のもののように感じられたんです。
作品についてのテキストを書くときも戸惑いを感じました。なぜなら私自身が作品に巻き込まれているせいか、客観的な記述に徹することができなかったからです。
ここにも距離感の問題が現れていると思います。つまり、作品制作を依頼した側である自分は、半ば作品に巻き込まれ、作品との適切な距離が取れない感覚に陥っている。奥村さんの作品はそういう戸惑いを与えるものになっています。私が感じたような戸惑いがオーディエンスの方々にも伝わればすごくいいなあと思っています。

空間的配置を頼りにできないオンライン展覧会のキュレーション。美術館の展覧会との違いは?
奥村:ところでオンライン展覧会の形式はどうですか? フィジカルな空間と、ウェブページという平面的な空間でキュレーションするのは、まったく違う経験だと思うんですよ。
桝田:今まで自分がやってきたことと全然違うなとは感じています。普段の美術館での仕事において頼りになるのは空間的な配置です。
作品の配置を通じて何かしらの文脈を作り、展示空間のなかでいかに具現化するか、というのが自分の仕事の中心だったわけです。つまり作品同士のわずかな距離の取り方によって見え方を変え、作品間の関係性を演出し、ある種のナラティブを作っていく。
そうした物理的な空間の中で展覧会を作るのとはまったく違う思考方法で作品について考えなければいけなかったことが、私にとっては非常にチャレンジングなことでした。
奥村:なるほど。オンライン空間に固有の特性に応答した、「ウェブサイト・スペシフィック」と呼べるような作品の可能性もありますよね。実際に今回も、普段から展覧会の文脈、状況、空間に合わせてアプローチを積極的に変えてきたアーティストが選ばれている気がしました。
木村:それは最初の段階で交わした議論でも大きなトピックの一つでした。新作をお願いする以上は、展覧会で我々が伝えたいある種の距離感や、それに対するもどかしさの感覚を含めて共有できるという意味での「スペシフィック」を求めたところがあったと思います。

リモートの環境は内輪的になりやすい? オンライン展示ならではの迷いや試行錯誤と、可能性
―展覧会が複合的な生態系、エコシステムであるというのは私の実感でもあります。だからこそなのですが、そこには想像しえない他者がいる必要があるとも思うんです。
コロナ禍以降多くの企業がリモート体制になり、オフィス自体を持たない業態に移る例も現れています。「それでも仕事はできる。生活との両立も可能。便利だ」というポジティブな声もありますが、いっぽうで新しく入社した人、転職してきた人が会社のなかで新しく関係性を作っていくのが難しい、という声も聞きます。この問題は、リモート授業を積極的に行っていた大学などでも起きていることでしょう。
これを展覧会、あるいは現代美術界みたいなものに当てはめると、そもそもコミュニケーションしやすい既知のアーティストがコロナ以降の展覧会に頻繁に参加する状態になり、多様性が生まれにくくなるということはないでしょうか? 実際、数多あるオンライン展覧会が内容も似ていて、参加作家もかぶっているという例が散見されます。
木村:質問に対する答えを象徴するアーティストとして、吉田真也さんが今回出品しています。彼は昨年開催されるはずだった『札幌国際芸術祭』にも選ばれていましたが、そもそもキュレーターと仕事をするのもほとんど初めてで、私自身も今回初対面でした。そういう意味では、コロナ禍以降に新しく会社に入った人と似た立場と言えるかもしれません。

木村:そこで生じる緊張感はじつは私の側にもあって、どういう風に話を聞こうかな、コミュニケーションしようかな、と模索し続けています。また、島根県に住んでいるので、リアルな打ち合わせもなかなかできない。
しかしそういった困難さを感じつつも、結局は「よい作品を見せたい」というモチベーションで動いているのがキュレーターだと思うんです。既得権益的なものを持った作家だけが生き残っていける、というようなことはないんじゃないかなと私自身は信じています。
奥村:もともと作品って作家から切り離されたもので、作品から始まる関係性が美術にはあると思うんですよ。もちろん会社や大学と共通する対人的な繋がりもあるけれど、それとは良い意味で微妙に違うところがあるんじゃないかなあ。
木村:亡くなっているアーティストの作品も、存命のアーティストの作品も、展覧会では等しく扱われますし、作品を鑑賞する時には、アーティストに直接会うことはほとんどありません。でも、作品を介して私たちはアーティストの深い部分に触れている感覚になることが多くあると思います。
それって一般的な社会生活ではなかなか得られない人間同士の関係性を作品越しに見出しているとも言えると思うんです。今のように、リモートでの交流が主体になった時代では、多くの人が生身の身体と切り離した、自分の別人格みたいなものを作り出して新しい関係性を構築している気がしています。そこに美術が持っている生態系を当てはめて考えることで、発見や活路を見出せるかもしれません。

奥村:僕は翻訳の仕事もしていますが、翻訳にも似たところがあります。死んだ人の文章を扱うことも多いし。著者が存命でも、どちらにしろ既に閉じられた文章だけをたよりにやりくりしていく。そんな距離感で、互いに孤立しながら進行する翻訳の仕事を、僕はとても気に入っているんです。
また、僕は今ヨーロッパにいますが、コロナ禍でリモート生活になり、相手が近くに住んでいても日本にいても、イコールな距離でやりとりしている。それは、人と人との本源的な繋がりと隔たりが社会に実装されたみたいで、個人的になかなか居心地のよい感じなんです。オンライン展覧会でも、作品と鑑賞者が別々の次元にいながら、1対1で正対しますよね。そこにはたくさん可能性があると感じます。


野村:もちろんオンライン展覧会が内輪的になってしまうところはあると思うんですよ。ありていに言ってしまえば、奥村さんの作品も楽屋オチみたいなものだから。
奥村:そうなんですよね(笑)。
野村:そういった限られた関係性から思考を始めていることも否定できないわけです。展覧会を作るにあたって私自身は努めてアノニマスな存在であろうとするタイプなので、奥村さんの作品によって可視化されることに葛藤もありました。でも、このアンビバレントな気持ちもオンライン展覧会というこの企画だからこそ生じた制約と挑戦だと思ってやっていますね。
奥村:ご協力いただきましてありがとうございます……! 内輪っていう話が出ましたけど、僕は決してそれが悪いと思ってないんですよね。
誰もが内輪の閉じた関係性のなかで生きているから、その点で響き合えるというか。そして、個々人のパーソナリティーの折り重なりによって歴史や文化は生まれている。
それは美術も同様で、例えば美術史というと固定された、客観的なものと考えがちなのですが、それだってアーティスト、キュレーター、ヒストリアンといったさまざまな人たちの主観性や欲望が相互に作用した結果の産物なんです。その偶発性に、僕はすごく興味があります。

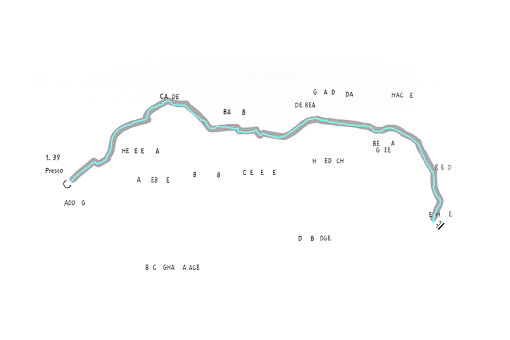
桝田:展覧会を作るってことは、何らかのフレームで区切ることですから、エコシステム自体をいったんは閉じざるを得ない。ただ、そのなかにいろんな要素を含ませておいて、そのフレームの外を想像させることはできるんじゃないかと思っています。
野村さんと違って僕はあまり抵抗感がなかったんですよ。名前を出すことで、キュレーターと呼ばれる人々が展覧会というフレームを区切っているのだと言明することができます。
そのことによって、フレームの「外」の可能性を想像させることもできるからです。展覧会に選ばれた作家がいるのと同時に、選ばれなかった数多の作家がいることが忘却されず浮き彫りになる。それは、展覧会を作るうえでの倫理的な態度を表すやり方の一つなんじゃないかと思います。
木村:フレームを作っているのは私たち(キュレーター)であると表明することが、逆にその先や外にある解釈に対して私たちは介入しません、という表明にもなるというか。
実際の空間でキュレーションを行う場合は、その態度表明の方法も様々にあります。空間のコントロールであれば、この作品はこの高さに置くとか、逆にこの作品の周囲には何も置かないだとか。
でも今回のようなオンライン展覧会ではすべてが等価になってしまって、むしろタイトルの重みが増してしまったりする。結果として、今回の4人のキュレーションの方針は、順路や導線を作らず鑑賞者をなるべく誘導しないようにするとなったわけですが、まだ迷いはありますね。
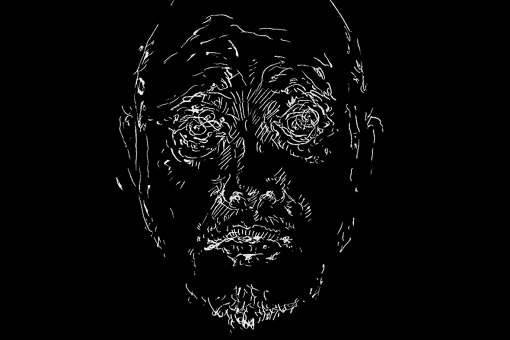

野村:作家名の並び順も迷いましたよね。結局、苗字のアルファベット順にして、この順番にはそれ以上の何の意味もないことを示したり。
奥村:以前、ある展覧会に参加したとき、参加アーティストの名前の並べ方に介入する作品案を出したんですよ。会場やチラシで、日本語表記ではアルファベット順に、英語表記ではあいうえお順にするっていう。和英で2列にすると、ほとんどの場合、別人の名前が横に並ぶことになる(笑)。
木村:どちらの言語でも「あ(A)」の人がトップに来ちゃいますね。
奥村:そうそう!
野村:「あ(A)」で始まる名前の人は既得権益を持っている(笑)。それは半ば冗談ですが、社会を見渡してみると生まれたときから決まっている有利不利というのはどうしてもあるんですよね。だからこそ、それをどう言う風に捉えるか、解釈して自分なりの意味を見つけることが大切ですし、それは大きな判断になります。
「Black Lives Matter」や「#MeToo」のムーブメントがあり、コロナ禍があって、本当にあらゆる局面でマジョリティーやパワーの問題を意識する時代になったと思っています。だからこそキュレーターも作家も、自分たちの責任や持っている力を自覚する必要があり、それを踏まえた表明をしていかなければならないんですよね。
- イベント情報
-

- オンライン展覧会
『11 Stories on Distanced Relationships: Contemporary Art from Japan(距離をめぐる11の物語:日本の現代美術)』 -
2021年3月30日(火)~5月5日(水・祝)
主催:独立行政法人 国際交流基金
参加作家:
荒木悠
潘逸舟
飯山由貴
小泉明郎
毛利悠子
野口里佳
奥村雄樹
佐藤雅晴
さわひらき
柳井信乃
吉田真也
キュレーター:
木村絵理子
近藤健一
桝田倫広
野村しのぶ
- オンライン展覧会
- プロフィール
-
- 木村絵理子 (きむら えりこ)
-
横浜美術館・主任学芸員、ヨコハマトリエンナーレ2020企画統括。主な展覧会に、“HANRAN: 20th-Century Japanese Photography”(ナショナル・ギャラリー・オブ・カナダ、オタワ、2019-2020)、「昭和の肖像:写真でたどる『昭和』の人と歴史」(2017)、「BODY/PLAY/POLITICS」(2016)、「蔡國強:帰去来」(2015)、「奈良美智:君や 僕に ちょっと似ている」展(2012)、「高嶺格:とおくてよくみえない」展(2011)、「束芋:断面の世代」展(2009-2010)、「金氏徹平:溶け出す都市、空白の森」(2009)ほか。この他、横浜トリエンナーレ・キュレーター(2014、2017、 2020)、關渡ビエンナーレ・ゲストキュレーター(2008、台北)、釜山Sea Art Festivalコミッショナー(2011、釜山)など。
- 桝田倫広 (ますだ ともひろ)
-
東京国立近代美術館・主任研究員。主な展覧会に「ピーター・ドイグ展」(2020)、「アジアにめざめたら:アートが変わる、世界が変わる 1960–1990年代」(共同キュレーション、東京国立近代美術館、韓国国立現代美術館、ナショナル・ギャラリー・シンガポール、2018–2019)、「No Museum, No Life?―これからの美術館事典 国立美術館コレクションによる展覧会」(共同キュレーション、2015)、「高松次郎ミステリーズ」(共同キュレーション、2014–2015)など。
- 野村しのぶ (のむら しのぶ)
-
東京オペラシティアートギャラリー シニア・キュレーター。主な展覧会に「カミーユ・アンロ|蛇を踏む」(2019)、「単色のリズム 韓国の抽象」(2017)、「サイモン・フジワラ|ホワイトデー」(2016)、「ザハ・ハディド」(2014)、「さわ ひらき Under the Box, Beyond the Bounds」(2014)、「エレメント 構造デザイナー セシル・バルモンドの世界」(2010)、「都市へ仕掛ける建築 ディーナー&ディーナーの試み」(2009)、「伊東豊雄 建築|新しいリアル」(2006)、「アートと話す/アートを話す」(2006)。外部の仕事に《都市のヴィジョンーObayashi Foundation Research Program》推薦選考委員、「シアスタ−・ゲイツ」(2019)、「会田誠展「GROUND NO PLAN」(2017)。
- 奥村雄樹 (おくむら ゆうき)
-
1978年、青森県生まれ。現在、ブリュッセルとマーストリヒトを拠点に制作活動を行う。奥村は、ビデオ、インスタレーション、パフォーマンス、キュレーション、翻訳など多岐にわたる実践に取り組んできた。例えば彼は1960年代から70年代にかけての美術動向や、河原温といった実際の作家などを取り上げ、再解釈や翻訳によってそれらに介入し、時にはフィクションのような挿話や設定を挟む。その過程で不可避的に生じる主客のずれによって、凝り固まった諸関係は一時的であれ可変的なものになる。近年の主な展覧会に、「29771日–2094943歩」(ラ・メゾン・デ・ランデヴー、ブリュッセル、2019)、「彼方の男、儚い資料体」(慶應義塾大学アート・センター、東京、2019)、「Na(me/am)」(コンヴェント、ゲント、2018)、「奥村雄樹による高橋尚愛」(銀座メゾンエルメスフォーラム、東京、2016)など。
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-





