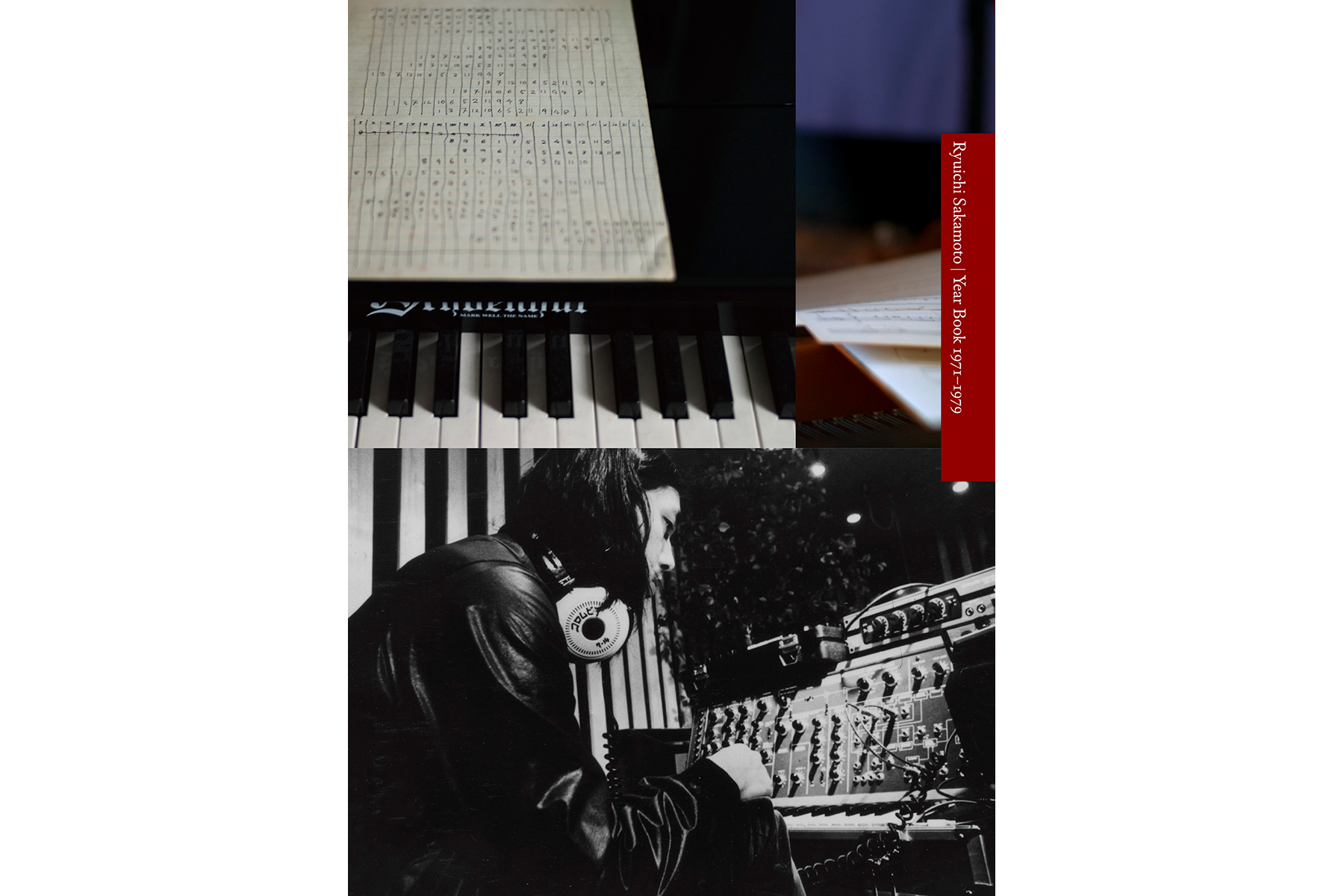クラシック音楽といえば「古典」のイメージが強いが、実際は、いまこの瞬間にも新しい音楽が生まれている、「現在進行形」の音楽だ。アートや映画と同じように、現代音楽もまた、そのときの社会や時代の空気に呼応しながら、変化を続けている。
この記事では、若手作曲家の登竜門でもある『第35回芥川也寸志サントリー作曲賞選考演奏会』の開催を前に、現代音楽に造詣の深いライターの小室敬幸が、いま注目してほしい日本の若手現代音楽作曲家を紹介。
ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』の音楽を手がけた坂東祐大、「Kawaii」カルチャーを作品にした山根明季子、バッハとスーパーマリオを融合させたような作品で注目された梅本佑利、少女をモチーフとした物語性のある作品を発表した向井響、ドラァグクイーンなどクィアをテーマとする作品を発表してきた向井航……。多様な作曲家たちによる表現の片鱗に触れることで、きっとあなたも現代音楽の世界に興味を惹かれるはずだ。
ヨーロッパ的な価値観から音楽を再解体する坂東祐大

坂東祐大 / (C)Shinto Takeshi
『怪獣8号』『大豆田とわ子と三人の元夫』『竜とそばかすの姫』といった映像作品や、米津玄師楽曲での共編曲などにより、作曲家の坂東祐大はジャンルを超えて注目される存在となった。多彩な活動は非常に眩しいが、坂東は一貫して自身の軸が「現代音楽」にあると発言している。
だが、そもそも現代音楽とは何なのか? 「現代の音楽」といえば、現代に誕生したあらゆる音楽が含まれるが、いわゆるクラシック音楽のなかの一分野を指すのが現代音楽だ。英語ではcontemporary classical music(同時代のクラシック音楽)などと表現されるが、「同時代」といいながら第二次世界大戦後から現在までを範囲とすることが多い。平たくいえば、現代アート(contemporary art)の音楽版といったところだ。
坂東は自身のプロフィールで「異化や脱構築による刺激と知覚の可能性などをテーマ」にしていると謳っている。具体的にいえば、初期には生演奏によるサンプリングを駆使した作品を手がけていたが、近年は西洋(=ヨーロッパ)的な価値観から音楽を解体―再構築するような作品が多い。
2025年2月に彩の国さいたま芸術劇場で発表された新作のシアターピース『キメラ - あるはずのないメソッドの空想』では、膨大なリサーチをしたうえで、現在とは異なるかたちで日本が西洋音楽を輸入していたら?……という仮定をもとに、和楽器が西洋の奏法を取り入れたかもしれない、もしもの可能性を実演してみせて観客を圧倒した。
坂東祐大“めまい(2015)”/英語の文章の下に日本語解説があるので必読。終盤にアルフレッド・ヒッチコック監督による同名映画の音楽をサンプリングしている。
坂東祐大“ドレミのうた(2020) - インヴェンション”/西洋音楽の基礎となる「ドレミ」を解体する試み。AC部のアニメーションが加わったことで、音楽のインパクトがより強まった。
必ずしも心地のよい音ばかりとは限らないが、作者のコンセプトを理解したうえで聴くと、面白くなってくる。多くの作品に触れていけば、絶対にあなたの心に響く現代音楽に出会えるはずだ。他の何にも代えがたい刺激的な体験となるだろう。
過剰な消費、少女性や痛みの感覚をテーマにする山根明季子

山根明季子 / photo by Ayano Sudo
坂東と同じぐらい、是非ともご注目いただきたい作曲家が山根明季子だ。出世作となった“水玉コレクション”シリーズは、ある1音(ひとかたまりの音)を視覚的に捉え、その質感を複数の音の集合体によって表現しようとした作品である。
山根明季子“水玉コレクション No. 4 (2009)”
音だけを聴くと抽象的だが、作曲者自身の解説を読むと具体的な視覚イメージが理解できるはず。
山根明季子“カワイイ^_−☆b”/“カワイイ^_-☆”には山根自身によるリアリゼーションとして、楽譜が書かれたバージョンがいくつかあり、この“b”もそのひとつ。
現在はプロフィールにも書かれているように「過剰な消費や管理、少女性や痛みの感覚、ポップ、マスカルチャーに関係する」テーマを取り扱うことが増えた。
テキストで「“かわいい”と主観的に感じる音を出す」とだけ指示された“カワイイ^_-☆”(2019)が象徴的なように、西洋芸術で重視されてきた「完成された崇高さや立派さだけに価値があるのではなく、そうではない表現にも魅力や価値があることを西洋クラシック音楽の世界でも共有できるようになってほしい」という思いが込められた作品が近年は多い。
アニメやネット文化をバックグラウンドにする新星、梅本佑利

梅本佑利
美術でいえばポップアートの延長線上に位置づけられるような作品を手がけているのは山根だけではない。彼女の音楽にも刺激を受けつつ、独自の作品を生み出しているのが梅本佑利である。なんとまだ高校生だった2019年にYouTubeで作品が注目され、そこからプロの演奏家に演奏されたり、作品を依頼されたりするようになったという新星だ。
これまでの代表作“Super Bach Boy”(2020)は、J.S.バッハの無伴奏チェロ組曲と『スーパーマリオブラザーズ』の音楽を融合させたような作品で、なんと2024年にはバッハの本国ドイツで開催される『テューリンゲン・バッハ週間音楽祭』でも取り上げられた。この他にも梅本作品はすでに海外で何度も演奏され、新作を依頼されているのだ。
梅本佑利“Super Bach Boy (2020) for cello”
梅本佑利“Confiteor (2024) - Mass (Volume I)”
彼の作品の根底には日本のアニメやインターネット文化からの影響があるが、自身のバックグラウンドであるキリスト教や合唱という要素も加わってくるのが興味深い。現在、J.S.バッハの“ロ短調ミサ”と同じ構成をもちながらも、アニメボイスで収録されたラテン語の典礼文が基調になる“ミサ曲”の作曲が進んでおり(ただし編曲――再作曲を繰り返す予定だという)、2025年3月の演奏会でその一部が発表された。
少女というモチーフに刺激を受けた向井響、クィアをテーマにする向井航
梅本同様に国際的に活躍しはじめている作曲家として向井響(ひびき)と向井航(わたる)も知ってほしい。
双子なのだが進路は微妙に違い、兄の響は桐朋学園大学を経てオランダとベルギーとポルトガルに留学、弟の航は東京藝術大学を経てドイツとスイスとオーストリアに留学している。

向井響 / ©︎Ayane Shindo
向井響は美術のモチーフとしてみられる少女(≒女神)から刺激を受けた「美少女革命」というタイトルで様々な編成の楽曲――パフォーマーから人形浄瑠璃まで!――を手がけている。2024年に初演された“美少女革命:下弦の月”はAIによって生成された戦う少女たちの物語を薩摩琵琶と語りで描くという内容で、筆者が昨年聴いた新作初演のなかでベストに推したい作品のひとつ。
一方、向井航はかつて尺八を含むカルテット(なんとドラマーは、今をときめく石若駿だ!)で、ジャズのアルバムをリリースしたこともあった。現在は、大学院の博士課程で本格的に取り組みはじめたLGBTIQ+、特にクィアに関するフィールド調査・研究を反映させた作品が中心になっている。

向井航 / ©︎Ayane Shindo
1960年代の米国におけるクィアコミュニティのダンスカルチャーと、2016年にフロリダ州のゲイナイトクラブで起きた銃乱射事件を題材にしたオーケストラ作品『ダンシング・クィア』(2022)は、『第33回芥川也寸志サントリー作曲賞』を受賞した。
向井航『ダンシング・クィア』(2022)初演の動画。中央にはアクティビスト役のスピーカーが語り手となり、著名なアーティストや政治家の言説などから引用した言葉を発する。語り手がメガホンを持っているのは椎名林檎のイメージだという。
2023年に開かれた個展『ドラァグの身体』ではドラァグクイーンが出演するオペラ『NOMORI』を上演し、自らもドラァグクイーンとなって舞台に登場した。さらに2024年6月には、同作を拡張させたオペラ『The Mirror of Nomori』をウィーンで上演している。
もうひとつの「芥川賞」、『芥川也寸志サントリー作曲賞』とは?
『芥川也寸志サントリー作曲賞』は日本を代表する作曲家のひとり、芥川也寸志(1925〜89/※芥川龍之介の三男)の功績を記念して1990年に創設された作曲賞である。2019年に名前が変わるまでの名称『芥川作曲賞』でご記憶のかたもいらっしゃるだろう。
前年度に初演されたばかりの新進作曲家の手による将来性に富むオーケストラ作品を選考する賞で、新進作曲家とはいっても年齢制限はなく、過去には50代の作曲家が受賞したこともある。坂東祐大と山根明季子も実は過去の受賞者だ。
文学界には純文学を対象にした『芥川龍之介賞』があるが、『芥川也寸志サントリー作曲賞』は日本の現代音楽の作曲家にとってはひとつの登竜門となっている。
受賞者には賞金が与えられるのみならず、新しいオーケストラ作品が委嘱されるという特典があり、受賞から2年後の『芥川也寸志サントリー作曲賞選考演奏会』で初演される。
今年は2年前に受賞した向井航の新作『クィーン』〜ユーフォニアム、エレキギター、女声アンサンブルと大オーケストラのための(オルガン付き)(2025)が披露される。
【向井航、委嘱新作を語る】-
パンクカルチャーから派生したサブカルチャーに「クィアコア」というムーブメントがある。1980年代半ばアメリカにて始まった社会/文化的運動で、クィアなパンクス達が、己の権利のため、そして、あらゆる差別に反対するため、声を上げた。前作の『ダンシング・クィア』でもクィアのために戦う様々な人々の声を取り上げたが、今作『クィーン』では声を、よりパンクに、そしてよりクィアに扱おうと考えた。もう一つのテーマには、ヘンツェやルーセルを始め、多くの作曲家が扱ったギリシャ神話『バッコス』を選んだ。バッコスの信女に見立てた女声アンサンブルが、クィアでパンクな饗宴をシアトリカルに、この日限りでサントリーホールに出現させる。
今年の候補作と見どころは? 選考が舞台上で公開される面白さ
向井作品が初演されたあと、第35回となる今年の候補作品が演奏される。3曲を簡単に紹介しよう。
まずは斎藤拓真(1992~ ):『アンティゴネーとクレオン』ソプラノ、アンサンブル、エレクトロニクスのための(2024)だ。ギリシャ悲劇のアンティゴネーの物語をAIによって現代化した作品で、ChatGPTが出力した文章に作曲者自身が手を加えた歌詞が用いられるのだという。しかもアンティゴネーはソプラノが歌うのに対し、彼女に死刑を宣告する叔父クレオンの台詞はディープフェイク技術を使って実在の独裁者の声で再生される。
廣庭賢里(2000~ ):『The silent girl(s)』ピアノと室内オーケストラのための(2024)は、誰かと同じようになりたいけれどなれない葛藤を、音楽だけでなく自作のテキストや身体表現を駆使して表現した作品だという。ピアニストと身体表現(クレジット上は「アシスタント」)の2人で、1人の少女の内面の変化を、室内オーケストラは少女の周りの環境を表現する。
松本淳一(1973~ ):『空間刺繍ソサエティ』(2024)は、音楽家たちの音による空間刺繍がテーマで、細い糸が延々と絡み合いながら編まれていくかのような音響ではじまっていく。だが同時に「ソサエティ(社会)」という言葉がタイトルに含まれているように、社会における個、全体における私という主体がいまこの時代にどうなっているのかを考えたのだという。実際、演奏者のうち12名はスタンドでソリストとして扱われ、指揮者のテンポとは異なるタイミングで音を飛ばして連携しあう。バロック時代に数多く作曲されたコンチェルト・グロッソの現代版といえそうだ。

斎藤拓真 / 廣庭賢里 / 松本淳一(©︎ Aya Sunahara)
新しい視座に出会える選考会の魅力とは
これら3曲を聴いたあと、選考委員――今年は伊左治直、小出稚子、安良岡章夫の3名――による選考会がおこなわれるのだが、なんと舞台上で公開されるというのが見どころとなる。
どういう理由でその作品を評価するのか、しないのか? その理由が包み隠さず、観客の前で議論されるのだ。現代音楽に詳しくなくても……いや詳しくないからこそ、自分が感じた印象との違いを聞くのは面白い体験になるはずである。
いまでも忘れられないエピソードがある。2019年に坂東祐大が弱冠28歳で初めて選考委員を務めた際には、彼は自分より30歳以上年上の作曲家のある発言に噛みつき、客席でみていた筆者はおもわず痺れた。こういう瞬間に立ち会えるのも『芥川也寸志サントリー作曲賞選考演奏会』ならではの魅力だ。
また、演奏と選考会のあいだには私たち聴衆各自が良かった作品に投票できる『SFA総選挙(※S=サマー、F=フェスティバル、A=芥川)』もある。選考会の行く末にますますドキドキできるので、最初から聴いて投票することを強く勧めたい。こういう仕組みがあるからこそ、行ってみたけど何だかよくわからなかった……という感想にはならないはず。選考会もセットで聞けば、必ずや新しい視座に出会えるからだ!
- イベント情報
-
 『第35回芥川也寸志サントリー作曲賞選考演奏会』
『第35回芥川也寸志サントリー作曲賞選考演奏会』
2025年8月30日(土) 15:00開演 (14:20開場)
会場:サントリーホール大ホール
◾️プログラム
芥川也寸志:『交響管弦楽のための音楽』(1950)
〇第33回(2023年)芥川也寸志サントリー作曲賞受賞記念サントリー芸術財団委嘱作品
向井航:『クィーン』ユーフォニアム、エレキギター、女声アンサンブルと大オーケストラのための(オルガン付き)(2025)
ユーフォニアム:佐藤采香 エレキギター:藤元高輝
女声アンサンブル:松島理紗/岡﨑陽香/浅野千尋/個々・マユミ・歌楽寿/庄司絵美
〇第35回芥川也寸志サントリー作曲賞候補作品(五十音順/曲順未定)
斎藤拓真:『アンティゴネーとクレオン』ソプラノ、アンサンブル、エレクトロニクスのための(2024)
ソプラノ:薬師寺典子 エレクトロニクス:今井慎太郎
廣庭賢里:『The silent girl(s)』ピアノと室内オーケストラのための(2024)
ピアノ:天野由唯 アシスタント:鈴木彩葉
松本淳一:『空間刺繍ソサエティ』(2024)
指揮:杉山洋一
新日本フィルハーモニー交響楽団
〇公開選考会
司会:長木誠司
選考委員(五十音順):伊左治直、小出稚子、安良岡章夫
◾️チケット料金
指定席 前売一般 3,000円/U25席 1,500円
指定席 当日窓口一般 3,500円/U25席 2,000円
※U25席はサントリーホールチケットセンター(WEB・電話・窓口)のみ取り扱い。25歳以下、来場時に身分証提示要。お一人様1枚限り。
※チケット引き取り方法「eチケット」を選択すると、紙チケット発券なしでご入場いただけます。
※前売券は、公演当日の正午までWEBで購入いただけます。
- フィードバック 11
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-