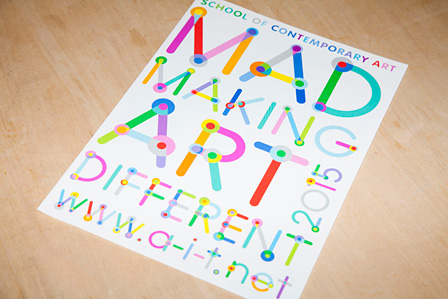アートの仕事に就く。学芸員やギャラリスト、インディペンデント・キュレーター、パブリッシャー、ジャーナリストなどさまざまな仕事はあるけれど、「どうすればなれるのか?」と問われると明確な道筋を答えるのは難しく、一般的に「アートの仕事=狭き門」というイメージは強い。
だが、本当にそうだろうか? セカンドワークやワークシェアなど、多様な働き方が生まれつつある現代、アートの世界でもスキルや職業のバリエーションは広がりつつあるように思う。たとえば全国で芸術祭や地域のアートプロジェクトが増加していることも、アートの仕事が多様化した1つのあらわれとも言えるかもしれない。
NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ(以下、AIT)が運営する現代アートの学校「MAD(Making Art Different―アートを変えよう、違った角度で見てみよう)」は、そんなアート業界に多くの卒業生を輩出しつつ、今年で15年目を迎える。今回、AITの共同設立者の一人である小澤慶介と、美術家の森弘治を招き、近年のアートの環境を巡る対談を行った。イギリスとアメリカで美術教育を受けた二人の対話から、現在のアートシーンにおける「働き方」が見えてくる。
日本には、アートの動向や展覧会について気軽に話し合う場がないことに気が付いて、MADを始めました。(小澤)
―小澤さんと森さん、いずれも海外でアートの勉強をされた後、日本に戻って仕事を始められた二人ですが、付き合いはいつ頃からになるんですか。
森:もう10年以上前ですね。アメリカから帰国して日本のアートシーンのことが全然わからなかったとき、知り合いのアーティストから「小澤さんに作品を見てもらったら?」と言われて。それで小澤さんが当時働いていた麹町画廊を訪ねたのがきっかけですね。
小澤:その頃、僕は美術雑誌の仕事を辞めて、麹町画廊という小さなギャラリーのディレクターとして、展覧会や美術の読書会の企画をしていました。僕もロンドン留学から戻ってきたばかりでいろんな人に会いたかったし、もっと勉強したかったから、アートが好きな人たちが集まれるサロンのような場を作りたいと思ったんです。
森:そのときはポートフォリオ(作品集)を見てもらっただけで、それから5年くらい経って、AITのアーティスト滞在制作プログラムに誘ってもらいましたよね。
小澤:ギャラリーを辞めて、AITやMADの活動を始めた頃ですね。森さんには、韓国で滞在制作をしてもらったり、MAD「アーティストコース」のゲスト講師をお願いしていました。
―小澤さんのほうから森さんに声をかけたのはなぜだったんですか?
小澤:アートと社会の関係について、僕たちAITのスタッフが持っていた問題意識と共通する部分を、森さんはたくさん持っている気がしたんですよね。
―どんな問題意識だったんでしょう?
小澤:当時はMADを始めたばかりで、「多角的な現代アートの見方を日本に根付かせる!」って僕らも必死だったから、たとえば「アーティストコース」を受講してくれたアーティストたちに、キュレーターの視点で厳しく批評・講評をしていたんですよ(苦笑)。でも、それじゃダメだと気づいたんです。それで、対話に長けているだけでなく、作り手の視点を持っていて、アーティスト教育にも関心を寄せていた森さんに声をかけました。
―当時、森さんの関心はどのようなところにあったのでしょうか。
森:アメリカの大学院でアートを学んできたので、作品に対する考え方や、批評における日本と欧米の違いを強く感じていましたね。
―日本と欧米で、美術教育がかなり異なるというのは、よく言われます。
森:アメリカの大学院では、他のアーティストや、ディレクターとしてプログラムを動かしている人たちと、かなり濃密なディスカッションをするんです。「作品をどう作ったか?」はもちろん、作品になる以前のリサーチ、どのようにストーリーを構築したのかなどを、社会科学的な視点や他分野の思考を使いながら、徹底的に話し合う。日本でそういうディスカッションは、あまり一般的ではないんですよね。

MADレクチャー風景(講師:ロジャー・マクドナルド) Photo by Yukiko Koshima
―森さんは当初、多摩美術大学で日本画を学ばれていたそうですが、そこでは物足りなさを感じていた?
森:疑問には思っていました。徒弟制とまではいかないけれど、師匠がいて弟子がいて、その関係上で技術を学んでいく文化が日本画の世界にはあります。それはそれで大事であるけれど、今考えるとすごく「視覚的 / 造形的」な感じがしていて。「何かを思考して描く」っていうよりも、ただ「そこにあるものを視覚的に表現する」っていうか。
小澤:僕はロンドンの大学院で美術史を勉強していましたが、ある先生なんかは、ほとんど何にも教えてくれないんですよ(笑)。「自分で学びなさい」という感じで、最初の15分で大きな質問を投げかけて、さーっと消えてしまうこともあった。それで学生たちは街の本屋や図書館に行って調べたり、展覧会を観て回って肌で感じ取るんです。リサーチの方向性や思考はそれぞれに委ねられていて、僕は心理地理学を学んでいたので、そこから考えていったりしました。
―小澤さんも、海外で美術教育における「考えること」の重要性に気付かれたんですね。
小澤:ロンドンでは「考えること」が当たり前だったのに、日本には「考えること」に重きを置いた美術教育を行う場がないことに気が付いて、似たような問題意識をもつ友人たちとともにMADを始めたんです。僕は、見えている部分だけではなくて、その背後にある時代思潮などについても考えることが好きだし、アーティストとキュレーターの立場の違いはあっても、森さんとはその部分を共有できるのが大きかったですね。
アーティストとして食べていきたいと思っていたけど、活動費のことを考えると夢みたいな話だなと痛感したんです。(森)
―アメリカで日本画からメディアアートへと大きな変化を遂げた森さんですが、帰国後はアーティストによるアーティストのための芸術支援システム「ARTISTS' GUILD」を立ち上げています。
森:2004年に帰国したんですが、当時ドイツで行なわれたフィルムフェスティバルに参加したら、自分のフィーは梱包発送費だけでなくなってしまって(笑)。その他にも個人でHDビデオ機材を買い揃えるのはきついなあとか、そういう辛い思いがいっぱいあって。アーティストとして食べていきたいと思っていたけど、活動費のことを考えると夢みたいな話だなと痛感したんです。
―周りのアーティストも、同じような悩みを抱えていたんでしょうか?
森:はい。友人のアーティストと会うたびに、何かしなければいけないと話していましたね。アーティストは限られた予算内で作品を制作するわけですが、特に映像は撮影場所だったり、出演者だったり、機材だったり、扱う範囲が広いので、色々やろうとするとそのぶんお金を確保しなければいけない。そういう現実的な問題がたくさん見えてきたので、どうにか制作費などを抑える方法はないかと考え、2009年に「ARTISTS' GUILD」を立ち上げました。
―「ARTISTS' GUILD」では、アーティスト同士で機材を共有するシステムを構築していますね。
森:52インチのモニターで観せたい作品が、予算がないから32インチで、となってしまうと、表現したいものも表現できなくなってしまいますよね。そういうときに「ARTISTS' GUILD」で52インチのモニターを用意して、理想の展示状況を実現すると同時に、本来かかるはずの機材費を制作費にまわすことができるようになりました。ただ機材費を安くできるということだけでなく、その仕組み全体をアート業界の人たちに知ってもらうことで、問題意識を共有していこうと努めています。
―「ARTISTS' GUILD」の活動は、どうやって社会とコミットしていくのかという、アーティスト側の問題意識を感じさせますね。
森:そういうことは他のアーティストともよく話しますし、意識はどんどん高まっているように感じます。
僕は、人が変わっていく力や、いきいきと生きる力とか、力そのものがアートだと思っているんです。(小澤)
―アートが社会とどう関わっていくかというテーマは、いろんなところでされている議論でもありますが、欧米と日本を見比べて、あらためて気が付いたことはありましたか?
森:帰国した当時は、「視覚的 / 造形的」なビデオアートを作る作家が多いと感じました。帰国直後に参加した『Have We Met ? 見知らぬ君へ』展(国際交流基金フォーラム、2004年)では、プラカードを持って女性専用車両に関するモノローグを語りながら役者が歩くという、社会への問題意識を反映した映像作品を展示したんですが、賛否両論でさまざまな反応がありました。日本でビデオアートとされるものとそうでないものの違いを考えるいい機会でしたね。
小澤:僕もその作品を観たんですが、「むしろ、アートってこうじゃない?」と共感しました。たしかに、当時の日本のビデオアートって、動きや造形といった視覚的な要素を表現するものだとされていて。でも、森さんの作品は画面の中で完結せず、観る人の想像力を作品の外の社会空間に飛ばしたいという意思を感じましたね。
森:自分の持っている社会的な問題意識からリサーチを経て、映像作品として展開していくことを考えていたんです。そういう意味では、小澤さんがMADで伝えていこうとしている「どのように思考して、多角的な視点からアートを観ていくのか」という部分とは、共通点があると思います。

MADお出かけレクチャー(訪問先:アートスペースSUNDAY)
―MADはアーティストだけじゃなく、キュレーターやギャラリスト、ライターなど、さまざまな形でアートの仕事に携わりたいと考えている人が受講しています。アートと社会との接点というのは、小澤さんたちにとっても重要なテーマでもあるのでしょうか?
小澤:そうですね。ロンドンの大学院では、一度社会に出て経験を積んでから通う人が多いので、じつは僕が一番若かったんです。実社会で積んだ経験がディスカッションにも反映されるから、内容も具体的で面白くて。学部からすぐ大学院に行くと、まだ実社会との回路が開いていない状態なので、抽象的な議論の積み重ねになっていきがち。MADも社会人の受講生がとても多く、閉じたアカデミズムよりも風通しの良い議論ができていると思います。
―具体性がなく曖昧なままで終わってしまうのは、日本の芸術表現の弱点とも言えそうです。
小澤:「アート」を考えるときは、美術館やギャラリーのような枠組みとか、制度的なものを頼りにすることが一般的。だけど僕は、人が変わっていく力や、いきいきと生きる力とか、力そのものがアートだとも思っているんです。社会彫刻を提唱したヨーゼフ・ボイスではないけど、すごくクリエイティブな消防士がいてもいいですよね。「この消火方法はおかしいからこうしよう!」みたいな(笑)。だけどイチイチ考えないほうがラクだから、惰性的に物事を見てしまうわけだけど、きっとそこにアートの種はないんですよね……。これは自分に対する戒めでもあるんですが(笑)。
自分でフィードバックを繰り返しながら、「アートで何かできるんじゃないか」っていう着地点を見極めていくことが必要なのかもしれません。(小澤)
―アートと社会の関係のお話ですが、「アートの仕事」についても詳しくお伺いできればと思います。お二人とも現場で15年以上にわたって活動されてきたわけですが、これからのアート業界ではどんな仕事や役割が求められていくと感じていますか?
小澤:特にここ10年は、芸術祭やアートプロジェクトが全国各地でたくさん始まって、いろんな意味で間口は広くなってきていると思います。より社会との関係は密接になっているし、アートが扱う範囲も広くなっているから、その状況をどうマッピングしていくのかが、関係者のみならず鑑賞者にも求められている。今年度のMADプログラム「アドバンス・スタディーズ」でも、『大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ』について、現地に住んで研究を行っている文化人類学が専門の兼松芽永さんや、比較文学者でもある小説家の小野正嗣さんに講師に来ていただくなど、いろいろな角度からアートへのアプローチを試みています。

MADレクチャー風景(講師:ロジャー・マクドナルド) Photo by Yukiko Koshima
森:僕が普段活動する、いわゆるメディアアートの現場ではインスタレーション作品が増えていて、エンジニアの協力が不可欠になってきています。もちろん技術を持っている人は探せばいるんだけど、アートという目線から一緒に考えてくれるエンジニアは本当に少ない。
小澤:それはありますね。僕が関わった映像インスタレーションの展示設営にあたって、アーティストの要求を実現できるエンジニアが見つからなくて、森さんに相談したくらいです。
森:そうでしたね(笑)。
―いろんな表現やメディア、価値観があって、かつてはアートとは言い難かったものも作品になりうる状況になりました。一方で、アート自体が液状化した状態ともいえて、その中で活動していくのは難しい部分もあったりするのでは、とも思ったのですが。
小澤:でも逆に言えば、自分が「こうじゃないか?」と思ってやってみたことが、ずれて返ってくる面白さもありますよね。思っていたところとは違う部分を褒められるとか。そうやって液状化しながらも裾野が広がっていく中で、フィードバックを繰り返しながら、「アートとは何か?」「アートで何かできるんじゃないか?」という自分なりの着地点を見極めていくことが必要なのかもしれません。
―自分なりにアートで社会に対して何ができるのか、その意義さえ掴めていれば、いろんな仕事の可能性が現れてくるのかもしれませんね。小澤さんも、そういったフィードバックを繰り返してきましたか?
小澤:そうですね。というのは、自分がキュレーターになるとは思ってもいませんでしたから。美術雑誌で働いてみたり、周りに面白そうなアーティストがいたから小さな展覧会を企画してみたり、それだけじゃ食べていけないからアートフェアの事務局で働いてみたり。並行して、AITやMADみたいなオルタナティブな活動に興味を持ち、最近では十和田市現代美術館のキュレーターとして展覧会を企画したりして。その時々では必死なんですが、今思うと不思議な感じがします。でも、試してみないとわからないことは多いですよね。
-
- 3コマから学べる現代アートの学校「MAD」
- イベント情報
-
- 『MAD2015相談会』
-
2015年4月以降開催
会場:東京都 代官山 AITルーム
料金:参加無料(要予約)
※詳細はオフィシャルサイト参照
- プロフィール
-
- 小澤慶介 (おざわ けいすけ)
-
1971年生まれ。ロンドン大学ゴールドスミスカレッジにて現代美術理論修士課程修了。現代アートの学校MADの受講生とともに守章『終日中継局』展(2012)、泉太郎『たしかめる』展(2013)などの実験的な展覧会企画を手掛ける。『十和田奥入瀬芸術祭 SURVIVE この惑星の、時間旅行へ』(2013)キュレーターを経て、2014年4月より十和田市現代美術館チーフ・キュレーターを兼務。
- 森弘治 (もり ひろはる)
-
多摩美術大学卒業後渡米、マサチューセッツ工科大学(MIT)大学院修了。社会空間への介入をテーマに、主に映像作品を制作している。『越後妻有アートトリエンナーレ2009』や『第52回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際企画展アルセナーレ』(2007、ヴェネツィア)、『アート・スコープ2005/2006』(2006、原美術館)などで作品を発表している。
- フィードバック 1
-
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
-